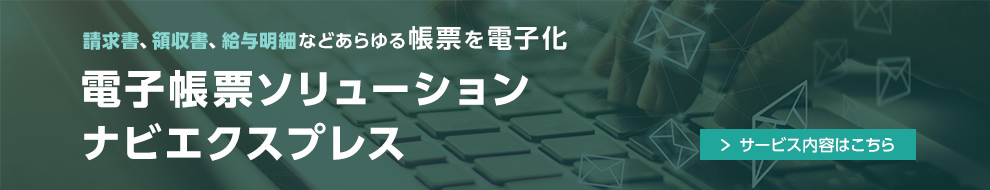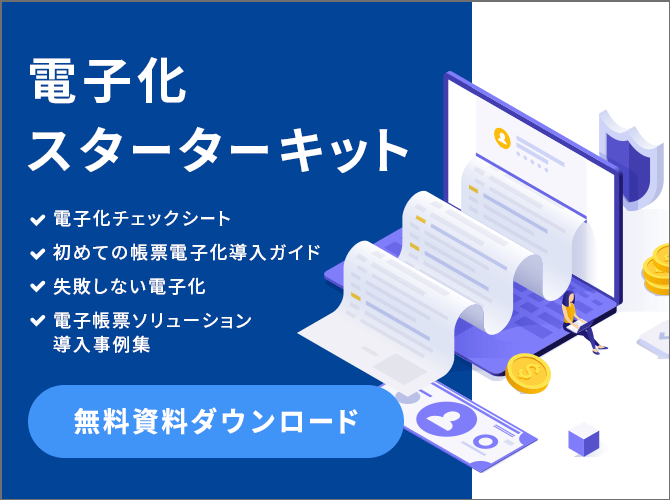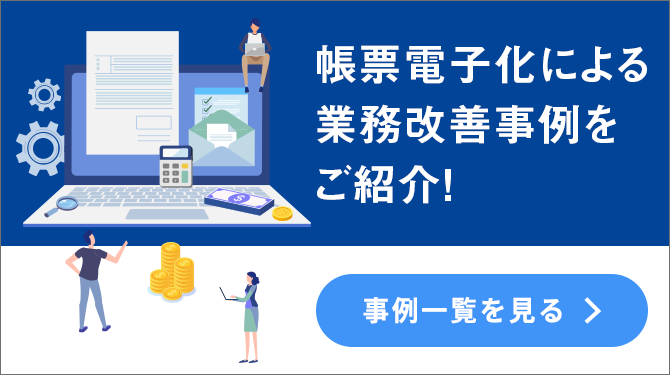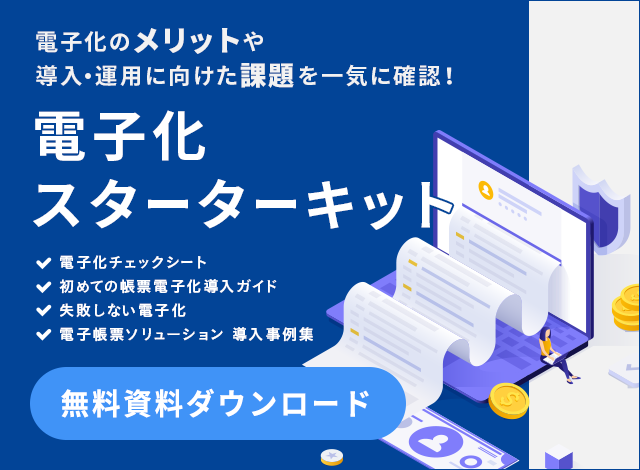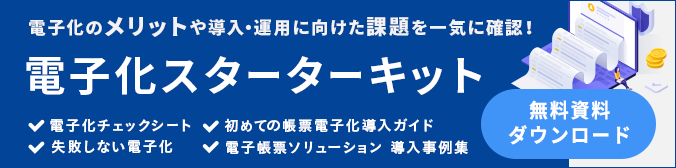2025/10/22
帳票、書類の電子化
紙の手形・小切手の廃止はいつ?代替手段や支払通知書の電子化についても解説
請求書等の電子配信にお悩みはございませんか?
基幹システムに手を加えず連携し、電子化をご提案いたします。
商取引の全帳票を電子化し、即日到着でコスト削減・業務効率化を実現します!
⇒ まずは電子帳票ソリューション ナビエクスプレスの資料を見てみる
2026年度末をもって、紙の手形・小切手が廃止される方針が正式に示されています。これまで支払い業務で手形や小切手を活用してきた企業にとっては、経理業務に大きな影響が及ぶことが予想されます。ほかの決済手段にスムーズに移行するには、廃止までのスケジュールを正確に把握し、システムの導入や社内体制の見直しを早めに進めなければなりません。
本記事では、紙の手形・小切手が廃止される背景から今後の対応、電子化のメリットや注意点などをわかりやすく解説します。
- 紙の手形・小切手が2026年度末に廃止されることを受け、各金融機関では新規発行の受付終了や最終振出期限の設定などの対応が進められている
- 紙の手形・小切手の代替手段として、でんさいやインターネットバンキングなどの電子取引が挙げられる
- 電子取引への移行によって、事務負担の軽減やコストの削減、紛失やヒューマンエラーの防止など、さまざまなメリットが得られる
- 代替手段への移行に際しては、システム導入による費用負担やセキュリティ対策、取引先との調整などが必要になる点に注意
2026年度末に紙の手形・小切手は廃止される
紙の手形・小切手は、2026年度末(2027年3月末)をもって廃止される予定です。はじめに、廃止に至るまでのスケジュールや、その決定に至った背景について詳しく見ていきましょう。
紙の手形・小切手の廃止のスケジュール
2026年度末(2027年3月末)までに紙の手形・小切手を廃止するという方針は、政府が2021年6月に発表した「成長戦略実行計画」の中で明らかにされました。この計画には「5年後の約束手形の廃止に向けた取り組みを推進する」「小切手の全面的な電子化を図る」という2つの方針が盛り込まれています。
これを受けて、全国銀行協会は2021年7月に「手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画」を公表しました。この中で、2026年度末までに電子交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにする目標が掲げられています。
なお、このスケジュールはあくまで「目標」であり、2027年度以降に手形や小切手を使用しても罰則を受けるわけではありません。しかし、廃止後はこれまでどおりの取り扱いができなくなる可能性が高く、多くの金融機関が2026年度末を待たずに前倒しで手形・小切手の取り扱いを縮小する動きもあるため、代替手段への早めの切り替えが求められています。
参考:全国銀行協会「手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画」
紙の手形・小切手の廃止の背景
紙の手形・小切手が廃止される背景には、事務負担やコスト面など、企業側にとってのデメリットが多いという事情があります。
紙の手形・小切手は、印刷・押印・郵送・保管といった工程が必要で、事務処理の負担が大きくなりがちです。また、郵送料や印紙税、現金化のための取引手数料など、直接的なコストも少なくありません。
さらに、紛失や盗難のリスクがあるほか、現金化までに数週間から数ヶ月かかることもあり、資金繰りに影響を与えるケースもあります。こうした課題のある紙の手形・小切手は、デジタル化・ペーパーレス化が進む現代のビジネスシーンにそぐわないとされ、非効率な仕組みとして見直しが進んできました。
こうした背景から、政府や金融機関はより効率的で安全な電子的取引の普及を目指し、紙の手形・小切手の廃止が決定されました。
紙の手形・小切手の廃止に対する各金融機関の動き
紙の手形・小切手の廃止に向け、各金融機関では以下のスケジュールで対応を進めています。
| 銀行名 | 発行受付終了 | 預金入金扱い受付終了 | 最終振出期限 |
|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 | 2025年9月30日 | - | 2026年9月30日 |
| 三菱UFJ銀行 | 2025年9月30日 | 2026年3月31日 | 2026年9月30日 |
このほか、みずほ銀行でも2027年4月以降を期日とする手形・小切手の代金取立を停止するなど、各行がそれぞれ紙の手形・小切手の廃止に向けた準備を進めています。
参考:三井住友銀行「手形・小切手の発行終了等に関するお知らせ」
参考:三菱UFJ銀行「手形・小切手ご利用にあたっての今後のご留意事項」
参考:みずほ銀行「手形・小切手の全面的な電子化に向けた関連商品・サービスの商品性改定およびお取扱終了のご案内」
紙の手形・小切手が廃止されることのメリット

紙の手形・小切手の廃止により電子取引へ移行することで、これまでの事務負担やコスト、リスクを軽減できるだけでなく、資金繰りの安定など、さまざまなメリットを得られます。ここでは、主な4つのメリットについて詳しく見ていきましょう。
事務負担が軽減される
紙の手形・小切手の廃止により、「でんさい」やインターネットバンキングを活用した電子取引へ移行すれば、印刷・押印・発送・保管といった紙の管理業務が不要になります。これにより、経理担当者の作業時間を削減でき、事務負担を大幅に軽減できるのが大きなメリットです。
また、取引先や金融機関への郵送・持参の手間がなくなり、自動的に入金が処理されるため、支払や入金確認の効率も大幅に向上します。さらに、入出金の管理がオンライン上で完結するため、テレワーク環境やクラウド会計システムとの相性も良く、在宅勤務など柔軟な働き方にも対応しやすい体制を整えられます。
コストの削減につながる
紙の手形・小切手から電子取引へ切り替えることで、印紙税や郵送料、印刷費など、紙の現物をやり取りする際に発生していたコストを大幅に削減できます。さらに、現物の保管や廃棄にかかる管理費用も不要となり、経費の無駄を抑えられる点もメリットです。
また、電子化によって処理スピードが向上すれば、業務効率が高まり、人件費の削減にもつながるでしょう。このように、紙の手形・小切手の廃止をきっかけに、さまざまな側面でコスト削減効果が期待できます。
紛失や盗難、ヒューマンエラーのリスクが軽減される
紙の手形・小切手が廃止されると現物を扱う必要がなくなるため、紛失・盗難・改ざんといった物理的なリスクを大幅に軽減できます。また、支払データを自動的に記録・保存する仕組みを導入すれば、転記ミスや二重登録といった人的ミスも防ぎやすくなります。
さらに、電子取引では入金処理が自動化されるため、支払期日の失念による取立漏れなどの心配もありません。このように、正確かつ安全に取引ができるようになる点も、紙の手形・小切手の廃止による大きなメリットといえるでしょう。
資金繰りの不安が軽減される
紙の手形・小切手の廃止に伴い、振込など別の決済手段に切り替えることで、現金化までの期間を短縮できる可能性があります。これにより、資金繰りに対する不安を軽減できる点も見逃せないメリットです。
また、支払や入金のタイミングがオンラインで可視化されることで、資金の動きをリアルタイムで把握でき、より精度の高い資金管理が可能になります。
紙の手形・小切手が廃止されることのデメリット
紙の手形・小切手の廃止は、業務効率化やコスト削減といった多くのメリットをもたらす一方で、切り替えに際して新たな対応や負担が発生するケースもあります。ここでは、主なデメリットとして想定される課題を紹介します。
代替となる決済方法の導入による負担が発生する
紙の手形・小切手が廃止される前に、企業は代替となる決済手段を導入しなければなりません。政府や金融機関が推奨しているのは、インターネットバンキングなどの電子取引ですが、これらを導入する際には新たなシステム構築や運用に伴う費用が発生します。こうした初期投資やランニングコストは、特に中小企業にとっては負担となるケースが多いでしょう。
さらに、決済方法の切り替えにあたっては、業務フローの変更や新システムの操作レクチャーなど社員教育も必要です。業務が一時的に混乱したり、移行初期にトラブルが発生したりするリスクも考慮しておかなければなりません。
また、電子化によって現物の紛失や盗難といった物理的リスクは軽減される一方で、不正アクセスや情報漏洩など、サイバーセキュリティ上のリスクへの備えが必要です。こうしたセキュリティ対策にも追加のコストや体制整備が求められる点も、デメリットといえるでしょう。
取引先との調整が必要になる
決済手段の変更は自社だけで完結するものではなく、取引先との調整が不可欠です。取引先によっては、従来どおり紙の手形・小切手での取引を希望されるケースや、切り替え時期を個別に指定される場合もあります。
そのため、各社との合意形成やスケジュール調整に時間がかかることも少なくありません。結果として、一時的に担当者の業務負担が増えたり、決済処理の遅延が発生したりする可能性もあるため、早めの準備と社内外の調整が求められます。
紙の手形・小切手に代わる代表的な決済手段

紙の手形・小切手の廃止により、企業は代替となる新しい決済手段への切り替えが求められます。ここでは、電子化によってより効率的かつ安全に取引を行える代表的な決済方法を紹介します。
電子記録債権(でんさい)
電子記録債権(でんさい)は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)が運営する、債権情報を電子的に管理できる仕組みです。従来の手形取引を電子化したもので、金融機関のシステムを通じて債権の発行や譲渡、支払いがスムーズに行える点が特徴です。
電子データとしてやり取りされるため、印紙税や郵送費などのコストが発生せず、手形管理に伴う事務負担を大幅に軽減できます。支払側が所定の手続きを行うだけで、期日になると自動的に受取側の口座へ入金される仕組みで、安全性も高い決済方法です。
政府が推奨する電子決済の中心的な仕組みではあるものの、現時点での普及率はおよそ10%前後にとどまっているのが実情です。
インターネットバンキング
インターネットバンキングは、パソコンやスマートフォンを通じて銀行取引をオンラインで行えるサービスです。残高確認や振込、振替といった手続きが24時間いつでも可能なため、銀行窓口やATMに足を運ぶ必要がありません。
さらに、各金融機関が提供するインターネットバンキングは、クラウド会計ソフトとの連携にも対応しているものも多くあります。入出金データを自動的に取り込めるため、入力ミスを防ぎつつ、経理処理のスピードと正確性を高められます。帳簿への反映作業が効率化されることで、日常の経理業務を大幅に効率化できる点もメリットです。
クレジットカード決済・デビットカード決済
企業間取引でも、クレジットカードやデビットカードを活用するケースは少なくありません。これらのカード決済は銀行振込のように振込手続きの手間や手数料といったコストがかからず、キャッシュレスでスムーズに取引できるのが特徴です。
また、利用明細を会計ソフトに自動で取り込めるサービスもあり、経理処理の自動化や事務作業の軽減にも役立ちます。
注意点として、クレジットカードには利用上限額が設定されているため、高額決済を行う際は上限の引き上げ手続きが必要になる点が挙げられます。また、デビットカードは決済時に口座から即時引き落としが行われるため、銀行残高を超える支払いはできません。こうした決済の特性を理解した上で使い分ける必要があります。
電子マネー決済
少額決済では、電子マネーの活用も有効です。ICカードを利用する電子マネー決済は、スピーディーで現金管理の手間を減らせるのが魅力です。一部の電子マネーサービスは、クレジットカード同様に利用明細を会計ソフトへ自動反映できるため、小口現金の管理や経費精算の効率化にも役立ちます。
紙の手形・小切手の廃止にともなう企業の対応の流れ
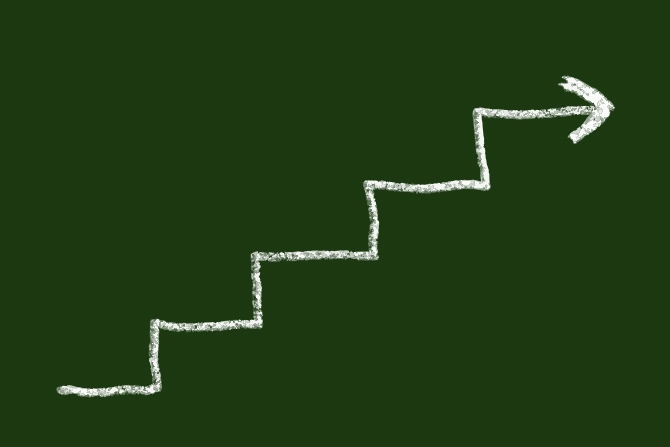
紙の手形・小切手の廃止に向けて、企業には早めの準備が求められます。ここでは、企業がスムーズに電子化へ移行するための具体的な対応ステップを順に紹介します。
手形・小切手についての現状の把握
まずは、自社でどの程度手形や小切手を利用しているのかを把握することから始めましょう。発行・受領の両方について、取引先や金額、頻度、支払サイトなどを整理すると、決済方法の切り替えによってどの業務にどれほど影響が出るのかを明確にできます。
また、印紙代・郵送費・保管コストなど、紙のやり取りに伴うさまざまな費用を洗い出しておくと、電子化によるコスト削減効果を具体的にイメージできるでしょう。こうした事前の現状分析によって、次のステップである代替手段の検討・選定をスムーズに進めやすくなります。
代替となる決済方法の検討・金融機関への相談
次に、紙の手形・小切手に代わる決済手段を検討しましょう。「でんさい」やインターネットバンキングなど、複数の電子取引方法があるため、それぞれの特徴や導入コスト、利便性、セキュリティ面などを比較し、自社の業態や取引規模、取引先の対応状況に合った方法を選びます。
例えば、取引金額が大きく資金繰りの管理が重要な企業であれば、支払期日を設定できる「でんさい」が第一の選択肢になるでしょう。反対に、少額取引が頻繁に発生する小売業やサービス業などでは、クレジットカードやデビットカードといった決済方法が便利です。
代替となる決済方法を選定したら、取引のある金融機関へ相談し、導入までの流れや必要な手続き、新たなシステム導入の必要性などを確認します。この段階で導入スケジュールを大まかに検討しておくと、次のステップである取引先や社内への周知にスムーズに移行できます。
取引先への周知と調整
新しい決済方法を導入する際には、取引先への周知と調整が欠かせません。選定した決済手段や切り替え時期を丁寧に説明し、双方の業務スケジュールをすり合わせます。
取引先がすでに電子取引を導入している場合はスムーズに移行できるケースもありますが、従来どおりの紙取引を望む企業も少なくありません。そうした場合には、電子化のメリットや運用方法を説明し、理解を得ながら慎重に対応する必要があります。取引先の要望をヒアリングし、フォローアップや個別説明の機会を設けると良いでしょう。
業務フローの改修と社内教育
決済方法の切り替えに伴い、社内の業務フローも変更が必要になります。実務を担う経理担当者や管理部門の意見も取り入れながら、新しい仕組みに合わせて業務フローを見直しましょう。
切り替え後の混乱を防ぐためには、導入スケジュールを社内で共有し、操作説明会やマニュアル配布などの教育体制を整えることも重要です。新システムの操作方法やトラブル時の対応を事前に周知しておくと、スムーズに運用を始められます。
支払通知書も「ナビエクスプレス」で電子化しよう
これまで、紙の手形や小切手は「支払通知」としての役割も果たしていました。しかし、でんさい以外の決済手段に切り替える場合は、支払内容を相手に知らせる支払通知書の発行が必要になります。あらゆる業務でペーパーレス化が進む今、この機会に支払通知書や請求書の電子化も併せて検討してみてはいかがでしょうか。
その際におすすめなのが、NTTコム オンラインが提供する「ナビエクスプレス」です。商取引に関わるあらゆる帳票を電子化して即日配信できるシステムで、既存の帳票デザインをそのまま活用できる点が大きな特徴です。
また、基幹システムとの連携によって帳票の作成から配信までを自動化でき、誤送信などのヒューマンエラーの防止にも役立ちます。さらに、SSLによる暗号化など強固なセキュリティ対策も備えており、取引データの安全かつ確実なやり取りが可能です。
帳票の電子化を効率的に進めたいとお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
紙の手形・小切手の廃止に向けて着実に準備をすすめよう
紙の手形・小切手の廃止によって、企業は決済業務の見直しを迫られています。2026年度末の廃止を見据え、今のうちから代替手段の検討や業務フローの見直しを進め、スムーズな移行と業務効率化を目指しましょう。
電子取引への移行は単なる制度変更への対応にとどまらず、事務負担やコスト削減、資金繰りのリスク軽減など、企業運営全体の改善につなげられるチャンスでもあります。これを機会に、支払通知書や請求書といった帳票類の電子化も検討してみてください。
「ナビエクスプレス」のような自動配信システムを活用すると、セキュリティを確保しながら効率的に帳票の電子化を進められます。今後の変化に備え、着実に準備を進めていきましょう。

【
帳票、書類の電子化
】
最新のコラム

2025/12/09

2025/10/22