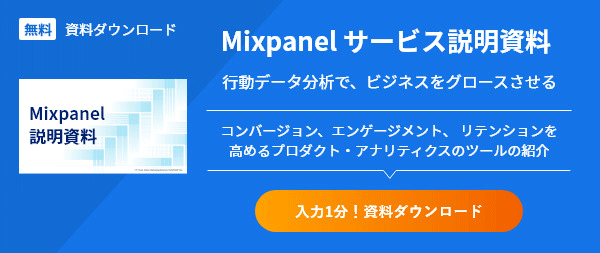スティッキネス(粘着性)の意味・計測方法とは?向上させる秘訣も解説
- 目次
-
近年、リピーター獲得の重要性が高まっており、「スティッキネス(粘着性)」という考えが注目を集めています。スティッキネスとは、ユーザーが「商品・サービスに熱中している度合い」のことです。ユーザーにプロダクトの価値を感じてもらいスティッキネスを向上させることは、顧客獲得や売上向上にもつながります。
本記事では、スティッキネスが重要視される理由や数値を高めるポイント、計測方法などについて解説します。また、スティッキネスを高めリピーターを獲得するコツも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
- 記事の要約
-
- スティッキネスとは、ユーザーが「商品・サービスに熱中している度合い」のこと
- スティッキネスを高めるためには、顧客を深く理解し、顧客ごとに適したメッセージを届けることが大切
- スティッキネスを向上してリピーター獲得につなげるためには、ユーザーに質の高いアフターフォローやカスタマーサクセス、リピートにつながるメリットなどを提供する必要がある
スティッキネス(顧客の粘着性)の意味とは?
まずは、スティッキネスの意味や重要視される理由、エンゲージメントやリテンションとの関係性について見ていきましょう。
スティッキネスとは「商品・サービスに熱中している度合い」
スティッキネスとは、ユーザーが「商品・サービスに熱中している度合い」を示す言葉です。ユーザーが商品・サービスを利用している時間の長さや利用頻度、リピート回数などをもとに計測します。スティッキネスが高い場合、ユーザーが頻繁かつ定期的にサービスにアクセスしていると判断できます。
スティッキネスが重要視される理由
スティッキネスが重要視される理由として、インターネットの普及により他社との差別化が難しくなっている点が挙げられます。市場に似たような商品・サービスが多く出回っている状況では、もはや商品・サービス自体の優劣や価格だけで差別化を図るのは容易ではないでしょう。
また、サブスクリプション型ビジネスが普及し、継続的に利用されるプロダクトづくりが求められていることも背景にあります。サブスクリプション型のビジネスは、ユーザーが中長期的に商品・サービスを利用することで利益が上がるため、スティッキネスが低い状態ではビジネスを継続できません。そのため、顧客に商品・サービスの価値を感じてもらい、スティッキネスの高い状態を作り上げることが重要になっています。
スティッキネス・エンゲージメント・リテンションの関係性
スティッキネスと似た概念に「エンゲージメント」があります。エンゲージメントには「約束」「契約」といった意味があり、マーケティング領域では「顧客と企業が良好な関係を結ぶこと」を指します。エンゲージメント率はマーケティングにおける重要な指標の一つです。エンゲージメントが向上すれば商品・サービスを長く利用してもらうことができ、新規顧客の獲得や企業の売上向上、またユーザーが自発的に商品・サービスの利点を広めてくれるといった状態にもつながりやすくなります。
このエンゲージメントが醸成されることでスティッキネスが向上し、その結果、リテンション率(顧客維持率)の向上にもつながります。
エンゲージメント・スティッキネスを高めるポイント
ここからは、エンゲージメントやスティッキネスを高めるためのポイントについて解説します。
深い顧客理解
エンゲージメントやスティッキネスを高めるためには、顧客理解を深めることが大切です。顧客の属性や購買履歴、Webサイト・アプリでの行動データなどを収集・分析することで、エンゲージメントの醸成につながる適切な施策を実施できます。例えば、適切な分析結果を得ることで、アプリのインターフェースやweb広告の内容を最適化することができるでしょう。新規顧客・既存顧客のデータを収集するためのツールの導入や仕組みを整え、分析をしたうえで具体的な施策を検討しましょう。
【関連記事】
ユーザー行動分析とは?8つのフレームワークと具体的な手法を解説
メッセージのパーソナライズ
顧客への理解を深めることができたら、誰に向けてどのような内容のメッセージを、どんな方法で伝えるのかを考えます。顧客全員に同じメッセージを送っても、特定のセグメントに対する効果しか得ることができないため、顧客ごとに適したメッセージを届けることが重要です。
例えば、一度も商品を購入したことがないユーザーには初回割引クーポンを送ったり、ロイヤルティユーザーには限定キャンペーンを実施したりするのも有効です。セグメントごとに効果的な手法、届けるコンテンツの内容を検討して施策の効果を最大化させましょう。顧客データを分析し、仮説を立てたうえで施策を実施することが大切です。
効果的なSNS戦略
SNSはユーザーとの距離感が近いため、エンゲージメントの醸成に有効です。実際、自社の商品・サービスのファンを獲得する手段として、SNSを活用する企業は多く見られます。SNSは投稿へのいいねやコメントへの返信などを通じて、ユーザーとコミュニケーションを取りやすいツールです。なんらかの反応が戻ってくる手応えがあれば、ユーザー側も積極的にアクションを起こしやすくなるでしょう。
SNS上でユーザーに質問を募集し、動画やインスタライブなどでそれらの質問に回答するといった使い方もできます。このようにユーザーと双方向のコミュニケーションを取ることで、商品やサービスへの関与・共感を強くすることができ、エンゲージメントの向上にも期待できます。
スティッキネスの計測方法【DAU/MAU比率】
スティッキネスはユーザーの商品・サービスの利用時間や利用頻度など、さまざまな視点からの計測が必要です。スティッキネスを計測する方法の一つが「DAU/MAU比率」です。
- DAU=1日あたりのアクティブユーザー数
- MAU=1カ月あたりのアクティブユーザー数
DAU/MAU比率を用いることで、Webサイト・アプリにおけるスティッキネスやエンゲージメントを測定することができます。DAU/MAU比率の計算式は以下のとおりです。
DAU/MAU比率(%)=DAU ÷ MAU × 100
例えば、DAU/MAU比率が40%の場合、ユーザーが毎月平均12日間(30日の40%)Webサイトやアプリを利用している計算になります。DAU/MAU比率が高いアプリはシェアやアプリ内課金をされる機会も多いと考えられ、収益増につながる可能性が高くなります。
【関連記事】
アクティブユーザーの定義とは?重要性や向上させるポイントを解説
DAU/MAU比率の目安とは?
実際に、どれくらいのDAU/MAU比率があれば良しとされるのでしょうか。以下は、DAU/MAU比率の目安です。
(DAU/MAU比率)
- 10~20%:標準
- 20%以上:優秀
- 50%以上:非常に優秀
一般的に、DAU/MAU比率が20%を超える状態であれば、日常的に多くの人が利用しているプロダクトだといえます。ただし、比率の目安はプロダクトのジャンルや用途、ターゲット層などによって異なる場合があります。
スティッキネスを高めリピーターを獲得するには?
続いて、スティッキネスを高め、リピーターを獲得する具体的な方法について解説します。
質の高いカスタマーサクセス
スティッキネスを高めてリピーターを獲得するためには、質の高いカスタマーサクセスが欠かせません。カスタマーサクセスとは、企業が能動的に「顧客の成功(体験)」を支援することです。
近年、他社との差別化が難しくなってきているうえ、サブスクリプション型サービスが台頭しているのもカスタマーサクセスが重要視されている背景にあります。商品やサービスの購入がゴールではなく、継続して使い続けてもらうことが前提となるため、その魅力を理解してもらう必要があるのです。
カスタマーサクセスを支援する具体的な方法に、導入支援やモニタリングがあります。導入支援でユーザーの「わからない」を解決し、モニタリングでは自社商品・サービスをうまく活用できていないユーザーを洗い出すなどして、能動的にサポートすることが可能です。
質の高いアフターフォロー
商品やサービスの購入後に質の高いアフターフォローを行うと、スティッキネスが向上する傾向にあります。例えば、顧客からの問い合わせに迅速に応えたり、クレーム対応を丁寧に行ったりすることで、リピート購入につながりやすくなるでしょう。特に、ユーザーがクレーム対応に満足すれば、問題が起こらなかった場合よりステッキネスが高まる可能性もあります。
また、定期的に購入する商品であれば、消費するであろうタイミングでメールを送るなど、細やかなフォローを行いましょう。
リピートするメリットの提供
ユーザーにとってリピートするメリットがあると、自然とスティッキネスは高まります。例えば、リピーター限定の商品を用意する、リピーターに優先的に販売する、特別価格で商品・サービスを提供するなどの施策により、ユーザーはリピートするメリットを感じられるでしょう。
また、ポイント制度やランク制度を設けることで、リピート購入するモチベーションにもつながります。ランクごとに「ポイント◯倍」「送料無料」といった特典を用意するなどしてリピートするメリットをアピールできます。
顧客ニーズに合った高品質なコンテンツの作成
メールなどで顧客にコンテンツを届ける際、その質やマッチング度合いが高いほどスティッキネスは高まります。コンテンツの質が低ければ、商品やサービスへの評価を上げることは難しいでしょう。それどころか、自分に興味のないコンテンツばかり配信されると、印象が悪くなる恐れもあります。
企業やブランドの専門性を活かした価値あるコンテンツを、興味のある顧客に届けることが重要です。
インタラクティブな機能の追加
プロダクトにインタラクティブ(双方向)な機能を追加することで、より魅力的に感じられるほか、付加価値としても作用します。例えば、企業のWebサイト内にチャットボットを設置することで、ユーザーの課題を素早く解決することが可能です。チャットボットで解決できないような相談については、有人のカスタマーセンターへスムーズにアクセスできるようにしておくとよいでしょう。
また、情報を画像でわかりやすくまとめる「インフォグラフィック」などの視覚効果を活用することで、ユーザーが必要とする情報へスムーズに促すことも可能です。
紹介制度・会員制度の実施
紹介制度や会員制度もリピーターの獲得に有効です。紹介制度とは、既存ユーザーが知人や家族に商品・サービスを紹介し、紹介した方と購入した方の双方にメリットが提供される制度です。紹介制度によりリピート率の向上に加え、新規ユーザーの獲得も期待できます。
また、登録ユーザーだけが参加できる会員制度を設けることで、ユーザーと長期的な関係を構築することも可能です。スポーツジムの会員やショップ会員、ファンクラブなどが一例で、会員限定の特典を提供したり、先行販売を行ったりなどしてリピートを促進します。会員へのきめ細かいアプローチで満足度を上げられれば、スティッキネスの向上にもつながるでしょう。
顧客データの計測・分析の実施
どのような施策を行う場合でも、顧客データの計測・分析は欠かせません。顧客データの分析は施策を検討する際の材料として活用することに加え、実施した施策を評価する材料にもなります。
データドリブン(データを活用してビジネスにおける意思決定を行うこと)の概念に基づいて施策の立案・修正を行うことで、より精度の高いマーケティング施策の実施につながります。これらを繰り返すことで、よりスティッキネスの高い商品・サービスに成長させることもできるでしょう。
顧客データの計測や分析には適切なツールの導入が必要です。ツールを選定する際には、自社に必要な機能があるか、使いやすいか、システムに柔軟に連携できるか、サポート体制は充実しているかなどを確認したうえで導入を検討しましょう。
スティッキネスの向上に寄与する「Mixpanel」
Mixpanelは自社プロダクト内におけるユーザーの行動データを収集・分析し、ユーザー体験を向上させることを目的とする分析ツールです。「自社プロダクトのリピートユーザーは誰か」「ユーザーがサービスを利用するきっかけとなった施策は何か」「プロダクトの新機能がユーザーにどのような影響を与えたか」などを分析することで、スティッキネスの向上に効果的な施策を立案することができます。
また、ユーザーの定着率を視覚化したり、パワーユーザーの行動パターンや顧客が休眠に至った要因などを特定したりすることも可能です。ユーザーに紐付けたマスターIDにより複数のデータベースを一括管理できるうえ、すでに利用している他システムとの連携もできるなど、業務の効率化にも役立つツールです。
導入事例|Rakuten Viber 様
Rakuten Viber様は、メッセンジャーアプリサービスを運営する企業です。現在はWhatApp、Messengerに次ぎ、世界第3位のユーザー数を誇っています。同社はよりユーザーに満足してもらいたいとの思いから、エンゲージメントの増加やリテンションの改善のために何ができるのか把握するための正確なデータを必要としていました。
同社はMixpanelを導入後、ユーザーに喜ばれるメッセージパターンの分析や、どのような機能変更がサービス利用に良い影響を与えるのかを把握するためのABテストなどを実施しました。その結果、メッセージ送信数が15%増加、グループチャット数が10%増加するなど目に見える成果を得たとのことです。Mixpanelが改善すべきUXを把握するために大変役立ったと満足されています。
スティッキネスの向上はプロダクトの成長に重要な要素
スティッキネスの向上は、プロダクトの成長やリピーターの獲得にもつながる重要な要素です。スティッキネスを高めるためには、カスタマーサクセスの実現や、顧客がリピートしたくなるメリットの提供など、顧客に満足してもらえる施策が必要になります。また、顧客データを詳細に計測・分析し、ユーザー行動や自社の課題を把握することで、どのような施策を実施すべきかが理解できるはずです。
NTTコム オンラインでは、データ分析に関する無料セミナーやイベントを開催しています。また、Mixpanelについての各種資料もダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。