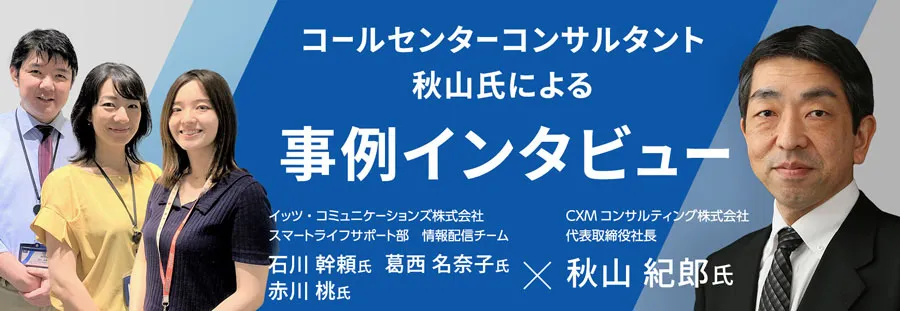

おもに東京都や神奈川県など東急電鉄の沿線地域でケーブルテレビやインターネットなどのサービスを提供するイッツ・コミュニケーションズ株式会社様。お客さまのお問い合わせに対して、電話、有人チャット、チャットボット、FAQといった幅広いチャネルを用意し手厚い対応を行っています。これらのチャネルの入口として導入したのが、NTTコム オンラインの「モバイルウェブ ビジュアルIVR」です。今回は、コールセンター領域のスペシャリストとして活躍するCXMコンサルティング株式会社 代表取締役社長 秋山 紀郎氏が、同社の石川氏、葛西氏、赤川氏に、対談形式で導入の経緯や効果についてお話をお聞きしました。
FAQやチャットなどチャネルを充実させたが、アクセスが伸び悩んでいる
コロナで問い合わせが増加。電話オペレーターの人手不足もあり、電話以外のチャネルの利用促進が必要だった
従来電話をしてきたお客さまの3~4%を、ビジュアルIVRに誘導できている
サポートの質を落とさず、電話以外のチャネルへ誘導することに成功
電話サポートとWebサポートの一体感が増し、特にWebサポートの質が向上した
画面の変更が容易なためPDCAを回しやすく、より一層の運用改善が実現しつつある
秋山氏:今日は、イッツ・コミュニケーションズ株式会社様のビジュアルIVR活用事例をお聞かせいただけるとのこと。どんなお話が飛び出すのか、大変、楽しみにしております。詳しいお話をお聞かせいただく前に、まずは、簡単に部署のご紹介をお願いできますでしょうか。
石川氏:私たちが所属するスマートライフサポート部 情報配信チームは、おもに、PBXをはじめとするコールセンター設備の管理、お客さま向けFAQやチャットボットといったWebシステムの運用、障害情報やメンテナンス情報のとりまとめを担当している部署になります。設備や仕組みを管理してコールセンター業務を下支えする、そんなポジションのチームです。
秋山氏:コールセンターにお電話いただかなくても、便利なWebサポートをご案内する目的でビジュアルIVRを導入されたとお聞きしています。そもそも、コールセンターの利用者はどのような方々で、どのような内容のお問い合わせが多いのでしょうか?
石川氏:ケーブルテレビ、インターネット、ガス、電気などのサービスにすでにご加入されている一般のお客さまがメインです。
お問い合わせ内容で多いのは、「ケーブルテレビの観られるチャンネル数を増やしたい」「インターネットの速度を上げたいがどうしたらよいか」といった内容です。現在は、お問い合わせのうち約75%について電話で対応し、25%については電話以外のチャネルでサポートしています。
秋山氏:どのような課題や経緯があり、ビジュアルIVRを導入されることになったのでしょうか?
石川氏:課題が浮上したのは3~4年前のことでした。当時からFAQにかなり注力しており、充実したものを作成していたつもりだったのですが、その割には見ていただけないということが続いておりました。どうしても電話でのお問い合わせに偏ってしまうことに悩んでいました。
そうこうしているうちに新型コロナウィルスの感染拡大により、テレワークが広がって、電話でのお問い合わせが一気に増えるという事態が発生しました。オペレーターの人手不足もあり対応しきれないことも多くなってしまい、ますます「電話以外のチャネルを充実させなければならない」「合わせて電話以外のチャネルに誘導する手段も必要だ」と考えるようになりました。こうした経緯で、2021年の8月に、有人チャットとチャットボットを導入し、続く同年12月にビジュアルIVRを導入しました。
ビジュアルIVRを導入することで、お客さまからの電話問い合わせを、有人チャットやチャットボット、FAQと適切なチャネルへ誘導することが可能になります。例えば「軽微な質問ならチャットボットへ」「よくあるトラブルならFAQへ」と、お客さまのお困りごとに適したチャネルへ誘導することができ、コールセンター側だけでなくお客さまの負担を大幅に減らすことにもつながると考えました。それでチャットを導入する段階で、計画的にビジュアルIVRを導入しようと決めていました。
秋山氏:なるほど。チャットを導入してからビジュアルIVRを導入したのではなく、もともとビジュアルIVRを導入する計画だったのですね。これはなかなかすごいことだと思います。多くの企業は、チャットやFAQなど新たに導入したチャネルが思ったほど利用されないという課題に直面すると、チャットのエンジンを入れ替えたり、それぞれのツールを強化したりと個別最適化の方向に走ってしまいがちです。そのまま迷走しまうこともあれば、困って困ってビジュアルIVRにたどり着くこともありますが、いずれにせよそこで停滞してしまうことが多いのです。そんななか、早い段階でビジュアルIVRに目を付けていらっしゃる。これは非常にセンスがいいと思いました。
石川氏:ありがとうございます。日頃からよく展示会に行ったり、コールセンター関連の専門紙を読むなどして情報収集をしたりしていましたので、ビジュアルIVRの有用性に気付けたのだと思います。
秋山氏:現在は、どのようにビジュアルIVRを活用していらっしゃるのでしょうか。
石川氏:お問い合わせのお電話に対し、まずは音声IVRで「Webでの解決でもよろしい方はこちら」とご案内し、承諾してくださった方にビジュアルIVRのURLを記載したSMSをお送りしています。
秋山氏:効果についてはいかがでしょうか? 実際に使ってみてのご感想なども交えてお聞かせください。
石川氏:いまのところ、お電話くださった方のうち、だいたい3~4%ぐらいの方がSMSを選んでくださっていますね。これを5%まで引き上げることが目下の目標です。
実際に使ってみてよかったと感じるのは、ビジュアルIVRで作成した画面が、スマホの画面に最適化されていて見やすいというところでしょうか。当社のお客さまは、約6割の方がスマホでコールセンターやWebサイトにアクセスするということがわかっています。ですから、スマホの画面が見やすいというのはとても大きなアドバンテージです。他社の類似サービスより使いやすく、有難いと感じています。
秋山氏:一般的なコールセンターの場合は50%程度が携帯電話からの入電だと言いますから、御社の場合は標準より少し携帯電話の方が多めですね。恐らく、テレビやPCを観ながら、スマホを操作する方が多いのでしょう。
なにか実際に運用してみて感じるメリットなどありますか?
葛西氏:どちらかというと副次的なメリットではあるのですが、ビジュアルIVRを導入したことで自社Webサイトの質が上がったと感じています。
ビジュアルIVRで振り分けられたその先には自社Webサイトがあり、Webサイトの情報が不十分だと、お客さまは、お電話をかけざるを得なくなってしまいます。
それでは、ビジュアルIVRを導入している意味や、Webサービスを強化してきた意味が薄れてしまいます。
やはり導入したからには、よりよくしていこうと思うようになり、従来より密にWebチームと連携ができるようになりました。
またWebチームも「Webサイトの掲載内容と入電傾向には相関関係があること」を改めて意識してくれるようになって、双方でよいコミュニケーションができていると感じています。
それから、ビジュアルIVRのメニューページの設定が簡単なところも気に入っています。慣れれば自分たちでも調整ができ、ページをつくることができます。実際にいま、メニューページを、お客さまのお困りごとに即してより細かくしようと調整しているところです。
秋山氏:それはいいですね。ビジュアルIVRの特長のひとつが、音声IVRに比べてカスタマイズがしやすいところです。PDCAを回しながらよりよくしていくという運用に適した仕組みです。他に、ビジュアルIVR導入後の変化について教えてください。
赤川氏:ビジュアルIVRを導入したことで、現場のオペレーターから「チャットやFAQの利用率が上がり、入電数が減ったと感じる」という声を聞くようになりました。これは率直に嬉しいですね。
最近は、ビジュアルIVRで作成した画面のURLをQRコードにして、このQRコードを総合パンフレットや重要事項説明書に掲載するという取り組みも始めています。これによって、電話からだけでなく紙媒体をきっかけにした流入が増え、ますますビジュアルIVRの利用率が上がっていると感じます。
石川氏:今後は、ビジュアルIVRとWebサービスの連携で、現在25%程度である「電話以外のチャネルの利用率」を30%まで上げたいと思っています。音声チャットボットや、ユーザー同士がナレッジを共有し合うコミュニティサイトのようなものなど新しいチャネルの導入を検討しつつ、「電話以外のチャネルの充実を図る」ことを目指し続けたいと考えています。
秋山氏:今後の広がりが楽しみですね。すべてのチャネルへの入口として、計画的かつ戦略的にビジュアルIVRを導入し、さらにPDCAを回しながら活用しようとされていらっしゃる。まさに「ビジュアルIVR」の理想的な活用法だなと感じました。本日は有意義なお話をお聞かせいただき、誠にありがとうございました。
<インタビュアーについて>
代表取締役社長 秋山 紀郎氏
マーケティング、セールス、サービスなどCRMソリューションを専門として、20年以上のコンサルティング経験があり、特に、顧客接点であるコンタクトセンターに関しては、戦略策定、設立・統合、ベンダー選定、評価、BPR、教育、業務改善など幅広い経験を保有。セミナーおよび寄稿も多数。