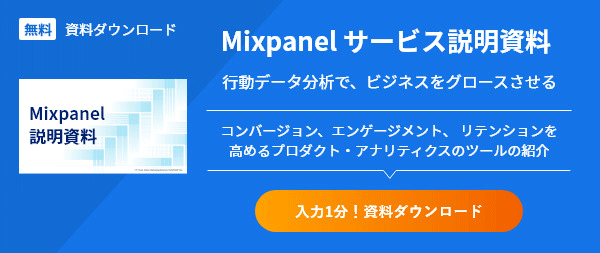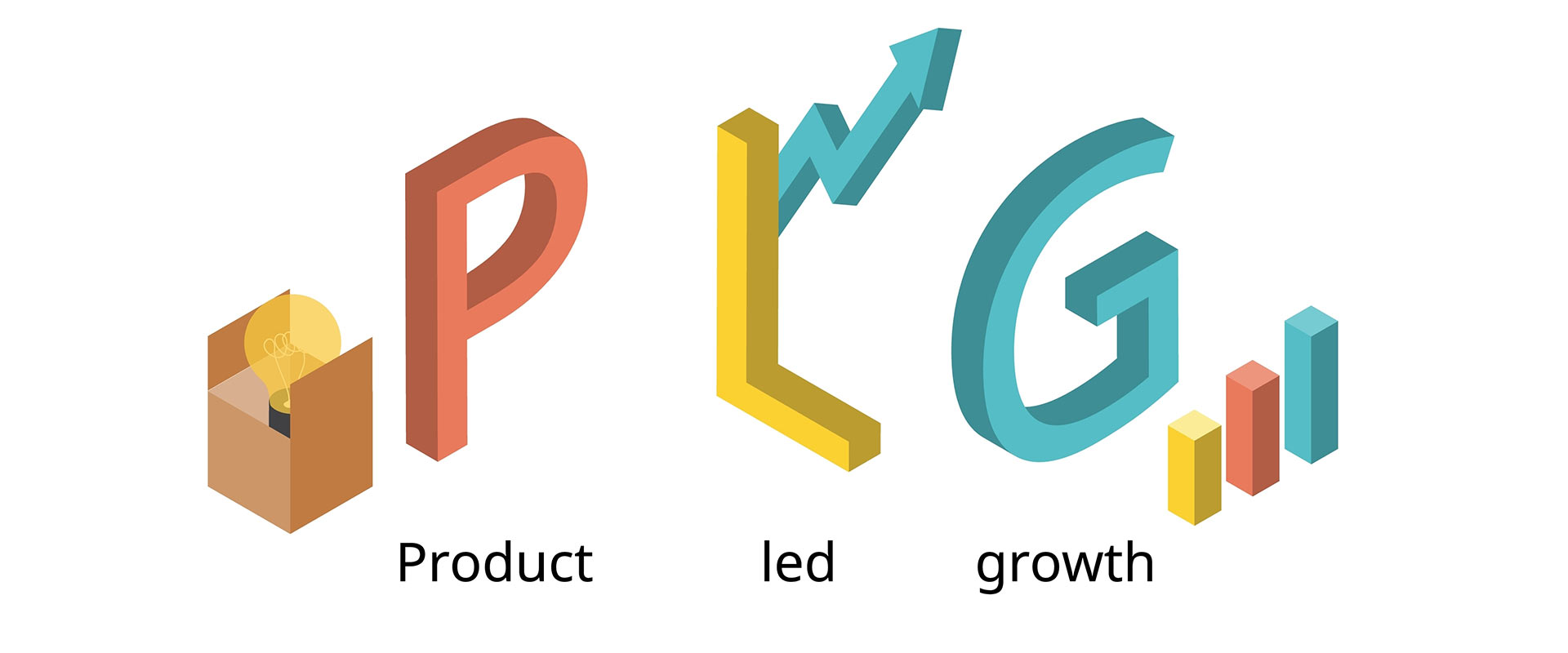
PLG(プロダクトレッドグロース)とは? 成功に必要な要素や企業の事例を紹介
- 目次
-
低コストで事業や利益の拡大を目指せるビジネスモデルとして近年注目を集めているのがPLGです。PLGは、従来の営業を主としたマーケティングと違い、プロダクト自体がもっている価値や魅力によってユーザー数と売り上げの向上が期待できます。
この記事では、PLGの概要から従来の事業モデルとの違い、PLGの成功に必要な要素、PLGの成功事例などを解説します。PLGの理解を深め、自社のマーケティングにおいても活用したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
- 記事の要約
-
- PLG(プロダクトレッドグロース)とは、プロダクトがもっている価値や機能が営業・マーケティングにつながっていくビジネスモデル
- PLGは、ユーザーが自ら学習したり、人に勧めたりして売り上げにつながるため、低コストでの事業拡大が期待できる
- PLGを成功させるには、成功体験を得られるデザインや直感的なUIデザイン、適切なCTAなどが重要
- PLGを導入する際は、MOATフレームワークを利用して自社のプロダクトを分析すると良い
PLG(プロダクトレッドグロース)とは?
はじめに、PLG(Product-Led Growth:プロダクトレッドグロース)の意味や概要、ビジネスモデル、SLGとの違いなどについて解説します。
PLG(プロダクトレッドグロース)とは「プロダクト主導の成長」
PLGとは、「プロダクトレッドグロース(Product-Led Growth)」を略した用語で、直訳すると、「プロダクト主導の成長」を意味します。プロダクトそのものがもっている機能・価値がそのままマーケティングや営業につながっていく販売戦略です。「プロダクト自身が新たにプロダクトを売る」事業モデルといえるでしょう。
たとえば、最初はユーザーに無料で利用してもらい、価値を感じた場合に有料版へと移行してもらうフリーミアムなどは、PLG型のビジネスモデルといえます。
プロダクトが営業やカスタマーサポート、カスタマーサクセスを行うため、マーケティング等に人を介する必要がなく、低コストを実現できるのがPLGのメリットです。
PLGとSLGの違い
PLGとSLGは、契約の成立にあたって、プロダクトと営業のどちらが主要な役割を果たすかが異なります。
SLGは、PLGによく似た用語の1つで、「Sales-Led Growth:セールスレッドグロース」を略した言葉です。SLGは、営業がプロダクトを売り込んでいく従来型の事業モデルを指します。PLGとSLGの違いを顧客獲得までのフローで比較すると、以下の通りです。
PLG
- 無料版などで見込み客(リード)にプロダクトに触れてもらう
- 実際に利用したリードがプロダクトに価値を感じる
- さらにプロダクトを利用するため有料版に移行する
- 契約成立
SLG
- マーケティング戦略によってリードを獲得する
- 営業がユーザーに対してプロダクトを売り込む
- 営業の説明やアプローチを聞いたユーザーがプロダクトの購入を決める
- 契約成立
SLGでは、会社や営業担当者が、直接ユーザーにプロダクトの魅力やメリットを伝えなければなりません。対して、PLGはまずユーザーにプロダクトに触れてもらうのが大切です。魅力的なプロダクトと購入・有料化の仕組みを用意しておけば、ユーザーが自ら学習したり、人に勧めたりして契約につながります。
PLGが注目されている背景
近年、PLGが注目されている背景として、SaaSを提供する企業が増えた点があげられます。SaaS(Software as a Service)とは、主にインターネットを通じて、低価格もしくは無料でユーザーにソフトウェアを提供するサービスです。SaaSの普及により無料や低価格のソフトウェアが一般的になったため、従来の買い切り型のパッケージソフトのように人員やコストをかけるのが難しくなりました。
また、SaaSによってユーザー側の導入ハードルも下がっているのも理由の1つです。以前であれば、企業がソフトウェアを刷新する際は、数ヶ月単位の時間を要していました。しかし、SaaSはインターネットを介して手軽に導入できるほか、ユーザーが自ら学びながら利用できる設計なので、新しいサービスを導入しやすくなっています。販売側の起業でも、従来のようなコストをかけずに、プロダクトの成長を実現できるようになりました。
このようなビジネスモデルの変化やテクノロジーの進化により、PLGの重要性が高まっており、注目を集めています。
PLGを成功させるために必要な要素
企業が自社のプロダクトでPLGを成功させるために必要な要素は、主に以下の通りです。
- 成功体験を得られる設計
- 直感的なUIデザイン
- 適切なCTA(Call To Action)
- データに基づいた製品・サービスの改善
それぞれの要素について、詳しくみていきましょう。
成功体験を得られる設計
PLGを成功させるには、早い段階でユーザーにプロダクトの価値を感じてもらうのが重要です。企業は、迅速なプロダクトの提供に加え、使ってすぐに価値を実感できるよう設計する必要があります。ユーザーが早くから小さな成功体験を得られれば、有料版にアップグレードする可能性も高まるでしょう。
プロダクトを使いやすくデザインするとともに、以下のようなテックタッチ(人員を介さないテクノロジーによるサポート)によるサポート体制を充実させましょう。
- ステップメール:会員登録や購入など一定のアクションをとったユーザーに対して、スケジュールに沿ったメールを送信。購入やプランのアップグレードを促す。
- チュートリアルの活用:ユーザーが自分で初期設定や初歩的な運用を行えるようチュートリアルを充実させる。
- AIチャットボット:ユーザーの疑問や問い合わせに対応するAIチャットボットを用意すれば、人的負担を軽減しながら、充実したカスタマーサポートが実現する。
- パーソナライズされたメッセージ:定型の文章だけでなく、顧客一人一人の行動に応じたメッセージを配信すれば、成約率向上が見込める。
ステップメールの詳しい送り方や作成のポイントについては、以下の記事もご覧ください。
「ステップメールとは?メリットや作り方、企業の成功事例を紹介」
直感的なUIデザイン
PLGでは、人を介さず優れたプロダクトを提供するため、直感的に利用できるUIが必要です。従来よりも商品・サービスの販売やカスタマーサポートに人の手をかけないPLGでは、UIが使いにくい場合、自己解決するためのハードルが高くなってしまい、ユーザーが離脱する恐れがあります。そのため、ユーザーが触れてみれば自然と使い方が分かる設計のプロダクトが求められているのです。
PLGでは、市場に出す前にプロダクトの完成度をユーザーにストレスを感じさせない程度まで高めておかなければなりません。リリース前にα版などの段階で、ユーザーフィードバックを収集し、製品に反映させながら改善していくのが大切です。
UI設計のコツや改善するポイントについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
「UX/UIの意味とは?優れたUX/UIの例や設計のコツ・改善のポイントを解説」
適切なCTA(Call To Action)
PLGにおいては、ユーザーの行動を促すCTA(Call To Action:行動喚起)が重要です。CTAとは、もともとWebサイトなどで使われていた言葉で、ユーザーを何らかのアクションに誘導するためのテキスト、イメージ、リンクなどを指します。
CTAは、PLGにおいても有効な考え方です。PLGでは、無料版から利用を始めるユーザーがほとんどであり、収益を上げるためには有料版にアップグレードしてもらわなければなりません。PLGを提供する企業でも、以下のようなCTA施策を取り入れてみると有効です。
- 特定の利用率・利用回数に達したときにメッセージを送信
- ユーザーの利用頻度に応じて、営業担当者に通知が届くような設定
- 有料版の価値を伝えるコンテンツの提供
データに基づいた製品・サービスの改善
PLGを成功させるためには、データに基づいた継続的な改善が必要です。行動に基づく施策を実施すれば、よりユーザーをアクションへと導きやすくなるでしょう。サービス内におけるユーザーの行動データを分析すれば、以下のように、さまざまな要素を把握できます。
- 正確なユーザーニーズの把握
- 離脱ポイントの特定
- 価値を生み出している機能の特定
- セグメントごとの利用傾向
- より良いUIへのブラッシュアップ(UIの改善点)
収集したデータを基に適切な施策を繰り返し行えば、ユーザーの利用継続率や有料版へのアップグレード割合などの改善が見込め、MRR(月間経常収益)の向上につながるでしょう。
ユーザーの行動分析およびMRRなどの収益分析については、以下の記事も合わせてご覧ください。
「ユーザー行動分析とは?8つのフレームワークと具体的な手法を解説」
「MRR・ARRとは?計算方法やSaaSでの重要性、改善する方法を解説」
PLGを成功に導くMOATフレームワーク
MOATフレームワークに基づいてプロダクトをチェックすれば、自社の商品・サービスがPLGに適しているのかを判断できます。「MOAT」とは、プロダクト分析に使用する以下の4つの言葉の頭文字をとった用語です。
- Market strategy:市場戦略
- Ocean conditions :ブルーオーシャン・レッドオーシャン
- Audience:意思決定者
- Time-to-value:プロダクトに価値を感じるまでの時間
それぞれの用語の意味について、さらに詳しく解説します。
Market strategy:市場戦略
はじめは、プロダクトを販売する市場(Market)での戦略です。市場戦略は「プロダクト価格」と「プロダクトの優位性」によって決定されます。PLGに適しているとされるのは、以下の2つの戦略です。
- 「ドミナント戦略」:市場にある既存のプロダクトよりも安価で使用方法が明快、機能的に優れているプロダクトの採るべき戦略
- 「ディスラプティブ戦略」:機能面は既存製品からダウングレードしているが、低価格になっているプロダクトの採るべき戦略
どちらの戦略も低価格と機能の分かりやすさ、シンプルさが強みとして発揮される点がPLGに向いています。一方、高価格だが特定のニーズに特化していく「差別化戦略」は、きめ細やかな対応などを求められるためPLGには不向きです。
Ocean conditions :ブルーオーシャン・レッドオーシャン
「Ocean conditions 」は、「競争環境」を意味しており、大きくブルーオーシャンとレッドオーシャンの2つに分けられます。レッドオーシャンとは、競合が多く競争の激しい市場で、ブルーオーシャンは、競争相手の少ない未成熟な市場です。両者のうち、PLGには、レッドオーシャンが向いています。
レッドオーシャンは成熟した市場で、既存のプロダクトに対する課題点や不満など、顧客のニーズが明らかになっているため、使い方のシンプルなPLGのプロダクトが価値を発揮しやすいでしょう。
反対に、ブルーオーシャンは競争相手が少ないものの、どのようなプロダクトが求められているかもはっきりしていない未成熟な市場です。潜在的な顧客ニーズの把握やプロダクトの価値説明などが必要になるため、PLGには不向きといえるでしょう。
Audience:意思決定者
プロダクトを利用するかどうか判断する顧客側の意思決定者です。PLGにおいては、ユーザーに実際にプロダクトを利用・体験してもらい、価値を感じてもらうのが大切になります。プロダクトの利用者と導入の可否を判断する意思決定者が同一の場合は、PLG戦略が機能しやすくなるでしょう。
反対に、2つが別々の場合は、意思決定を行う人間がプロダクトを体験しないため、ユーザーがいくら利便性を感じていても導入は難しくなってしまいます。特に、会社全体や複数部署が関係するプロダクトだと、1人の利用者だけで決められないケースが多く、意思決定者向けに導入を促すための異なるアプローチが必要です。
Time-to-value:プロダクトに価値を感じるまでの時間
「Time-to-value(プロダクト理解までの時間)」とは、利用者がプロダクトを体験してから製品に価値を感じるまでの時間です。Time-to-valueは短いほど良く、PLG戦略に適しています。サインアップが面倒だったり、初期設定に時間がかかったりすると、価値を感じる前にユーザーが離脱してしまう要因になるでしょう。PLG戦略を採る際は、プロダクトがユーザーにとって本当に分かりやすく、使いやすいものになっているかをよく検討しましょう。
PLGの成功事例
ここからは、実際にPLG戦略を用いて成功したとされる以下の3つのプロダクトの事例について解説します。
- オンラインミーティングサービス「Zoom」
- コミュニケーションチャットツール「Slack」
- SFA・CRMプロバイダー「Salesforce」
それぞれの詳細な事例や成功の要因についてみていきましょう。
オンラインミーティングサービスを提供する「Zoom」
「Zoom」は、アメリカのZoom Video Communications 社が提供しているオンラインでのミーティングサービスです。コロナ禍でリモートワークが普及し、オンラインミーティングの需要が高まったため急成長を遂げました。
Zoomは基本無料で利用でき、使用時間や機能の制限を解除するためには有料プランへの移行が必要となるビジネスモデルです。URLを送るだけで簡単に招待できるシンプルさと高い通話品質をあわせもっており、利用したユーザーは、簡単に価値や利便性を理解できるでしょう。
同時に、無料版での利用可能な時間は40分で、最適な会議時間とされる45分より若干短い点など、ユーザーに利便性をアピールしながらも、自然に有料版へアップグレードを促すPLGの仕組みになっています。
コミュニケーションチャットツールの「Slack」
「Slack」は、ビジネスに利用されるコミュニケーションチャットツールです。Zoomと同様にリモートワークの普及で多用されるようになったサービスで、2019年にはユーザー数が1,000万人を突破しました。
シンプルかつ使い勝手の良いサービスを無料で利用できますが、メッセージの表示期間を延長したり、さまざまな機能を利用したりしたい場合は有料版に移行する必要があります。業務に必要不可欠な存在として社内で広く使われるようになってから、さらに便利な機能を利用するため有料版へのアップグレードを促す方式で、シンプルながら有効なPLGとなっています。
SFA・CRMプロバイダーの「Salesforce」
「Salesforce」は、企業で使われるSFA(営業支援システム)・CRM(顧客情報管理システム)のプロバイダーとして世界的な成功をおさめた企業です。商品・サービスの売上向上を目指す営業モデル「The Model」の生みの親としても知られています。
Salesforceでは、自社製品を利用している企業に、Salesforce商品の営業から定着支援までを行ってもらうコンサルティングパートナーを提案。ビジネス上のメリットを与えて、ユーザーとしてのノウハウやスキルを活かしながら、自社製品の普及に貢献してもらっています。プロダクトそのものではなく、プロダクトのユーザーが主体になっているのが特徴的であり、PLGの1つの方法といえるでしょう。
PLGに貢献するプロダクトアナリティクス「Mixpanel」
「Mixpanel」は、顧客の行動データの収集・解析ができる、PLGに最適なプロダクト・アナリティクス分析ツールです。データの収集はもちろん、インサイト分析やフロー分析など、さまざまな分析機能を搭載しています。
データは視覚的に見やすく表示され、直感的に操作が可能です。データの統合やクロスチャンネル、担当者ごとのダッシュボードも作成できます。さらに、他サービスとの連携も充実しています。「Mixpanel」を利用して顧客の行動を正しく分析できれば、無料プランから有料プランへの行動パターンの把握や転換率の向上など、課題を把握しやすく解決策を導きやすくなるでしょう。
導入事例|DocuSign
DocuSign様は、アメリカに本社を置く電子契約サービス運営企業です。電子契約分野で全世界7割のシェアを誇ります。
DocuSignでは、「Mixpanel」を活用し、製品のどの機能が無料ユーザーからプレミアムへの移行に貢献しているかを把握しています。また、ファネル分析やインサイト分析を使い、A/Bテストの効果測定にも活用。さらに、新機能のリリース前後でユーザーの行動にどのような変化が起きるかの分析にも利用しています。結果、新規アカウント作成数15%増加、有料ユーザーへのグレードアップ率10%を実現しています。
導入事例|DocuSign 様
PLGは低コストで事業拡大を目指せる戦略
PLGは、通常のマーケティングと異なり、プロダクトそのものがもっている価値によってユーザーや利益を上げていけるビジネスモデルです。従来型の事業モデルと異なり、人を介して顧客への売り込みを行わなくても良いため、低コストで売上向上や事業拡大を目指せる戦略といえます。
PLG戦略を成功させるには、顧客がどのように無料から有料プランに移行するか、行動パターンの把握が欠かせません。「Mixpanel」は、顧客の行動データ収集・分析するのに最適なツールです。自社でもPLG戦略を取り入れたいと考えている場合は、ぜひ導入を検討してみてください。