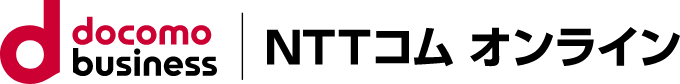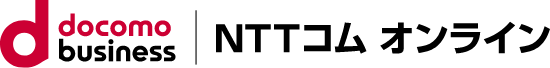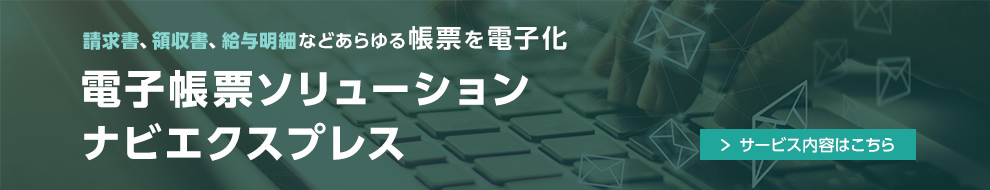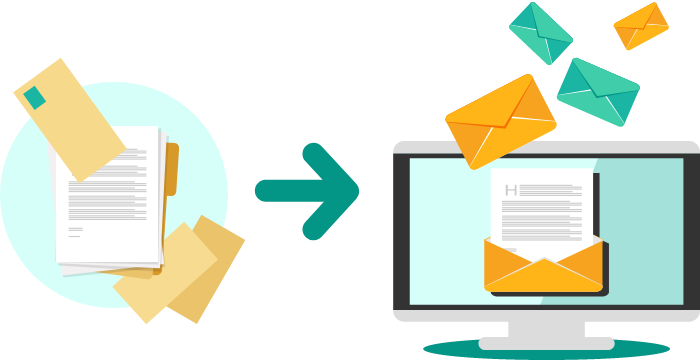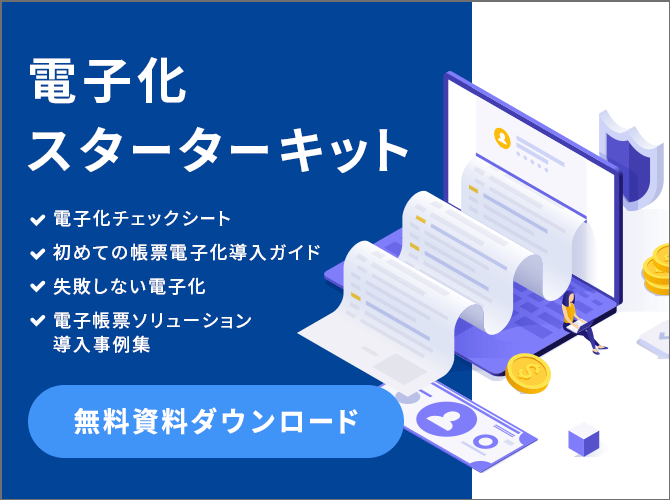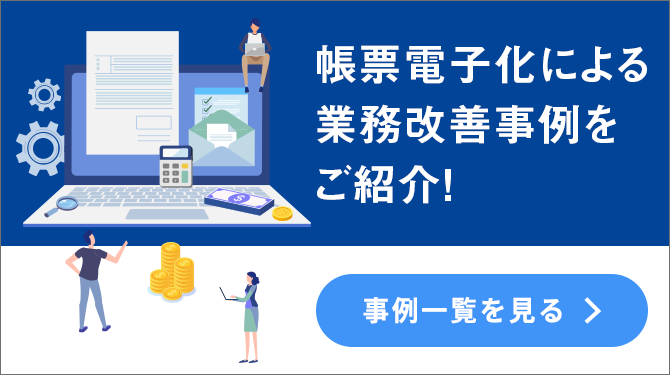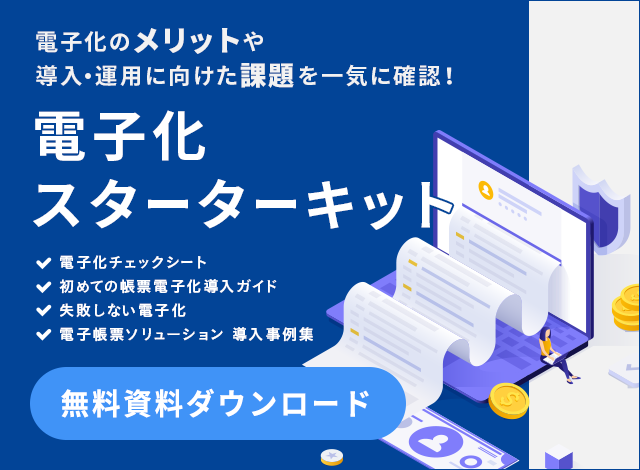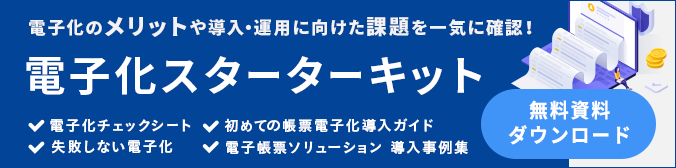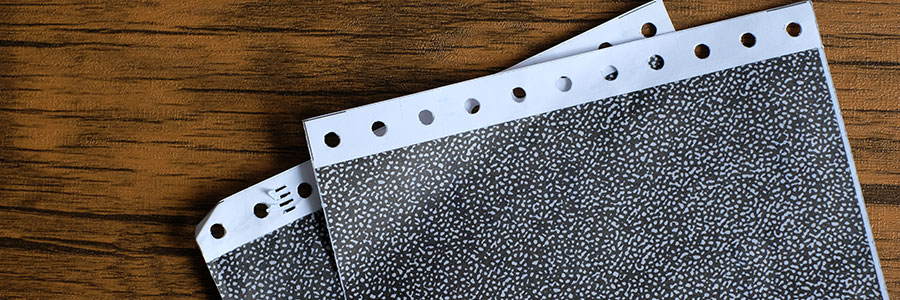
更新日:2024/03/21(公開日:2020/11/11)
帳票、書類の電子化
労働条件通知書の電子化で業務効率アップ
労働基準法で定められている決まりとして、労働契約締結時に「労働条件通知書」を書面で通知する義務があります。しかし、人事担当者の業務は幅広く、書面通知の業務も負担が大きい作業の1つでした。そこで、厚生労働省は、労働条件通知書を「条件付きで電子化しても良い」と規制緩和しました。この記事では、「労働条件通知書の電子化をするために必要な条件」や「注意すべき点」など詳しく紹介します。
- 正社員、派遣社員、アルバイト、パートなどで従業員を雇用する際には労働条件通知書を交付する必要がある
- これまで書面で取り交わされてきたが、電子化が可能となり、メールなどで送れるようになった
- 電子化をするには契約を結ぶ従業員が希望しているかなどの確認が必要
- 電子化には専用のシステムやツールを使用することで、コストや手間が削減でき、誤送信などのミスが防げるようになる

2019年から電子化解禁に!「労働条件通知書」
正社員・派遣社員・パートなど従業員を雇う際の労働締結では、労働条件通知書を交付しなければなりません。2019年3月までは書類による交付をするようにと決められていましたが、2019年4月1日以降は電子化も可能となりました。こちらでは、労働条件通知書の電子化をするための条件などについて紹介します。
書類交付が義務だった労働条件通知書
労働基準法の第15条には、企業は労働締結をする際、労働条件について書面で通知するようにと定められています。書式は特に決められていませんが、必ず記載しなければならない内容は決められています。たとえば、「賃金」「契約期間」「勤務時間や勤務地」「業務内容」などです。ちなみに、労働条件通知書は日本人の従業員だけではなく、外国人の従業員に対しても交付する必要があります。その場合、日本語と英語(もしくは、その従業員の母国語)で記載するほうが無難です。
2019年4月から電子化が可能に
必ず書類で交付しなければならなかった労働条件通知書は、2019年4月1日から条件付きではあるものの、電子化することが可能となりました。これにより、業務の負担が軽減されたという声も多くあがっています。電子化する方法として認められているのは、メール・FAX・LINE・メッセンジャーなどです。
労働条件通知書の電子化に伴う条件とは
労働条件通知書の電子化が可能になったことで業務の効率化や負担軽減につながります。しかし、必ず電子化で交付できるわけではありません。電子化で交付するためには、3つの条件を満たす必要があります。
労働契約を結ぶ従業員が電子化を希望している
「必ずしも電子化で交付できるわけではない」理由は、労働者によって書面で交付してほしいと希望する人もいるからです。電子化の条件の1つとして、「労働条件通知書を交付される労働者が電子化に納得し、希望していること」というものがあります。労働者が書類で交付してほしいと希望していれば、必ず書面で交付しなければなりません。
閲覧できるのは本人のみである
電子化して交付するにあたり、「交付する本人だけが閲覧できる状態で送信すること」が条件となっています。労働条件は労働者によって違うため、誰でも見ることができる状態で送信するのは避けましょう。たとえば、共有フォルダでアップロードすると誰でも閲覧できてしまうので違反行為です。
書面として出力できる
労働条件通知書は、労働者が希望した際、いつでも書面として出力できるものでなければなりません。「期限付きのファイル」「特定の電子デバイスでのみ閲覧できる」「SNS上(印刷を前提をとしないツール)で交付する」などは書面として出力できないため、電子化の要件を満たしていないことになります。
労働条件通知書を電子化するメリット
労働条件通知書を電子化した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。
業務の効率化
労働条件通知書を電子化することで、通知書を書面で作成するより手間と時間がかからなくなります。大企業で雇用する人数が多いほど書面作成の負担は大きいため、電子化によって業務負担の軽減が期待できます。
コスト削減
労働条件通知書を書面で交付している場合、印刷・封筒・切手などの費用がかかります。電子化すると、それらの費用は不要になるのでコスト削減につながります。労働条件通知書は決められた期間保管をしておく義務があるので、電子化で保管スペースが不要になる点も大きなメリットです。それまで保管に使用していたスペースはほかの業務のために利用できるようになります。
管理しやすくなる
膨大な量が保管されている中から特定の人物の書類を見つけだすのは大変ですが、電子化することですぐに必要な情報を探しだせるようになります。企業側だけではなく、労働者側も書類の紛失をする心配がなくなるので管理しやすいです。
労働契約通知書を電子化する際の注意点
労働条件通知書の電子化には、法令遵守も含め、いくつかの注意点があります。事前によく確認して準備をしておきましょう。
電子化をしても労働条件通知書の内容は変わらない
書面から電子データへと形式が変わるだけで、労働者に通知する内容自体は変わりません。電子化する際に簡素化しないように注意してください。
また、書面から電子データへ変更する機会に、現在の法令と照らし合わせて不備がないように、あらためて確認することをおすすめします。
2024年4月からは労働条件明示のルールが変わり、すべての労働者に対しては就業場所や業務変更の範囲を、有期契約労働者に対しては更新上限の有無と内容を明示しなければなりません。
また、無期転換ルールに基づいて無期転換申込権が発生した際の契約更新時には、無期転換後の労働条件の内容などを記載する必要があります。
出典:厚生労働省|2024年4月から労働条件明示のルールが変わります
電子帳簿保存法を遵守して保管する
公的には示されていませんが、労働条件通知書は「電子取引」に該当する可能性があり、電子帳簿保存法に則った保存が必要という見解もあります。
電子帳簿保存法とは「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等」に関する法律で、領収書や帳簿などの国税関連の書類を電子データで保存する際のルールが明示されています。
労働条件通知書が電子取引に該当する場合、義務とされている保管期間は7年間となっています。労働条件通知書の保管義務は5年間とされていますが、念のため7年間保管していたほうが良いでしょう。
電子帳簿保存法での保存方法として以下があります。
- 電子的に作成した書類をそのまま保存する「電子帳簿保存」
- 紙で作成した書類をスキャニングして保存する「スキャナ保存」
- 電子的に授受したデータをそのまま保存する「電子取引データ保存」
作成した労働条件通知書は電子帳簿保存もしくはスキャナ保存で保管し、労働者から受領した電子通知の希望や労働契約締結の同意はスキャナ保存もしくは電子取引データ保存で保管するのが良いでしょう。
電子帳簿保存法についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
【2024年施行】電子帳簿保存法の改正内容をわかりやすく解説|制度の概要から紹介
電子化の条件を満たしているかチェックする
上述のように、労働条件通知書はただ電子化すれば良いわけではなく、いくつかの条件を満たさなければなりません。具体的には、「希望の有無を確認」「本人しか閲覧できないようにする」「出力できるデータでの送信」という3条件を満たす必要があります。
以下のような方法で確認や送信をすると、ミスを避けられます。
労働者が電子交付を希望しているかの確認
希望の確認については採用時など労働条件通知書交付前に、「従来通りの書面」「メール」「FAX」のいずれを希望するか確認し、書面に残しておくと良い。
本人のみが閲覧できる状態での送信
通知する際には複数人がアクセスする共有フォルダを使用したり、複数人にまとめてメールを送ったりしないように注意しましょう。本人しか見ることがないアドレスなどに、パスワードを設定して送るなどの注意が必要です。
書面として出力できるデータでの送信
受信者の環境によって、閲覧・出力できるデータ形式は異なるため、PDF化したファイルを添付して送るのが良いでしょう。SNSのメッセージ機能は印刷を前提としていないためおすすめできません。
事前に交付日を伝える
電子化した労働条件通知書を交付する場合、何らかの問題が起きて労働者本人に届かない可能性があります。その対策として、事前に労働条件通知書の送付方法や交付する日付を伝えておくことが重要です。もし、当日になっても届かなかった場合は、連絡をするように決めておきましょう。送付する方法によっては「送受信数が多く、ファイルが行方不明になる」「一定期間ごとに自動消去される」などもあるため、早めに出力・保存をするように前もって伝えておくと安心です。
労働者が通知書を閲覧したか確認する
労働条件通知書を交付しても、労働者が閲覧したことを確認しなければ通知したことになりません。メールでの送信の場合、相手が閲覧していない可能性があるので、必ず確認しましょう。
相手がメールを見ていないケースには、迷惑メールのフォルダに入ってしまった場合や、保管期限が経過して削除されてしまった場合などがあります。
トラブルを避けるためにも、労働契約の締結に同意すると記載した文面を、メールやSNSのメッセージなどで送り返してもらい、保管しておくようにしてください。
また、労働者に返信をしてもらう際も、印刷・保存がしやすいように、添付ファイルで送り返してもらうのをおすすめします。
労働条件通知書を作成する際のポイント
労働条件通知書を電子化する際、注意すべき点を知っておきましょう。
労働条件通知書を交付するタイミングはいつ?
交付のタイミングは企業によって違いますが、ほとんどの場合、内定から入社するまでの間や入社日当日などに行われます。労働契約の締結はあくまでも入社日に行うため、当日交付にこだわる企業もあります。労働条件について入社前に知りたい場合は、その旨を伝えて交付してもらうことも可能です。
労働条件通知書に記載すべき内容
労働条件通知書は書式に決まりはありませんが、必ず記載しなければならない内容があります。
労働期間や有期労働期間の更新の基準
労働期間については必ず記載する必要があります。派遣社員やパート・アルバイトなどは期間限定で就業していることもあるため、労働期間や期間終了後の更新についてハッキリしておかなくてはなりません。更新可能な場合は「条件があるのかないのか」「条件がある場合はどのようなものなのか」などを記載します。
就業場所・業務内容
労働契約なので、就業場所や業務内容についての記載も必須です。業務内容は配属部署などで、ほかにも始業就業時間や休憩時間、所定時間外労働などについての記載も必要です。
賃金や保健関係(社会保険・雇用保険など)
労働契約をする際に重要な項目の1つが賃金です。収入は生活していくために必要なものなので、きちんと納得して契約しなければなりません。また、休日や休暇なども働くうえでは重要な項目であり、必須記載事項となっています。何かあった際に必要になる社会保険や雇用保険なども労働条件通知書に必ず記載すべきものです。
退職に関する事項
事情があって退職しなければならないケースや定年などもあるため、退職に関する項目も記載すべき点です。事情があって退職する場合、引継ぎの問題もあるため、いつまでに伝えておかなければならないのか記載しておくとわかりやすいです。さらに、定年後やその後の更新をできるのかどうかなども記載必須となっています。
パートや派遣社員の場合、昇給や退職手当・賞与の有無・賃金の見込み額などの記載もします。労働条件通知書は正社員だけではなく、パートや契約社員を含む労働契約を締結する全従業員に対して交付しなければなりません。
日付や担当者名を記載する
労働条件通知書には交付する従業員の氏名を記載しますが、作成者の氏名も記載しておくほうが安心です。万が一、作成した労働条件通知書に不備があった場合など、記載していない場合、トラブルにつながるケースもあるからです。作成者の名前以外では、企業名なども記載しておきましょう。これらに関しては記載義務はありませんが、トラブル防止という意味で詳細な情報を書いておきましょう。労働条件通知書は、厚生労働省に雛型があるため、参考にできます。
労働条件通知書と雇用契約書は違うもの
労働条件通知書と間違えられやすいものとして「雇用契約書」があります。この2つの違いについて紹介しましょう。
雇用契約書とは?
「雇用契約書」は、民法第623条で定められている雇用主と労働者の間で交わす契約書です。双方の間で雇用契約に関して納得し、合意したことを証明するものとなっています。雇用契約書には「労働期間」「就業場所や業務内容」「始業・終業時刻や残業の有無」など労働に関する詳細を記載します。特に、賃金の項目では賃金の計算方法や支払い方法、賃金の締切、支払い時期も記載することが多いです。
雇用条件通知書と雇用契約書の違い
雇用条件通知書と雇用契約書は記載する項目が同じものもあり、間違えられることも少なくありません。しかし、この2つは別のものなので、どのような違いがあるのか紹介します。
雇用契約書の交付は義務ではない
大きな違いとして、原則書類で交付する義務がある雇用条件通知書に対し、雇用契約書は義務ではない点があげられます。雇用契約書は、民法第623条で契約を結んでいることで有効となる点が定められています。義務ではないので口頭でも問題はなく、契約書を交わさなくても法律違反にはなりません。ただ、契約内容を口約束で決めると、後々、「言った・言わない」という問題が起きる可能性もあるため、作成したほうが安心です。
一方、雇用条件通知書は労働基準法で必ず交付しなければならないものとして、義務化されています。もし、労働契約を結んだにも関わらず、労働条件通知書を入社日当日までに交付しなかった場合、労働基準法に違反しているとして30万円以下の罰金が科せられます。有期労働期間で更新をするケースでは、更新する度に労働条件通知書を交付することになります。更新時の交付は義務ではないため、交付しなかったとしても法律違反にはなりません。しかし、更新後の条件がはっきりしていなければトラブルになる可能性があるので、毎回交付するのが通例です。
「一方的に送る」か「同意が必要」かという違いがある
労働条件通知書は労働に関する条件を細かく記載し、義務として交付しなければなりません。そのため、企業側(雇用主側)から一方的に送る必要があるものです。しかし、労働契約書は契約内容を読み、納得したことを証明する書類なので双方の同意が必要です。そのため、労働契約書には必ず署名・捺印もします。
労働条件通知書は保管義務がある
労働基準法第109条に「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない」と記載されています。交付しなかったときの罰金同様、保管していなかった場合も罰金30万円を支払わなくてはなりません(労働基準法第120条)。罰金は労働条件通知書の保管をしていなかった人数分支払う必要があるので、たとえば、10人分の労働条件通知書を保管していなかった場合は300万円の罰金を支払うことになります。
労働条件通知書や雇用契約書の一般的な形式
労働条件通知書や労働契約書を交付する際には、3つの形式があります。
労働条件通知書のみ交付する
雇用契約書は交付する義務がないため、必ず交付しなければならない労働条件通知書のみを作成します。この形式にする企業は少なくありませんが、トラブル防止のためには、できるだけ雇用契約書も交付しておいたほうが無難でしょう。
労働条件通知書と雇用契約書をそれぞれ交付する
労働条件通知書を交付し、それとは別に、雇用に関する細かな条件や就業規則で重要な部分を抜粋してまとめた契約書を作成する企業もあります。トラブル防止という意味では非常に有効ですが、雇用締結の度に交付することになるため、手間と時間が必要になります。
労働条件通知書と雇用契約書を1枚にまとめる
時間や手間をなるべくかけないように工夫し、「労働条件通知書兼雇用契約書」を作成する企業もあります。基本は労働条件通知書で作成し、書類の項目の1つに「そのほか」を設けるのです。「そのほか」の項目には、「社会保険の加入状況」「雇用保険の適用の有無」、そのほかに必要な事項の記載を加えます。さらに、日付や住所、名前などの署名欄スペースも作成して、雇用契約書としての役割も兼ねる書類にします。
労働条件通知書の電子化には「ナビエクスプレス」
「ナビエクスプレス」は請求書や納品書、領収書、支払通知書などの帳票類以外にも、労働条件通知書の電子化、メール送信にも対応した電子帳簿ソリューションです。書面での送付と異なり、紙代やインク代などのコストを削減でき、業務の効率化も実現できます。
CSVファイルを送ればPDFファイルを自動作成できるうえ、 今まで使用してきたフォーマットをそのまま使用できます。各種インターフェースを取りそろえているため、システム連携もカスタマイズ可能です。
また、SSLによる暗号化や明細書ごとのパスワード付与などのセキュリティがあり、安全に書類を送信できます。
送信状況や開封状況をリアルタイムで確認できるため、送った相手が見ていないなどのトラブルを避けられるので、労働条件通知書での活用におすすめです
導入事例:人材派遣会社 様
派遣社員の労働条件通知書を紙出力して直接または郵送で渡していましたが、手間や時間、コストが相応にかかっていました。
そこで、法令で電子化が可能となったことを機に、ナビエクスプレスを活用して電子化に切り替えました。その結果、印刷代や紙代、配達証明代などのコストが削減でき、手渡しをする手間も省けるようになり、業務効率が改善しています。また、労働条件通知書の作成から配信、受取確認までワンストップで行えるようになりました。
業務の負担軽減に有効な労働条件通知書の電子化
2019年4月から可能となった労働条件通知書の電子化は、3つの条件「本人のみ閲覧可能」「書面として出力可能」「労働者が希望している」をクリアしている必要があります。また、交付や保管をしていなければ罰金が科せられるため、注意が必要です。しかし、業務の効率化やコスト削減などのメリットもあるので、業務の負担を軽減するために労働条件通知書の電子化をするのも良いのではないでしょうか。
「ナビエクスプレス」は、労働条件通知書に加え、請求書、領収書、給与明細などにも活用しています。電子化に役立つ資料をご用意していますので、ぜひ下記のリンクからご確認ください。
【
帳票、書類の電子化
】
最新のコラム

2025/06/19

2025/06/16