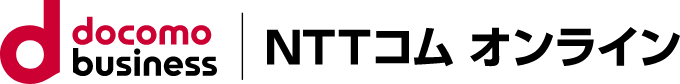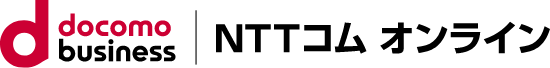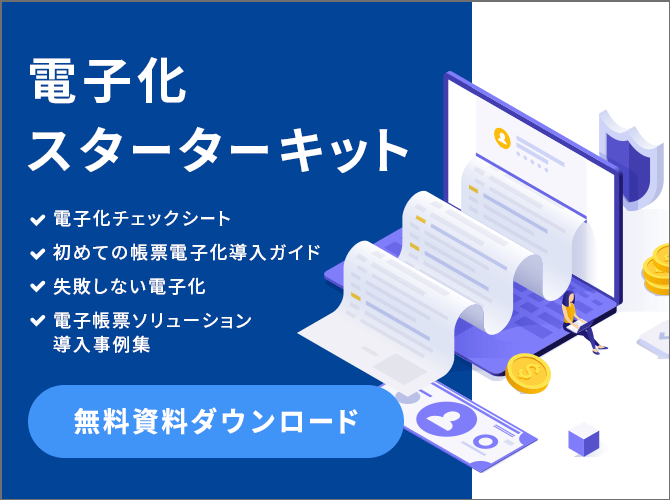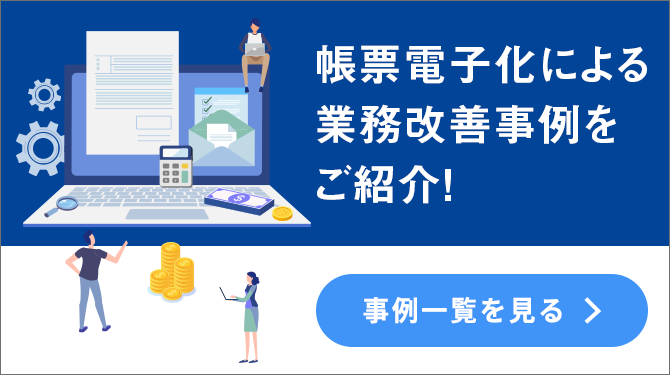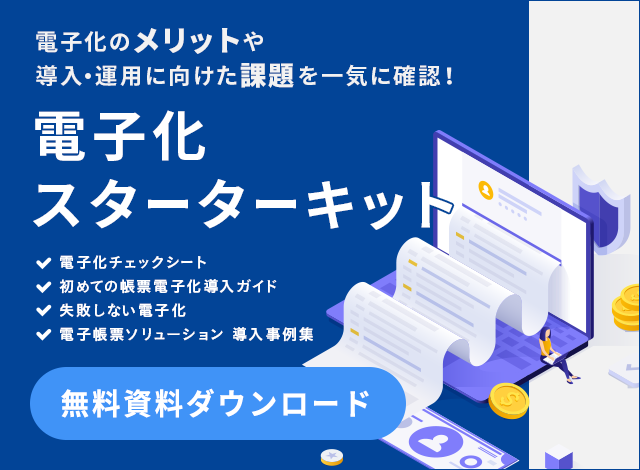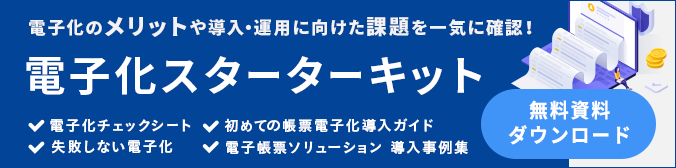更新日:2024/02/05(公開日:2023/08/01)
法令遵守(電子帳簿保存法、インボイス制度など)
【2024年施行】電子帳簿保存法の改正内容をわかりやすく解説|制度の概要から紹介
請求書等の電子配信にお悩みはございませんか?
基幹システムに手を加えず連携し、電子化をご提案いたします。
商取引の全帳票を電子化し、即日到着でコスト削減・業務効率化を実現します!
⇒ まずは電子帳票ソリューション ナビエクスプレスの資料を見てみる
DX促進やペーパーレス化に伴い、帳簿類の電子化を検討している企業さまも多いのではないでしょうか。とりわけ電子取引における電子保存の義務化により、電子帳簿保存法への対応は迅速に取り組むべき課題の1つとなっています。
そこで本記事では、まず電子帳簿保存法の概要を、そして近年の改正内容について詳しく解説します。また、電子帳簿保存法に対応するメリットやその際のポイントなども紹介するのでぜひ参考にしてください。
- 電子帳簿保存法は帳簿・書類の電子保存を認める法律
- 電子帳簿保存法には「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」という3つの区分があり、それぞれ対象書類や保存要件が異なる
- 電子帳簿保存法の改正内容は2024年1月1日から施行される

電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法とは、各税法により保存が義務付けられている帳簿・書類の電子保存を認める法律です。コストの削減や業務の効率化などを目的として制定され、文書を電子データとして保存する際の手続きや要件などが定められています。
同法には、書類の作成や保存方法により「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」という3つの区分があります。また、1998年7月の施行以降、改正が重ねられてきました。
電子帳簿保存法の対象者
電子帳簿保存法は、普通法人や公益法人、個人事業主など、規模や業種に関係なく事業を営むすべての人に適用されます。すべての事業者には、法人税や所得税などを申告し納税するにあたり、各税法の規定に則って帳簿や書類を作成・保存する義務があるからです。
書類や取引方法などによっては従来通り紙での保存もできますが、電子取引された書類に限っては電子保存が義務化されました。そのため、より多くの事業者が迅速な対応を求められています。
電子帳簿保存法が対象外のケース
電子帳簿保存法は「電子取引を通じて取引された国税関連の文書のデータ保存」について規定した法律であり、企業・個人事業主を問わず適用されるものです。一方、電子取引をしていない企業・個人事業主、要するに紙でのやり取りしか行っていない事業者については、文書を電子データで保存する義務はありません。
該当しない場合、電子帳簿保存法に対応しなくても問題ありませんが、電子化は国が主体となって推進している取り組みです。取引先の企業も電子化を進めることを踏まえれば、できるだけ早急に対応したほうが事業成長において有利と考えられるでしょう。
電子帳簿保存法の区分と対象書類
電子帳簿保存法の3つの区分内容と対象書類を解説します。
1|電子帳簿等保存(任意)
電子帳簿等保存では、自身が電子計算機(パソコン等)で作成した帳簿・書類の電子保存を認めています。電子データはCDやサーバーなどの媒体へ、もしくは電子計算機出力マイクロフィルム(COM)での保存が可能です。
また、一定範囲の帳簿を事前に申告したうえで「優良な電子帳簿」の要件を満たして保存すると、過少申告加算税の軽減措置を受けられます。
対象書類
対象書類は、パソコンや会計ソフトを使用して作成した「国税関係帳簿」と「国税関係書類」です。
国税関係帳簿には、仕訳帳や総勘定元帳、売掛帳、買掛帳などがあります。国税関係書類には「決算関係書類」と「取引関係書類」の2種類が含まれます。決算関係書類は貸借対照表や損益計算書など、取引関係書類は請求書や注文書、見積書、契約書、領収書などです。
電子的に作成したデータは、印刷し紙でも保存できます。
2|スキャナ保存(任意)
スキャナ保存では、紙に印刷された一部の国税関係書類やその写しをスキャナ等で読み取って画像データを保存します。読み取りには、要件を満たしたデジタルカメラやスマートフォンなども使用できます。
対象書類
スキャナ保存の対象書類は、国税関係書類のうち取引関係書類だけです。
取引関係書類には、契約書や領収書といった資金や物の流れに直接関係する「重要書類」があります。また、見積書や検収書などの「一般書類」も含まれます。書類を自社で発行したか受領したかを問わず、希望すればスキャナ保存が可能です。
一方、国税関係帳簿や決算関係書類はスキャナ保存できません。売上伝票などの国税関係書類とはみなされない伝票類も対象外です。
3|電子取引(義務)
電子的な取引により授受した書類のオリジナルデータを、送った側も受け取った側も、電子データのまま保存しなければならない制度です。従来はプリントしたうえでの紙保存も可能でしたが、2022年の法改正により電子保存が義務化され、紙保存は廃止されました。(2023年12月31日までは宥恕〘ゆうじょ〙措置があり、2024年1月1日以降は猶予措置が整備されるので、実質的には紙保存も可能。)
対象書類
電子保存は、EDIやインターネット、電子メール、クラウドサービスなどを利用し電磁的方式で行われた取引すべてに適用されます。
例えば、メールに添付された請求書のPDFファイルや、ダウンロードした納品書、サイトで表示された受領書のスクリーンショットなどがあります。クレジットカードや交通系ICカード、インターネットバンキング、スマートフォンアプリによる決済などの利用明細類も対象です。
電子帳簿保存法の対象外となる書類
国税関係帳簿や書類に該当しない文書や伝票類は電子帳簿保存法の対象外です。
また、初めから手書きで作成された国税関係帳簿類は、電子データでの保存が認められていません。スキャナ保存の対象外となるため、紙のまま保存します。
さらに、書類の作成や取引に電子システムを一切使用していない場合は、従来通り紙での保存が可能です。
電子帳簿保存法改正の目的
経済社会におけるデジタル化やDXが進むにつれ、国税関係帳簿・書類の保存に係わる負担を軽減するために電子帳簿保存法の改正が重ねられてきました。
そもそも同法には、電子システムを用いた帳簿類作成が普及し、電子保存の需要に対応するために創設されたという背景があります。しかし、デジタル技術が進歩し働き方が多様化する一方で、電子帳簿保存法への対応はハードルが高く、なかなか電子化が進みませんでした。そこで、段階的に手続きや要件等を緩和し、電子保存に対応しやすくするための見直しが行われてきたのです。
電子帳簿保存法の詳しい変遷に関してはこちらもご覧ください
電子帳簿保存法の保存要件を確認
電子帳簿保存法の保存要件は区分ごとに異なるので、それぞれ概要や注意点について解説します。なお、すべての要件や状況別の細かい対応までは掲載していないので、詳細を調べたい方は国税庁のホームページも参照してください。
出典:電子帳簿保存法一問一答(Q&A)電子帳簿保存の保存要件|国税庁
電子帳簿等保存の保存要件
電子帳簿等保存における保存要件は、以下の通りです。
- 記録事項の訂正・削除を行った際、その履歴が残るシステムを使用する
- 通常の業務処理期間を経過後に入力した際、その事実を確認できるシステムを使用する
- 電子化した帳簿記録事項とそれに関連する他の帳簿の記録事項との間で、相互に関連性が確認できる
- システム関係書類(システム仕様書や操作説明書など)を備え付けている
- 保存場所に電子計算機・プログラム・ディスプレイ・プリンター・各機器の操作マニュアルを備え付けて、画面および書面を整然・明瞭かつ速やかに出力できる
- 検索条件
6-1 取引年⽉日・取引金額・取引先によって検索できる
6-2 日付または金額の範囲指定によって検索できる
6-3 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件で検索できる - 税務職員の求めに応じて電子データのダウンロードができる
出典:はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存(電子帳簿等保存)|国税庁
なお、具体的な要件は「優良な電子帳簿」と「その他の帳簿」によって若干異なるので、そちらも押さえておきましょう。
「優良な電子帳簿」の満たすべき要件
「優良な電子帳簿」と認められるためには、上記1~6の保存要件を満たす必要があります。ただし、要件7に沿ってダウンロードの求めに応じることができる場合、要件6-2および6-3は不要です。
優良な電子帳簿に関する要件を満たせば、過少申告加算税が5%軽減されるほか、個人事業主なら65万円の青色申告特別控除の対象になります。
「その他の帳簿」の満たすべき要件
「その他の帳簿」と認められるためには、上記4・5・7の要件を満たす必要があります。ただし、優良な電子帳簿の要件1~6をすべて満たしている場合、要件7は不要です。
その他の帳簿については、優良な電子帳簿のような優遇措置はありません。その代わり満たすべき要件も少ないので、電子データの保存で手間をかけずに済みます。
書類の保存で満たすべき要件
国税関係の「書類」と認められるためには、その他の帳簿と同じく上記4・5・7の要件を満たす必要があります。ただし、要件6-1および要件6-2に沿って取引年月日や取引金額で検索でき、なおかつ日付・金額に関する範囲を指定して検索できる場合、要件7は不要です。
書類にも保存要件が定められているため、一緒に覚えておきましょう。
スキャナ保存の保存要件
スキャナ保存の保存要件については、契約書・納品書・請求書・領収書といった「重要書類」と、見積書・注文書・検収書といった「一般書類」で差異があります。
まずは両方が満たすべき要件をまとめたので、きちんと押さえておきましょう。
【重要書類・一般書類】
1. 解像度200dpi相当以上で読み取ること
2. スキャンデータを整然・明瞭かつ速やかに出力できる
3. スキャナ保存のシステム関係書類(システム概要書や操作説明書など)を備え付けている
4. 一の入力単位ごとにタイムスタンプを付与する(編集履歴が残るシステムの使用でも可)
5. スキャンデータの訂正・削除の事実やその内容を確認できるシステム、もしくは訂正・削除ができないシステムを使用する
6. 検索機能を確保する
6-1 取引年月日またはその他の日付・取引金額・取引先での検索
6-2 日付または金額に係る記録項目について範囲を指定した検索 ※
6-3 2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた検索 ※
※税務職員の求めに応じてスキャンデータのダウンロードができる場合は不要
重要書類は上記1~6の要件に加えて、以下の追加要件も満たす必要があります。
【重要書類】
7. 業務処理に係る通常期間を経過してから速やかに入力する
8. スキャンデータとそれに関連する他の帳簿の記録事項の間で、相互に関連性がある
9. 赤色・緑色・青色の階調がそれぞれ256階調以上で読み取る
10. カラーディスプレイ(14インチ以上)・カラープリンター・操作説明書を備え付けている
11. 大きさ情報を保存する
一般書類については、グレースケール(白黒階調)での読み取りも可能です。グレースケールの場合、カラー非対応のディスプレイ・プリンターで出力しても問題ありません。
複数ページで構成される書類については、複数回に分けてスキャンすることが認められています。原本の大きさを変えたコピーを作成し、それをスキャンすることはNGです。
また、スキャンした書類の原本は破棄しても問題ありませんが、入力期間の超過や読み取りの不備があった際、原本が役立つ可能性もあるので、一定期間は保管しておきましょう。
電子取引の保存要件
電子取引の保存要件は「真実性」と「可視性」に分かれており、それぞれ個別に満たす必要があります。
| 真実性の要件 |
以下4つのうち、いずれかを実施
|
|---|---|
| 可視性の要件 |
|
また、要件とされない要素もまとめたので、併せてご確認ください。
- ファイル形式(PDFやスクリーンショットも可)
- ディスプレイやプリンターの性能・台数
- データを保存する外部記憶媒体の種類(ハードディスクやUSBメモリなど)
- バックアップデータの保存
なお、電子取引については、2024年以降も一定の条件を満たせば、紙で出力・保管することも可能です。
電子帳簿保存法改正の内容(2024年1月1日施行)
令和5年度(2023年)税制改正大綱で改正した点を解説します。施行は令和6年(2024年)1月1日です。
詳しくは国税庁の説明をご覧ください
国税庁:電子帳簿保存法の内容が改正されました
電子帳簿保存の改正内容
「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の対象範囲が改正されました。対象は仕訳帳と総勘定元帳に加えて、以下の記載事項に係る帳簿に限定されます。
- 売上その他収入に関する事項(売上帳など)
- 仕入れその他経費に関する事項(仕入帳など)
- 売掛金に関する事項(売掛帳など)
- 買掛金に関する事項(買掛帳など)
- 手形上の債権債務に関する事項(受取手形記入帳など)
- その他の債権債務に関する事項(貸付帳など)
- 有価証券に関する事項(有価証券受払い簿など)
- 減価償却資産に関する事項(固定資産台帳など)
- 繰延資産に関する事項(繰延資産台帳など)
スキャナ保存の改正内容
スキャナ保存に関する改正内容を解説します。
読み取り情報保存の廃止
国税関係書類をスキャナで読み取って電子化する際に、解像度・階調・大きさに関する情報を保存する必要がなくなりました。
解像度(200dpi以上)や階調(カラー画像が原則)など、スキャナ保存の要件自体は変更されていません。
入力者情報の確認の廃止
従来はスキャナ保存時に記録事項の入力者・監督者情報を確認できるようにしておくよう求められていましたが、改正以降は不要になりました。
帳簿との相互関連性を確保する書類の限定
スキャン保存したデータとの相互関連性を確認できるようにしておく必要のある書類が限定されました。対象になるのは、国税関係書類のうち資金や物の流れに直接関係する重要書類(契約書や領収書など)だけです。
一般書類(見積書や注文書など)をスキャナ保存する際は、相互関連性を確保する必要はありません。
電子取引の改正内容
電子取引に関する改正内容を解説します。
検索機能の不要措置における対象者の見直し
税務調査などで電子取引データをダウンロードできるようにしていればすべての検索機能が不要となる措置に関して、対象者が見直されました。
まず、基準期間の売り上げが5,000万円以下の保存義務者に対象が拡大されます。また、電子取引データを印刷した書面を、日付や取引先ごとに整理された状態で提出できる場合も対象です。
「宥恕措置」に変わる「猶予措置」の整備
令和4年度税制改正で整備された電子取引における電子保存の宥恕措置に代わり、新たな猶予措置が適用されます。
具体的には、2つの条件を満たしている場合に、改ざん防止や検索機能などに関する要件を満たしていなくても電子取引データを保存できます。条件は「要件に従って保存ができなかった相当の理由がある」と「税務調査の際に電子取引データと印刷した書面の双方を提出できる」です。
改正電子帳簿保存法に対応するメリット
電子帳簿保存法に対応するメリットを、発行側と受領側の観点から解説します。
発行側のメリット
帳簿や書類の電子化により、コストの削減や業務の効率化が期待できます。紙の書類を作成・印刷・確認・発送するのにかかる時間やコストが削減できるため、本来の業務により集中できるでしょう。誤入力や漏れといったヒューマンエラーの防止や、セキュリティ性の向上にもつながります。
また、すべてWeb上で完結しわざわざ出社する必要がなくなるため、リモートワークの促進にも有効です。送受信の確認も容易になり、修正や再発行といったイレギュラーにも対応しやすくなります。
受領側のメリット
電子データで書類を受領すれば、リードタイムが削減できます。郵送で書類を受け取るには、2〜3日ほどの時間がかかるものです。地域や天候によってはさらに時間がかかるケースもあるでしょう。電子取引なら、早ければ書類が作成されたその日のうちに確認し返信まで完了できます。
また、紙の書類を保管するのに必要なスペースやコストが削減できるのもメリットです。特定の書類を探す際も検索に手間がかからず、保存や管理がしやすくなります。
その他メリット・デメリットに関してはこちらもご覧ください。
電子帳簿保存法に対応する手順
電子帳簿保存法の対応手順も区分によって変わるので、個別に把握しておく必要があります。やり取りの流れや使用する機器がそれぞれ異なるため、事前に確認したうえで準備を進めたいところです。
各区分の概要も踏まえつつ、対応手順をまとめました。
電子帳簿等保存への対応手順
電子帳簿等保存への対応手順は、以下の通りです。
- 要件を満たすシステムを準備する(優良な電子帳簿のみ)
- パソコンやプリンターなどの機器を備え付ける
- パソコンなどで帳簿等を作成する
- 電子保存を行う
電子帳簿等保存とは、電子的に作成した帳簿や文書の電子保存を指します。電子保存とは、ハードディスク・USBメモリ・DVD・クラウドサービスなどに電子データを保存することです。
優良な電子帳簿については、システムの要件も加わります。
スキャナ保存への対応手順
スキャナ保存への対応手順は、以下の通りです。
- 紙で作成・受領した書類を準備する
- 各種要件を満たせる状態でスキャンする
- 一定期間内に入力・タイムスタンプの付与を行う
- その他の要件を満たして電子保存を行う
スキャナ保存とは、紙の書類を専用装置(スキャナーやプリンターなど)で読み取り、電子データとして保存することです。重要書類と一般書類で保存要件が異なっており、前者はより多くの要件を満たす必要があります。
スキャンの段階で解像度・色の階調・大きさ・出力形式などの要件が定められていますが、それらを満たせるならスマートフォンやタブレットで対応することも可能です。
なお、編集履歴を記録できるシステムを使用するなら、タイムスタンプの付与は不要です。
電子取引への対応手順
電子取引への対応手順は、以下の通りです。
- 電子取引データを授受する
- 電子取引に対応したシステムなどを準備する
- 規定の改ざん防止措置を実施する
- パソコンやプリンターなどを備え付ける
- 電子保存を行う
電子取引とは、電子的にやり取りしたデータを発行側・受取側のどちらも電子保存することです。インターネットやクラウドサービスを通じて行われた取引はすべて該当するので、対象書類も幅広くなっています。
電子取引の際は、真実性の要件に基づいて改ざん防止措置を実施しなければなりません。タイムスタンプの付与や訂正・削除の記録が残るシステムの使用など、規定の措置をいずれか1つ講じる必要があります。
また、出力や検索機能に関する可視性の要件は、すべて満たさなければならないので要注意です。
改正電子帳簿保存法に対応する際のポイント
電子帳簿保存法に対応する際に大切な4つのポイントを紹介します。
現状の確認と電子化する書類を検討する
まず、すでに社内で電子取引されている経理関係の書類をリストアップし、現状を把握するとよいでしょう。次に、取引先ごとの授受方法や件数などを確認したうえで、電子化する書類を選定していきます。
コストの削減や業務の効率化につながるか、電子化しやすいかといった観点から選ぶのがポイントです。例えば、郵送の手間が削減できる書類や、発行数が多く活用頻度が高い書類などは、管理や検索がしやすくなる電子化に向いています。
電子化すべき書類や電子化の方法、手順など関してはこちらもご覧ください。
適切なシステムを導入する
適切なシステムを導入すれば、電子帳簿保存法へスムーズに対応できます。
具体的には、請求書や納品書などの発行を電子化するなら、作成・発行などを自動化できる電子帳票システムが役立ちます。受領した帳票の管理などを効率化したいなら、請求書受領システムの導入を検討するとよいでしょう。
自社の目的やコストに見合っているか、拡張性はあるかといった観点からどのシステムを導入するかを選ぶのがポイントです。
電子帳票システムに関してはこちらもご覧ください
保存方法や業務フローを策定する
電子帳簿保存法への対応に際し、あらかじめ保存・運用方法を決めておきましょう。
例えば、タイムスタンプを付与するタイミングを決める必要があります。編集履歴が残るシステムと全く改変のできないシステムのどちらを使用するかによっても、運用ルールは異なるはずです。自社サーバーや導入システム、クラウドサービスなどの中から、保管場所も決めます。
また、不正を防ぐための社内規定の整備も欠かせません。真実性やセキュリティ性を担保したうえで、紙に印刷せずに効率よく運用できるフローを検討しましょう。
実施前に関係者へ周知する
電子化を実施する際は、あらかじめ取引先や関係者に周知をして同意を得ておくのも大切です。導入するシステムによっては、取引先のデータ取得が必要なケースがあります。電子帳簿保存法に対応するメリットを伝えると、協力を得やすいかもしれません。
また、社内の不安や混乱を避けるために、前もって研修を実施したりマニュアルを整備したりして電子化に向けた準備をしておくとよいでしょう。
改正した電子帳簿保存法への対応には「ナビエクスプレス」
ナビエクスプレスは、請求書や領収書、納品書などの書類を電子化し、自動配信する電子帳票システムです。以下のような機能や効果があります。
- 電子帳簿保存法とインボイス制度に対応
- 基幹システムとの連携が可能
- 既存のフォーマットを使用可能
- 初期導入時の取引先の情報収集を代行
- 各種帳票の電子化により、印刷・郵送コストの大幅ダウンやリードタイムの削減を実現
- 各種帳票の自動配信により、業務の効率化と人的ミスの削減を実現
- 各種セキュリティ機能による安全な配信が可能
- 要望やニーズに合った方法・フォーマットでの配信により、顧客の満足度アップを実現
導入事例1|岡谷マート株式会社 様
岡谷マート株式会社 様は、住宅設備機器や配管資材などを扱う総合商社です。もともと毎月7,000通もの納品書と請求書を手作業で発行・送付していましたが、発送作業の大きな負担や誤配送のリスクが課題でした。そこで、既存フォーマットの使用や書類ごとに送付先が異なるお客様への対応などが可能なナビエクスプレスを導入し、帳票類の電子化に踏み切ります。
その結果、誤配送と業務負担の大幅な削減に成功、郵送コストも30%削減されました。また、帳票の内容をすぐに確認できるため、顧客満足度がアップしています。
導入事例2|NTTロジスコ 様
NTTロジスコ 様は、NTTグループの情報通信技術力とロジスティクスのノウハウを融合した総合物流サービスを展開しています。以前は毎月約4,000通の請求書発送業務が発生、しかもお客様ごとの要望に沿った請求書を発行する必要がありました。
しかし、ナビエクスプレスの導入により、請求書の発行や発送にかかるコストを年間で約700万円も圧縮することに成功。請求業務の負担が大幅に減り、営業担当者は本来の業務に専念できるようになりました。テレワークの促進やリードタイムの削減にもつながっています。
電子帳簿保存法の改正に対応した電子化は急務
電子取引における電子保存の義務化に伴い、電子帳簿保存法への対応は急務となっています。加えて、帳票類の電子化は業務の効率化やコストの削減に有効で、セキュリティ性や顧客満足度のアップにもつながるメリットの多い施策でもあります。
自分で多くの保存要件を確認したり、法改正の度に対応を見直したりするのは大変ですが、専用システムを導入すればスムーズです。ぜひこの機会に、さまざまな業界で豊富な実績がある「ナビエクスプレス」の導入を検討してみるのはいかがでしょうか。
【
法令遵守(電子帳簿保存法、インボイス制度など)
】
最新のコラム

2024/02/05
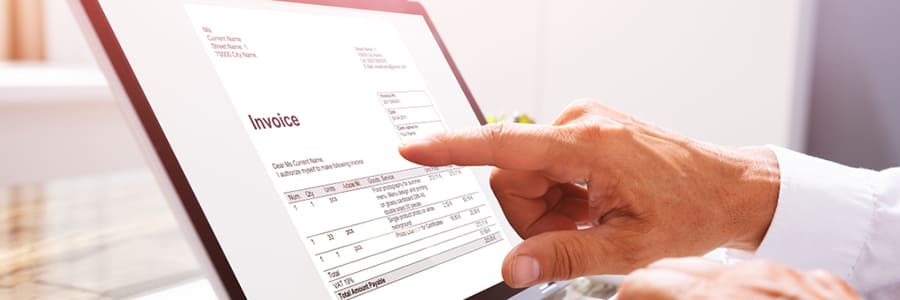
2023/07/31