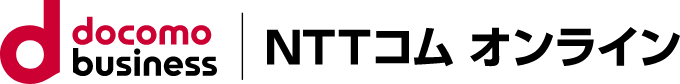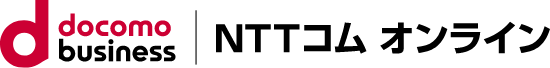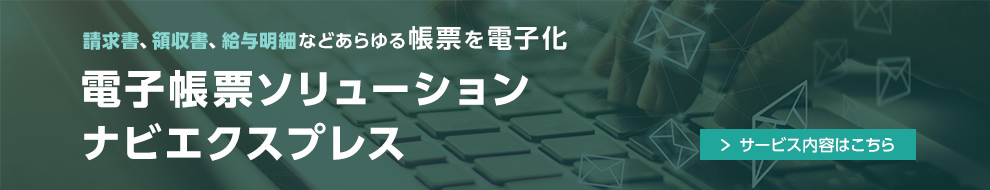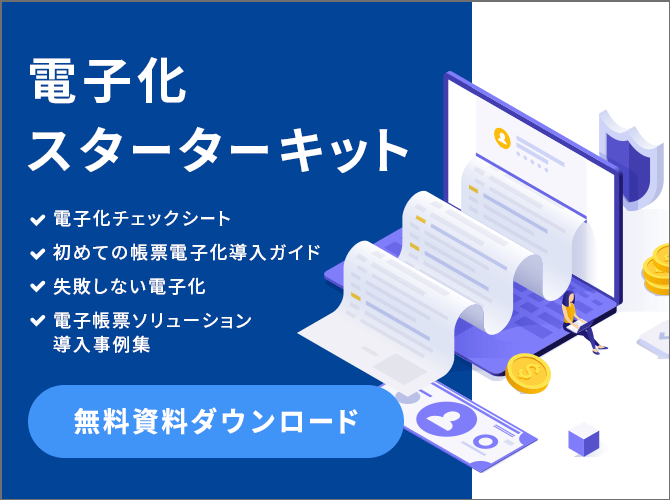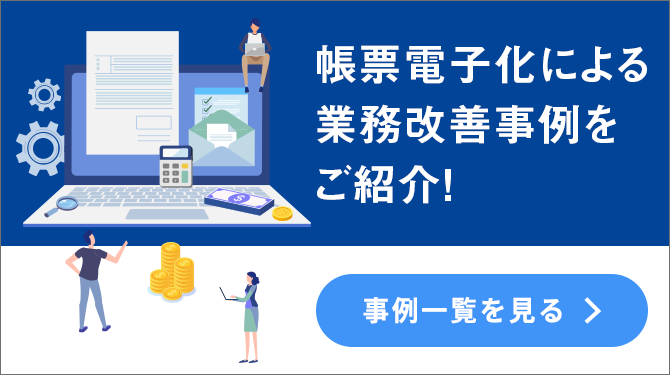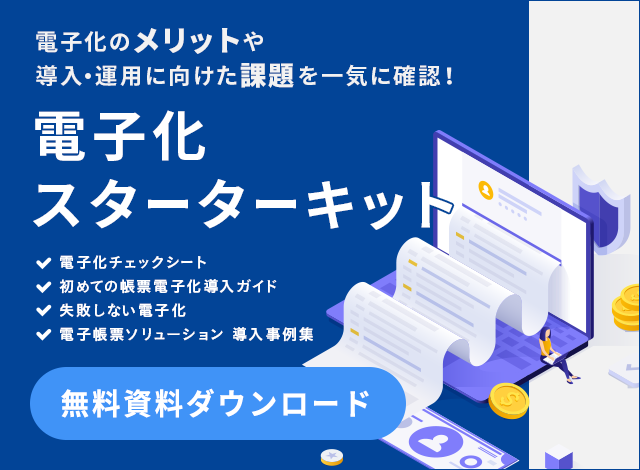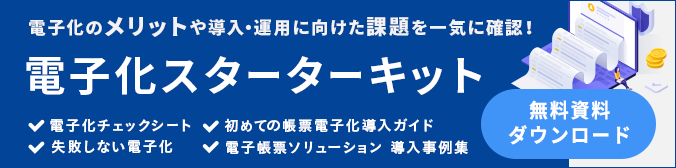2025/01/30
帳票、書類の電子化
圧着ハガキの郵送料金とは?種類やメリット・デメリットを解説
請求書等の電子配信にお悩みはございませんか?
基幹システムに手を加えず連携し、電子化をご提案いたします。
商取引の全帳票を電子化し、即日到着でコスト削減・業務効率化を実現します!
⇒ まずは電子帳票ソリューション ナビエクスプレスの資料を見てみる
圧着ハガキは、顧客へのDMに用いられる手段の1つです。通常のハガキよりも多くの情報量を安い料金で送れるため、新商品・新サービスの案内や特別なキャンペーンなどで用いられています。ただ、あらゆる場面で電子化が進んでいる現代において、圧着ハガキを使うメリットがあるのか疑問を感じる人もいるでしょう。
本記事では、圧着ハガキの種類や郵送料金、通常のハガキとの違いなどについて解説します。圧着ハガキを利用するメリットとデメリットを押さえ、自社にとって最適な顧客への情報伝達方法を活用するためにぜひお役立てください。
- 圧着ハガキとは、印刷面をUVニスや糊などで接着させたはがきで、2つ以上に折られており、接着面を開封することで内容を確認できる
- 用紙のサイズや接着方式によって複数の種類に分けられるものの、多くの場合は第二種郵便物の料金で送付でき、広告郵便物の割引もある
- 圧着ハガキは、通常のはがきの郵送料金でより多くの情報量を掲載できるため、コストパフォーマンスが高い点が大きなメリット
- 封書よりも圧着ハガキの方が開封率が高い上、記載内容が外から見えないためプライバシーが守られるため個別の情報を送りやすい
- 圧着ハガキは温度や湿度に弱く、長期保存には不向きな上、料金が高くなる可能性もあるため、長期的に見ると紙媒体よりも電子化が適している
圧着ハガキとは

圧着ハガキとは、ハガキの中面をUVニスや糊で接着したハガキのことです。専用の接着剤を印刷面に塗布し、熱や圧力で接着させており、受け取った側が開封すると中身を確認できる仕様です。
仕上がりは通常のハガキと同じサイズが多いですが、2つ以上に折られており、印刷面が多い分通常のハガキより多くの情報を伝達できます。新商品の紹介や個別のキャンペーン案内などのDM(ダイレクトメール)、パスワードリセットや請求書、納品書、領収書などの重要情報の連絡などに活用されています。
請求書、納品書、領収書など重要性の高い書類は、圧着ハガキで送る方法の他にも電子化することも有効です。電子化することで、コスト削減や業務効率化が期待できます。
電子化をご検討の場合は、NTTグループの電子帳票ソリューション「ナビエクスプレス」がおすすめです。「ナビエクスプレス」では、請求書の電子化で約86%のコスト削減を実現した事例もあります。電子化の課題に対し最適なご提案、構築、サポートを行いますので、お気軽にご相談ください。
圧着ハガキと通常ハガキの違い

圧着ハガキには、V型やZ型などの種類がありますが、ほとんどの場合仕上がりは通常のハガキと同じサイズです。そのため、通常のハガキと同じ郵送料金で、より多くの情報を送付できます。また、通常のハガキは裏面を見ることができますが、定型ハガキは中身が外部から見えないため、プライバシーが守られている点も特徴です。
圧着ハガキの郵送料金

通常のハガキは「第二種郵便物」という郵便種類に該当し、郵送料金は1通あたり85円、往復ハガキは1通あたり170円です。圧着ハガキは、一般的に通常ハガキのサイズであるため、第二種郵便物の料金で送付できます。
ただし、第二種郵便物の規定を満たしている必要があるため、事前に確認が必要です。通常ハガキの規格は、郵便法に基づいて定められた「内国郵便約款」にて以下のように規定されています。
- サイズ:たて(長辺)14cm~15.4cm、よこ(短辺)9cm~10.7cm
- 重さ:圧着ハガキ2g~6g、往復ハガキ4g~12g
- その他:ハガキの一番面積が大きい面に「郵便ハガキ」または「POSTCARD」の記載、往復圧着ハガキは「往信はがき」「返信はがき」の記載
- 圧着面は容易に剥がれない強さで接着する
上記の条件を満たしていない圧着ハガキは、封書と同じ「第一種郵便物」として扱われるため、料金が上がる点に注意しましょう。
圧着ハガキの種類
圧着ハガキは、用紙サイズや接着方式の種類があり、用途や記載する情報量などによって適したものを選択できます。ここでは、圧着ハガキの主な種類について解説します。
用紙サイズ
圧着ハガキの用紙は、通常の定型ハガキサイズからA4サイズなどの大判サイズまで種類があります。代表的なものは、以下の通りです。
- V型(二つ折り):圧着ハガキの定番タイプ。定型ハガキの3倍もの面積がある。
- C型(内三つ折り):A4用紙を三つ折りにしたタイプ。3面のうち2つの面が圧着されていて、一枚剥がした後にもう一枚剥がすことが可能。
- Z型(外三つ折り):A4用紙を三つ折りにしたサイズで、ハガキの表面と裏面両方が圧着されている。定型ハガキよりも5倍の面積があるため、多くの情報を掲載できる。
- 往復8面展開型:二つ折りのサイズで、2面ともを圧着し、それぞれを剥がして8面を展開させるタイプ。
- 往復冊子型:本や冊子のようにページが分かれているタイプ。通販DMなどストーリー性のあるものや複数商品の案内などに向いている。
C型は、アンケートや通販など受取人の返信が必要なケースで用いられます。V型やZ型は公共機関や企業の広告などでよく見られます。
接着方式
圧着ハガキは、用途や記載内容によって接着方式が異なります。主に以下2つの接着方式に分類されます。
- 先糊(さきのり)方式:感圧糊と呼ばれる特殊な糊が塗布された用紙に印刷し、圧着する方式。メールシーラーなども該当。重要な情報の通知に向いている。
- 後糊(あとのり)圧着方式:通常の用紙に印刷し、後で感圧糊を塗布して圧着する方式。フルカラー印刷にも適している。
- UVニス圧着方式:印刷後にUVニスを塗って印刷面を圧着する方式
- フィルム熱圧着方式:接着面に特殊フィルムを挟み、熱を与えながら圧着する方式
- フチ糊圧着:ハガキの三辺にのみ糊を塗布する方式
上記の他にも、AQUAニスや抗菌ニスが用いられるタイプもあります。先糊圧着方式は印刷範囲に制限がありますが、後糊圧着方式には制限がありません。また、UVニス圧着方式やフィルム方式は、粘着力が弱いものの光沢があり、美しく仕上がるため宣伝やキャンペーンの案内などに用いられています。
いずれの方式でも、接着面は一度剥がしてしまうと再度貼り合わせることはできないため、請求書や通知書などプライバシーに関する内容の伝達にも使われます。
圧着ハガキのメリット
圧着ハガキを販促や顧客への情報伝達に活用することで、さまざまなメリットが期待できます。ここでは、圧着ハガキの主なメリットを紹介します。
通常ハガキより情報量が多い
圧着ハガキの最大の特徴として、通常のハガキより記載できる情報量が多い点が挙げられます。定型ハガキは、裏面にしか印刷できませんが、圧着ハガキは用紙サイズが大きい分、より多くの情報を送ることが可能です。
例えば、V型(二つ折り)のタイプなら最大で3面に内容を記載できます。三つ折りなど用紙サイズがさらに大きなものなら、掲載スペースが増えるため、より多くの情報を効果的に盛り込むことができるでしょう。
顧客に合わせた情報を提供できる
圧着ハガキは、印刷方法によって顧客ごとに特化した情報を送付できます。バリアブル印刷(可変印刷)と呼ばれる手法を用いることで、顧客の名前や住所、商品の画像、クーポンの割引率などを変更可能です。
顧客に合わせた情報を最適なタイミングで送れるため、問い合わせや申し込み、新規購入の増加が期待できます。新サービスやキャンペーンの案内に使いやすいでしょう。
プライバシー保護に優れている
圧着ハガキは、記載内容が外部から見えないため、プライバシーが守られています。通常のハガキは、裏面に情報が記載されるため、郵送中に誰かに見られる可能性があります。
一方、圧着ハガキなら折りや圧着シールで印刷面を隠せるため、漏洩の心配がありません。個人情報や契約内容など機密性の高い情報も、安心して掲載できるでしょう。また、圧着ハガキは一度開封すると二度と接着できないため、受け取った人以外が開封しにくい点もセキュリティ面のメリットです。
通常はがきや封書に比べて開封率が高い
圧着ハガキは中身が見えない分、隠されている内容を確認したくなるという心理を引き起こします。受け取った人は好奇心を刺激されるため、ついつい開封してしまうという心理効果により、通常のハガキやDMよりも高い開封率を誇ります。
新しい商品・サービスやキャンペーンの案内、休眠状態にある顧客への再認知などさまざまな目的で利用できるでしょう。また、封筒と違って開封する手間がかからず、その場ですぐに開封できる点も開封率の高さにつながっています。
封書よりもコスパが高い
圧着ハガキは、通常のハガキの郵送料金で送付できるため、コストパフォーマンスに優れています。定型ハガキで収まりきらないほどの情報を送るなら、封書にする必要があるため、ハガキよりも郵送料金が高くなります。
一方、圧着ハガキは、定型ハガキと同様のサイズで6g以下であれば、定型ハガキと同じ料金で利用できます。また、広告郵便物として認可されている場合は、部数に応じて割引が適用されるためさらにお得にDMを送付することが可能です。
加えて、封書よりもコンパクトなため、保管コストを抑えやすいというメリットもあります。
圧着ハガキのデメリット
圧着ハガキはプライバシー性やコスト面など多くのメリットがありますが、取り扱う際に注意したい点もあります。ここでは、圧着ハガキのデメリットを解説します。
高湿・高温に弱い
圧着ハガキは、高温多湿に弱い性質です。圧着面が水で濡れると、糊が剥がれて粘着力が弱まってしまうことがあります。そのため、雨や雪などで郵送途中に濡れてしまった場合、届く前に剥がれる可能性があるでしょう。
また、水に濡れた後で糊やニスが再び固まれば、受取人が剥がせなくなることも考えられます。高温多湿の環境で扱うのは不向きな上、ハガキを送付した後にコントロールできない要素による影響も考慮した上で利用する必要があります。
長期保管に向いていない
圧着ハガキに用いられる糊やニスは、時間経過とともに劣化して弱まりやすいため、長期保管には適していません。印刷してから発送まで時間が空いてしまうと、接着力が弱まる可能性があります。
圧着ハガキの明確な使用期限はありませんが、最長でも印刷後1ヶ月以内に送付するのが望ましいでしょう。また、長期保存をしなくて済むように、まとめ刷りではなく必要な部数だけ印刷するなど、印刷スケジュールを調整することも大切です。
通常ハガキより郵送料金が高くなる可能性がある
圧着ハガキは、郵送時のサイズは通常のハガキと同じであるため、定型ハガキと同じ第二種郵便物の郵送料金が適用されます。ただし、元の用紙サイズは大きく、インクの量も多く使われているため、郵便法で定められた規定に収まらない可能性があります。
重量や表記、加工などの規定を超えた場合、第一種郵便物として扱われるため、郵送料金が高くなる点に注意が必要です。
郵便規定をクリアする必要がある
圧着ハガキは、郵便規定をクリアする必要があります。広告郵便物として申請し認可を受けることで、部数に応じた割引が適用される可能性があります。ただし、逸脱すると発送コストが増えるため、事前確認が重要です。
具体的には、以下のような条件を満たす必要があります。
- 最も面積が大きい面に「郵便はがき」または「POST CARD」と表記
- 往復圧着ハガキは「往信はがき」もしくは「返信はがき」と表記
- 上記を認識しやすいように、白色または淡い色の用紙を使用
- 規定重量やサイズを遵守
請求書を電子化した事例
東洋カーマックス株式会社では、約1万件という膨大な請求書を毎月発送するために、多くの人的リソースや郵送費がかかっていました。また、顧客に届くまでのタイムラグに配慮し、要望に応じてメールやFAXで請求書を送らなければならず、業務負担が大きい点が課題となっていました。
業務効率化を図るため、2021年にNTTコム オンラインが提供する「ナビエクスプレス電子帳票ソリューション」を導入。約1万件の請求書のうち8割を電子化し、業務コストを月間で約60万円削減することに成功しています。
また、郵送時のタイムラグが解消され、請求書データを即日送付でき、メールやFAXによる個別対応も不要となりました。業務負担の大幅な軽減とコスト削減を実現しています。
郵便コストの削減には電子化もおすすめ
圧着ハガキは、通常のハガキより多くの情報量を掲載しつつ、同じ郵送料金で送付できます。受け取った人が開封するまで中身が見えないため、プライバシーが保護される上、高い開封率が見込めるため販促や重要事項の伝達にも向いています。
ただし、高温・高湿や水分に弱く、接着剤の経年劣化があるため長期保存には不向きです。また、郵便規定を超えると料金が上がる可能性もあるため注意しましょう。顧客の手元にハガキが届くまでのタイムラグや保存性などのデメリットを考慮すると、書類の電子化がおすすめです。
NTTコム オンラインが提供する「ナビエクスプレス」は、請求書や明細書の電子化に対応しています。毎月発生する書類を電子化することで、郵送にかかる手間やコストを削減可能です。自動配信やシステム連携など多彩な機能により、業務効率化も促しますので、この機会にぜひお気軽にご相談ください。

【
帳票、書類の電子化
】
最新のコラム

2025/06/19

2025/06/16