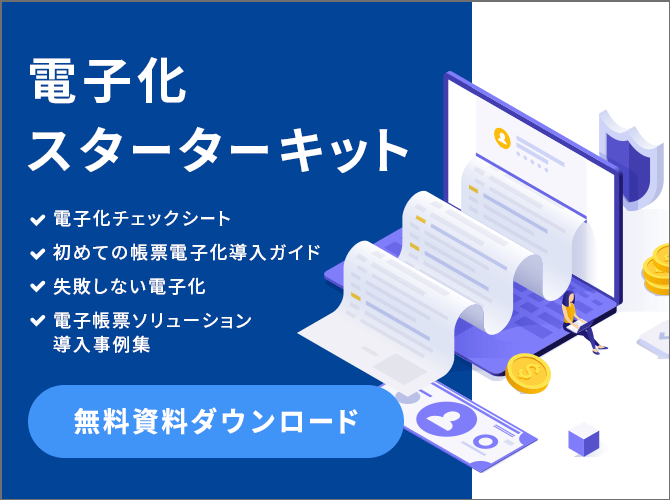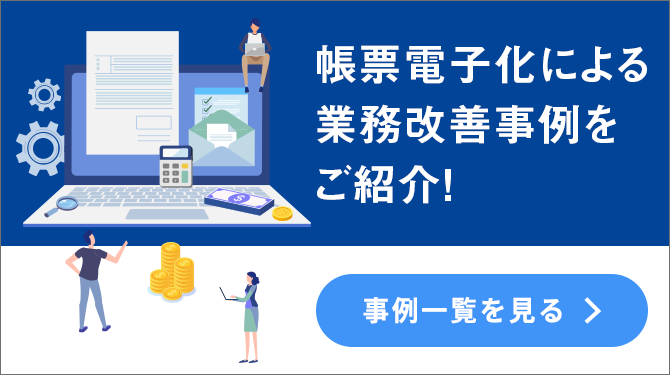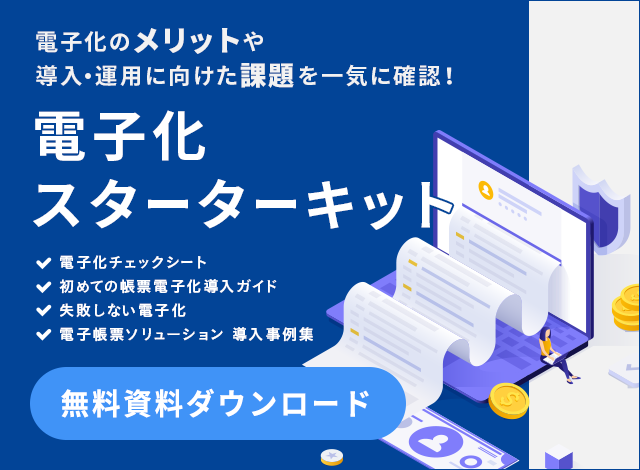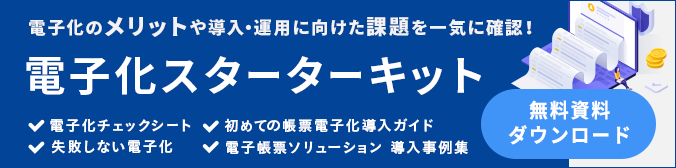2025/08/22
帳票、書類の電子化
電子配信とは?種類や導入手順、メリットと活用事例を解説
請求書等の電子配信にお悩みはございませんか?
基幹システムに手を加えず連携し、電子化をご提案いたします。
商取引の全帳票を電子化し、即日到着でコスト削減・業務効率化を実現します!
⇒ まずは電子帳票ソリューション ナビエクスプレスの資料を見てみる
インターネットやスマートフォンの普及に伴い、電子配信は日常やビジネスのさまざまな場面で活用されるようになりました。特に企業においては、請求書や給与明細、契約書などのやり取りを効率化し、コスト削減やペーパーレス化を進める手段として注目を集めています。
この記事では、電子配信の種類や導入のメリット、具体的な導入手順、さらに実際の活用事例までわかりやすく解説します。電子配信の導入を検討している企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
- 電子配信とは、これまで紙で配布していた情報を電子データとして配信する仕組みで、印刷や郵送のコストがかからない点や業務効率化につながる点がメリット
- 企業が電子配信システムを導入する際は、まず導入目的を明確にしたうえで、適切なツールを選定して自社の業務フローに組み込む必要がある
- 電子配信システムを選定する際は、「導入目的に合う機能を備えているか」「費用対効果が高いか」「基幹システムと連携できるか」といった点を確認する
電子配信とは?
電子配信とは、これまで紙媒体で配布していた情報を、インターネットや専用システムを通じて電子データとして配信する仕組みを指します。例えば、請求書や明細書、社内通知などをPDFといった電子データに変換し、SMSやメール、Webサイトなどを通じて受け取れるようにするケースが一般的です。
紙の印刷や郵送を伴わないため、コスト削減や業務効率化につながる点が大きな特徴です。受取側もインターネット環境があれば場所を問わず確認できるため、利便性の高い情報伝達手段として多くの企業で導入が進んでいます。
電子配信が普及している背景
電子配信が普及している背景には、インターネットやスマートフォンの浸透により、デジタル技術が生活やビジネスの基盤として定着したことが挙げられます。日常的にオンラインで情報をやり取りできる環境が整い、電子データによる配信は自然な流れとして広がりました。
また、ビジネスの現場では、ペーパーレス化や働き方改革の推進が進み、紙の印刷や郵送を必要としない効率的な業務運用が求められています。こうした背景から、電子配信は多くの企業で活用が進んでいます。
電子配信の種類と具体例

電子配信は、さまざまなシーンで活用されています。ここでは、電子配信の代表的な種類と具体例を取り上げ、それぞれの概要や導入による効果について解説します。
電子請求書
電子請求書とは、従来の紙の請求書に代わり、電子データとして作成・送信する形式の請求書です。取引先や顧客には、PDFファイルをメールに添付して送ったり、SMSで閲覧用のURLを送信したりして提供します。
これにより、印刷や郵送にかかるコストの削減や、業務負担の大幅な軽減が可能になる点がメリットです。電子請求書は、請求書発行業務のデジタル化を推進する手段として、多くの企業で採用が進んでいます。
電子給与明細
電子給与明細は、給与明細を紙ではなくPDFなどの電子データで作成・配布する仕組みです。従業員はスマートフォンやパソコンから明細を確認でき、紛失リスクの低減にもつながります。電子請求書と同様に印刷や郵送の手間やコストを削減できるため、人事・総務部門の業務負担軽減につながる点も大きなメリットです。
電子契約書
電子契約書は、オンライン上で契約書の作成から締結までを行える仕組みです。契約の完全性や本人性を担保するために、タイムスタンプや電子証明書を用いて法的効力を確保している点が特徴です。
すべてのやり取りがオンラインで完結するため、郵送や収入印紙のコストを削減できるほか、遠隔地の取引先とも迅速に契約を進められます。これにより、契約業務全体のスピードと効率を大幅に向上させられるのがメリットです。
ウェビナー
ウェビナーは「ウェブ」と「セミナー」を組み合わせた言葉で、ビデオ会議ツールなどを利用してオンライン上で実施するセミナーのことです。専用の会場を借りる必要がなく、大規模な設営も不要なため、コストや手間を大幅に抑えつつ効率的に情報発信ができます。
さらに、地理的な制約がないため遠方の参加者も参加しやすく、録画機能を活用すれば後日でも視聴が可能なため、より多くの顧客に情報を届けられる点も大きな魅力です。
電子書籍
電子書籍は、スマートフォンやタブレット、パソコンなどの端末で閲覧できる書籍のことです。書店に行かずに手元の端末から購入し、その場ですぐに読み始めることができます。さらに、フォントサイズの変更や文章の読み上げなど、紙の書籍にはない利便性を備えている点も大きなメリットです。
日本国内でも電子書籍市場は年々拡大しており、通勤時間や外出先で気軽に読書が楽しめるツールとして、多くのユーザーが利用しています。
動画配信・音楽配信
動画配信・音楽配信は、インターネットを通じて動画や音楽を視聴・再生できるサービスです。電子書籍と同様に市場規模が年々拡大しており、場所を問わず動画や音楽を楽しめる点から、多くのユーザーに支持されています。
近年では、個人や企業が自由に動画をアップロードできるプラットフォームも普及し、情報発信や商品・サービスのプロモーション手段としても幅広く活用されています。
電子請求書・電子給与明細の電子配信を行うメリット
多くの企業で導入が進んでいる電子配信として、電子請求書や電子給与明細が挙げられます。ここでは、これらを電子配信することで得られる主なメリットについて解説します。
コストの削減につながる
請求書や給与明細を紙で発行する場合、印刷用の紙やインク、郵送費といったコストが発生します。さらに、封入や発送作業を行うための人員を確保する必要があり、そのための人件費も無視できません。取引先や従業員の数が増えるほど負担は膨らみ、月末や繁忙期に業務が集中して残業代がかさみやすい点も課題です。
電子配信に切り替えれば、印刷・郵送費用や人件費を含むトータルコストを大幅に削減できるため、継続的な経費削減に直結するのが大きなメリットといえます。
業務効率化につながる
電子配信を導入すると、紙の印刷や封入、郵送といった手作業が不要になり、業務効率化に大きく貢献します。特に、帳票の作成から配信までを一元管理できる電子帳票配信システムを活用すれば、帳票関連の業務をシステム上で完結でき、担当者の負担軽減が可能です。
結果として、空いた時間や人員を他の業務や付加価値の高い業務に充てられるようになり、部署や企業全体の生産性向上にもつながります。
ヒューマンエラーの軽減につながる
紙の帳票の場合、印刷・封入・郵送の各工程で封入間違いや誤送付、記載ミスなどが発生しやすい傾向があります。一方、電子配信を導入すればシステムによる自動作成・送信が可能になり、上記のような手作業に起因するヒューマンエラーを大幅に減らせるのもメリットのひとつです。
さらに、配信履歴や送信ログが残るため、送付状況の確認やトラブル発生時の原因特定がしやすくなるというメリットもあります。
情報を素早く提供できる
電子配信はメールやSMSを通じて即時に送信できるため、紙の郵送に比べて圧倒的に早く情報を届けられるのが特徴です。これにより、例えば「従業員が給与明細をすぐに確認できる」「取引先が請求書を迅速に受け取れる」など、相手側の利便性も向上します。
紙媒体では避けられない郵送遅延のリスクもなく、必要な情報をタイムリーに届けることで、業務全体のスピード感を高められる点が大きなメリットです。
環境負荷の軽減につながる
電子配信を導入すると帳票の印刷が不要となり、紙やインクの使用量を大幅に削減できます。さらに、郵送に伴う輸送エネルギーやCO₂排出量の削減にもつながり、環境負荷の軽減が可能です。
こうした取り組みは、CSRやESGといった社会的責任の観点でも評価されやすく、環境意識の高い企業としてのイメージ向上にもつながります。このように、電子配信はコスト削減や業務効率化だけでなく、自社の社会的価値を高める点でも有効な取り組みです。
電子配信を行う際の注意点

電子配信はコスト削減や業務効率化に効果的ですが、導入にあたってはいくつか注意すべきポイントがあります。ここでは、電子配信を行う際に押さえておきたい4つの注意点について、詳しく見ていきましょう。
導入コストがかかる
電子配信を導入する際には、専用システムやツールの初期費用や月額利用料が発生する点に注意が必要です。特に、帳票作成機能やセキュリティ対策が充実したシステムほど導入コストは高くなる傾向があり、予想以上の負担となる場合もあります。
さらに、既存システムとの連携や自社業務に合わせたカスタマイズを行う場合には、追加費用が発生するケースも少なくありません。電子配信の導入を検討する際は、こうしたコストを事前に把握し、予算計画に組み込んでおく必要があります。
法規制への対応が必要となる
電子配信を行う際は、電子帳簿保存法や個人情報保護法などの関連法規を遵守するよう注意しましょう。例えば、帳簿や請求書を電子データで保存する場合は「真実性」「可視性」などの要件を満たさなければなりません。また、個人情報を取り扱う場合には適切な管理・保護体制の整備が不可欠です。
こうした法令を理解したうえで運用ルールを明確化し、社内教育を徹底するとともに、業務フローやセキュリティ体制を定期的に見直すことが、安全で適切な運用につながります。
関連記事:【2024年施行】電子帳簿保存法の改正内容をわかりやすく解説|制度の概要から紹介
システム障害の際は利用できなくなるリスクがある
電子配信はシステムやネットワーク環境に依存するため、サーバー障害や通信トラブルが発生すると利用できなくなるリスクがある点に注意が必要です。重要なデータが確認できなくなると業務が滞る恐れがあるため、バックアップ体制の整備や障害発生時の復旧フロー、代替手段を事前に検討しておかなければなりません。
これらの準備を怠ると、突発的なトラブル発生時に社内業務だけでなく取引先への対応にも支障が出る可能性があるため、事前の対策が不可欠です。
事前の周知や導入のサポートが必要になる
電子配信の導入に伴い業務フローが変わる場合、関係部署や取引先への事前周知が欠かせません。周知が不十分だと混乱を招き、業務に影響を及ぼす可能性があります。さらに、デジタル操作に不慣れな社員や取引先が対応できず、運用に支障をきたすケースも想定されるため、丁寧な説明と対応を徹底しましょう。
電子配信の導入時には、マニュアルの作成や研修の実施、サポート窓口の設置といった支援体制を整えることが重要です。こうした取り組みにより、社内外の理解と協力を得ながら、円滑に移行を進めやすくなります。
電子配信システムを導入する手順
電子配信システムを導入する際は、以下の手順に沿って進めるとスムーズです。
- 導入の目的を確認する
- 電子配信を実現するツールを選定する
- 効果測定と改善を行う
それぞれのステップで取り組むべきポイントを、以下で詳しく解説します。
導入の目的を確認する
電子配信を導入する前に、まず取り組みの目的を明確にしておくことが大切です。コスト削減や業務効率化、ペーパーレス化の推進など、具体的な目的を整理すれば導入の方向性が定まり、システム選定や運用計画の検討もスムーズに進められます。
社内での合意形成や導入後の効果測定もしやすくなるため、初期段階でしっかりと目的を定めておきましょう。
電子配信を実現するツールを選定する
導入の目的を明確にしたら、次のステップはツールの選定です。目的に適した機能を備えた複数のツールを比較し、コストやセキュリティ、サポート体制なども総合的に確認したうえで、自社に最適なものを見極めましょう。
可能であれば、選定時に無料トライアルやデモを活用して操作性や現場の業務フローとの相性を確認しておくと、導入後のトラブルを防ぎやすくなります。
効果測定と改善を行う
電子配信の運用を開始したら、導入目的が達成できているかを確認するために効果測定が必要です。コスト削減や業務効率化の進捗を、具体的な数値や現場の意見をもとに検証し、改善すべき点がないか確認しましょう。
ツールを導入して終わりではなく、検証と改善を繰り返すことで、電子配信の効果を最大限に引き出せます。
電子配信システムの選定ポイント

電子配信システムは種類が多く、導入目的や業務内容に合ったものを選ばなければなりません。ここでは、自社に合ったシステムを見極めるための選定ポイントを紹介するので、比較検討時の参考にしてください。
必要な機能があるか
電子配信システムを選定する際は、まず自社の目的に合った機能が備わっているかを確認しましょう。例えば、オリジナルデザインの帳票作成、電子署名、アクセス制限といった機能は、多くの企業で必要とされる代表例です。
一方で、不要な機能が多いとコスト増につながる恐れがあるため、導入前に業務フローを整理し、どの工程をシステム化すべきかを明確にしておくことが大切です。そのうえで、必要な機能を過不足なく備えたシステムを選定すれば、導入効果を最大限に高められます。
費用対効果は十分か
電子配信はコスト削減が期待できる一方で、導入や運用には一定の費用が発生します。初期費用や月額利用料、運用コストと、削減が期待できる印刷・郵送費や人件費とを比較して検討しましょう。
さらに、長期的な費用削減や業務効率化による生産性向上など、間接的なメリットも含めて評価することが重要です。このように費用対効果を総合的に見極めることで、無理のない運用が可能になります。
操作は簡単にできるか
現場の担当者が直感的に操作できるかどうかは、システムが定着するかを左右する重要なポイントです。操作が複雑でわかりにくいと現場での活用が進まず、負担や不満の原因になりかねません。
特に、「デジタルに不慣れな社員でも扱いやすい画面構成か」「操作手順がシンプルで理解しやすい設計になっているか」といった点を確認しましょう。可能であれば、無料トライアルやデモを通じて実際に操作感を試し、現場での利用イメージを明確にしておくと安心です。
基幹システムとの連携ができるか
基幹システムと連携できる電子配信システムであれば、既存の販売データや顧客情報、給与データなどを取り込み、帳票を自動で作成できます。
これにより、データの二重入力や手作業による転記ミスを防ぎ、作業の正確性も高まります。基幹システムとの連携は業務効率の向上や作業負荷の軽減に直結するため、導入前に自社のシステム環境に適した連携機能が備わっているかを必ず確認しておきましょう。
基幹システムと電子配信システムとの連携については、以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。
サポートは充実しているか
安定した運用を実現するためには、サポート体制の充実度が重要です。導入時に設定支援や操作トレーニングを受けられるか、運用後にトラブルが発生した際の対応が迅速かどうかを事前に確認しておきましょう。
また、電話・メール・チャットといった問い合わせ手段の有無や、マニュアル・FAQ・オンラインヘルプの内容も重要なポイントです。これらのサポートが整っていれば、導入後も安心してシステムを活用できます。
電子配信に移行した事例
最後に、実際に電子配信を導入して成果を上げている企業の事例を紹介します。具体的な取り組みや得られた効果を知ることで、導入後の運用イメージがより明確になるでしょう。電子配信システムの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
株式会社桑原
アパレル製品の検品と補修を専門に手掛ける株式会社桑原様では、国内10カ所、海外20カ所の工場拠点を展開し、各拠点の経理業務を本社の総務部が一括管理しています。請求書の発行件数は月平均1,500~2,000件に上り、従来は印刷から捺印、封入、発送までをすべて手作業で行っていたため、業務負担の大きさが課題でした。
こうした状況を改善するため、同社は電子帳票配信システムを導入し、基幹システムと連携して業務改善を進めています。これにより、約300~400件が電子化され、発送業務の大幅な削減につながりました。
基幹システムで請求書を発行後、配信ボタンをクリックするだけで自動配信されるようになっており、操作も簡単です。実際にWeb配信へ移行した取引先からは「在宅勤務でも請求書を受け取れて、すぐ処理できるので助かる」といった声が寄せられ、利便性の高さも評価されています。
青森綜合警備保障株式会社
綜合警備保障(ALSOK)グループの青森綜合警備保障株式会社様では、多くの社員が委託先で勤務しているため、給与明細などの紙書類の受け渡しに日数がかかるという課題を抱えていました。経営層から全社的なIT化推進の方針が示され、SDGsの観点からも帳票の電子化を進めることになり、まずは給与明細と賞与明細の電子化に着手しています。
同社は年齢層が高くデジタルに不慣れな社員も多いため、スマートフォン操作に慣れていない社員でも直感的に使えるシステムを採用しました。その結果、本社人事部の給与担当者の業務時間が毎回約4時間短縮されただけでなく、配送コスト削減や各支社・営業所の担当者の負担軽減にもつながっています。
給与・賞与明細は個人アカウントへ自動配信され、支給日に確実に全社員へ届く体制が整いました。年齢層の高い社員が多い同社においても、IT化を推進する大きな一歩となっています。
電子配信で業務を効率化しよう
電子配信は、印刷や郵送にかかるコスト削減や業務効率化を実現できる有効な手段です。請求書や給与明細の電子化をはじめ、契約書や社内文書の配信まで幅広く活用できるため、企業のペーパーレス化や働き方改革を後押しします。
導入にあたっては、目的や業務フローに適したシステムを選び、効果測定や改善を繰り返しながら活用範囲を広げていくのがポイントです。電子配信を取り入れて、効率的な組織運営を目指しましょう。
NTTコム オンラインが提供する「ナビエクスプレス」は、既存の帳票レイアウトをそのまま電子化できる電子帳票配信システムです。ExcelやCSVなどのファイル送付に対応しているほか、基幹システムと連携し、登録済みの配信先や帳票情報を活用したワンストップ配信も可能です。電子配信の活用をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【
帳票、書類の電子化
】
最新のコラム

2025/12/09

2025/10/22