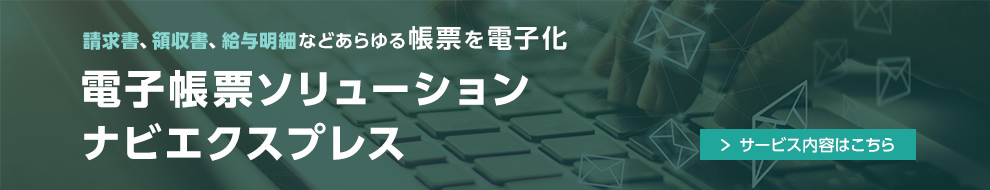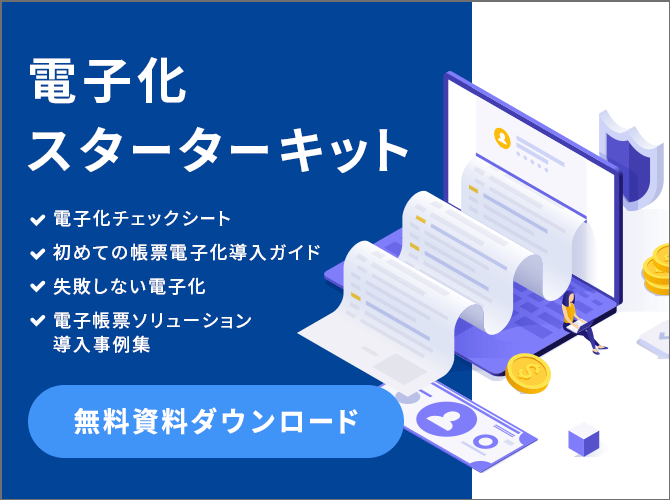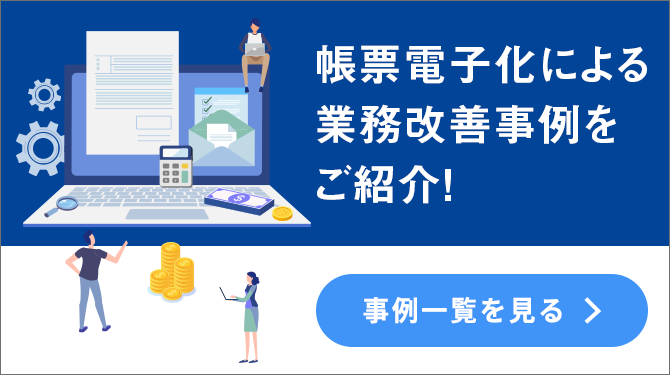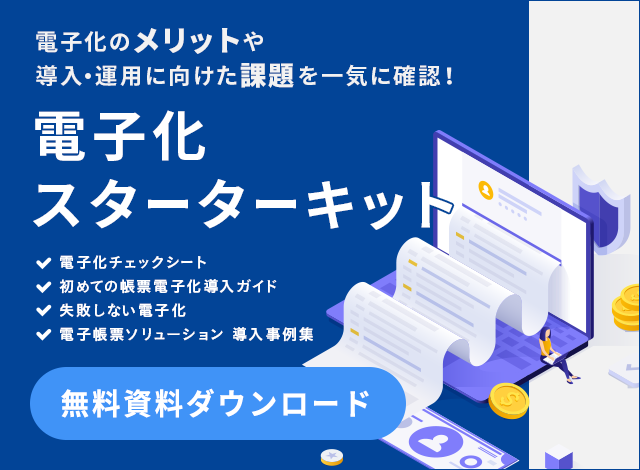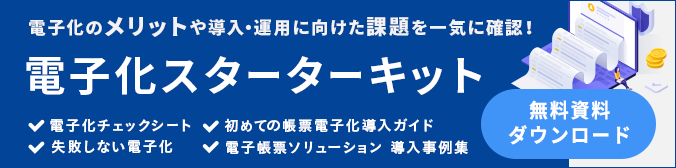2025/08/07
帳票、書類の電子化
電子帳票配信サービスとは?導入のメリットや選ぶポイント、注意点を解説
請求書等の電子配信にお悩みはございませんか?
基幹システムに手を加えず連携し、電子化をご提案いたします。
商取引の全帳票を電子化し、即日到着でコスト削減・業務効率化を実現します!
⇒ まずは電子帳票ソリューション ナビエクスプレスの資料を見てみる
多数の顧客や取引先と日々やり取りを行う企業にとって、請求書や注文書といった帳票の作成・送付業務は大きな負担となっています。こうした帳票業務の効率化を実現する手段として注目されているのが、「電子帳票配信サービス」です。
本記事では、電子帳票配信サービスを導入するメリットや選定時のポイント、注意点までわかりやすく解説します。導入企業の事例も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
- 電子帳票配信サービスとは、請求書や注文書といった帳票を電子データとして作成・送付・管理できるシステムのこと
- 電子帳票配信サービスを導入すると、印刷や郵送にかかるコストの削減、業務の効率化、法制度への対応など、多くのメリットがある
- 電子帳票配信サービスを選定する際は、既存帳票のフォーマットに対応できるかどうか、法制度への対応状況、セキュリティ対策の内容などを確認することが大切
電子帳票配信サービスとは?
電子帳票配信サービスとは、請求書や注文書などの帳票を電子データとして作成・送付し、一元的に管理できるシステムです。
紙帳票の場合は印刷・封入・郵送といった手間が発生し、Excelでの管理においてもPDF変換やメール添付といった作業負荷が避けられませんでした。
電子帳票配信サービスを導入すれば、帳票の作成・配信をひとつのシステム上で完結させることが可能です。さらに、基幹システムとの連携により、帳票作成から配信までのプロセスを自動化できるケースもあります。
このように、電子帳票配信サービスは業務の効率化やコスト削減を目的に、多くの企業で活用されています。
電子帳票配信サービスが求められる理由

電子帳票配信サービスは、すでに多くの企業で導入が進んでいます。ここでは、電子帳票配信サービスが求められている理由について詳しく見ていきましょう。
ペーパーレス化やDX化の推進
働き方改革の一環として、ペーパーレス化やDX化に取り組んでいる企業は少なくありません。帳票業務においても、注文書や請求書などの各種文書をデータで作成・管理することで、紙資料の削減が可能です。
特に、電子帳票配信サービスでは帳票の作成や送付だけでなく、管理まで行えるため、帳票を紙で保存しておく必要がなくなります。また、基幹システムと連携させることで、帳票の作成・送付といった一連の作業を自動化でき、業務プロセスの大幅な効率化が期待できます。
こうした点から、電子帳票配信サービスはペーパーレス化やDX化を推進する企業にとって、非常に有効なツールといえるでしょう。
ペーパーレス化のメリットや導入方法は以下の記事で詳しく紹介しているため、ぜひ併せてご覧ください。
関連記事:ペーパーレス化で業務効率改善!導入方法と注意点やメリット・デメリットを解説
電子帳簿保存法改正とインボイス制度の導入
2022年1月の電子帳簿保存法の改正により、電子メールやクラウドサービスなどを通じて授受された取引情報は、紙ではなく電子データとして保存することが義務化されました。電子データで帳票を管理する場合は「真実性」や「可視性」といった要件を満たす必要があり、法令に準拠したシステムの活用が安全かつ確実な対応方法となります。
さらに、2023年10月に開始されたインボイス制度をきっかけに、電子帳票配信サービスの導入を検討する動きも見られます。インボイス制度に対応したサービスであれば、適格請求書に必要な情報(登録番号、消費税額、発行者情報など)を自動で反映でき、請求業務の負担を大幅に軽減できるためです。
このように、法制度への確実な対応と業務の効率化を同時に実現できる点も、電子帳票配信サービスが求められている理由のひとつです。
電子帳簿保存法とインボイス制度については、以下の記事でそれぞれ詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
関連記事:【2024年施行】電子帳簿保存法の改正内容をわかりやすく解説|制度の概要から紹介
関連記事:インボイス制度とは?電子インボイスのメリットや従来の請求書からの変更点
リモートワークの普及
リモートワークの普及に伴い、帳票の電子化が促進されたという背景もあります。従来の紙帳票や押印を前提とした運用はオフィスへの出社が前提となっており、リモートワーク実施の妨げとなっているケースも少なくありません。
その点、電子帳票配信サービスを活用すれば、帳票の作成・送付・保管までをオンラインで完結でき、場所にとらわれない柔軟な働き方を実現できます。また、アクセス制限や操作ログの管理機能を備えたサービスを活用することで、リモート環境においてもセキュリティの確保が可能です。
こうした利便性と安全性から、リモートワークを実施する企業にも電子帳票配信サービスが求められています。
電子帳票配信サービスの代表的な3つの機能
電子帳票配信サービスでは、大きく分けて次のような機能が提供されています。
- 帳票の作成・取り込み
- 帳票の配信
- 帳票の保存・管理・検索
それぞれの機能について、以下で解説します。
帳票の作成・取り込み
取り込んだデータをもとに、希望するレイアウトやフォーマットに沿って帳票を作成するための機能です。作成した帳票は、ExcelやPDFといった形式で出力できます。
帳票の元となるデータは、CSVファイルによる手動取り込みに加え、基幹システムとのAPI連携によって自動的に取得することも可能です。
帳票の配信
システム上で作成した帳票を、取引先に送付する機能です。配信方法は複数用意されており、取引先のニーズや運用状況に応じて配信方法を使い分けることが可能です。主な配信方法には、以下のようなものがあります。
- メールにファイルを添付して送付
- メールで帳票のダウンロード用URLを送信
- FAX送信
- 郵送代行サービスを利用した送付
- EDI(電子データ交換)による自動送信
帳票の保存・管理・検索
配信した帳票を、システム上で適切に保存・管理できる機能です。サービスによっては、受領した帳票の管理にも対応しています。また、電子帳簿保存法に対応したシステムであれば、検索機能やタイムスタンプの付与、変更履歴の保存といった要件を満たす機能も備えています。
電子帳票配信サービス導入のメリット

電子帳票配信サービスを導入すると、次のようなメリットがあります。
- 紙・郵送コストの削減
- 帳票業務の効率化
- セキュリティの強化・内部統制の強化
- 一元管理による検索性の向上
- 電子帳簿保存法・インボイス制度への確実な対応
- BCP対策
それぞれのメリットについて、以下で詳しく見ていきましょう。
紙・郵送コストの削減
電子帳票配信サービスを導入する代表的なメリットのひとつが、紙や郵送にかかるコストを大幅に削減できる点です。帳票を電子データとして送付できるため、用紙代・インク代・切手代などが不要になり、郵送にかかるコストを大幅に抑えられます。
また、印刷・封入・発送といった手作業が発生しないため、人件費の削減も可能です。さらに、紙帳票の保管スペースも不要になり、オフィスの省スペース化にも貢献します。
帳票業務の効率化
電子帳票配信サービスを導入することで、帳票の作成から配信、保管までシステム上で対応でき、帳票業務の大幅な効率化が可能になります。
従来のように手作業で印刷や郵送をする必要がなくなり、担当者の作業負担を大きく軽減できるのがメリットです。さらに、誤送付や送付漏れといったヒューマンエラーのリスクも抑えられます。
加えて、帳票業務の自動化により、担当者は他の業務により多くの時間を割けるようになり、結果として部門全体の業務効率の向上にもつながります。
セキュリティの強化・内部統制の強化
アクセス権限の設定や操作ログの記録に対応した電子帳票配信サービスを導入することで、不正な改ざんや情報漏洩といったセキュリティリスクを抑えられます。帳票データの操作履歴が残るため、万が一トラブルが発生した場合にも原因や影響範囲の特定がしやすく、迅速な対応が可能です。
さらに、ユーザーや部門ごとに閲覧や編集などの操作権限を細かく設定できるため、帳票業務の透明性が高まり、内部統制の強化にもつながります。
一元管理による検索性の向上
電子帳票配信サービスを活用して帳票類を一元管理すると、必要な情報をすぐに検索できるようになります。キーワード検索や項目別の絞り込みなど、検索機能が充実しているサービスも多く、目的の帳票を短時間で探し出せるのが大きなメリットです。
これにより、帳票を探すための時間を大幅に削減でき、業務のスピード向上につながります。また、問い合わせ対応やトラブル発生時の状況確認もスムーズになり、業務の正確性や対応力の強化が可能です。
電子帳簿保存法・インボイス制度への確実な対応
企業としては、電子帳簿保存法やインボイス制度といった法制度に確実に対応しなければなりません。これらの制度に準拠した電子帳票配信サービスであれば、タイムスタンプの付与や検索機能、変更履歴の保存など、求められる要件を満たすための機能があらかじめ揃っています。
そのため、制度対応に伴う業務負担の軽減が可能です。こうした法制度にスムーズかつ確実に対応できる点も、電子帳票配信サービス導入の大きなメリットといえるでしょう。
BCP対策
災害などによって出社が困難になった場合でも、電子帳票配信サービスを活用すれば帳票業務をリモートで継続できます。これにより、業務の中断リスクを最小限に抑えることが可能です。
また、紙の帳票は火災や水害などによる消失リスクが高い一方、データであれば別拠点にバックアップを取っておくことで復旧が可能です。特にクラウド型サービスであれば、データセンターの冗長構成や定期的なバックアップ体制により、データ消失のリスクをさらに低減できます。
電子帳票配信サービスの選ぶ際のポイント

電子帳票配信サービスは多様な製品が提供されており、自社に最適なものを選ぶことが大切です。ここでは、サービス選定を進める際にチェックしておきたいポイントを紹介します。
導入目的にあった機能があるか
電子帳票配信サービスにはさまざまな製品があり、それぞれに特徴があります。そのため、自社の導入目的を明確にし、それに対応した機能が備わっているかを確認することが重要です。
例えば、業務効率化が目的であれば、基幹システムと連携可能なAPI機能の有無がポイントになります。また、取引先によって配信方法を使い分けたい場合は、複数の配信形式に対応しているかどうかを確認しましょう。
あらかじめ必要な機能を洗い出しておくことで、サービス選定をスムーズに進められます。
入力・出力フォーマットは豊富か
CSV・Excel・PDFなど、対応している入力・出力フォーマットの種類も確認しておきましょう。対応フォーマットが豊富であれば、既存の業務システムや資料とスムーズに連携でき、データの加工や活用の幅も広がります。特に、既存システムで扱うデータ形式に対応していれば、最小限の手間で活用を進められます。
オリジナルフォーマットに対応できるか
既存の帳票や伝票を電子化する際には、これまで使用していたフォーマットをそのまま再現できるかどうかも重要なポイントです。特に、取引先からの要望により記載している項目がある場合は、それに対応可能なサービスを選定しなければなりません。
オリジナルフォーマットに対応した電子帳票配信サービスであれば、従来の帳票レイアウトを維持したまま電子化できるため、社内外の混乱を防ぎつつスムーズな移行が可能です。
処理スピードは十分か
電子帳票配信サービスを選定する際は、処理スピードにも注目しましょう。特に、取引先が多く、大量の帳票を一括で作成・配信する業務がある場合、処理能力が不足していると作業が滞り、業務に支障をきたすおそれがあります。また、帳票の発行件数などに上限が設けられているケースもあるため、想定される運用規模に対応できる性能かも併せて確認が必要です。
電子帳簿保存法やインボイス制度に対応できるか
電子帳簿保存法やインボイス制度への対応状況も、確認しておきたいポイントのひとつです。例えば、電子帳簿保存法に準拠するためには、タイムスタンプの付与、検索機能、変更履歴の保持など、一定の要件を満たす必要があります。
インボイス制度に対応するには、請求書に登録番号や税率・消費税額などの情報を正確に記載する機能が必要です。こうした法制度に対応したサービスであれば、法令遵守と業務効率化を両立できます。
セキュリティ対策は十分か
請求書や注文書などの帳票には、顧客情報や取引金額などの重要なデータが含まれています。そのため、電子帳票配信サービスを選ぶ際には、セキュリティ対策の内容を必ず確認しましょう。
例えば、ユーザーごとのアクセス権限の設定やログイン履歴の管理、操作ログの記録、データの暗号化などの機能が備わっていれば、情報漏洩や不正アクセスのリスクを低減でき、帳票業務を安全に運用できます。
サポート体制が充実しているか
スムーズに運用を開始するためには、サポート体制が充実しているかどうかも重要なポイントです。例えば、導入時の初期設定やオリジナルレイアウトの作成、基幹システムとの連携などでつまずいた際に、適切なサポートが受けられるサービスなら心強いでしょう。
また、運用開始後のトラブルや操作に関する不明点への対応内容についても、事前に確認しておくと安心です。加えて、チャット・メール・電話といった問い合わせ手段や、対応時間も確認しておきましょう。
基幹システムと連携できるか
帳票の作成から配信までを自動化したい場合は、基幹システムとの連携機能が欠かせません。配信先マスタや帳票名など、基幹システム上の情報を自動で取り込めるサービスであれば、帳票の作成から配信までをワンストップで実行でき、作業の手間やミスを大幅に削減できます。API連携機能の有無や、自社の既存システムとの連携に対応しているかどうかも、事前に確認しておきましょう。
料金体系は利用用途にあっているか
電子帳票配信サービスを選定する際は、料金体系が自社の利用用途や運用規模に適しているかを確認することも大切です。サービスを導入することで郵送コストや人件費の削減が期待できますが、それ以上の費用がかかってしまっては、費用対効果が高いとはいえません。
例えば、配信する帳票の件数が多い場合は、定額制のほうがコストを抑えやすいでしょう。一方、配信数が少ない場合は、従量課金制のほうが費用対効果が高くなるケースもあります。
初期費用・月額費用・追加機能の料金なども含めて、トータルでのコストを比較・検討しましょう。
電子帳票配信サービスの活用事例
ここでは、電子帳票配信サービスを実際に活用している企業の事例を紹介します。導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
Pasco / 敷島製パン株式会社様
「Pasco」ブランドで広く知られる敷島製パン株式会社様では、毎月約5,000枚にのぼる請求書発行業務の負担軽減を目的に、電子帳票配信サービスを導入しました。
従来は、大量の請求書をPDF出力し、手作業で封入・郵送するというプロセスを踏んでおり、多くの手間とコストが発生していました。さらに、郵便法の改正により土日祝日の配達が休止となったことで、取引先への請求書の到着が遅れるという新たな課題も生じていました。
こうした背景から電子帳票配信サービスの導入に踏み切った結果、現場からは「封入作業にかかる時間が大幅に短縮された」といった声が寄せられています。現在は一部の取引先を対象に運用を進めていますが、将来的にはすべての取引先との帳票やり取りを電子化する方針とのことです。
株式会社東急コミュニティー 様
マンションから公共施設まで幅広い不動産の管理運営を手がける株式会社東急コミュニティー様では、協力会社への膨大な支払明細の発送業務による負担を軽減するため、電子帳票配信サービスを導入しました。
同社では建物単位で支払金額を細かく管理しており、1社あたり月に数千件もの支払明細が発生します。全体では月間10万件以上の支払明細を処理する必要があり、そのうち6~7万件を協力会社へ送付していました。
支払いは月4回に分けて行っており、1回の処理に3~4時間、月末など繁忙期には1日かかることもあったそうです。
電子帳票配信サービスの導入により、従来の郵送作業にかかっていた時間を大幅に短縮できました。さらに、Web上で明細内容を確認できるようになったことで、支払明細に関する問い合わせも大きく減少し、業務効率の向上を実感しています。
電子帳票配信サービスを導入する際の注意点
電子帳票配信サービスは帳票業務を効率化できる一方で、導入時にはいくつかの注意点があります。スムーズに運用を開始するために、事前に注意点についてもチェックしておきましょう。
電子化する帳票の整理をする必要がある
電子帳票配信サービスを導入する際は、どの帳票を電子化の対象とするかを明確にしておく必要があります。まずは、自社で発行している帳票の種類を整理し、優先的に電子化すべきものを見極めましょう。
送付件数が多く、業務への影響が大きい帳票を優先して電子化を進める場合は、発行件数が少ない帳票についても将来的な対応を見据えておくと安心です。
このように、自社の運用実態に応じて電子化の範囲と優先順位を明確にしておくことで、導入後のトラブルや混乱を防ぎ、スムーズな活用につなげられます。
導入の際に教育コストがかかる
新たなシステムを導入する場合、操作方法や運用ルールを関係者に習得してもらわなければなりません。電子帳票配信サービスも例外ではなく、一定の教育コストが発生します。
例えば、導入直後は操作ミスやルールの理解不足によるトラブルが起きやすいため、事前にマニュアルを整備し、研修や説明会を実施しましょう。併せて、導入後の問い合わせ対応や継続的なフォローアップを想定し、社内の教育体制を整えておくことも重要です。
電子帳票配信サービスで業務を効率化しよう
電子帳票配信サービスを導入すれば、帳票の作成・配信・管理をシステム上で一元化でき、紙や郵送にかかっていた手間やコストを大幅に削減できます。法制度への対応やBCP対策の面でも効果が期待できるため、ぜひ活用を検討してみてください。
NTTコム オンラインが提供する「ナビエクスプレス」は、既存の帳票や伝票のレイアウトをそのまま電子化できるうえ、ExcelやCSVなど帳票以外のファイル送付にも対応しています。さらに、基幹システムと連携し、既存の配信先マスタや帳票名を利用してワンストップ配信が可能です。電子帳票配信サービスの導入をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【
帳票、書類の電子化
】
最新のコラム

2025/12/09

2025/10/22