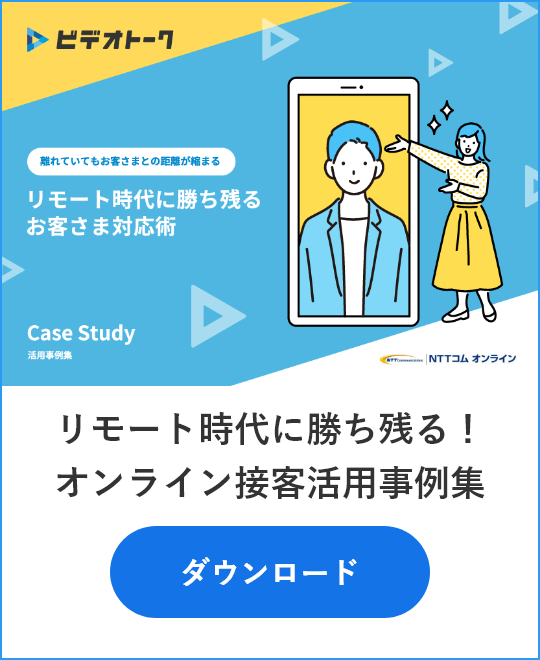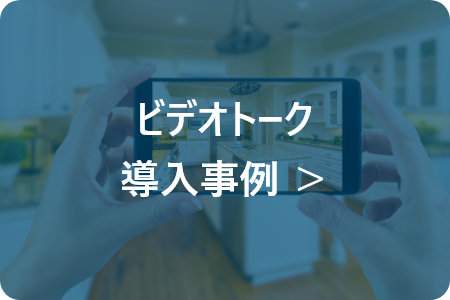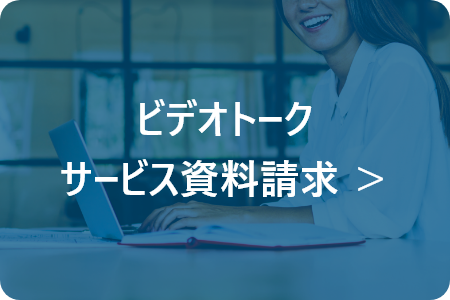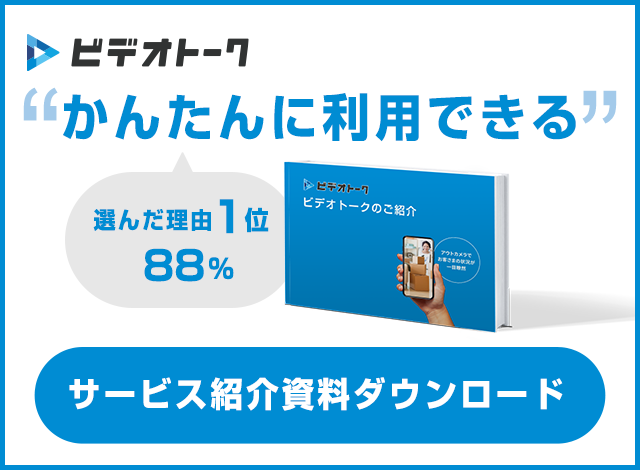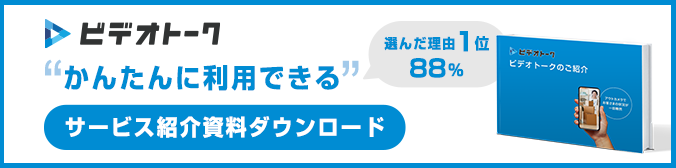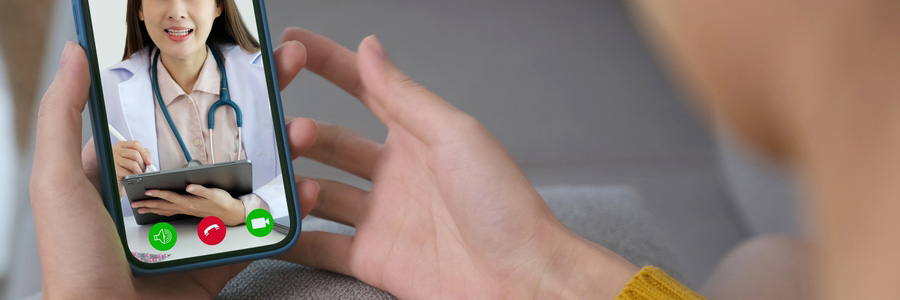
2025/02/14
オンライン診療は電話のみではできない?オンライン診療の条件と事例を紹介
新型コロナウイルス感染症が流行した際、オンライン診療の実施条件を緩和する特例が設けられました。しかし、その特例は2023年7月で終了しており、現在は基本的に電話のみのオンライン診療は認められていない点に注意が必要です。
本記事では、オンライン診療を継続的に行うための条件や、実際にオンライン診療を導入している医療機関の事例を紹介します。オンライン診療におすすめのビデオ通話ツールも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
- オンライン診療とは、医師と患者がビデオ通話ツールや電話を使って症状を伝え、遠隔で診療を行う方法
- 0410対応によって電話やビデオ通話による診療や服薬指導が一部解禁されたが、この特例は2023年7月31日に終了した
- 現在、オンライン診療を行うためには、映像と音声の両方で患者の状態を確認できるビデオ通話ツールが必須となっている
- オンライン診療専用ツールのほか、一般的なビデオ通話ツールでもオンライン診療は可能なため、目的や予算に合ったツールを選ぶ必要がある
オンライン診療とは?電話診療では処方箋発行ができない?

オンライン診療は、医師と患者が遠隔地にいても診療を受けられる便利な方法です。しかし、現在は電話のみでのオンライン診療では処方箋の発行が認められていません。
この背景には、新型コロナウイルス感染症の流行時に時限的・特例的に定められた「0410対応」があります。はじめに、オンライン診療の概要や0410対応について詳しく見ていきましょう。
オンライン診療とは?
オンライン診療は、医師と患者がビデオ通話ツールや電話を使って症状を伝え、診療を行う方法です。自宅や遠隔地にいながら医師の診療を受けられるため、「頻繁に通院するのが難しい」「近隣に専門医がいない」など、さまざまな事情で対面診療が困難な場合に役立ちます。
もともと、オンライン診療は離島や過疎地域に住む患者への医療提供手段として活用されていました。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行を受け、感染防止対策の一環として電話やビデオ通話を用いたオンライン診療が急速に普及しました。
0410対応とは?
「0410対応」とは、令和2年4月に新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて定められた、時限的・特例的なオンライン診療の緩和措置のことです。これにより、電話や情報通信機器を使った診療や服薬指導が一部解禁され、多くの医療機関で取り入れられました。
この特例措置は、院内感染を含む感染拡大のリスクを抑えることを目的としており、患者が医療機関に足を運ばなくても診療を受けられる環境を整えるためのものです。0410対応によって、慢性疾患のある患者や感染リスクを避けたい患者が、自宅から診療や処方箋の発行を受けられるようになりました。
2023年7月で0410対応が終了
0410対応は新型コロナウイルス感染症の感染対策として導入された一時的な特例措置であり、2023年7月31日をもって終了しました。これにより、現在は電話のみで診療を行った場合、処方箋を発行することができなくなっています。
オンライン診療を実施する際は、患者の顔や状態を確認できるビデオ通話の使用が求められ、以前のような緩和措置は適用されません。初診はもちろん、再診でも電話診療のみでの処方箋発行はできないため、注意してください。
オンライン診療を継続的に行うための条件
0410対応の終了後も、すべてのオンライン診療ができなくなったわけではありません。2023年8月以降は、一定の条件を満たす場合に限り、オンライン診療の実施が認められています。
オンライン診療が可能なのは、以下のケースです。
- 初診のオンライン診療
- 再診の電話診療
- 再診のオンライン診療
一方で、次のような場合にはオンライン診療は認められていません。
- 初診の電話診療
- 再診の電話診療での処方箋発行
厚生労働省はオンライン診療について、リアルタイムで視覚および聴覚の情報を含む通信手段を使用することを指針としており、文字・写真・録画映像のみのやりとりでは診療を完結させてはならないと定めています。
そのため、医療機関がオンライン診療を継続的に行うためには、ビデオ通話が可能なシステムを導入した上で、最新の指針に沿った対応が必要です。
オンライン診察を行うためにはビデオ通話ツールの選定が必要となる

オンライン診療を行うには、映像と音声をリアルタイムでやりとりできるビデオ通話ツールの導入が必須です。利用できるツールは、オンライン診療専用ツールと一般的なビデオ会議ツールの大きく2種類に分かれます。
オンライン診療専用ツールは、ビデオ通話機能に加え、予約受付・問診票作成・決済機能などが標準搭載されている点がメリットです。診療業務を一括管理できるため、効率的に運用できます。
一方、一般的なビデオ会議ツール(ZoomやMicrosoft Teamsなど)は、導入コストを抑えやすいのが特徴です。また、仕事やプライベートで使い慣れたツールなら、患者側もスムーズに操作できるでしょう。
それぞれ機能やコストが異なるため、目的や予算に応じて最適なものを選んでください。
オンライン診療を始めるための準備や流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。
関連記事:オンライン診療の始め方とは?流れと注意点、事例を解説
「ビデオトーク」を活用したオンライン診療の事例

NTTコム オンラインが提供するビデオ通話ツール「ビデオトーク」は、医療機関のオンライン診療にも活用されています。専用アプリのインストールやアカウント登録が不要で、簡単な操作でオンライン診療が行えるのが特徴です。
ここでは、ビデオトークを実際に導入している医療機関の事例を紹介するので、オンライン診療の導入を検討している方はぜひ参考にしてください。
社会医療法人財団石心会 第二川崎幸クリニック
第二川崎幸クリニックでは、新型コロナウイルス感染症の流行時に、保健所の健康観察業務をサポートする目的でビデオトークを導入しました。オンライン診療は特別な診察室の設置や厳しいゾーニングが不要で、陽性者が増えた際にも柔軟に対応できる体制を整えました。
ビデオトークの大きなメリットは、SMSでビデオ通話用のURLを患者に送信し、アクセスするだけで診療を開始できる操作のシンプルさです。専用アプリのインストールが不要なため患者側の負担が少なく、忙しい医師も直感的に使いこなせます。
今後は、MRIやCTスキャンなどの検査に訪れる患者の初診や、セカンドオピニオンの相談窓口としても活用を広げていく予定です。
あかちゃんとこどものクリニック
あかちゃんとこどものクリニックでは、定期的に通院している患者や軽症の患者、継続的な処方を希望する患者などを対象にオンライン診療を実施しています。
以前は専用アプリやアカウント登録が必要なビデオ通話ツールを使用していましたが、操作の手間や利便性の課題があり、事前設定の不要な「ビデオトーク」に切り替えました。これにより、患者側の負担を軽減し、スムーズなオンライン診療が可能となっています。
また、患者がトークルームに入室したことを確認した上で医師が入室できるため、対面診療との調整がしやすくなった点も大きなメリットです。今後は、離乳食や授乳など子育てに関する個別指導や相談にもビデオトークを活用できないか検討を進めています。
オンライン診療はアカウント登録・アプリダウンロード不要のビデオトークがおすすめ
2023年7月31日に「0410対応」が終了し、オンライン診療を行うには、映像と音声のやりとりが可能なビデオ通話ツールの導入が必須となりました。オンライン診療を受ける患者の中には、体調不良や怪我、育児、介護など、さまざまな事情を抱えている方も多いため、できるだけ負担を軽減できるツールを選ぶことが重要です。
NTTコム オンラインが提供する「ビデオトーク」は、アプリのダウンロードやアカウント登録が不要で、SMSに届いたURLをタップするだけで簡単にビデオ通話を開始できる手軽さが特徴です。
本記事で紹介したように、実際に医療機関でも活用されており、スムーズなオンライン診療を実現しています。オンライン診療向けのビデオ通話ツールをお探しの方は、ぜひお気軽にご相談ください。