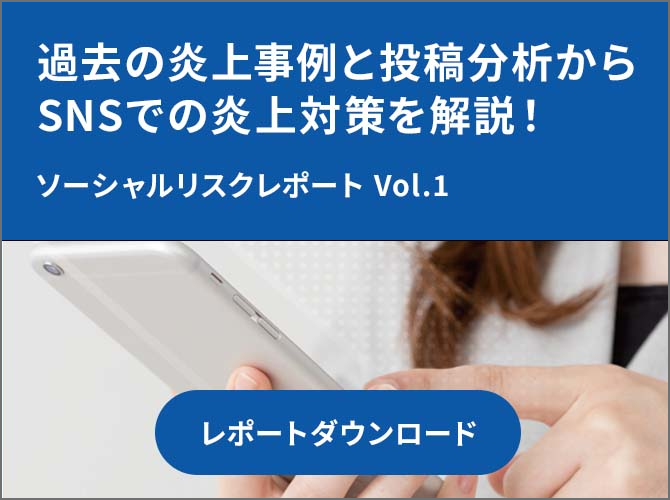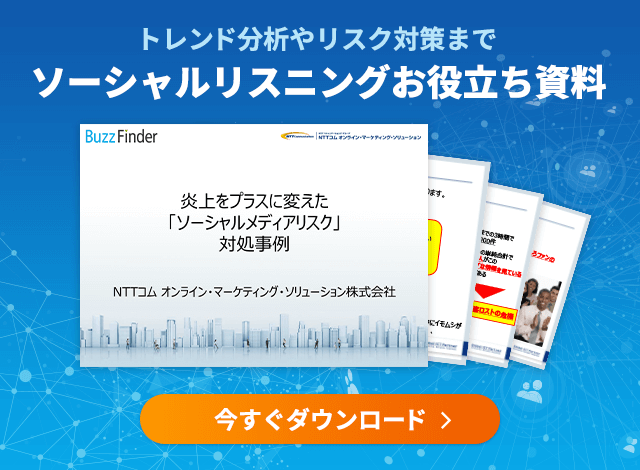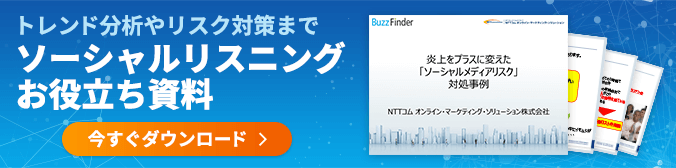2025/08/01
ソーシャルリスニングによるトレンド分析
ニーズ調査とは?7つの手法やフレームワーク、成功のポイントを解説
顧客の本音を把握し、商品やサービスの改善に活かすためには「ニーズ調査」が欠かせません。ニーズ調査とは、顧客が本当に求めているものや、まだ言語化されていない潜在的なニーズを明らかにするための取り組みです。適切な調査を行えば、マーケティング戦略や商品開発の方向性が見え、競合との差別化にもつながります。
本記事では、ニーズ調査の効果や実践的な調査手法、成功のポイントなどを網羅的に紹介します。ニーズ調査を実施したいと考えている企業のご担当者様は、ぜひ参考にしてください。
- ニーズ調査により顧客の顕在・潜在ニーズを把握することで、市場での差別化や商品改善につなげることができる
- アンケートやインタビュー、行動観察などの多角的手法を組み合わせることで、深い洞察と定量データをバランスよく収集できる
- ニーズ調査を成功させるためには、調査目的とターゲットの明確化、目的に応じた手法の選定、データの分析・共有などが必要
ニーズ調査の目的とは
ニーズ調査とは、顧客や市場の需要・要求を体系的に把握する市場調査手法の一つです。企業が商品やサービスを開発・改善する際に、消費者の本当のニーズを把握することで、的確な意思決定が可能になります。
また、ニーズ調査はマーケティング戦略を構築するための重要な情報収集プロセスでもあります。ニーズ調査の主な目的は、以下の通りです。
- 新商品・サービス開発時の需要予測
- 既存商品の改善ポイントの特定
- 競合他社との差別化要因の発見
- 新たな市場機会の発見
- 顧客満足度の向上
ニーズの種類(顕在ニーズ・潜在ニーズ)
ニーズには、すでに表面化している「顕在ニーズ」と、本人も自覚していない「潜在ニーズ」があります。これらを正しく見極めることは、効果的な商品開発やマーケティング戦略の立案において非常に重要です。
顕在ニーズ
顕在ニーズとは、顧客が自ら明確に意識している「これが欲しい」「これが必要だ」と感じているニーズのことです。このようなニーズは、アンケートやヒアリングなどの手法で比較的簡単に把握することができます。
たとえば、エアコンが壊れたために「新しいエアコンが欲しい」と思うのは顕在ニーズです。すでにニーズが表面化しているため、商品化に向けた需要予測もしやすく、企業側も対応しやすい傾向にあります。マーケティング施策を立てるうえで、最初に捉えやすいニーズといえるでしょう。
潜在ニーズ
潜在ニーズとは、顧客自身がまだ気づいていない、あるいはうまく言葉にできていない欲求や要求のことです。表面的には見えにくいため、行動の観察や深層心理の分析などを通して探る必要があります。
たとえば、「不便だと感じていたが、改善方法が思いつかなかった」という状況に、潜在ニーズが隠れていることがあります。これを的確に捉えることができれば、競合他社にはない、独自の価値を提供できる可能性が高まるでしょう。潜在ニーズは、革新的な商品やサービス開発のヒントとなります。
ニーズとウォンツの違い
「ニーズ」と「ウォンツ」は似たような意味に思われがちですが、マーケティングにおいては明確な違いがあります。ニーズとは、生活上の課題や不足を補いたいという「本質的な欲求」を指し、一方のウォンツは、その欲求を満たすための「具体的な手段」を意味します。
たとえば、「喉が渇いた」という状態がニーズであり、「水を飲む」「炭酸飲料を飲む」といった選択がウォンツです。まずはニーズを的確に捉え、それに応じたウォンツを提案・具体化することで、効果的なマーケティング戦略を展開することが可能になります。
ニーズ調査の効果
ニーズ調査を行うことで、顧客の本当の要求や市場の動向を正確に把握でき、商品やサービスの開発・改善に役立てることができます。ここでは、ニーズ調査によって得られる主な効果について紹介します。
新商品・サービス開発の成功につながる
ニーズ調査を実施することで、顧客が本当に求めている価値や課題を把握でき、市場に受け入れられやすい商品・サービスの開発が可能になります。特に、開発の初期段階でニーズを明確にすることは、無駄な試作や方向転換を減らし、開発コストの削減や成功率の向上にもつながるのです。
調査結果をもとにすることで、以下のような効果が期待できます。
- 市場ニーズに合致した機能の優先順位付け
- 開発リソースの効率的配分
- 開発期間の短縮と品質向上
既存商品・サービスの満足度向上につながる
既存の商品やサービスに対する顧客のニーズを調査することで、具体的な改善点を明確にでき、満足度の向上につなげられます。顧客満足度の向上は、顧客のロイヤルティを強化し、結果として売上増加にも寄与する重要な要素です。調査を通じて不満の原因を特定し、その背景を理解することで、的確な対応が可能になります。
既存商品・サービスにおけるニーズ調査には、以下のような改善効果が期待されます。
- 不満点の把握と改善による顧客離れ防止
- 追加機能やサービス開発による付加価値の向上
- リピート率の増加
- ポジティブな口コミやレビューによる新規顧客の獲得
新たなニーズや市場機会の発見につながる
ニーズ調査を実施することで、企業がこれまで想定していなかった新たな市場機会を発見することができます。特に潜在的な需要を見つけ出すことは、新規事業の立ち上げや既存事業の拡大に大きな可能性をもたらすでしょう。
このような調査は、市場の隙間や新しいニーズを捉える重要な手段です。ニーズ調査の具体的な効果としては、以下が挙げられます。
- 未開拓の市場セグメントを特定
- 新しい用途や使用場面を発見
- 新たなビジネスモデル創出の機会を得る
ニーズ調査の種類
ニーズ調査には大きく分けて、「定量調査」と「定性調査」の2つがあります。それぞれの特徴を理解することで、適切な調査方法を選択できます。
定量調査
定量調査は、数値データを収集し、それを統計的に分析することで市場や顧客の動向を把握する調査手法です。大規模なサンプルを対象とするため、客観的かつ信頼性の高いデータを得られ、市場全体の傾向や消費者の行動パターンを明確にできます。
主な手法には、アンケート調査やWeb調査、会場調査などがあり、多数の対象者から効率的に情報を集められるのが特徴です。特に、製品の需要や顧客の属性、購入意欲などを数値化して分析したい場合に有効です。こうしたデータは経営やマーケティングの意思決定に活用され、戦略の基盤として重要な役割を果たします。
定性調査
定性調査は、数値化できない質的な情報を集めて、顧客の深い心理や行動の背景を理解する調査手法です。少数のサンプルから詳細な意見や感情を聞き出すことで、新たな発見や仮説の創出につながります。
代表的な方法には、インタビュー調査やグループインタビュー、行動観察調査などがあり、潜在ニーズを知りたいときや、より具体的な改善点を知りたいときなどに適しています。定性調査は、表面的なデータだけでは見えにくい顧客の本音や価値観を捉えられるため、より効果的な商品開発やサービス改善が期待できるでしょう。
ニーズ調査で役立つフレームワーク
ニーズ調査を効果的に進めるためには、体系的に情報を整理・分析できるフレームワークの活用が欠かせません。ここでは、代表的な手法を紹介します。
RFM分析
RFM分析は、顧客の購買行動を「最新購入日(Recency)」「購入頻度(Frequency)」「購入金額(Monetary)」という3つの指標で評価する手法です。この分析を用いることで、顧客を価値レベルごとにセグメントし、それぞれのグループに合ったニーズを特定できます。
たとえば、最近商品をよく購入している顧客や高額を使っている優良顧客を明確にし、効率的にアプローチできるのが特徴です。RFM分析の主な効果は、以下のとおりです。
- 優良顧客の特定とニーズ把握
- 顧客のライフサイクルに応じたニーズ変化の理解
- セグメント別のマーケティング戦略の策定
- 顧客維持や新規獲得施策の最適化
セグメンテーション分析
セグメンテーション分析は、市場を似た特徴やニーズを持つ同質のグループに分割し、各セグメントのニーズを明確にするフレームワークです。人口統計学的要因(年齢・性別)、心理学的要因(価値観・ライフスタイル)、行動学的要因(購買行動)、地理学的要因(地域)を基準に市場を細かく分類します。セグメンテーション分析は効果的な戦略立案に欠かせない手法であり、以下のような効果が期待できます。
- 同質のニーズを持つ顧客グループの特定
- セグメント間のニーズの違いの明確化
- ターゲット市場の選定と集中戦略の策定
- 効率的なマーケティングリソースの配分
CTB分析
CTB分析は、顧客を「カテゴリー(Category)」「テイスト(Taste)」「ブランド(Brand)」の3つの視点から分類するフレームワークです。
- カテゴリー(Category):顧客が関心を持つ商品やサービスの種類
- テイスト(Taste):顧客の好みや嗜好、スタイル
- ブランド(Brand):顧客が支持する特定のブランドやブランドイメージ
CTB分析は顧客の主観的な好みに焦点を当てた手法であり、以下のような効果が期待できます。
- 趣味嗜好をベースにしたマーケティング戦略の立案
- 商品コンセプトの明確化
- 潜在顧客の特定
ニーズ調査の7つの手法
ニーズ調査には多様な手法があり、それぞれ特徴や目的に応じて使い分けることが重要です。ここでは、代表的な7つの手法を紹介します。
1|アンケート調査
アンケート調査は、あらかじめ作成した質問票を用いて顧客から回答を集める調査手法です。短期間で多数の回答を得られるため、広範囲のデータ収集に適しています。調査の効果を高めるには、目的に沿った仮説を立て、それに基づいて質問票を丁寧に設計することが重要です。
実施方法はオンライン調査や郵送調査など多様で、対象や状況に応じて使い分けられます。こうした特徴から、アンケート調査はニーズ把握の基本かつ代表的な手法として広く活用されています。
アンケート項目の例
効果的なアンケート調査には、目的に合った質問項目の設計が不可欠です。以下に、カテゴリー別の具体的な質問例をご紹介します。
商品・サービスを知った経路に関する質問例
「どのような媒体で当商品を知りましたか?」
購入・利用理由に関する質問例
「当商品を選んだ主な理由は何ですか?」
商品・サービスの品質に関する質問例
「商品の品質についてどの程度満足していますか?」
商品・サービスの満足度に関する質問例
「全体的な満足度を教えてください」
このような質問を組み合わせることで、ニーズを的確に把握することができます。
アンケート調査で守るべきマナー
アンケート調査を実施する際は、回答者の負担をできるだけ減らし、信頼性の高いデータを得るためにマナーを守ることが重要です。実施する際には、以下のようなマナーを守りましょう。
- 調査の目的や回答にかかる時間をわかりやすく伝える
- 個人情報の取り扱いについて説明し、同意を得る
- 質問数や回答時間を適切に設定し、回答者の負担を軽減する
- 1つの設問では1つの情報だけを尋ねる
- 表現は明確でわかりやすくする
- 回答者への感謝を伝え、調査結果を共有する
これらを守ることで、誠実な調査運営と良質なデータ収集が可能になります。
2|インタビュー調査
インタビュー調査は、調査対象者と直接対話しながら、より詳しい情報を得る手法です。アンケートでは見えにくい背景や理由、感情といった深い洞察を得るのに適しています。
1対1のインタビューでは個別の意見や体験をじっくり聞き取ることができ、グループインタビュー(フォーカスグループ)は複数人の意見交換から多角的な視点を引き出せます。
また、オンラインインタビューは場所を問わず実施可能で、手軽さが特徴です。質問はオープンクエスチョン(自由回答)で対象者の考えを広く引き出し、クローズドクエスチョン(選択肢回答)で具体的な情報を得るなど、使い分けることで調査の質を高めることができます。
インタビュー調査で守るべきマナー
インタビュー調査では、対象者との信頼関係を築き、本音を引き出すためのマナーが非常に重要です。以下の点に配慮することで、より有意義な情報を得ることができます。
- 事前に日程調整を行い、相手にとって負担の少ない時間・場所を選ぶ
- 録音や録画を行う場合は事前に許可を取り、個人情報の取り扱いについて説明する
- リラックスした雰囲気をつくり、相手の話に耳を傾ける姿勢を保つ
- 相手の答えを誘導するような質問は避け、中立的な問いかけを意識する
- インタビュー時間を守り、長時間にわたって負担をかけないよう配慮する
- これらを徹底することで、回答者からの信頼を得られ、質の高い回答を引き出すことができるでしょう。
3|行動観察調査(エスノグラフィー)
行動観察調査(エスノグラフィー)は、対象者の自然な行動を観察することで、言語化されていないニーズや課題を明らかにする調査手法です。質問による調査とは異なり、顧客の発言に依存せず、実際の顧客の行動を客観的に把握できるのが特徴です。たとえば、店舗での動線や商品の扱い方、無意識のしぐさなどを観察することで、潜在的なニーズや改善のヒントを得ることができます。
行動観察調査には、以下のような効果が期待できます。
- 無意識の行動パターンの発見
- 実際の使用場面における課題の特定
- 顧客の言動と行動の違いの把握
- 新たな使用方法や用途の発見
調査で得られた観察結果は、商品・サービスの改良や新たな企画立案に活用できます。
4|競合調査
競合調査は、同じ市場で活動する他社の製品・サービスや戦略を分析し、自社との違いや強み・弱みを把握する調査手法です。特にニーズ調査においては、競合がどのような顧客ニーズに応えているかを知ることで、まだ満たされていない潜在ニーズを発見する手がかりになります。
調査方法には、競合のWebサイトや広告・SNSの分析、実店舗やECサイトの利用体験、口コミの収集などがあり、差別化戦略や新規企画の立案に役立ちます。
5|AIを活用した調査
AIを活用した調査では、ChatGPTやGeminiなどのAIツールを用いて、大量のデータを短時間で分析し、これまで見つけにくかったニーズを特定できます。たとえば、SNSや口コミサイトに投稿された文章から共通の意見や不満を抽出したり、購買履歴データから顧客の潜在的なニーズを予測したりするなども可能です。また、Web上の顧客行動ログを分析することで、行動パターンや関心の変化を捉えることもできます。
AIの活用には以下のような効果が期待できます。
- 大量のテキストデータからのニーズ抽出
- 購買データからの潜在ニーズの予測
- 顧客行動パターンの分析
ただし、AIだけでは得られない深い洞察もあるため、他の手法と併用することが重要です。
6|社内情報を活用した調査
社内情報を活用した調査は、企業がすでに保有している内部データをもとに顧客ニーズを把握する手法です。新たに調査を行う必要がないため、コストを抑えつつ、実用的なインサイトを得ることができます。
たとえば、顧客データベースや販売履歴、サポート対応の記録などを統合的に分析することで、顧客の行動傾向や課題を浮き彫りにできます。また、営業担当者やカスタマーサポートなど、顧客と接点のある従業員へのヒアリングも有効です。社内情報の活用には、以下のような効果があります。
- 顧客の購買履歴からのニーズ推定
- サポート問い合わせからの課題発見
- 営業担当者の顧客情報の活用
7|ソーシャルリスニング
ソーシャルリスニングは、SNSやレビューサイト、掲示板などに投稿されたユーザーの発言を収集・分析し、顧客のニーズや感情を把握する調査手法です。自然な状況で発せられた意見だからこそ、リアルな本音や潜在的なニーズを発見しやすいのが特徴です。
特にX(旧Twitter)やFacebook、InstagramといったSNSプラットフォームを活用すれば、トレンドや評判、顧客の期待や不満などを把握することができ、新たな商品開発やサービス改善にもつながるでしょう。
【関連記事】
ソーシャルリスニングとは|意味や分析方法の解説と導入事例を紹介!
ソーシャルリスニングの効率・精度を上げるには?
ソーシャルリスニングの効率と精度を高めるには、専用ツールの活用が不可欠です。自社だけで膨大なSNS投稿やレビューを手作業で分析するのは時間と労力がかかり、限界があります。ソーシャルリスニングツールを使うことで、大量のデータを迅速かつ正確に解析できるようになります。
さらに、感情分析やトレンド検出など多彩な機能を備えたツールを選ぶことで、顧客の本音や潜在ニーズを効率よく抽出し、マーケティング戦略に活かすことができるでしょう。
【関連記事】
ソーシャルリスニングツールの選び方とは?比較のポイントを詳しく解説
ニーズ調査の基本的なフロー
ニーズ調査を効果的に進めるためには、目的設定からデータ収集、分析、報告までの基本的な流れを押さえることが重要です。ここでは、それら主要なステップを解説します。
アンケート調査の例
アンケート調査は以下のような流れに沿って行います。
- 調査目的とターゲットの明確化
- 企画の設計
- 質問項目の設計と事前テスト
- アンケート調査の実施
- データ収集と分析
- 報告書作成と関係者への共有
このような流れで進めることで、信頼できるデータをもとに、より実践的な改善や提案につなげていくことができます。
ソーシャルリスニングの例
ソーシャルリスニングの基本的なフローは以下のとおりです。
- 目的やターゲットの明確化
- 分析するプラットフォームの選定
- キーワードの設定
- データ収集期間の設定と実施
- 収集データの分類と整理
- データの分析(感情分析・トレンド分析など)
- 結果の共有とマーケティングへの活用
このような手順を踏むことで、SNS上の声を的確に読み取り、マーケティング施策に活かすことができます。
ニーズ調査を成功させるポイント
ニーズ調査を成功させるには、目的の明確化や適切な手法選択、そして正確なデータ分析などが必要です。ここでは重要なポイントを解説します。
調査目的とターゲットを具体的に設定する
調査目的が曖昧だと、有効な結果を得ることは難しくなります。たとえば、新商品のニーズ把握や既存サービスの改善点特定など、具体的な課題を設定することが重要です。また、調査結果をどのように活用するかも事前に検討しておく必要があります。さらに、調査対象となるターゲット層を明確に定義することで、より的確なデータ収集が可能となります。
手法は目的に合ったものを選ぶ
調査目的やターゲットに応じて、最適な調査手法を選ぶことも重要です。定量調査は多数のデータを数値化し全体の傾向を把握するのに適し、定性調査は深い洞察や背景理解に向いています。目的に合った手法を選ぶことで、効率的かつ効果的にニーズを把握できます。
また、予算や調査にかけられる時間、必要な人材などのリソース、収集したい情報の種類なども考慮して、最適な手法を選択しましょう。
複数の手法を組み合わせて実施する
単一の調査手法だけでは見落としがちなニーズを発見するためには、複数の手法を組み合わせることが効果的です。たとえば、アンケート調査とソーシャルリスニングを併用することで、異なるセグメントから多様なデータを収集できます。手法を組み合わせることにより、以下のような効果が期待できます。
- 幅広い視点からの総合的にニーズを把握できる
- 調査結果の信頼性と妥当性が向上する
- 異なる手法により結果を相互補完できる
調査対象に先入観を持たない
調査者の先入観や仮説が調査結果に影響を与えることを防ぐため、常に客観的な姿勢を保つことが重要です。たとえば、質問設計で特定の答えを誘導する表現を避けることが挙げられます。また、分析時にも偏りに注意し、多角的にデータを検証する必要があります。
中立的な質問文を作成し、異なる視点を持つメンバーで分析チームを組むことで、偏りのない公正な結果を導きやすくなります。こうした配慮が、信頼性の高いニーズ調査につながるでしょう。
複数のセグメントで調査を実施する
顧客は一様ではないため、異なるセグメントごとにニーズの違いを把握することが重要です。年齢、性別、職業、地域などの属性別に分析し、各セグメントの特有のニーズを明確化します。
また、競合他社の主要なユーザー層と比較することで、自社の強みや改善点を把握できるでしょう。こうした多角的な調査は、より精度の高いターゲティングや商品・サービスの差別化ポイントの特定に役立ち、市場での競争力向上につながります。
データを分析して社内で共有する
収集したデータを適切に分析し、組織内で共有することで、ニーズ調査の価値を最大化できます。分析結果はグラフやチャートなどで分かりやすく可視化し、関係者が理解しやすい形で報告することが重要です。
また、統計的に有意な結果を抽出し、その背景を正しく解釈したうえで、具体的な改善提案や戦略立案につなげることが求められます。こうした一連のプロセスが調査成果の実践的な活用を後押しします。
調査項目の抜け漏れを防ぐ
調査項目に抜け漏れがあると、重要なニーズを見逃すリスクが高まります。そのため、体系的な項目設計が不可欠です。フレームワークやチェックリストを活用して、調査項目の網羅性を確保しましょう。
また、項目を整理・分類し、複数の視点からチェックを行うことも重要です。さらに、事前テストを実施して質問の妥当性や理解度を確認し、必要に応じて修正することで、質の高い調査設計が実現します。
SNSでのニーズ調査に有効なソーシャルリスニングツール「Buzz Finder」
「Buzz Finder」は、NTTコム オンラインが提供するソーシャルリスニングツールです。企業のリスク対策や顧客の声(VoC)の分析に特化しています。主な特徴として、X(旧Twitter)の公式全量データをほぼリアルタイムで収集し、迅速な分析と通知が可能です。また、ニュース、掲示板、Facebook、Instagramなど、多様なメディアの投稿分析にも対応しています。
特にニーズ調査においては、以下の機能が有効です。
- 投稿分類機能:キーワードによって投稿を自動的に分類し、分析対象を明確にします。
- ノイズフィルタリング:分析対象外の投稿を除外し、データの精度を向上させます。
- デイリートピックメール:毎日の投稿量と主な話題をメールで通知し、手軽に最新の顧客の声を把握できます。
導入事例|情報通信サービス業 様
情報通信サービス業様は、以前以下のような課題をお持ちでした。
- [広報部門]SNS上で炎上が発生した際、投稿内容を踏まえたメディア対応の準備を整えたい
- [カスタマーサービス部門]SNSに寄せられる利用者の声を、自社のサービス改善に役立てたい
- [お客様対応センター]炎上やクレームが表面化する前に、影響の兆しをつかんでおきたい
- ツール導入後は、以下のような効果を実感されています。
- [広報部門]急増する投稿の検知と自動レポートにより、報道対応やプレス対応のスピードが向上した
- [カスタマーサービス部門]SNS上の顧客の声を社内で共有する体制が整い、改善への取り組み意識が全体で高まった
- [お客様対応センター]SNSの反応を日々モニタリングすることで、小さな変化にも素早く対応できるようになった
ニーズ調査はマーケティング戦略の方向性を決める効果的な手法
ニーズ調査は、顧客が本当に求めていることを明らかにし、商品やサービスの改善、訴求方法の最適化につなげる重要な取り組みです。市場の変化に柔軟に対応し、競合との差別化を図るためにも、調査結果をもとにした戦略設計は欠かせません。的確なニーズ把握が、マーケティングの方向性を定める大きな指針となるでしょう。
Buzz Finderは、SNS上の投稿をリアルタイムで収集・分析できるソーシャルリスニングツールです。炎上リスクの早期発見や顧客の声の把握に役立ち、広報・CS業務の質を高めます。NTTコム オンラインでは、ソーシャルリスニングに関する事例レポートを公開しています。効果的なソーシャルリスニングの実践に役立つ情報を、ぜひご活用ください。
関連記事

2022/07/28

2021/08/12