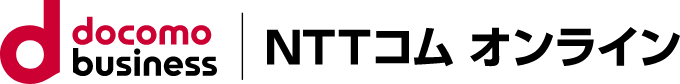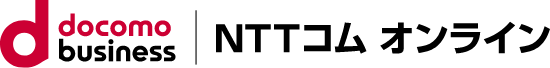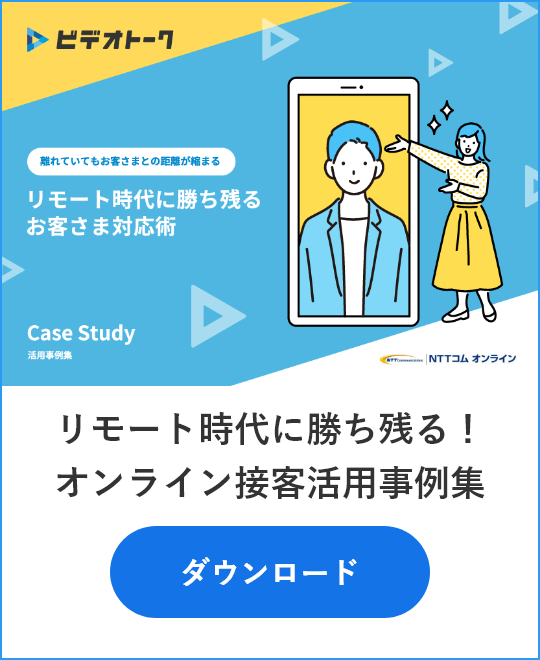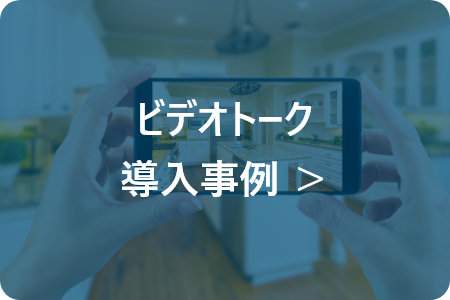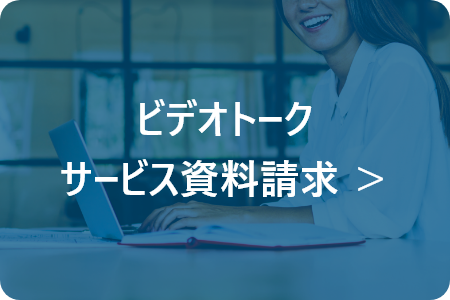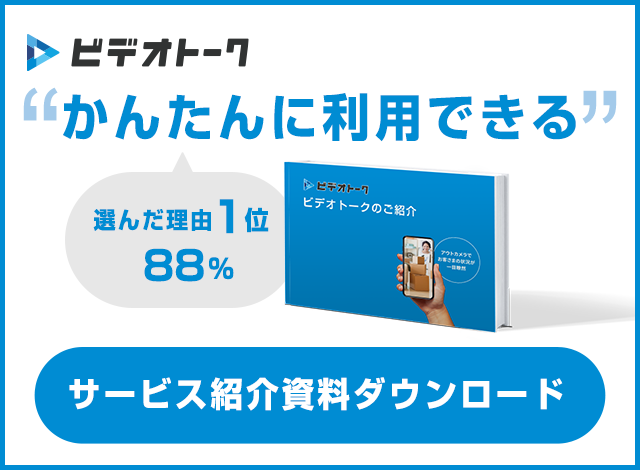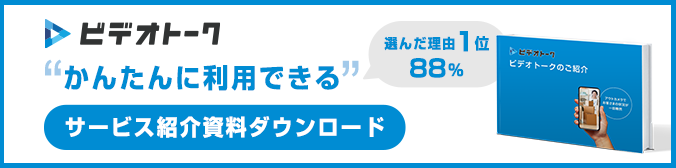更新日:2023/12/18(公開日:2021/06/15)
【医療機関向け】オンライン診療の基本知識とツールの選び方
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、オンライン診療の利用が一気に進んでいます。通院の必要がなくなることで、オンライン診療は、病院側・患者側双方にメリットをもたらします。導入を検討しているものの、何から始めるべきか迷うという病院関係者も多いでしょう。
そこで今回は、オンライン診療の導入を検討している病院関係者の方に向けて、オンライン診療のメリットや診察の流れ、必要なもの、オンライン診療に必要不可欠なツールの選び方をご紹介します。
- オンライン診療とは、ビデオ通話を通してインターネット上で行う診療・治療のこと
- オンライン診療は新型コロナウイルスの影響や高齢化への対応、デジタル化が求められるなかで注目を集めている
- オンライン診療は通院の負担を軽減できる、24時間予約ができる、通院の継続率が高まるなど患者と医療機関の双方にメリットがある
- オンライン診療ツールを選ぶ際はコスト、機能、使いやすさ、サポートの充実さをチェックする
オンライン診療とは
オンライン診療とは、スマートフォン・パソコン・タブレットのビデオ通話を通して、インターネット上で行う診察・治療のことです。患者は通院することなく、居場所を問わずに診察を受けられます。
オンライン診療は、厚生労働省が2018年3月に発表した「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、次のように定義されています。
“遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。”
(出典:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針 平成 30 年3月 (令和4年1月一部改訂)」)
オンライン診療が注目されている背景
オンライン診療が注目されている背景には、厚生労働省による推進の動きと、新型コロナウイルス感染症拡大による規制緩和があります。
オンライン診療は、もともとは「遠隔診療」の一つとして、離島やへき地など、医療機関が少ない地域で限定的に活用されていました。しかし、2018年3月にはオンライン診療のさらなる普及に向けて、厚生労働省から医療機関向けに、医療の質のさらなる向上と、よりよい医療を得られる機会を増やすためのガイドラインが出されました。
その後、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、厚生労働省は2020年4月13日以降、2回目からの診察に限定されていたオンライン診療を初診でも認める決定をしました。
スマートフォン端末や光回線が普及し、高齢化への対応やデジタル化が求められるなか、今後もオンライン診療は、さらに広がっていくと見られています。
関連記事:オンライン診療と親和性の高いビデオ通話。IT活用で患者にとってより良い医療の提供を
オンライン診療の対象者
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた特別措置によって、以前よりも多くの人が、オンライン診療の対象者となりました。
オンライン診療は、2018年度に保険適用とされましたが、本来、医療保険を利用してオンライン診療を受けられるのは、生活習慣病やがん、難病、認知症などで、定期的に医療機関を受診する人に限定されていました。
しかし、新型コロナウイルス感染症が拡大していることに鑑みた時限的・特例的な対応として、厚生労働省は2020年4月10日にオンライン診療に関する通達を発出しました。この通達によって、対象者を特定の疾患に限定せず、医師の判断で初診も含めた電話やオンラインによる医療相談・受診ができるようになりました。
患者にとってのオンライン診療のメリット

オンライン診療は多くのメリットがあります。まずは患者にとってのオンライン診療のメリットについて紹介します。
通院にかかる負担を軽減できる
オンライン診療の大きなメリットは、通院にかかる負担を軽減できることです。病院に足を運ばなくても自宅などから診察が受けられるため、通院する時間的負担から解放され、待ち時間も削減されます。また、オンライン診療は距離的な負担もなくすことができます。移動に負担がかかる高齢者や、けがなどが原因で通院が難しい場合も受診が可能です。さらに移動のための金銭的なコストも削減できます。
仕事の休憩時間や、予定と予定との間などのすきま時間を有効活用できるため、「忙しいから通えない」という状況も避けやすくなります。
24時間予約ができ、好きな場所・好きな時間に診療を受けることができる
病院の予約をしようと思っても、受付時間外のためできなかったという経験を持つ方は多いのではないでしょうか。特に仕事が忙しい方は、病院の受付時間帯である日中に時間を作ることが難しいかもしれません。そのため定期的な受診が必要な場合でも、後回しになってしまうこともあるでしょう。
オンライン診療であれば、システムによって違いもありますが基本的に24時間オンライン予約を受け付けています。予約可能な時間帯も確認できるため、スケジュール調整がしやすくなります。
他の患者や受付などに会わずに診察を受けることができる
心身の状態などのプライバシーに関わることは、なるべく周囲に知られたくないという方も多いでしょう。なかには病院で知人に会うかもしれないと考えて、通院を控えてしまう方もいます。
しかし、オンライン診療であれば、他の患者や受付スタッフなどに会わずに診療を受けられます。基本的にビデオ通話で医師と1対1で話すため、病状を他の誰かに聞かれる心配もありません。また自宅などのプライベートな空間で診療を受けられるため、リラックスした状態で相談ができます。
受診のハードルが下がるため、気軽に受診ができる
病状がひどい場合は多くの人が積極的に受診をしますが、「少し調子が悪い」「気になっていることがある」程度では病院まで足を運ぶハードルは高くなるでしょう。移動時間も含めてスケジュールを調整しなければならないため、面倒に感じる方も多いかもしれません。
その点、オンライン診療なら予約から受診までスムーズに行え、移動の必要もないため気軽に受診できます。予約が空いていれば、思い立ったらその日すぐに受診することも可能です。受診の機会が増えれば、大きな病気の早期発見につながるなど、さまざまなメリットが期待できます。またPC以外にスマホやタブレットから受診できることも受診しやすいポイントです。
遠方に引越ししても継続的に治療を行うことができる
遠方に引っ越してこれまでのかかりつけの病院に通院できなくなった場合、改めて信頼できる病院を探すには多くの労力がかかります。また、自分の症状の専門医が近くにいないケースもあるでしょう。
オンライン診療であれば離れた地域に引っ越しても、オンラインで同じ病院への受診を継続できます。自分の病状や治療方針について深く理解した医師の診察を長期間受けられることもオンライン診療のメリットです。また、高度な医療を求めて特定の地域の専門医を受診したい場合にも、オンライン診療なら全国どこからでも受診できます。
会計の待ち時間や手間を省くことができる
通常は診察が終わったあとに待合室で会計手続きを待ち、支払いを行わなければなりません。この待ち時間が長く、ストレスに感じる方も多いでしょう。
オンライン診療であれば、システムやアプリ内で支払いを行える場合があります。たとえばクレジットカードを登録しておけば、診察内容によって自動的に決済が行われるといったものです。こうしたシステムを利用すれば、診察が終わった後は待たずにすぐ終了できます。受診のための時間と手間を削減して、効率化することが可能です。
自宅や近所の薬局で薬を受け取ることができる
通常の受診では薬は院外処方が多いため、病院での診察と会計が終わったあとに処方箋を持って調剤薬局へ足を運ばなくてはなりません。調剤薬局でもさらに待ち時間や支払いの手間が発生します。
しかし、オンライン診療なら、薬や処方箋を自宅まで郵送してもらうことも可能です。自宅でそのまま薬を受け取ることができれば、薬局へ行くための時間や移動を気にしなくて済みます。処方箋の場合でも、都合の良いタイミングで自宅や職場の近くの調剤薬局で受け取ることができます。
医療機関がオンライン診療を始めるメリット
病院がオンライン診療を始めることで得られるメリットには、さまざまなものがあります。
ここでは5つのポイントを紹介します。
患者の通院や治療の継続率が高まる
オンライン診療には、病院側・患者双方に大きなメリットがあります。患者は診療を受けやすくなり、結果として、病院側は通院や治療の継続率が高まります。
また、新型コロナウイルス感染症が拡大する昨今、院内感染リスクを恐れて通院をためらう人も多いでしょう。特に高齢者や持病を持っている人など、治療の継続が必要な人ほど、通院をリスクに感じることもあります。そんな人でも、オンライン診療なら安心して、自宅にいながら治療を継続してもらうことができます。
新たな患者獲得ができる
オンライン診療によって、新たな患者を獲得できるメリットもあります。通院してもらう場合、距離的な制約から患者は近隣の居住者や勤務者に限定されがちです。しかしオンライン診療なら、遠くて通院できなかった患者の診療もできます。
また、センシティブな悩みを持った患者は、人目を気にして通院しづらい場合もあります。オンライン診療は、そういった患者の背中を押すきっかけにもなります。
スムーズな診療を行える
オンライン診療には、診察データを活用することによって、スムーズに診察を行えるというメリットもあります。
たとえば、患者に通院してもらう場合には、診察と問診は同日に行うのが一般的です。しかし、オンライン診療なら、問診だけを事前に行っておき、そのデータをもとに診察までに診療方針を立てることも可能です。また、オンライン上に保管された前回の診察データを見ながら診察することもできます。
院内感染のリスクにさらされない
院内感染のリスクにさらされない点も、大きなメリットです。オンライン診療を行うことで、患者だけでなく医療従事者も感染のリスクが抑えられます。
2020年4月、オンライン診療に関する規制の一部が時限的・特例的に撤廃された背景には、オンライン診療の活用が、患者のみならず、医師・看護師を院内感染リスクから守るためにも重要との見解がありました。
万が一院内感染が起きた場合、診療の停止や縮小は避けられません。院内感染のリスク対策としても、オンライン診療は有効です。
事務の負担が軽減される
受付や会計を担当する事務スタッフの負担が軽減される点も、オンライン診療のメリットの一つです。オンライン診療では、受付や会計、次回の予約などの業務はオンラインですべて完結するため、スタッフがその場で対応する必要がありません。
事務処理の作業は、スタッフが空いている時間に対応することができるため、業務負荷の分散や、人件費の削減にもつながります。
ビデオトーク > 活用シーン > 医療・介護業界:オンライン診療 / オンライン面会
オンライン診療のデメリット
患者にとっても医療機関にとってもメリットの多いオンライン診療ですが、一方でデメリットも存在します。効果的なオンライン診療を行うためには、このデメリットについてもきちんと把握しておくことが大切です。ここでは、オンライン診療のデメリットについて紹介します。
オンライン診療に適さない疾患もある
オンライン診療は基本的に問診や画面越しの対話による診察になります。対面での診察のように直接見たり触れたりして症状の把握・診断をすることができないため、疾患の種類によっては詳細な診察が難しいケースもあります。また、直接何らかの処置を行う場合も対面での受診が必要です。
具体的には腹痛・頭痛などの急性症状や、検査が必要な疾患などはオンライン診療に適さないケースが多いです。一方で生活習慣病の継続治療や軽度の症状の疾患などは、オンライン診療にも適しているといえます。
検査ができないなど診断における情報量が少ない
オンライン診療では血液検査やレントゲン、呼吸機能検査などの検査をすることができません。触診もできないため画面越しでの状態確認のみになります。そのため対面診療と比較するとどうしても情報量が少なくなり、患者の状態を正確に把握することは難しいでしょう。また処方した薬の効果が出ているか、副作用の影響はないかといった確認も難しくなります。
正確な診断が難しい疾患の場合や、体調不良の度合いによっては対面診療が必要になる場合もあります。オンライン診療と対面診療を併用することも可能なため、適切な判断が必要です。
通信トラブルで診療を行えない場合もある
オンライン診療はネットワーク環境に左右されやすいこともデメリットです。ネットワーク環境が不安定な場合、会話にタイムラグが生じたり通信が中断されたりする可能性があります。あまりに不安定だと、時間がかかる、あるいは十分な診療が行えないこともあるため注意しなければなりません。
診療を行う医療機関のネットワーク環境を整えることはもちろんですが、受診する患者側のネットワーク環境にも左右されてしまいます。双方のネットワーク環境に配慮しなければならないことが難しいポイントです。
スマホやパソコンの操作が苦手な方にはハードルが高い
オンライン診療はビデオ通話で行うため、PCやスマホを操作する必要があります。基本的には難しい操作ではありませんが、高齢者など、こうした機器の操作に慣れていない人にはハードルが高くなってしまいます。
自分一人で操作ができない場合、操作方法を教えてくれる家族や周囲の人に協力を求めなければなりません。また医療機関のスタッフが来院時に使い方をレクチャーすることもありますが、手間や時間がかかってしまいます。そのため機器の操作が難しい方のためにオンライン診療だけでなく、電話診療も併せて提供している医療機関もあります。
オンライン決済が必要となる場合が多い
オンライン診療では現金での支払いではなく、クレジットカードやアプリ決済などのオンライン決済のみの場合もあります。使い慣れている人にとっては非常に便利ですが、オンライン決済をあまり利用したことがない人にとっては難しく感じる場合があります。またクレジットカード自体を持っていなかったり、オンラインでの決済に不安を感じたりする場合もあるでしょう。こうしたケースにおいても、家族や周囲の人の協力が必要になるかもしれません。
オンライン診療の流れ

実際にオンライン診療を導入した際の基本的な流れを説明します。
1. 予約を受ける
まずは、予約をオンラインシステムまたは電話で受け付けます。オンライン診療に必要なものがあれば、患者側に準備してもらうよう伝えます。
ただし症状によってはオンラインによる診療で診断や処方とはならず、対面診療や受診勧奨が必要となる場合もあります。
2. オンライン診察をする
予約された日時にビデオ通話などを用い、オンライン診察を行います。患者の端末に、医師の側から接続して行います。医師免許証などを提示し、自身が医師本人であることを証明します。保険診療の場合、患者側には被保険者証を提示させ、受給資格を確認してから診察を開始します。
3. 請求する
領収書と明細書を、電子メール、または郵送かFAXで患者に交付します。クレジットカード決済や銀行振込、その他の電子決済などにより、支払いを受けます。
4. 薬を処方する
必要があれば、薬を処方します。処方には3つの方法があります。
1つ目は、患者に病院まで取りに来てもらう方法です。
次に、患者が薬の配送を希望する場合には、処方箋を薬局に送付し、薬を郵送で患者宅へ送ってもらう方法があります。患者が希望する薬局宛に、処方箋情報をFAXなどで送付します。処方箋原本は、可能な時期に郵送などで薬局に送付します。
最後の方法は、処方箋を患者へ送る方法です。患者は自分で薬局へ行き、薬を受け取ります。
オンライン診療を始めるのに必要なもの

医療機関がオンライン診療を始めるためにはオンライン診療用のツールやネットワーク環境の整備が必要です。オンライン診療を始めるのに必要なものと注意点を説明します。
オンライン診療ツール
お客様からの信頼を得ることは世代を問わず重要なことですが、特にZ世代にとってはインターネット上の行動や評判が重要であることを意識しましょう。特にZ世代は商品やサービスを利用する前にインターネットで入念な情報収集を行います。
企業のホームページやSNSアカウントで発信する内容によっては、企業に対する信頼感に大きく影響するため、慎重に行わなければなりません。一方でZ世代の興味を惹く魅力的な発信を行えば、信頼感を高めたり興味を持ってもらえたりするきっかけにもなります。
通信機器とネットワーク環境
次に、スマートフォンやパソコン・タブレットなどの通信機器が必要です。通信機器は、インターネットに繋がる必要があります。OS、ブラウザは、使用するツールの推奨環境を確認しておくと良いでしょう。
インターネット環境は、患者とスムーズな通信が行えるよう、光回線など高速で安定したインターネット回線が望ましいです。
使用する通信機器やツールによっては、ビデオ通話用のウェブカメラやマイクを用意しておく必要があります。
オンライン診療ツールを選ぶ4つのポイント
オンライン診療を行うのに必要不可欠なのが、オンライン診療ツールです。導入するツールを検討する際の4つの比較ポイントを紹介します。
コスト
一つ目の比較ポイントは、コストです。イニシャルコストとしては、ツール導入の初期費用とPCなどの機材費がかかります。ランニングコストとしては、定額の月額料金のほか、システムによっては、決済額に応じた利用料(手数料)が発生する場合もあります。
機能
オンライン診療ツールの機能はさまざまです。代表的な機能に、予約・問診・診察・決済の4つの機能があります。機能が多い方が良いというわけではなく、目的に応じて必要な機能を決めることが大切です。
患者/病院側双方の使いやすさ
ツールの使いやすさは、病院側だけでなく患者側の視点も重要です。アプリのダウンロードや事前の使用説明が必要なツールもあれば、それらの必要がなく、接続手順がシンプルなツールもあります。高齢者でも困難なく使用できるツールなら、より多くの患者にオンライン診療を活用してもらえます。
サポートの充実さ
サポート体制が充実しているかどうかも重要です。オンライン診療は、導入を検討している病院のほとんどが、はじめての経験なのではないでしょうか。オンライン診療の導入・運営をスムーズに行うため、疑問や困りごとを、すぐに相談できると安心です。
オンライン診療ツールを活用した事例
オンライン診療を導入することは、患者だけでなく医療機関にとってもさまざまなメリットがあります。ここからは、ビデオ通話を活用したオンライン診療の事例を2つ紹介します。
社会医療法人財団石心会 第二川崎幸クリニック様
社会医療法人財団石心会川崎幸病院の外科系外来施設として機能しているのが第二川崎幸クリニックです。
新型コロナウイルスの感染者拡大により保健所の対応が逼迫したことをきっかけに、健康観察業務の応援を行うため、NTTコム オンラインが提供するビデオ通話サービス「ビデオトーク」を利用したオンライン診療を開始しました。
感染ピーク時は発熱外来が2週間待ちというような状況だったのに対し、軽症の患者さんをオンライン診療で対応するようになってからは、重症の患者さんが早く対面診療を受けられるようになりました。
今後は検査予約のための来院や遠方からの来院などを、ビデオトークによるオンライン診療で対応することを検討しています。患者さんの負担を減らすことで、より多くの患者さんへ適切な医療を提供することにつながっています。
ビデオトーク > 導入事例 > 社会医療法人財団石心会第二川崎幸クリニック様
Dクリニック東京(医療法人社団ウェルエイジング)様の事例
Dクリニックは、東京、大阪、福岡、名古屋でAGA(男性型脱毛症)の外来治療を中心に手掛けている自由診療のクリニックです。
Dクリニックは、専門クリニックのため、遠方からご来院される患者様も多く、月1回の通院でも負担になるケースがありました。
通院の負担を軽減するために導入されたのが、「ビデオトーク」を使ったオンライン診察です。オンライン診察により、通いやすくなったことで、来院しづらい患者様の背中を押すきっかけになっています。
また、オンライン診察の導入により自宅で治療を受けられるようになったため、新型コロナウイルス拡大による外出の不安の軽減にもつながっています。
ビデオトーク > 導入事例 > Dクリニック東京(医療法人社団ウェルエイジング)様
一般社団法人レインボークリニック様の事例
PrEP療法(HIV感染を予防するための内服療法)とED治療の専門クリニックである一般社団法人レインボークリニックでは、「ビデオトーク」でのオンライン診療を導入しました。
立地条件やプライバシーといったハードルを超え、より多くの人に必要な医療を届けたい、という強い思いからオンライン診察を始められました。
悩みの性質上、オープンに診察を受けること自体に抵抗があり、クリニックに通うことが難しいケースもあるため、プライバシーを保てるという点でもオンライン診察は適しています。
専用アプリのインストールや、アカウント登録などの事前準備が必要なく、診療を受ける方の負担が少ないという点がポイントとなり、「ビデオトーク」を活用されています。
ビデオトーク > 導入事例 > 一般社団法人レインボークリニック様
「ビデオトーク」ならアプリのダウンロード不要でオンライン診療が可能
オンライン診療に必要なビデオ通話サービスならNTTコム オンラインが提供する「ビデオトーク」がおすすめです。
ビデオトークなら、患者はアプリインストールやアカウント作成などの面倒な事前作業は不要です。医師側から患者の携帯電話番号宛にビデオ通話用URLをSMS送信します。患者側は、届いたSMSに記載されたURLをタップするだけです。
また、ビデオトークは複数回線を使えるため、同時に複数のオンライン診療が可能です。
患者の通院・来院への負荷を軽減し、より良い医療を提供するオンライン診療を、ビデオトークではじめてみませんか。ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。