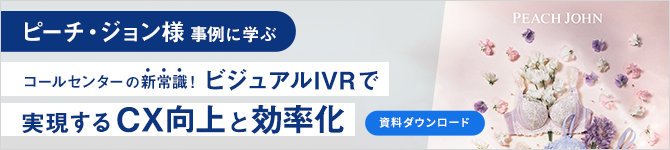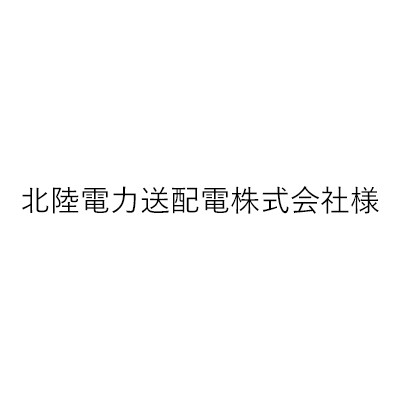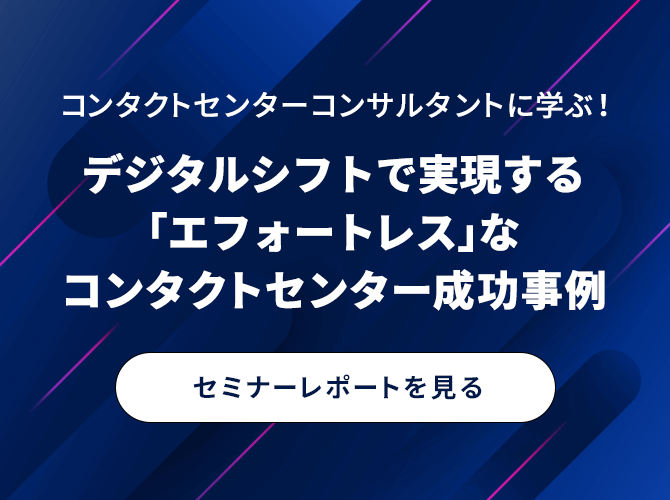更新日:2025/09/11(公開日:2021/09/28)
ビジュアルIVR
ビジュアルIVRとは?メリットや導入事例、IVRとの違いを解説
コールセンターの業務改善で「IVR」というシステムが注目されるようになってきました。そして、IVRの発展形といえるのが「ビジュアルIVR」です。ビジュアルIVRはUX(ユーザー体験)を向上させるために、非常に重要なシステムのひとつです。この記事では、ビジュアルIVRの基本的な意味からメリットやデメリット、導入事例などを解説します。
- ビジュアルIVRはIVRを発展させたもので、視覚的にメニュー操作ができるシステム
- 企業と顧客の橋渡し、IVRからの入電振分、請求確認などのサポート画面などで活用されている
- ビジュアルIVRは顧客満足度の向上や待ち時間対策など、多くのメリットが期待できる
- ビジュアルIVRサービスを選定する際は、自由にカスタマイズできるか、外部ツールと連携できるか、サポート体制は十分か、などを確認することが重要

コンタクトセンターの実現方法
をご紹介!
「オペレーターの人材不足」「電話対応による限界」
「アンケート回収率の低下」などを解決する
SMSソリューションをご紹介します。
ビジュアルIVRとは
ビジュアルIVRとは、従来のIVRを進化させた、顧客が視覚的にメニューを操作できるシステムです。コールセンターでの応答率改善にも効果があることから、注目されています。まずはIVRの意味や、IVRとビジュアルIVRの違いから見ていきましょう。
IVRの意味とは
下記コラムでもIVRについての解説を行ってきました。
(関連記事:IVRとは何か?コールセンターに導入するメリットや導入方法)
IVRとは「Interactive Voice Response」の略で、「自動音声応答システム」のことです。従来のコールセンターでは入電に対し、オペレーターが応答してきました。しかし、オペレーターの人手が不足している現場では、応答率を100%にするのは困難です。また、ユーザーのリクエストに対応できるオペレーターが担当できるとは限らず、コールセンターにストレスを抱く人は少なくありませんでした。こうした問題を解決するために導入されたのがIVRです。
IVRならオペレーターの手がふさがっている状態でも、とりあえずは機械が自動音声で対応してくれます。ユーザーはIVRの声にしたがい、プッシュボタンを押して質問に答えていきます。そして、IVRがユーザーのリクエストを聞き出してからオペレーターにつなぐので、担当者のマッチングに失敗しません。さらに、「よくある質問」をシステムにインプットしておくことで、IVRだけで問題解決できるケースも多くなります。
【比較表】IVRとビジュアルIVRの違い
IVRを発展させたシステムが「ビジュアルIVR」です。通常のIVRは自動音声だけでユーザーに応答してきました。それに対し、ビジュアルIVRでは視覚的なメニューがサービスに加わっています。スマホやパソコンなどの画面に案内画面が映し出されており、音声でそれらのメニューを説明しながらユーザーに対応していきます。すでにメニューが画面に映し出されているため、ユーザーはガイダンスを最後まで聞く必要がありません。ガイダンスの途中でも、適切なメニューを選んで次の対応へと進んでいけます。
さらに、ユーザーの状況によってはFAQサイトやチャットボットなどにも誘導可能です。これらの画面では、具体的にユーザーへと情報を発信できます。ユーザーはトラブルの解決方法をこれらの画面で探し、自力解決を図れる仕組みです。その間、オペレーターがまったく関与しないことも少なくありません。IVRは顧客満足度向上とオペレーター側の人手不足解消をより高次元で行えるシステムなのです。
IVRとビジュアルIVRのもっとも大きな違いは、「音声」と「画面」です。一見、ビジュアルIVRはIVRよりも便利なシステムに思えます。ただ、視覚情報を収集することが苦手な人にとっては、IVRのほうがより親しみやすいサービスです。ビジュアルIVRの導入でIVRを切り捨てるのではなく、両者の併用がコールセンターには求められます。
| IVR(電話自動応答システム) | ビジュアルIVR | |
|---|---|---|
| 案内方法 | 音声ガイダンス | 視覚的な案内 |
| 特徴 | ・要件に応じて最適なオペレーターへ自動接続 ・音声ガイドで即時解決も可能 |
・要件に応じて適切な窓口へ誘導(FAQ、チャットボット、ボイスボット、会員サイトなど) |
| メリット | ・オペレーターの業務負担を軽減 ・顧客の待ち時間を短縮 |
・視覚的メニューで聞き漏れを防止 ・オペレーターの業務負担を軽減 ・応答までの時間やIVR聞き取り時間を含む顧客の待ち時間を短縮 |
ビジュアルIVRが注目される背景
ここでは、ビジュアルIVRが注目される背景を解説します。
CX(顧客体験)の重要性が増している
近年、商品やサービスは品質や機能、価格の面で差別化が難しくなり、企業選びの基準としてCX(顧客体験)の重要性が高まっています。RadialとCFI Groupの調査では、選択肢がある場合、55%の顧客がビジュアルIVRを利用する可能性があると回答しており、直感的な操作や待ち時間の短縮といった利便性がCX向上に寄与することが示されています。
また、Salesforce Researchの調査では、顧客の80%が「企業が提供する体験は製品やサービスと同等に重要」と考えていることが明らかになっています。
さらに、QualtricsとServiceNowの調査によると、顧客の80%が「顧客体験の悪さを理由にブランドを切り替えたことがある」と回答。43%が「たった1回の不満足なカスタマーサービス体験後、少なくともある程度はブランドを切り替える可能性がある」と答えており、このことからもCX改善が競争力強化の鍵であることがわかります。
参照
CFI Group|Radical Report- May 2018
salesforce|What Are Customer Expectations, and How Have They Changed?
qualtrics.|80% of customers said they have switched brands because of poor customer experience
自己解決を促進できる
ビジュアルIVRは、疑問やトラブルを顧客自身が解決できる新しいサポート手段として注目されています。画面上で多様な解決方法を分かりやすく提示するため、顧客はオペレーターと直接話す心理的負担を感じることなく、自分のペースで問題を解消できます。
Salesforceの調査でも、とくに簡単な問い合わせや操作に関しては、顧客の61%がセルフサービスチャネルを利用することを好むと回答されており、ビジュアルIVRが効率的に自己解決を促進できるツールであることが裏付けられています。このように、ビジュアルIVRが企業側のオペレーター負担の軽減や、応答時間の短縮にもつながることが期待されます。
参照
salesforce|Customer Self-Service: What It Is, Importance & Best Practices
ビジュアルIVRへの3つの誘導方法

ビジュアルIVRへ誘導するには、主に次の3つの方法があります。
- URLをSMSで送信する
- 問い合わせ先としてリンクを設置する
- 専用アプリから誘導する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
URLをSMSで送信する
1つ目は、ビジュアルIVRへアクセスできるURLをSMS(Short Message Service)で送信する方法です。SMSは相手の携帯電話番号がわかればメッセージを送信できるため、コールセンターへ入電のあった顧客の電話番号に対してビジュアルIVRのURLを記載したメッセージを送信します。顧客は記載されたURLにアクセスすると、ビジュアルIVRのメニュー画面を開ける仕組みです。
問い合わせ先としてリンクを設置する
2つ目は、企業やサービスなどのWebサイト上に、問い合わせ先としてビジュアルIVRのリンクを設置する方法です。これまでWebサイト上の問い合わせ先としてコールセンターの電話番号を記載していた箇所に、ビジュアルIVRへのリンクやボタンを追記したり置き換えたりします。問い合わせ方法の選択肢が増えれば、電話での問い合わせを躊躇していた顧客も問い合わせやすくなるでしょう。
専用アプリから誘導する
3つ目は、専用のアプリから誘導する方法です。顧客には事前に特定のアプリを自分の使用する端末にインストールしてもらう必要があります。問い合わせをしたい際にアプリを起動すると、問い合わせ方法の1つとしてビジュアルIVRを選択することが可能です。
ビジュアルIVRはどのような場面で活用されているのか
多くの現場でビジュアルIVRは実用化され、成果を上げつつあります。ここからは、ビジュアルIVRの活用方法を紹介していきます。
顧客とのやり取りが発生するアクセスポイント
企業と顧客の橋渡しになる存在が「アクセスポイント」です。そして、アクセスポイントが機能するかどうかは、顧客満足度を大きく左右してきました。顧客が企業側に問い合わせをしたいのに放置されたままだと、新しく不満が募ってしまうからです。そのため、コールセンターのサービス向上は顧客ロイヤリティを育むうえで、無視できないテーマだといえるでしょう。ビジュアルIVRはコールセンターにおける、重要なアクセスポイントとして注目されています。
そもそもIVRは顧客の入電をただ受けるだけでなく、こちらから質問し、リクエストを絞り込んでいけるサービスです。顧客には放置されている感覚が生まれにくく、オペレーターにつながれた後の対応も充実させられます。そのうえで、ビジュアルIVRであればより具体的なやり取りで顧客のリクエストに応じられます。IVRだけでは「分かりづらい」「面倒」「音声ガイダンスが長すぎる」と感じる顧客の不満も解消できるでしょう。
IVRからの入電振分
これまで時間外の入電では、IVRで「おかけ直しください」と案内するのが普通でした。オペレーターがコールセンターにいないので、有人対応をユーザーから求められても不可能だったからです。しかし、IVRからビジュアルIVRに振り分けるという、新しい選択肢がコールセンターで生まれつつあります。ユーザーが時間外であっても詳細な対応を求めているとき、SMS経由で公式ホームページや特設サイトへと案内します。その後はビジュアルIVRが画面を説明しながら、ユーザーのリクエストに対応する流れです。
もちろん、ビジュアルIVRにインプットされていない種類のトラブル、質問には完璧に対応しきれないでしょう。それでも、時間外の応答率をゼロから引き上げられるので、多くの企業に活用されている方式だといえます。
毎月請求確認などのサポート画面
複雑な説明をともなう電話対応で、ビジュアルIVRはサポートの役割を果たします。その代表例が毎月の請求確認です。月々の請求額をユーザーに説明するとき、情報量が多すぎて音声だけでは聞き取れないことも珍しくありません。「何月に発生した」「いくらの料金を」「いつまでに支払うべきか」といった項目が正しく伝わっていないと、後々のトラブルを招きかねないでしょう。
ビジュアルIVRで適切に請求明細ページへ誘導することで、ユーザーはビジュアルで請求額を確認できるため、金額や支払日の勘違いが起こりにくいのです。また、支払方法についても画面で見られるのは魅力です。オペレーターの時間を割かれやすい業務をビジュアルIVRに委ねて、現場の回転率を上げられるのもポイントのひとつでしょう。
コールバック予約の受付
待ち呼となった顧客に対してIVRで応答し、SMSで送信されたリンクからビジュアルIVRの利用へとスムーズに誘導できます。顧客は画面上で希望する日時を直感的に操作して予約できるなど、コールバック予約に対応可能です。
また、音声でのやり取りを省略できることで、予約時間の入力ミスや言い間違いといったトラブルも防げます。さらに、ビジュアルIVRの仕組みにより、オペレーターの応答速度が向上し、対応効率の改善にも大きく寄与することが期待されます。
【関連記事】
コールバックとは?コールセンターでの活用例とメリットを解説
待ち呼(あふれ呼)とは?コールセンターで発生するリスク・原因・改善方法を解説
予約の確認(医療・観光業など)
ビジュアルIVRは、日時・場所・人数などの予約内容を画面上で一覧表示し、顧客が自分で確認・修正できる仕組みを提供します。業種別の応用例としては、医療では診察予約の確認、観光業では宿泊やツアーの予約確認など、直感的に操作できるユースケースがあり、顧客の利便性向上とオペレーター負担の軽減に役立ちます。
注文状況の確認
ユーザーは注文番号を入力するか、画面上で選択するだけで、出荷状況や配達予定日を直感的に確認できます。情報が視覚的に整理、表示されるため、問い合わせ件数の削減につながるだけでなく、顧客満足度の向上にも寄与するでしょう。
加えて、必要に応じて配送業者の情報や問い合わせ用リンクをあわせて表示することで、さらに親切で分かりやすい案内が可能です。また、返品や交換の手続き、商品に関するFAQの確認も画面上で完結できるため、顧客にとってストレスの少ない利便性の高いサポートを提供できます。
ビジュアルIVR導入のメリット

さまざまな業種でビジュアルIVRが導入されたのは、現場で多くのメリットを得られるからです。ここからは、ビジュアルIVRのメリットについて解説します。
顧客とのやり取りをパーソナライズできる
顧客をいくつかの属性に分類し、それぞれに合ったサービスを用意することが「パーソナライズ」です。そして、ビジュアルIVRではパーソナライズ作業の精度を高め、個人のリクエストにより深く応答できるのがメリットです。顧客は自分の嗜好に合った情報をビジュアルで確認できるので、問題解決までの時間がスムーズになります。
自己解決率が向上する
ユーザーによっては、オペレーターを待たずに自分で問題を解決したいと思う人も多いでしょう。ビジュアルIVRはいわゆる「セルフサービス」に対して、充実したオプションを提供します。音声だけでなく、画面で視覚情報を確認することにより、ユーザーは適切な解決方法を自力で導き出せるでしょう。また、セルフサービスの頻度が増えればコールセンター側の負担は軽減されていきます。
顧客満足度の向上につながる
企業と顧客の接点を「チャネル」と呼びます。そして「オムニチャネル」とは、複数のチャネルがある状態です。ビジュアルIVRはオムニチャネルへの変換に役立ちます。もしもユーザーがコールセンターだけでは解決しづらいリクエストを発信してきた場合、ビジュアルIVRなら画面上で別のチャネルへと誘導できます。ユーザーに提示できる解決方法のバリエーションが増えるため、顧客満足度も向上するでしょう。
セキュリティ向上につながる
安全にサービスを使用したいと願うユーザーからも、ビジュアルIVRは支持されてきました。なぜならビジュアルIVRは情報を自分から開示せず、スピーディーに問題解決を図れる仕組みだからです。ユーザーの中には音声情報を知られたくなかったり、うっかり自分の情報をオペレーターに話してしまうことを恐れていたりする人もいます。また、個人情報を知られないためには、できるだけ早くコールセンターとのやり取りを終わらせたい場合もあるでしょう。これらの要望に応えられる手段として、ビジュアルIVRはぴったりです。
待ち時間対策になる
IVR系のシステムのメリットとして、待ち時間が解消されることは大きいでしょう。そのうえで、ビジュアルIVRは自動音声を聞いている時間まで省略できます。すべての案内を聞かなくても、画面に映っているメニューを参照できるからです。自動音声にありがちなストレスがなくなり、速やかに問題解決できるのがビジュアルIVRの強みです。
24時間サポート対応ができる
ビジュアルIVRは24時間いつでも稼働できるため、従来の電話サポートでは対応が難しかった深夜や早朝、あるいは営業時間外の時間帯でも、顧客の疑問やトラブルの解決方法を迅速に提示することが可能です。
顧客の要望に応じて、診察予約の確認や商品の出荷状況確認、FAQの閲覧など、多様な対応を直感的に行える点も大きな特徴です。これにより、電話対応が集中するピーク時間帯や従来では対応できなかった時間帯においてもサポート品質を一定に保つことができる点がメリットといえます。
オペレーターの負担を軽減できる
オペレーターによる電話対応は、同時に複数の問い合わせが発生することや、顧客一人ひとりの状況に応じた対応が求められるなど、精神的にも業務的にも大きな負担となります。ビジュアルIVRを導入することで、顧客が自己解決できる割合が高まり、オペレーターが対応すべき通話数を大幅に減らすことができます。
また、顧客情報の収集や入力作業も自動化できるため、オペレーターが手作業で情報を入力する負担が軽減されるのも特徴です。さらに、CRMやIVRログと連携することで、顧客情報を再入力する必要がなくなり、迅速かつ正確な対応が可能になるでしょう。
問い合わせが集中するピーク時であっても、オペレーターは落ち着いて対応できるようになるなど、心理的負担の軽減にも大きく寄与します。
ビジュアルIVRにデメリットはある?
いざビジュアルIVRを導入する際は、決して完璧なシステムではないという前提を踏まえましょう。わずかながら問題点を抱えており、それは人間のオペレーターで解決するしかありません。ここからは、ビジュアルIVRのデメリットについて解説します。
顧客が操作を間違える可能性がある
ビジュアルIVRは使いこなせば非常に便利ですが、顧客が操作を間違える可能性もあります。たとえば誤ったメニューを選択したり、正しくない入力をしてしまったりなどです。途中でフォローすることが難しいため、間違えた状態で操作を進めてしまう可能性が高く、後からオペレーターが修正や再確認をしなければならないこともあります。
そのため、かえって手間と時間がかかってしまうこともあり得ます。このような事態を回避するには、誰でも簡単かつ正確に利用できる画面設計が重要です。適切なメニュー表示ができているか、導線がわかりやすいかを確認し、整えましょう。
電話対応を好んでいる顧客もいる
忘れてはならないのが、ビジュアルよりも会話で対応してほしいと願っているユーザーの存在です。たとえば、視力が悪くて画面を見づらいユーザーの場合、ビジュアルIVRを不便に感じるでしょう。こうしたユーザー対策として、ビジュアルIVRとIVRを併用して相互補完することは必須です。また、ユーザーとの関係性を深く構築しにくいのもデメリットです。ビジュアルIVRではどうしても、冷たい印象を抱いてしまうユーザーがいます。ビジュアルIVRがあるからといって人間のオペレーターが不要になるわけではありません。オペレーターにつなぐ場合のマニュアルも用意しておきましょう。
顧客が操作する手間が増えてしまう
ビジュアルIVRは、顧客自身による操作の手数が増える点がデメリットです。そのため、デジタル操作に慣れていない顧客や高齢者にとっては、「操作が難しい」と感じる可能性があります。
また、動画や画像を多用すると、通信環境によっては画面の表示が重くなり、UX(ユーザー体験)が低下する場合もあります。このような課題を解消するためには、視覚的に分かりやすく、直感的に操作できる画面構成を設計することが重要です。適切なUI設計により、幅広い顧客がストレスなく利用できる環境を整えることができます。
大企業でも使われている!ビジュアルIVRの導入事例
有名企業の現場でも、ビジュアルIVRは実用化されています。この段落では、ビジュアルIVRの導入事例を紹介します。
ANA Xでの事例
マイレージクラブの企画運営で知られるANA X株式会社では、SMS送信とビジュアルIVRを組み合わせたサービスが導入されました。
このサービスでは、SMSによって画面へと誘導し、ユーザーに具体的なイメージを持ってもらいながら問い合わせに応答しています。資格情報をともなった「旅情感」により、顧客の満足度は向上しました。もともと、ANA XがビジュアルIVRに興味を持ったきっかけは、GoToトラベルの問い合わせでコンタクトセンターが激務になったことです。オペレーターの負担を減らしつつ、応答率を高めるための施策としてビジュアルIVRは成功しました。
少額短期保険ハウスガードでの事例
大東建託グループの少額短期保険ハウスガード株式会社はその名の通り、少額短期保険の事業を展開しています。少額短期保険ハウスガードでは顧客とのオンライン契約を推進してきました。そこでまず、NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社による「空電プッシュ」が選ばれました。それに引き続き、同社が提供しているモバイルウェブのビジュアルIVRも導入したのです。
少額短期保険ハウスガードがビジュアルIVRを必要としたのは、災害時にコールセンターがひっ迫することへの対策でした。ビジュアルIVRならSMS送信で特設ページにユーザーを誘導できます。そこで事故対応受付やFAQを自力で確認できるため、コールセンターの業務効率が改善されたのでした。
使いやすいビジュアルIVRにするためのポイント
ビジュアルIVRを導入しても、使いやすい設計でないと顧客に利用してもらうことはできません。ここでは、顧客にストレスなく利用してもらえるビジュアルIVRにするためのポイントを解説します。
現状の課題を棚卸しする
単に問い合わせが多いことを理由にビジュアルIVRを導入すると、本質的な問題解決につながらない場合があります。そのため、まずは課題を明確にすることが重要です。
たとえば、問い合わせ件数の増加が操作の分かりにくさや情報不足によるものかを把握しておくことで、適切な対応策を検討できます。ビジュアルIVRの導入とあわせて、Webサイトの見やすさやFAQの充実度、商品説明の分かりやすさなどの課題も整理しておくと、具体的な改善アクションに落とし込みやすくなります。
問い合せが多い内容を解決する仕組みを作る
まずは、どのような問い合わせが多いのかを調査することが重要です。たとえば、請求照会や注文状況の確認、コールバック予約といった問い合わせの件数が多い場合は、それに対してビジュアルIVRで自己解決できる仕組みを設計しましょう。
頻繁に発生する問い合わせを解決しやすくすることで、ストレスなく問題を解決できる顧客の割合が多くなります。ただし、電話や店舗での対応が必要な内容については、従来通りオペレーターが対応する仕組みを維持し、効率と顧客満足度の両立を図る必要があります。
直感的に利用できるユーザーインターフェースにする
ビジュアルIVRでは、ユーザーインターフェースを直感的に操作できるよう設計することが非常に重要です。メニューやカテゴリーが多すぎると選択に時間がかかり、顧客にストレスを与えてしまいます。
そのため、画面上のボタンやリンクは整然と配置し、カラーコントラストやラベル表記を工夫して選択ミスを減らす工夫が求められます。また、階層構造を分かりやすくし、適切な遷移先を設定することも重要です。さらに、スマートフォン画面でも見やすいよう、ボタンのサイズや配置に配慮した設計も必要になります。
ビジュアルIVRサービス選定のポイント

ビジュアルIVRサービスは複数ありますが、選ぶ際には次のようなポイントが重要です。
- 自由にカスタマイズできるか
- 外部ツールと連携できるか
- サポート体制は十分か
自社に適したサービスを選ぶために、それぞれ詳しく見ていきましょう。
自由にカスタマイズできるか
まず、画面や導線の設計を自由にカスタマイズできるかどうかが重要です。ビジュアルIVRは導入するだけで大きな効果が期待できるわけではなく、それぞれのコールセンターの特徴にあわせて最適化する必要があります。
そのため、課題が見つかったらすぐにメニューの表示や配置を変更できるサービスを選びましょう。もし操作がわかりづらくスムーズに調整できない、変更時にはベンダーに依頼する必要がある、といったサービスを選んでしまうと、課題解決までの時間が長くなり思うような効果が得られないかもしれません。
外部ツールと連携できるか
ビジュアルIVRはCRMシステムやチャットツール、FAQツールなどの外部ツールと連携することでより便利に活用できます。そのため、連携機能が充実しているかどうかも選ぶ際に重要なポイントです。
たとえば、すでに社内で使用しているCRMシステムと連携できれば、過去の問い合わせ履歴やナレッジをビジュアルIVRで活用できます。蓄積された情報を参考にすることで、オペレーターの対応品質の改善や業務の効率化に役立つでしょう。
サポート体制は十分か
サービスを提供するベンダーのサポート体制も確認しておきましょう。導入から設定までを一元的にサポートしてくれるサービスであれば、スムーズに利用を開始できます。また、導入したら終わりではなく、運用開始後にトラブルが発生する可能性もあります。運用開始後も継続的にサポートしてくれるサービスを選ぶことがおすすめです。
サポート内容はベンダーによりさまざまで、サイトの作成などを代行してくれる場合もあります。自社に必要なサポート体制を整理したうえで、各ベンダーのサポート内容や対応時間、対応方法を事前に調べて比較しましょう。
サポート品質向上をサポートするNTTコム オンラインの「モバイルウェブ」
NTTコム オンラインが提供する「ビジュアルIVR」は、顧客の自己解決をサポートして応答率を向上させるコールセンター向けサービスです。SMSで顧客へURL送信を行い、ビジュアルIVRへ誘導します。
NTTコム オンラインが提供する「ビジュアルIVR」の画面は、メニューの数や内容、遷移先ページを自由に設定でき、自社で用意した画像のアップロードも可能なため、ブランドイメージに合わせて設計できます。新規ページの追加や導線の変更は管理画面からいつでも編集できるため、課題に対して迅速に対応することが可能です。
ほかにもフォーム作成機能やページアクセス数を確認する機能、予約更新機能など、業務を効率化・改善するために役立つ機能が充実しています。さらに、導入時にはNTTコムオンラインが一元的にサポートするため安心です。
導入事例|北陸電力送配電株式会社 様
北陸電力送配電株式会社様では、停電や送配電設備に関する問い合わせが大規模災害時に通常の3倍以上に増加し、限られたオペレーターでの対応では効率とサービス品質の維持が課題となっていました。また、以前は電話応対に依存していたため、問い合わせ集中時に対応が追いつかず、オペレーターの負担が大きかったのも問題でした。
そこで2024年9月にモバイルウェブ(ビジュアルIVR)を導入すると、顧客をチャットやWebへ誘導し、自己解決を促進できるようになりました。これによりオペレーターの負担を軽減し、少人数でもサービス品質を維持できるようになったと満足されています。
顧客接点を大切に!IVRとビジュアルIVRでUX向上を
コールセンターは顧客と企業との大切な接点です。IVRやビジュアルIVRによってUXを向上させれば、顧客との関係性は深まっていきます。コールセンターへの不満がなくなり、顧客が抱えている問題も早期解決されます。その結果として、顧客の「囲い込み」が促進されるでしょう。また、さまざまな顧客に対応するにはIVRとビジュアルIVRの併用が肝心です。
コールセンターの応答率を改善したい方、ビジュアルIVRの導入を検討している方は、ぜひNTTコム オンラインが提供する「ビジュアルIVR」を試してみてください。