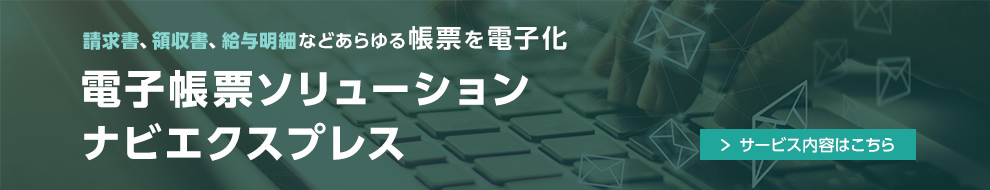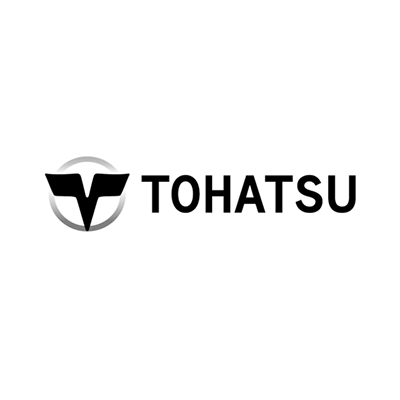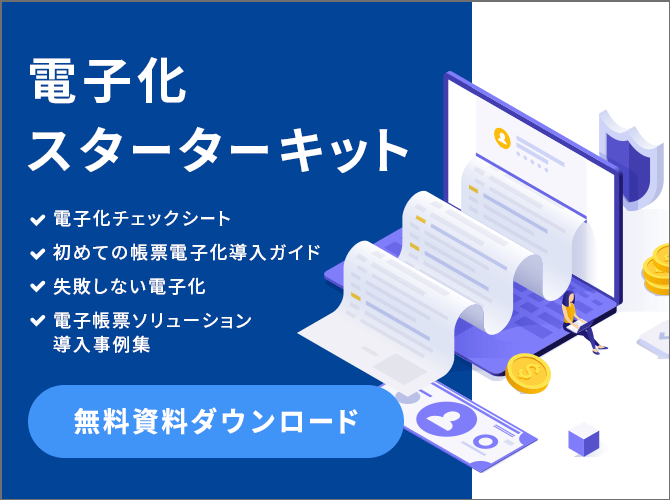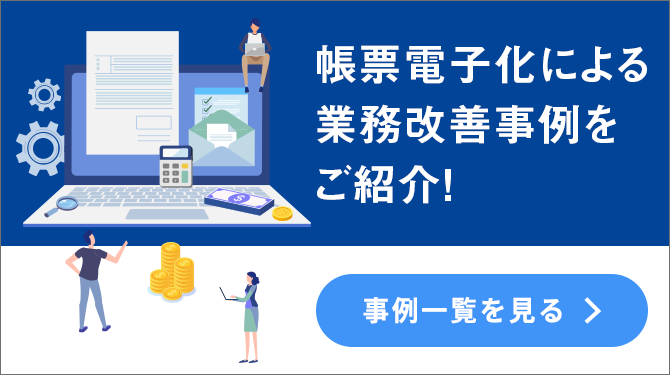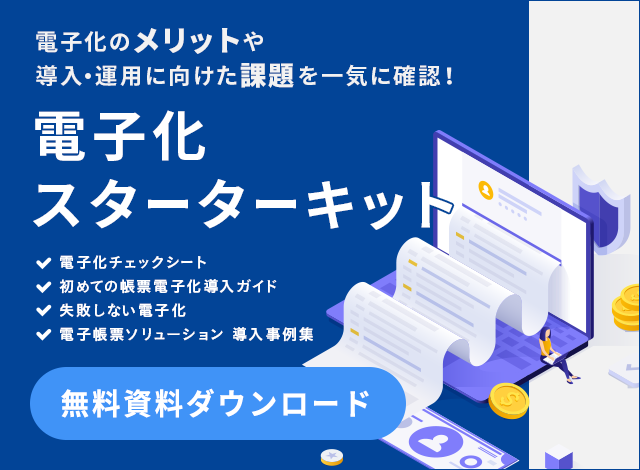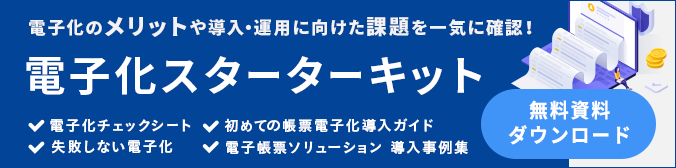更新日:2025/10/22(公開日:2025/08/07)
帳票、書類の電子化
ゆうメールの値上げはいつから?値上げの影響と電子化による対策を解説
請求書等の電子配信にお悩みはございませんか?
基幹システムに手を加えず連携し、電子化をご提案いたします。
商取引の全帳票を電子化し、即日到着でコスト削減・業務効率化を実現します!
⇒ まずは電子帳票ソリューション ナビエクスプレスの資料を見てみる
2025年4月の大口の特約ゆうメールの値上げを受け、帳票などの発送方法の見直しを進めている企業も多いのではないでしょうか。また、通常のゆうメールについても2025年11月からの値上げが発表されており、物流コスト上昇の影響は無視できない状況です。
本記事では、特約ゆうメールや通常ゆうメールの値上げの詳細や、利用時のメリットと注意点をわかりやすく解説します。コスト増への対策として注目される「電子化」の方法とその効果についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
- 大口の特約ゆうメールは、主に大手印刷会社やダイレクトメール発送業者などが利用しているサービスで、2025年4月に値上げが行われた
- 大口の特約ゆうメールを契約している印刷会社などを利用している企業においても、郵送コストの値上げにつながる可能性がある
- 通常のゆうメールについては2025年11月1日から料金が改定され、重量に応じて10円から20円の値上げとなる
- ゆうメール以外にもレターパックや定形郵便もすでに値上げが行われているため、幅広い企業で発送手段や物流コストの見直しが求められる
- ゆうメールをはじめとする郵便サービスの値上げ対策には、紙の発送が不要で郵送コストがかからない「電子化」が有効
ゆうメールの2025年11月からの値上げが発表
2025年8月、日本郵便は「ゆうメール」の基本運賃改定を正式に発表しました。実施時期は2025年11月1日からで、荷物の重量に応じて10円から20円の値上げが行われます。会報誌やカタログなどの発送手段として多くの企業に活用されてきたゆうメールですが、今回の改定によりコスト負担は大きく増すことになります。
ゆうメールの新運賃と旧運賃との比較表
ゆうメールの基本運賃は、2025年11月1日から以下のように改定されます。
| 重量 | 旧運賃 | 新運賃 |
|---|---|---|
| ~150g | 180円 | 190円 |
| ~250g | 215円 | 230円 |
| ~500g | 310円 | 320円 |
| ~1kg | 360円 | 380円 |
このように、一律で10円から20円の値上げとなります。金額自体は大きくないように思えますが、発送数が増えるほど負担は大きくなるため、早めの対策が求められます。
ゆうメールの値上げの背景
今回の値上げの背景には、昨今の物価高騰が大きく関係しています。燃料費の上昇や人件費の増加といった要因により、日本郵便の運営コストは年々増加しており、その負担は無視できません。
日本郵便は、今後も全国規模で安定的に物流サービスを提供していくためには、運賃の見直しが不可欠だと説明しています。利用企業としてはその背景を理解したうえで、自社の発送手段や物流コストの見直しを進めなければなりません。
大口の特約ゆうメールも2025年4月から値上げされている

2024年10月、郵便料金の上限額が従来の84円から110円に引き上げられました。コスト削減策として多くの企業が利用していた大口の特約ゆうメールも、2025年4月から料金が改定され、郵送コストへの関心が一層高まっています。
特に、大量の帳票や資料を郵送している企業では、従来よりもコスト負担が増すことになり、業務運用の見直しを迫られるケースも見られます。
参考:郵便局「2024年10月1日(火)から郵便料金が変わりました。」
関連記事:2024年に郵便料金の値上げを実施。料金や値上げの理由を解説
そもそも特約ゆうメールとは?
特約ゆうメールとは、日本郵便と個別に契約を結ぶことで利用できる、法人向けの「ゆうメール」サービスです。通常のゆうメールよりも割安な料金で郵送できるのが特徴で、コストを抑えつつ大量発送を行いたい場合に活用されています。
利用にあたっては、郵便局が定める一定の条件を満たす必要があり、事前に審査や打ち合わせを経たうえで契約が認められた場合にのみ利用が可能です。主な活用シーンとしては、請求書や納品書、会報誌、ダイレクトメールなど、定期的に多くの帳票や印刷物を発送する業務が挙げられます。
特約ゆうメールの種類

特約ゆうメールには、「大口の特約ゆうメール」と一般の「特約ゆうメール」の2種類があります。ここでは、それぞれの特徴を解説します。
大手印刷会社やDM発送業者が契約している「大口の特約ゆうメール」
大口の特約ゆうメールは、日本郵便と大口契約を結んでいる企業が、自社だけでなくクライアント企業の郵送物もまとめて発送できるサービスです。主に、大手印刷会社やダイレクトメール発送業者などが利用しており、大量かつ定期的な発送業務に適しています。
こうした大口の特約ゆうメールを利用している業者を活用すれば、郵便局と直接契約を結ばなくても、郵送費の削減や業務効率化が図れます。そのため、請求書などの発送に外部業者のサービスを利用している企業も少なくありません。
一般企業が契約している「特約ゆうメール」
一般の特約ゆうメールは、契約を結んだ企業が自社の郵送物のみを発送できるサービスです。帳票や案内状、会報誌などの定期的な郵送物を安定して届ける手段として、多くの企業に活用されています。
大口の特約ゆうメールとの違いは、契約企業以外の郵送物は対象外となり、自社利用に限定される点です。他社の発送業務を請け負っていない企業であれば、コストを抑えつつ、自社内で発送業務を完結できる有効な手段といえるでしょう。
特約ゆうメールのメリットと注意点
特約ゆうメールを利用する最大のメリットは、通常の郵便料金よりも割安な単価で発送できる点です。特に、大量の帳票やダイレクトメールなどを一度に発送する企業では、郵送コストの大幅な削減が期待できます。また、日本郵便と契約を交わすことで、安定した発送体制を整えられる点も魅力のひとつです。
一方で、契約には郵送物の種類・数量・内容に関する厳格な条件があり、これらを満たさなければ契約の締結や更新ができない場合があります。さらに、大口契約でなければ発送できるのは契約企業自身の郵送物に限られるため、取引先やクライアントの荷物を発送することはできません。
また、契約には事前の打ち合わせや審査が必要で、すぐに利用を開始できるわけではない点にも注意が必要です。
ゆうメールの値上げ対策として有効な「電子化」とは?

ゆうメールの値上げを受け、郵送コストの増加に不安を感じている企業も多いのではないでしょうか。そうした中で注目されているのが、帳票や書類を紙ではなく電子データで送付する「電子化」です。電子化を進めれば紙の発送が不要になるため、郵送コストはかかりません。
ExcelやPDFファイルを手動でメールに添付して送付する方法もありますが、作業の手間や送付ミスのリスクを考えると、電子帳票配信サービスの活用がおすすめです。帳票の作成から送付、保存までを自動化できるため、業務の正確性と効率性を高められます。
郵送コストの削減に効果的な電子化については、以下の記事で詳しく紹介しているので、ぜひ併せてご覧ください。
関連記事:郵便コストの削減に効果的な方法とは?値上げ対策に有効な電子化の方法も紹介
帳票を電子化してコスト削減した事例
ここでは、帳票を電子化してコスト削減に成功した企業の事例を紹介します。
月約10万円の郵送費削減に成功した事例
金型の製造に使われる特殊な鋼材の卸売業を手がける株式会社鐵鋼社様では、これまで印刷から封入まで手作業で行っていた納品書・請求書の発行業務を電子化しました。
同社では、毎日40〜50通の納品書を発行しており、その対応には約6時間を要します。特に月末には150通以上の請求書の発行も重なり、業務がひっ迫していました。また、封筒や切手などの郵送費も大きな負担となっています。
こうした課題を解消するために電子化を進めた結果、現在ではほとんどの取引先が電子での発行に理解を示しており、送付作業にかかる時間を約2時間削減できました。郵送費は月間で約10万円の削減を実現し、業務負担が軽減されたことで働き方の改善にもつながっています。
年間通して約7割のコスト削減に成功した事例
船外機や可搬消防ポンプの開発を手がけるトーハツ株式会社様では、年間でおよそ3万件にのぼる納品書・請求書を発行しています。こうした帳票発行に関する業務改善とコスト削減を目的に、帳票の電子化に取り組みました。
従来はすべての帳票を手作業で封入していたため、発送業務に多くの時間と人員を割く必要がありました。実際に、納品書・請求書の発送業務だけで、2人がかりで月に160時間以上を費やしていたといいます。
電子化導入後、同じ業務を1人あたり約70時間で対応可能となり、作業時間を大幅に削減できています。加えて、郵送費や紙代、作業コストなども含め、年間を通じて約7割のコスト削減に成功しました。
また、帳票業務の効率化によって債権管理業務のスピードが向上し、新たな業務の開拓にも人員を振り分けられるなど、業務全体の生産性向上にもつながっています。
ゆうメールの値上げや電子化に関するよくある質問
最後に、ゆうメールの値上げや電子化に関するよくある質問に回答します。
値上げでどれくらい料金が上がる?
特約ゆうメールの料金は、日本郵便と結ぶ契約内容や、郵送する物のサイズ・重さ・発送件数などによって個別に設定されているため、一律の金額や値上げ幅が公表されているわけではありません。
そのため、「どのくらい料金が上がるのか」といった具体的な金額の把握は困難です。値上げの影響を正確に把握するためには、まずは契約している郵便局への問い合わせが必要です。
一方、通常のゆうメールについては、2025年11月1日からの具体的な新料金が公表されています。重量区分ごとに10〜20円の値上げが行われ、例えば150g以内は180円から190円に、1kg以内は360円から380円へと引き上げられます。
他の郵便サービスも値上げする?
燃料費や人件費の高騰により日本郵便の運営コストが増加しているため、ゆうメール以外の郵便サービスでも同様に値上げが行われています。
例えば、2024年10月1日にはレターパックの料金が改定され、レターパックプラスは520円から600円に、レターパックライトは370円から430円に値上げされました。さらに、通常はがきや定形郵便についても同時期に料金が見直され、いずれも15〜20円程度の値上げが実施されています。
このように、日本郵便は安定したサービス提供を維持するため、幅広い郵便サービスにおいて料金改定を進めています。
電子化する際に取引先の同意は必要?
電子帳票への切り替えにあたっては、法律上、必ずしも取引先の同意を得る必要はありません。ただし、取引先の経理処理や業務フローに影響を及ぼす可能性があるため、事前の説明や案内は必須と考えてください。取引先の理解と協力を得ながら進めることで、トラブルを防ぎながらスムーズに電子化を導入できます。
ただし、さまざまな事情によって取引先から電子化を拒否されるケースも見られます。その場合の対処法については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せてチェックしてみてください。
関連記事:請求書の電子化を拒否された時の対処法とは?取引先が拒否する理由も解説
電子化する際のサービスの選び方は?
帳票を電子化するサービスを選ぶ際は、次のようなポイントを確認しましょう。
- 自社の目的に合うか
- 請求書以外の帳票にも対応できるか
- インボイスや電子帳簿保存法に対応できるか
- コストに問題はないか
- 連携できるデータやシステムは豊富か
- 信頼できるシステムであるか
- 操作性は良いか
- 郵送やFAXにも対応できるか
- 利用中のデザインでフォーマットを作れるか
- 導入支援やサポートに対応は十分か
具体的にどのような点を確認すべきなのか、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ併せてご覧ください。
関連記事:請求書を電子化するシステムの選び方とは?導入メリットや比較ポイントを解説
ゆうメールの値上げ対策には「ナビエクスプレス」がおすすめ
特約ゆうメールの値上げにより、帳票などの発送方法の見直しを迫られる企業が増えています。また、2025年11月には通常のゆうメールも値上げが予定されているため、企業にとって物流コスト上昇への対策は不可欠といえるでしょう。
こうした中で注目されているのが、帳票の「電子化」です。紙の帳票を電子データに切り替えることで、郵送にかかる手間やコストを削減でき、業務全体の効率化にもつながります。
帳票の電子化には、電子帳票配信サービスの活用がおすすめです。NTTコム オンラインが提供する「ナビエクスプレス」は、帳票の作成から送付までを自動化でき、既存の帳票レイアウトをそのまま電子化できます。さらに、ExcelやCSVといった帳票以外のファイルも送付可能なため、取引先ごとの個別の要望に柔軟に対応できるのも特徴です。
郵送コストの削減や業務効率化をお考えの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【
帳票、書類の電子化
】
最新のコラム

2025/12/09

2025/10/22