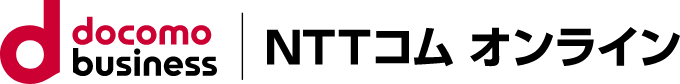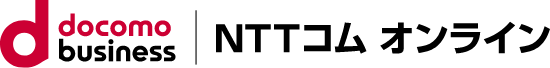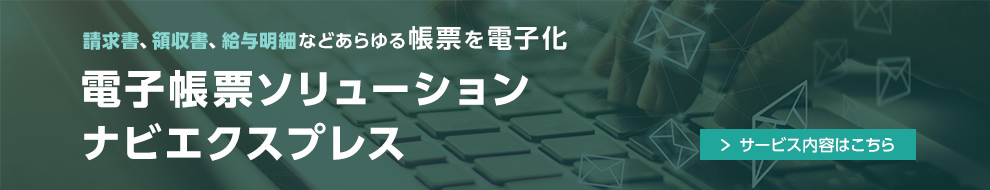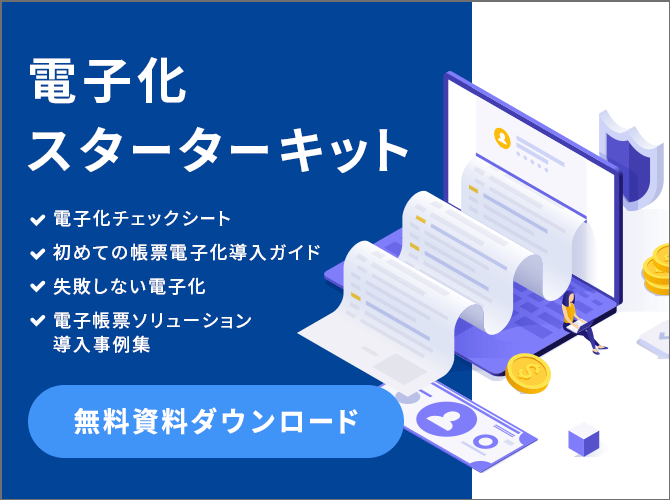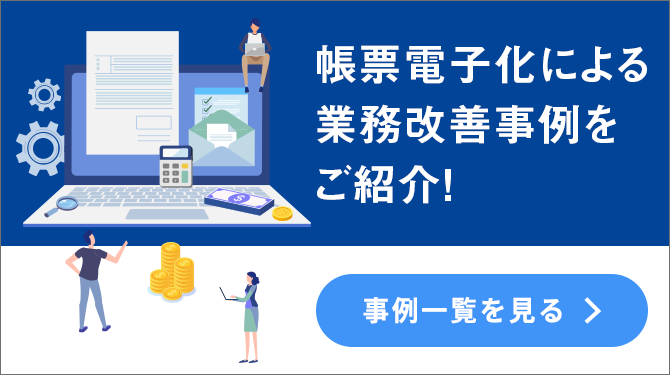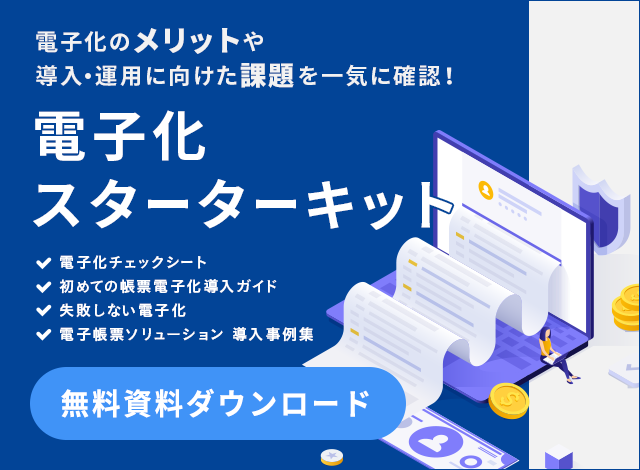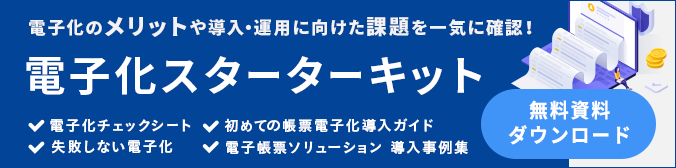2024/07/30
請求書の電子化
請求書の電子化を拒否された時の対処法とは?取引先が拒否する理由も解説
請求書等の電子配信にお悩みはございませんか?
基幹システムに手を加えず連携し、電子化をご提案いたします。
商取引の全帳票を電子化し、即日到着でコスト削減・業務効率化を実現します!
⇒ まずは電子帳票ソリューション ナビエクスプレスの資料を見てみる
取引先の企業に請求書の電子化を提案したものの、拒否されてしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。電子帳簿保存法の改正により、電子でやり取りされた請求書などはデータでの保管が義務となりました。しかし、まだ多くの企業が不安を抱え、電子化を断るケースも少なくありません。
本記事では、請求書の電子化を拒否しても良いのか、拒否された場合の対処法、電子化のメリット、電子帳票システムの選び方などを解説します。請求書の電子化を拒否されてお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。
- 電子帳簿保存法改正により、2022年1月1日から電子で取引された帳票類は電子データでの保存が義務化されている
- しかし、電子化を承諾しなければならないと決めた法律はないため、取引先から提案を拒否される可能性がある
- 拒否された場合の対処法には、紙との併用案のほか、サポート体制を整え、段階的な導入を提案してみると良い
- 電子化を提案する際は、コストやリードタイムの削減、管理のしやすさ、リモートワークへの対応などメリットを伝え、適切な電子帳票システムを選択する必要がある

請求書の電子化は拒否しても良い?
取引先に請求書の電子化を求められた場合は、拒否しても良いのでしょうか。
結論からいえば、請求書の電子化は拒否しても法的には問題ありません。現在、日本で取引先等から請求書の電子化を求められた際、承諾しなければならないと定めた法律などは存在しないのです。
しかし、電子化の利点である業務効率化や将来的な法改正への対応、取引先との関係維持などを考慮すると、会社の種類や規模を問わず取り組むべき課題といえます。電子化の潮流は今後も続くため、取引先も電子化に対応してもらえるように丁寧なコミュニケーションを取ることが重要です。
請求書は原則として電子データでの保存が義務
2021年度に行われた電子帳簿保存法の改正により、2022年の1月1日から「電子取引のデータ保存」が義務化されました。これにより、電子データでやり取りされた請求書などは、原則として電子データでの保存が必要になったのです。
完全な移行までには、2年間の宥恕(猶予)措置期間が設けられており、2023年12月31日までは、一定の事情がある場合などは紙での保存も可能でした。2024年1月1日からは完全に義務化されているものの、現在も一定の要件を満たした事業者は、保存条件が緩和される猶予措置を受けられます。ただ、原則としては電子データによる保存が義務化されているため、早急な電子化への対応が求められるでしょう。
電子帳簿保存法の改正について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
「【2024年施行】電子帳簿保存法の改正内容をわかりやすく解説|制度の概要から紹介」
請求書の電子化を拒否される理由とは?
取引先から請求書の電子化を拒否されてしまう主な理由は、以下の通りです。
- 技術的なハードルを感じている
- 現状の業務フローを変えたくない
- 企業の慣習や文化によるもの
- セキュリティに不安を感じている
電子化を拒まれる背景について、それぞれを詳しくみていきましょう。
技術的なハードルを感じている
取引先企業が電子化に技術的な難しさを抱えているケースです。請求書の電子化には、メールでの確認や電子署名、専用ツールなど、従来には使っていなかった新しい技術を取り入れる必要があります。特に年齢層が高い方などは、デジタルデバイスやデジタルツールなどに高いハードルを感じている場合も少なくありません。結果、電子化の拒否に結びついてしまいます。
現状の業務フローを変えたくない
現在、社内に定着している業務フローを変更するのが面倒に感じて拒否されるケースです。現状の業務フローを変更すると、マニュアルや人員の配置なども変えなければならない可能性があり、手間がかかってしまいます。また、今の慣れているやり方を変えてしまうと、ミスが増えるかもしれないといった不安もあるでしょう。
業務フローの変更に伴うコストやリスクは一時的ではあるものの、避けたいと考える企業は多く、電子化を拒否されてしまう場合もあります。
企業の慣習や文化によるもの
企業によっては、紙にハンコを押す慣習や文化が定着している場合があり、従来のやり方に馴染まないため電子化を拒否されるケースも考えられます。特に、古くからある企業などと取引している場合には、紙を使用した慣習や文化を変えるのが難しいと拒否されてしまう可能性もあるでしょう。
セキュリティに不安を感じている
電子化によって、ハッキングやデータ漏えいなどのリスクが高まるのを理由に拒否されるケースもあります。紙の書類による取引が、特別にセキュリティが高いわけではありません。しかし、実際に手で触れられない電子データのみでの取引にはセキュリティ面での不安を感じる企業も存在します。
特に、今まで電子化に取り組んでこなかった企業では、技術面の理解も遅れており、なおさらセキュリティのリスクに対する不安感が大きくなるケースもあるでしょう。
請求書の電子化を拒否された時の対処法
取引先の企業から請求書の電子化を拒否される場合の主な対処法は、以下の通りです。
- 紙と電子データを併用する
- 電子化のサポートを提案する
- 段階的な導入を提案する
それぞれの方法について、詳しくみていきましょう。
紙と電子データを併用する
取引先の業務ルール上、どうしても郵送でしか対応できないケースもあるかもしれません。そのため、あらかじめ請求書は紙でも対応できるようにしておき、電子化できない取引先だけに郵送すると良いでしょう。ただ、理想は完全な電子化です。取引先に対しては、電子化のメリットを伝えるなど、並行して導入を促すことをおすすめします。
電子化のサポートを提案する
拒否された理由が、電子化のやり方が分からずに不安を感じている場合は、自社がサポートすると伝えてみると良いでしょう。電子化までの道筋が見えれば安心感が生まれ、請求書の電子化に対応しようと考えるようになってもらえるかもしれません。
システムの使い方や電子化する際のファイル管理の方法など、取引先が不安に感じている内容をヒアリングして対策するとともに、問い合わせや質問にも丁寧に応じるようにしましょう。
段階的な導入を提案する
規模が大きな企業の場合は、電子化する書類の数も多くなるため、一気に変更しようとすれば、ハードルが高く感じる可能性があります。まずは、特定の部署の請求書だけを電子化するなど、順を追って移行できないかを相談してみると良いでしょう。
特定の部署で電子化を進め、上手くいってから同様のやり方を使って社内で段階的に広げていく方法なら、取引先も安心して電子化に取り組めるようになります。
電子化のメリットや成功事例を共有する
請求書の電子化には、送り手側だけでなく、受け取り側にもさまざまなメリットがあります。取引先が電子化に否定的なケースでは、電子データでのやり取りにどのようなメリットがあるのかをイメージできていない場合もあるでしょう。具体的なメリットを伝えれば、電子化を承諾してもらえる可能性があります。
電子化の利点を説明する際は、単にメリットを伝えるだけでなく、できれば他の取引先での成功事例なども共有しましょう。より具体的なイメージが湧いて電子化に前向きになってもらえるかもしれません。なお、請求書を電子化する際の受け取り側のメリットについては、次章で解説します。
電子化した請求書を受け取るメリット
取引先から電子化した請求書を受け取るようになると、以下のようなメリットがあります。
- リードタイムが減少する
- 閲覧したい請求書がすぐに見つかる
- 情報共有が容易になる
- リモートワークに対応できる
それぞれのメリットについて、詳しくみていきましょう。
リードタイムが減少する
請求書を電子化すると、リードタイムの削減につながります。リードタイムとは、あるプロセスの最初から終わりまでの時間(期間)を指す用語です。請求書を紙でやり取りしていると、作成してから印刷・封入・郵送といった作業が必要になります。
特に郵送の場合では、送る側がどれだけ作業を効率化しても一定の日数がかかってしまいます。一方、電子データでのやり取りなら、郵送よりもリードタイムが減少し、効率化が期待できるでしょう。
閲覧したい請求書がすぐに見つかる
請求書を電子化すれば、送付・受け取り後の管理も紙でのやり取りより楽になります。電子データの請求書は、社内システムによって一元管理でき、高い検索性をもっているのがメリットです。
紙の請求書なら管理している膨大なファイルのなかから探さなければならなかったところ、電子化すれば、件名や宛先、日付などで容易に検索して見つけられます。請求書の修正や再発行が必要になった場合にも、すぐに対応可能です。
情報共有が容易になる
電子化された請求書を利用すれば、社内での情報共有も容易になります。請求書はすべて電子データとして社内システムで一括管理され、権限さえあれば、受け取った本人以外も閲覧可能です。従来の紙請求書ならコピーして相手に渡す必要があったところ、電子化すれば個人のパソコンからでも簡単に閲覧できます。
請求書に関する無駄な労力を減らすとともに、社内での情報共有を迅速化できるため、さらなる業務効率化が期待できるでしょう。
リモートワークに対応できる
請求書の電子化は、リモートワークへの対応にも大きなメリットがあります。管理用にクラウド型システムを導入した場合、社員は場所や時間を問わず、自宅からでも業務が可能です。
紙の請求書を使用するケースでは、確認や押印、印刷・封入・発送など、出社しないとできない作業が必要とされていました。電子化の実施により、リモートワークへの対応が実現し、従業員はより自由で柔軟な働き方が可能になります。幅広い人材を確保する面においてもメリットがあるといえるでしょう。
電子帳票システムを選ぶ際のポイント
請求書を電子化する際は、効率化のために多くの企業が電子帳票システムを導入しています。電子帳票システムとは、請求書などの帳票類の作成や発送などを半自動化できるシステムです。機能性や信頼性・利便性に優れたシステムを導入すれば、取引先も電子化に対応しやすくなります。
電子帳票システムを選ぶ際の主なポイントは、以下の通りです。
- 導入目的を明確にする
- 対応する機能を確認する
- フォーマットやシステム連携を確認する
それぞれのポイントについて、さらに詳しくみていきましょう。
導入目的を明確にする
電子帳票システムを選択する際は、はじめに導入目的を明確にしておきましょう。電子帳票システムは、サービスによって対応できる業務範囲が異なります。使いたい機能が備わっていないシステムだと不便になるため、以下のように、自社が電子化したい業務範囲を明確にしておくのが大切です。
- 請求書を自動作成して業務効率を向上させたい
- 取引先への配信・受信を自動化したい
- 仕分けや保管など、帳票類の管理を効率化したい
対応する機能を確認する
電子帳票システムは、製品・サービスによって対応している機能も異なります。目的を明確にした後は、自社にとって必要なのはどの機能かを検討しましょう。
電子帳票システムの代表的な機能は、以下の通りです。
| 帳票作成 | 設定した書式・レイアウトに従い、帳票類を作成する機能 |
|---|---|
| 帳票配信 | 帳票類を指定した宛先・日時に自動配信する機能 |
| 自動リネーム | 電子化された帳票データを取り込むと、事前に設定された規則に従ってファイル名を自動的にリネームできる機能 |
| 自動振り分け | 帳票類を事前に設定した規則に従って自動的に分類・振り分けできる機能 |
| レイアウトのカスタマイズ | 作成する帳票類のレイアウトをカスタマイズする機能 |
| タイムスタンプ | システム内でのデータ編集作業にログを残せる機能 |
| データのバックアップ | 万一に備えてデータのバックアップを残せる機能 |
| メールアドレスの収集 | 取引先等のメールアドレスを自動で収集・管理する機能 |
フォーマットやシステム連携を確認する
導入する電子帳票システムと、自社の使用している電子帳票用のフォーマットや既存システムとの連携も大切なポイントです。
多くの企業では、電子帳票のフォーマットとしてPDFやExcel、CSVなどを利用しています。会社によっては異なるデータ形式を用いている場合もあるでしょう。新しいシステムが、自社や取引先の希望するフォーマットに対応しているかを確認する必要があります。
また、既存システムとスムーズに連携できるかも重要です。販売管理システムや会計システム、CRMなど、自社で利用しているシステムと連携ができるかについても事前にみておきましょう。外部のアプリケーションやシステムとのデータ連携を行うAPI連携の有無の確認も必要です。
セキュリティの水準を確認する
請求書をはじめ、重要な帳票を扱う電子帳票システムでは、高いセキュリティが求められます。重要情報の流出などあってはならず、セキュリティの強固なシステムを導入すれば、取引先の不安を払拭できるでしょう。電子帳票システムに搭載されている主なセキュリティ機能は、以下の通りです。
- 管理権限の付与:部署や従業員、役職ごとにアクセスできる情報の権限を変更できる
- 操作ログの記録:システムで編集などの操作を行った際、日時や利用者のログが残り、不正な操作を防止する
- 暗号化:帳票類の送付時など、外部から内容を見られないため暗号化を行う
電子帳票システムの詳細な機能やメリットなどについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
「電子帳票システムの機能やメリット・注意点を徹底解説」
請求書の電子化をサポートする「ナビエクスプレス」
「ナビエクスプレス」は、請求書や領収書、給与明細など、商取引における帳票の電子化に対応した電子帳票ソリューションです。使用中の明細書からデザインを変えずにフォーマットを作成でき、データは全て人の手を使わず自動で配信可能です。
帳票業務に関する人件費や郵送費などのコストを削減するとともに、リードタイムを大幅にカット。さらに、紛失や封入間違いなどの人的ミスも防止して、業務効率化に貢献します。セキュリティ対策によりデータを安全に保護し、各種インターフェースとのシステム連携も可能です。
ここからは、実際にナビエクスプレスを導入した企業様の事例を紹介します。
導入事例|シーバイエス株式会社 様
業務用洗剤に関するサービスを展開しているシーバイエス様では、取引先の飲食店や工場など、毎月1,700件ほどの請求書業務が発生していました。郵送に加え、郵便物では到着までに時間がかかるためFAXで送付してほしいとの要望もあり、作業負担はさらに大きくなります。
そこで、インボイスや電子帳簿保存法をきっかけにナビエクスプレスの導入を決めました。導入後は、郵送していた請求書の80〜90%を電子化。郵送にかかっていた費用も90%近い削減に成功し、請求書業務を大幅に効率化しています。
請求書の電子化は拒否されないように対策を検討しよう
電子帳簿保存法の改正に伴い、請求書のやり取りを電子データで行う企業は増えていますが、取引先によっては電子化を拒否されてしまうケースも考えられます。法律上、電子化の拒否に問題はなく、紙と電子データの併用など代替案もあるものの、今後の流れを考えれば電子化を促していくべきといえるでしょう。
取引先に提案する際には、電子化によるメリットの明示や成功事例の共有が大切です。また、請求書を電子化する場合は、自社のフォーマットや既存システムに応じた最適な電子帳票システムの選択も重要になります。
請求書の電子化を検討されている方は、帳票業務を効率化し、システム連携やセキュリティにも優れた「ナビエクスプレス」の導入をご検討ください。
こちらでは、「ナビエクスプレス」や帳票類の電子化に関する詳しい資料をダウンロードできます。ぜひご利用ください。
https://www.nttcoms.com/service/naviexp/download/
【
請求書の電子化
】
最新のコラム

2024/12/26

2024/11/22