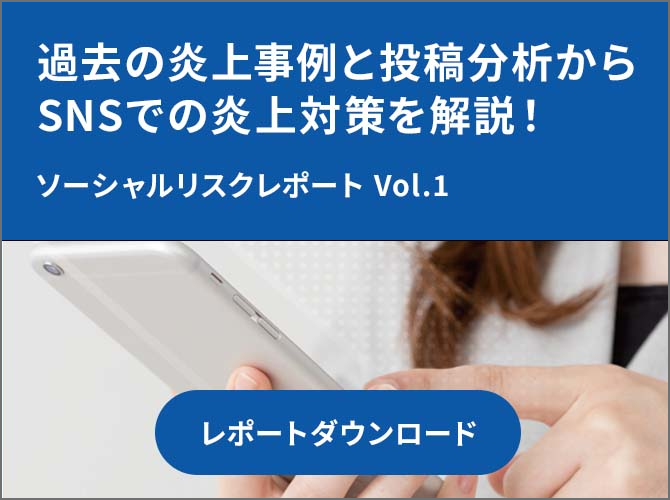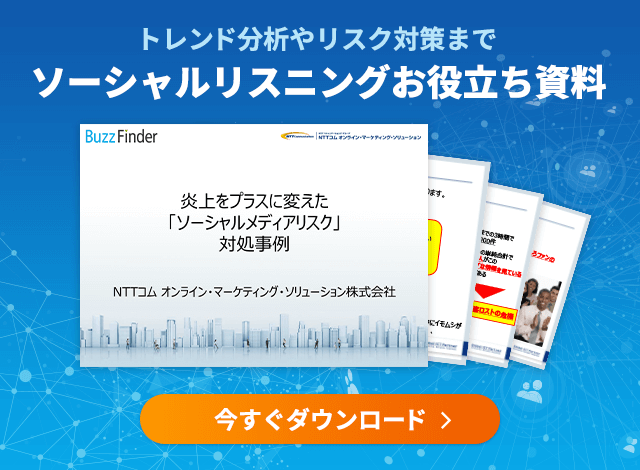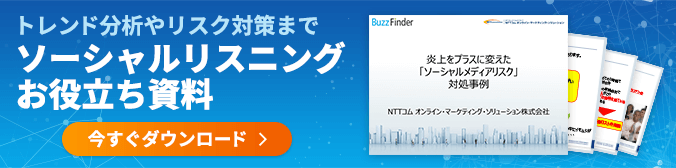2025/09/10
VOCマネジメント
顧客インサイトとは?ニーズとの違いや調査方法、活用までの5ステップを解説
顧客インサイトは、アンケートやインタビューなどに現れないユーザーの潜在的な欲求を表す用語です。顧客インサイトを把握して、商品・サービスの改善やマーケティングに利用できれば、売上の増加につながるだけでなく、顧客満足度向上や新しいビジネスチャンスの発見なども期待できます。自社ビジネスの発展のため、ぜひ顧客インサイトを積極的に活用していきましょう。
本記事では、顧客インサイトの解説から調査方法や分析手法、顧客インサイトを活用するメリットと分析のポイント、成功事例などを紹介します。自社の商品・サービスに顧客インサイトを活用していきたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
- 顧客インサイトとは、顧客自身も気づいていない、深層心理や無意識のうちに抱いている商品・サービスに対する欲求や要望
- 顧客インサイトを活用すれば、商品・サービスの最適化や市場理解・顧客満足度・マーケティング精度の向上、ビジネスの成長などのメリットがある
- 顧客インサイトを把握するには、ユーザーの声をデータとして収集するとともに、顧客目線での分析を行い、仮説を立てて検証する必要がある
- 顧客インサイトを把握するには、消費者の目的や行動の背景にある原因、顧客の声の矛盾点、ネガティブポイントに注目するほか、ソーシャルリスニングが有効になる
顧客インサイトとは?
はじめに、顧客インサイトの概要と、よく似た用語であるニーズとの違いを解説します。
顧客インサイトは「顧客の潜在的な欲求」のこと
顧客インサイト(カスタマーインサイト)とは、顧客が商品・サービスを購入した際の顧客自身も気づいていない、無意識下に眠る「潜在的な欲求」を指す用語です。英単語のインサイトには、「洞察・直感・発見」などの意味があります。
顧客が見慣れた商品に手を伸ばす背景には、無意識の心理が働いています。顧客になぜ商品を購入したのか尋ねると「安いから」「なんとなく」などの理由が返ってくるでしょう。しかし、顧客自身が話す不明確な回答は、多くの場合、本当の理由ではありません。
購買行動の背景には、本人も認識していない真の動機が隠れています。顧客インサイトを正しく理解していなければ、適切な販売戦略は立てられません。マーケティングでは、表面的な行動だけにとらわれず、顧客の深層心理や無意識の感情を理解するのが非常に重要です。
顧客インサイトとニーズ(顕在ニーズ・潜在ニーズ)の違い
マーケティングで使われる、顧客インサイトとよく似た言葉に「ニーズ」があります。ニーズとは顧客の欲求・要望を指す用語です。
ニーズには大きく「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」の2種類があります。顕在ニーズは、「手軽に調理できるキッチン家電が欲しい」「楽して部屋を綺麗にできる掃除機が欲しい」など、顧客自身が自覚している欲求です。
一方、潜在ニーズは「おいしくて健康的な食事を短時間で準備したい」「家事の時間を減らして自由な時間を増やしたい」など、顧客自身もまだ自覚していない欲求を指します。マーケティングでは、顕在ニーズはもちろん、同時に潜在ニーズも理解するのが大切です。
顧客インサイトは、「時間がなくてもきちんとした料理を家族に食べさせたい」「自由な時間が欲しいけど、家事もきちんとこなさないと、だらしない人間だと思われそう……」など、潜在ニーズのさらに深層にあって、本人も言語化できていない本音や心理を表します。
顧客インサイトが重要な理由
自社の商品・サービスで、他社と差をつけるためには顧客インサイトの理解が重要です。
現代は、高品質で手頃な商品やサービスが豊富にそろい、競合との差別化が難しい時代になりました。従来のように商品・サービスの品質や性能・価格を追求するだけでは、他社との差別化は難しく、商品が売りづらくなってきています。
今の時代において、自社商品を効果的にアピールするため、大切なのが顧客インサイトです。顧客自身が気づいていない無意識の購買理由を発見してアプローチできれば、競合との差別化につながるでしょう。
顧客インサイトを捉えるための調査方法
顧客インサイトを捉えるための具体的な調査方法は、以下の通りです。
- アンケート調査
- インタビュー調査
- 行動観察調査
- ソーシャルリスニング
それぞれの調査方法の詳細や注意点を解説します。
アンケート調査
あらかじめ用意した質問に対して、書面やインターネット上などで多数の人に回答を求める調査方法です。企業が顧客の声を集める際の代表的な手段の一つで、質問の定形化により効率的に回答を収集できるメリットがあります。アンケート項目をチェック式にすれば、表やグラフなどにまとめて定量データとして利用できます。
一方で、定性データとして顧客の本音を探る手掛かりになるのが自由記述欄です。選択肢タイプの質問ばかりだと、顧客の無意識の行動理由や深層心理まで捉えきれない可能性もあります。顧客インサイトを探るには、表面的な質問だけでなく、自由記述欄などを取り入れて、背後の理由まで深掘りできるような質問設計が重要です。
インタビュー調査
個別の回答者に対談形式で質問を投げかける調査方法です。アンケートと違い、実際に相手と対面して会話できるため、相手の本音を引き出しやすいメリットがあります。ただ、アンケートと同様にインタビューでも基本的に顧客は本音を言いにくく、本心を探るには工夫が必要です。
たとえば、回答者の表情や声のトーンなどに注目していれば、言葉だけでは語られない相手の気持ちを探り出せる可能性もあるでしょう。また、単純な「はい」「いいえ」だけで答えられる質問ではなく、回答が限定されない形式で問いを投げかけるのも重要です。「なぜ」「どのように」など、オープンな質問を繰り返して理由や原因を探っていけば、顧客の深層心理に迫れる場合もあります。
行動観察調査
顧客が飲食店でどのようにメニューを選んでいるか、新商品のプロモーションに対してどのような反響があったかなど、顧客の実際の行動を観察しながら購買行動のパターンを把握していく調査方法です。アンケートなどと異なり、顧客が自身でもわかっていない無意識の行動や選択プロセスなどを発見できる可能性があります。
店舗内での顧客の動線や商品を手に取る瞬間などを観察すれば、隠れた顧客インサイトを見つけられるケースもあるでしょう。また、アンケート結果のような顧客の発言と実際の行動の矛盾がある場合、両者になぜ齟齬が生まれるのかを考えていけば、顧客インサイトを発見する重要な手掛かりになります。
ソーシャルリスニング
ソーシャルメディア(SNS)の投稿やメッセージの分析から消費者の声を収集する手法です。SNSの投稿は匿名が多いため、消費者の正直な気持ちやリアルな反響が表れやすく、アンケートやインタビューではなかなか出てこないマイナスの意見も収集できます。ブランドや商品・サービスに対するユーザーの真の評価や改善点・ニーズなどを把握するにはソーシャルリスニングが有効です。
ソーシャルリスニングには、顧客から自然に発信される本音や感情をリアルタイムに把握できるメリットもあります。アンケートや行動観察は、調査から分析まで時間のかかる場合が多く、即時性ではSNSにかないません。顧客インサイトを迅速に把握して対応するためにはソーシャルリスニングが重要です。
ソーシャルリスニングについて、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
ソーシャルリスニングとは|意味や分析方法の解説と導入事例を紹介!
顧客インサイトの分析に有効なフレームワーク
顧客インサイトの分析に有効といえる主なフレームワークは、以下の通りです。
- ペルソナを設定
- 共感マップ
- カスタマージャーニー
それぞれの方法を詳しく解説します。
ペルソナを設定
はじめに対象となる顧客のペルソナを設定しましょう。ペルソナ設定は、ターゲットをはっきりとさせるため、商品・サービスの典型的なユーザー像を設定するフレームワークです。関係者の間で同じユーザー像を共有できれば、行動分析や顧客視点での施策検討などがやりやすくなるでしょう。
ペルソナを設定する際は、年齢や性別などの基本属性はもちろん、休日の過ごし方・趣味趣向なども含めて作成するのが重要です。曖昧なペルソナでは分析精度も曖昧になってしまいます。仕事の悩みやチャレンジしたい目標など、顧客の心理状態まで細かな部分まで特定するのがポイントです。また、一度設定したら終わりではなく、環境変化に応じたペルソナの改善・更新も求められます。
共感マップ
顧客を取り巻く環境や行動・感情などマップ(図)にして把握・理解するためのフレームワークです。共感マップ(エンパシーマップ)の作成により、ユーザーが置かれている状況がわかり、顧客と同じ感情をもち、共感が可能になります。普通なら目に見えない顧客の感情まで可視化できるため、商品・サービスを通じて解決できる悩みや叶えられる願望など顧客インサイトの特定にもつながるでしょう。
共感マップを作成する場合は、はじめに分析の対象者を設定して、以下のような要素を順に書き出していきます。
- 何を見ているか
- 何を聞いているか
- 考えや感じている事柄は何か
- 実際の言動と行動
- 悩みやストレスになっている事柄は何か
- やりたい事柄や将来の目標は何か
- 何に共感しているのか
カスタマージャーニー
ユーザーが商品・サービスを認知し、購入するまでの顧客体験の一連の流れを可視化するフレームワークです。認知から購入に至るまでの各段階において顧客の購買行動を時系列に整理できるため、購入に結びつく感情の変化を詳細に分析・理解できます。
カスタマージャーニーは、共感マップなど、ほかの方法と組み合わせると効果的です。特に、ユーザーと企業の接点である「タッチポイント」における顧客の感情整理には共感マップの情報が役立ちます。
カスタマージャーニーマップを作成すれば、顧客の購買プロセス全体を通して、隠れたインサイトの発見につながるでしょう。各段階での課題や改善点が明確に把握できるため、効果的な施策立案にも結びつきます。
顧客インサイトの見つけ方とは?活用までの5ステップ
顧客インサイトを発見・活用するための方法を以下の5ステップにわけて解説します。
- データを収集する
- データを分析する
- 分析結果から顧客インサイトを見つける
- 顧客インサイトの正否を検証する
- マーケティングに活用する
それぞれのステップを詳しくみていきましょう。
1|データを収集する
顧客インサイトを見つけるには、まず分析のもとになるデータの収集が大切です。顧客に関する情報が不十分なままでは、いくら分析を行っても顧客インサイトを発見するのは難しいでしょう。アンケートやインタビュー、行動観察調査、ソーシャルリスニングなどを通じて、必要なデータが揃っている状態で分析を行うのが重要です。
ただ、存在するデータをすべて集める必要はありません。顧客理解に求められるデータを整理しながら収集しましょう。いくつかの調査方法から、自社に合った手段を選択するか、または併用するのも効果的です。
2|データを分析する
データ収集が済んだら、集まったデータを分析して顧客に共通する傾向やパターンなどを見つけ出していきます。顧客インサイトでは、統計のように数字で表せる定量データと自由記述やインタビューなどの定性データを上手く組み合わせ、相互に分析していくのが大切です。
顧客の隠れたニーズや要望は、数値データだけでは十分に理解できません。分析にあたっては、まず定量データでおおよその傾向を把握し、続いて定性データで深掘りしていくアプローチが有効です。
顧客インサイトの分析では、以下のような分析手段が有効な方法として用いられます。
- データマイニング:大量のデータから情報を分析する方法
- クラスター分析:似たデータ同士をグループにする分析手法
- テキストマイニング:大量のテキストデータから情報を分析する方法
3|分析結果から顧客インサイトを見つける
データの分析結果にもとづき、顧客インサイトを見つけ出しましょう。顧客インサイトを見つける際は、「顧客はこう考えているはずだ」といった思い込みや固定観念を取り除くのが大切です。
顧客インサイトはユーザー自身も意識していない心理のため、消費者の声やデータと論理的に矛盾している場合もあります。固定観念をすべて取り払わなければ、顧客の深層心理には辿り着けません。徹底的に顧客目線になって、柔軟な視点から考える姿勢が重要です。
4|顧客インサイトの正否を検証する
顧客インサイトを見つけたら、本当に正しいかどうかの検証が必要です。再度アンケートを実施したり、実際の顧客の購買行動と照らし合わせたりすれば、顧客インサイトをよりブラッシュアップできます。
特定のセグメント(属性)の顧客に対してパーソナライズされたメッセージを送り、効果を検証する方法も有効です。また、導き出した顧客インサイトを社内の複数の関係者で議論し、多角的な視点から妥当性を検証する必要もあります。各種検証結果をもとに、さらなる改善や追加調査を実施しましょう。
5|マーケティングに活用する
検証が済んだ顧客インサイトは、積極的にマーケティング施策や商品開発に反映させていきましょう。商品リニューアルや新機能の追加など、従来よりも顧客の本音に近い悩みや要望に応えられるため、ユーザーにもリーチしやすくなるはずです。
顧客インサイトは一度だけでなく、継続的に活用していくのが大切になります。顧客の関心を引きエンゲージメントを高めるための手段として、個別メッセージやオファーの提供などが有効です。
顧客インサイトを捉えるメリット
企業がマーケティング施策として、顧客インサイトを捉えるメリットは、主に以下の通りです。
- 顧客や市場をより深く理解できる
- 製品・サービスを最適化できる
- 顧客満足度の向上につながる
- 競合との差別化につながる
- 新たな需要発見につながる
- マーケティングの精度が向上する
- ビジネスの成長につながる
それぞれのメリットを詳しく解説します。
顧客や市場をより深く理解できる
1つ目のメリットは、顧客や市場をより深く理解できる点です。顧客インサイトが把握できれば、表面的なニーズだけでなく、顧客の深層心理まで踏み込んで理解できます。ユーザーの行動パターンや購買動機を詳細に把握できるようになるため、従来の市場調査では見えなかった本音や感情まで織り込んだ施策が実施可能です。
製品・サービスを最適化できる
2つ目のメリットは、製品・サービスの最適化です。顧客インサイトを捉えられれば、顧客が本当に求めているものや価値を理解できるようになり、製品・サービスの改善に活かせます。
よりユーザーが求める商品が提供できるため、市場での競争力も向上するでしょう。また、改善できるのは単に機能や品質だけでなく、製品・サービスを通じてもたらされる顧客体験全体の最適化にもつながります。
顧客満足度の向上につながる
3つ目のメリットは、顧客満足度の向上です。顧客インサイトの理解により、製品・サービスの改善が進めば、比例してユーザーの満足度向上も見込めます。満足度の高い顧客はリピーターになりやすい傾向があるため、自社のファン獲得にも結びつくはずです。
また、高い満足度を感じた顧客が口コミや知り合いへの推薦などを通じて、新規顧客を引き寄せてくれる効果も期待できます。顧客満足度が高くなりユーザーとの間で良好な関係を築ければ、顧客ロイヤルティ(製品・サービスへの信頼・愛着)の向上にもつながるでしょう。
競合との差別化につながる
4つ目のメリットは、他社との差別化です。顧客インサイトを活用して製品・サービスの質を向上させていけば、他社との差別化も実現できます。競合他社を含めて、ほかの企業が捉えきれていない顧客の本音を理解できているのは、自社にとって大きな強みです。
顧客インサイトに基づく独自の価値提供を行えるようになれば、顧客にとっては自社がより魅力的な選択肢になります。結果的に他社への競争優位性を確立でき、売上の増加も期待できるでしょう。
新たな需要発見につながる
5つ目のメリットは、新しい需要の発見です。顧客インサイトを分析すれば、今まで顧客も企業側も気づいていなかった、新たな需要を満たす商品開発のきっかけとなるかもしれません。消費者自身も意識していない本音である顧客インサイトには、今は存在しない新しい市場を開拓する可能性もあります。顧客の声やアイデアから潜在的な市場ニーズを発見できれば、大きなチャンスになるでしょう。
マーケティングの精度が向上する
6つ目のメリットは、マーケティングの精度向上です。顧客インサイトを基にすれば、より顧客の望むニーズや価値にリーチできるようになるため、従来よりもマーケティング精度の向上が期待できます。顧客の心に響くメッセージやアプローチ方法の採用など、ターゲット市場の行動や好みを把握して効果的な戦略の展開が可能です。結果として、今までよりも広告やプロモーションの効果が上がり、キャンペーンの成功率向上にもつながるでしょう。
ビジネスの成長につながる
7つ目のメリットは、自社ビジネスの成長につながる点です。顧客インサイトを利用して効果的な戦略を立てられるようになると、ビジネスの成長を促進します。顧客の隠れた本音に寄り添ったマーケティングで信頼を獲得できれば、市場での存在感も強化できるでしょう。新規顧客獲得による売上拡大やクロスセル(顧客に関連商品を薦めるセールス方法)・アップセル(顧客に上位互換の商品を薦めるセールス方法)の機会創出につながる点もメリットです。
顧客インサイトを捉えることが難しい理由
顧客インサイトを捉えられれば多数のメリットがあるものの、実際には回答者にバイアスのかかるケースが多いため、的確に理解するのは難しいと考えられます。
顧客の声にバイアスが生じる主な理由は、以下の通りです。
- 社会的な望ましさ:他人からどう思われるかを考えて意見を変える
- 恥ずかしさ・気まずさ:自分の考えに恥ずかしさや気まずさを感じて本音を隠す
- 期待に応えたい気持ち:質問者の望む答えを予想して、無意識に合わせてしまう
- 無意識バイアス:顧客の意見が複雑な場合など、うまく言語化できず、本人も意識していないバイアスがかかるケースもある
- 面倒くさい・期待していない:アンケートが長すぎるなどの理由で面倒に感じる場合や「何を言っても企業はユーザーの意見なんか聞かないだろう」と考えている場合など、顧客が真剣に回答しないケース
顧客インサイトをマーケティングに活用した企業事例
続いては、実際に顧客インサイトをマーケティングに活用した以下の3つの企業事例を紹介します。
- カリフォルニア牛乳加工業者協会
- 日清食品株式会社
- カルビー株式会社
顧客インサイトの特定方法や活用のやり方などを詳しくみていきましょう。
カリフォルニア牛乳加工業者協会
カリフォルニア牛乳加工業者協会が1993年からカリフォルニア州で多くの人に牛乳を飲んでもらうためにはじめた「Got Milk?」キャンペーンは、アメリカで史上最も成功した広告キャンペーンの一つといわれています。
協会では消費者からの「パンやシリアル、クッキーなどを食べているとき、牛乳がないとストレスになる」との声をもとに、パンやシリアルの売り場にキャンペーンポップを出したり、朝食やおやつの時間にテレビCMを流したりする方法で、落ち込んでいた牛乳の消費量増加に成功しました。
日清食品株式会社
日清食品株式会社では、シニア世代向けにカップ麺を売り出すため、従来の健康志向から宣伝方法を変更しました。消費者の声を分析すると、「健康に気を遣っている」人がいる一方、揚げ物やビールなどが好きな人も一定数いると判明します。顧客インサイトを基に「アクティブシニア」をターゲットに商品設計とプロモーションを進め、従来よりも高価格帯ではあるものの、フカヒレやスッポンなどリッチな食材を使用した高級カップ麺「カップヌードルリッチ」を発売。シニア世代向けのヒットを成功させました。
カルビー株式会社
カルビー株式会社では、同社の主力商品の一つ「かっぱえびせん」の新商品開発に向け、顧客インサイト分析を行うため、絶品部「やめられない、とまらない」課と呼ばれるオンラインコミュニティを立ち上げました。顧客との直接のコミュニケーションを通じて「かっぱえびせん」の新しい需要として晩酌シーンを発見。顧客インサイトを反映した「お酒の時間を充実させる」コンセプトのもと、新商品を開発して「かっぱえびせん」ブランド全体の魅力向上に成功しています。
顧客インサイトを捉えるためのポイント
顧客インサイトを捉えるためのポイントは、以下の5つです。
- 顧客の目的に注目する
- 現象とその原因に注目する
- 顧客の矛盾に注目する
- ネガティブポイントにも注目する
- ソーシャルリスニングツールを活用する
それぞれのポイントを詳しく解説します。
顧客の目的に注目する
顧客インサイトの分析では、顧客が求めている手段だけでなく、背景にある目的にも注目します。
自動車産業で成功をおさめたヘンリー・フォードは、もし自分が顧客に要望を聞いていれば、彼らは「もっと速く走る馬が欲しいと答えただろう」と言いました。自動車の存在を知らない人々に要望をたずねても「自動車が欲しい」とは言いません。しかし、背景には「速い移動手段が欲しい」といった目的が隠されています。
同様に、マーケティング学のセオドア・レビット教授の「人々は四分の一インチのドリルを欲しがっているのではなく、四分の一インチの穴を欲しがっている」と述べました。顧客の要望を分析する際、ドリル(手段)に注目しがちですが、実は目的である「四分の一インチの穴」が達成されれば、手段はドリルでなくてもかまいません。
顧客インサイトの分析では、顧客が抱えている悩みを根本的に解決する方法を考えるのが重要です。手段から本来の目的を探っていけば、真の顧客インサイトに辿り着けるでしょう。
現象とその原因に注目する
顧客インサイトを捉える際は、現象から原因を探って問題を解決していく方法が効果的です。
ある調査では、スーパーマーケットで「特定スナック菓子の売上が平均より低い」現象が起こりました。原因を調査していくと、顧客の目線や手が届きやすい中段に商品がないため、存在に気づきにくい可能性があるとの結果が出ました。
参考:NCBI home page「BRAND PLACEMENT AND CONSUMER CHOICE: AN IN-STORE EXPERIMENT」
ある現象が起きた際、原因について思考をめぐらせると、新たな視点を生み出すヒントになる場合があります。顧客も気づいていない新しい発見から、顧客インサイトを導ける可能性が高まるでしょう。
顧客の矛盾に注目する
顧客インサイトを分析する手法の一つに、顧客の行動や発言をまとめたデータの中から矛盾を見つける方法があります。ユーザーは企業からのアンケートに対して、常に正直に回答するとは限りません。また、無意識に答えにバイアスが生じる可能性もあります。
あるハンバーガーチェーンでは、消費者の健康志向の高まりを受け、ヘルシーメニューを導入しましたが、売上は期待を下回る結果となりました。また、ある飲料会社では新しい味を好む消費者が多いとの調査結果から新商品を発売したものの、実際には多くの顧客は従来からある商品の味を好んでいたため受け入れられずに終わります。
顧客インサイトを捉える際、ユーザーからあがった声をそのまま鵜呑みにするのは危険といえるでしょう。
ネガティブポイントにも注目する
すべての物事はポジティブな面とネガティブな面の両方をもちあわせており、顧客インサイトでは、見方を変えてネガティブポイントを探るのも重要です。
英国自動車協会(AA)で「会員数や収益が長期的に減少している」といった現象に悩まされていました。顧客獲得や収益性向上を目指し、AAでは対策を実施。顧客インサイトの分析を基にして、消費者から「モータリングへのワクワク感や楽しさ」といった感情的価値が失われているという深層心理を推測します。AAでは広告をユーザーの理性から感情に訴える内容へと変更。従来の機能重視の広告から「楽しむ」を押し出し、感情に訴えるメッセージを展開して収益性の向上を成功させました。
ネガティブなポイントを深堀して顧客インサイトを捉え、ポジティブなメッセージに転換して成功した事例といえます。
ソーシャルリスニングツールを活用する
顧客インサイトの分析には、ソーシャルリスニングツールを活用しましょう。現在、ユーザーの声を集める際にソーシャルメディア(SNS)の調査・分析は欠かせません。しかし、リアルタイムに大量の投稿が行われるSNSの分析(ソーシャルリスニング)に必要な時間と手間は膨大です。自社のリソースだけで行うのは難しいケースも多いでしょう。
ソーシャルリスニングを手軽かつ効率的に実施できるようにするのが、ソーシャルリスニングツールです。ソーシャルリスニングツールを活用すれば、SNS投稿の収集・分析から広告の効果測定、炎上リスク対策など、さまざまな効果が期待でき、効率的な顧客インサイト分析が可能になります。
ソーシャルリスニングツールについてのさらに詳しい解説や選び方のポイントを知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
ソーシャルリスニングツールの選び方とは?比較のポイントを詳しく解説
顧客インサイトの特定に有効なNTTコム オンラインの「Buzz Finder」
「Buzz Finder」はソーシャルリスニングによるVOC分析(顧客の声を収集して企業活動に活かす分析手法)やSNS上での炎上リスク対策に効果的なソーシャルリスニングツールです。
「Buzz Finder」の主な機能は、以下の通りです。
- X (旧Twitter)の投稿を公式全量データでリアルタイム収集
- デイリートピックメールや投稿急増時のアラート通知で炎上対策
- キーワード収集時のノイズ除去や専門コンサルタントによる分析
- InstagramやFacebookなど、他のSNSにも対応
「Buzz Finder」は、SNSでの投稿をタイムリーに収集・分析でき、手軽にユーザーの生の声を集められるだけでなく、アラート通知機能によって炎上時の迅速な対応にも役立ちます。また、集めたデータはトレンド分析や関連語分析・ネガポジ分析など、各種分析機能で詳しく解析でき、投稿に表れにくい顧客インサイトの把握も可能です。
続いては、実際に顧客インサイトの分析に「Buzz Finder」を利用している企業様の事例を紹介します。
導入事例|情報通信サービス業 様
ある情報通信サービス企業様では、SNS上にあるユーザーの声を自社サービスの改善に役立てるため「Buzz Finder」を導入しました。
「Buzz Finder」のSNS投稿のリアルタイム収集とVOC分析機能を活かし、自社と競合のサービスに関する顧客の声をポジティブ・ネガティブ別に役立つ順番でサマリー化。傾向や対策などのアドバイスをまとめ、毎月レポートとして関係社員から幹部までが共有を行い、社内の改善意識の高まりへとつなげるのに成功しました。
導入事例:情報通信サービス業 様
顧客インサイトは効果的なマーケティングに欠かせない要素
企業の商品・サービスに対して顧客が無意識のうちに抱いている欲求である「顧客インサイト」は、消費者に対する効果的なマーケティング施策を実施するために欠かせない要素です。しかし、顧客インサイトはユーザー自身も気づいていない要望のため、アンケートなどを行っても簡単には把握できません。顧客インサイトを理解するには、データ収集・分析によって顧客の深層心理にある需要に辿り着く必要があります。
なかでも、SNSをはじめとするインターネット上の投稿は、顧客の生の声が表れやすく、顧客インサイトの分析に重要です。顧客インサイトを製品・サービスの改善やマーケティングに活用したいとお考えの方は、ぜひソーシャルリスニングツール「Buzz Finder」の導入を検討してみてください。
以下のリンクからソーシャルリスニングやVOC活用に関する資料・レポートをダウンロードできます。ぜひご利用ください。
https://www.nttcoms.com/service/social/download/
関連記事

2022/03/14

2022/01/06