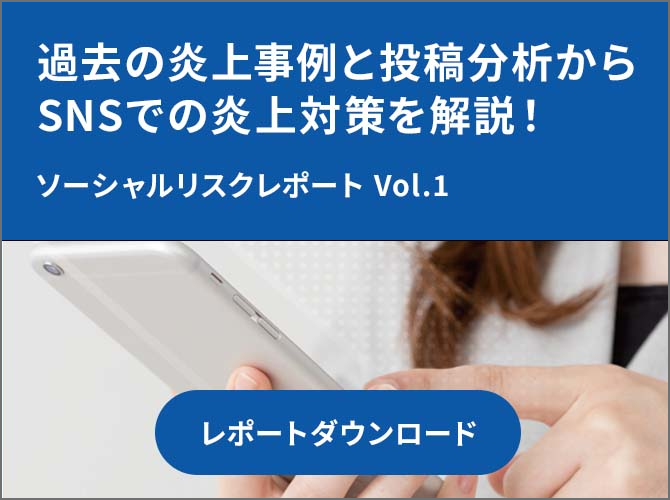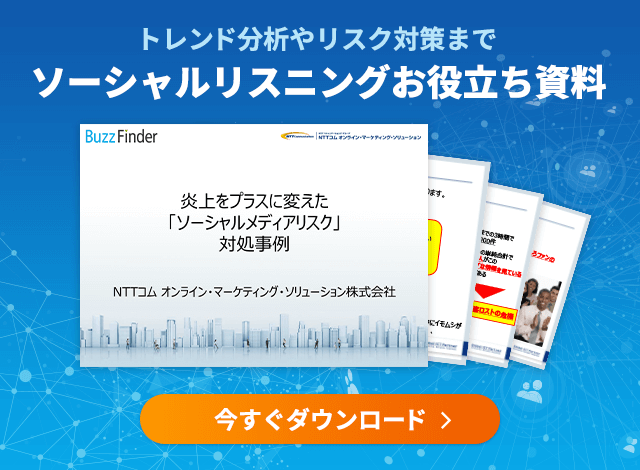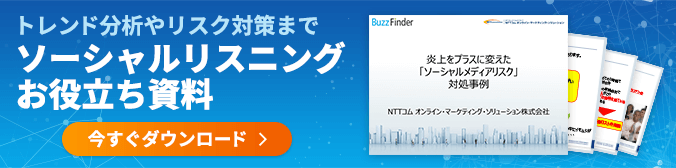2025/08/01
VOCマネジメント
公聴とは?自治体が実施する利点や実施方法、成功のポイントや注意点を解説
公聴とは、自治体が政策や条例の策定・改正など重要な意思決定を行う際に、利害関係者や専門家、市民などの意見を直接聴取する正式な手続きです。
本記事では、公聴の基本的な意味や自治体が実施する利点、具体的な実施方法、さらに効果的に公聴を進めるためのポイント・注意点について詳しく解説します。効果的な方法で公聴を実施したい行政のご担当者様は、ぜひ参考にしてください。
- 公聴を実施し市民や専門家の声を取り入れることで、より納得感があり、実効性のある政策が生まれやすくなる
- 公聴には、政策の質向上、住民との合意形成促進、信頼性の向上といった多くのメリットがある
- 自治体がSNSで公聴する際には、個人情報やプライバシーに配慮する、炎上のリスクに備える、SNS上の意見の偏りに注意するなどの配慮が必要
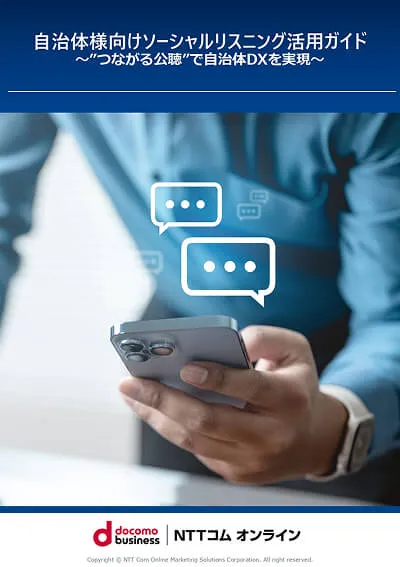
公聴の意味とは?
公聴とは、行政機関や議会などが政策や制度を決定する過程で、利害関係者や専門家、市民などの意見を公式に聴く制度です。主な実施主体には、国会、地方議会、行政機関があり、それぞれの目的に応じて実施されます。
公聴の方法には、公聴会やパブリックコメントをはじめ、最近ではSNSを活用する例もあります。多様な立場の声を取り入れることで、より透明性と納得感のある政策形成を目指す仕組みです。
公聴が必要とされる理由
公聴が求められる背景には、民主主義における住民参加の重要性があります。政策が市民の生活に直結する以上、その決定プロセスには多様な意見を反映させる必要があるのです。
多様な専門知識はもちろん、現場の実情や市民の声を取り入れることで、より実効性のある政策が生まれると考えられています。また、公聴は行政と市民の間に信頼関係を築く機会にもなり、透明性や納得感のある行政運営にもつながります。
公聴と広聴の違い
「公聴」と「広聴」はいずれも、「一般(市民)から幅広く意見を募る」という点では共通しています。一般には「広聴」がより広く用いられ、辞書などでも行政の住民意見の収集活動にはこの漢字が使われています。一方の「公聴」は、重要な政策決定の際に利害関係者や専門家の意見を聴く「公聴会」など、より限定的かつ公式な手続きに使われます。
このように、公聴は重要案件で使用されることが多いですが、本記事内では主に市区町村などの行政機関で、意見を収集する行為を総称した意味合いで使用します。
公聴とソーシャルリスニングの違い
「公聴」と「ソーシャルリスニング」は、いずれも市民の声を把握するための方法ですが、その性質は異なります。公聴は行政機関などが主体となり、住民や関係者から意見を聴取する正式なプロセスで、制度に基づいて実施されます。
一方のソーシャルリスニングは、SNSなどに投稿された発言を受動的に収集・分析し、世論の傾向や感情を読み取る手法です。ただし、最近では公聴の一環として、行政がソーシャルリスニングを活用する動きも広がっています。
【関連記事】ソーシャルリスニングとは|意味や分析方法の解説と導入事例を紹介!
自治体が公聴を実施する利点
自治体が公聴を行うことで、住民の声を政策に反映しやすくなり、施策への理解と信頼を得ることが期待できます。ここでは、公聴を実施することによる主な利点について紹介します。
政策の質が向上する
公聴を通じて住民や専門家、利害関係者の多様な意見を取り入れることで、政策の盲点に気づき、より実効性の高い内容に改善できる点が利点です。現場の声をもとに政策と実態とのギャップが明らかになり、現実的かつ持続可能な方向に政策を導くことが可能になるでしょう。
さらに、政策を実施する前に課題や懸念を把握できるため、実施後の混乱や修正のリスクを抑える効果もあり、政策の実効性を高めることが期待できます。
住民との合意形成が促進できる
公聴を通じて政策の背景や必要性を丁寧に伝え、住民の声を反映するプロセスを設けることで、理解と当事者意識が育まれます。行政と住民が直接意見を交わすことで相互理解が進み、批判的な意見にも真摯に対応することで、住民の納得感も高まるでしょう。
このような合意形成プロセスを経ることで、政策実施時に住民の協力を得やすくなり、政策のスムーズな運用と高い成果が期待できるところが大きな利点です。
透明性の確保により信頼性が向上する
政策決定に至る経緯や根拠を明確に示し、会議録や意見書を公表することで、住民は行政の意思決定プロセスを確認することができます。住民から寄せられた質問や疑問に行政や外部専門家が明確に回答することで、理解を深めることも可能です。
このような透明性の高い行政運営は信頼感を高め、住民との継続的な協力関係の構築にもつながります。結果として、政策の実効性や社会的な受容も向上するでしょう。
自治体が公聴を実施する方法
自治体が住民の声を政策に反映させるには、適切な方法で公聴を実施することが必要です。ここでは、代表的な手法やその特徴について紹介します。
公聴会
公聴会は地方自治法に基づく正式な意見聴取手続きで、重要な条例制定や施策決定時などに開催が義務付けられています。以下は、公聴会の流れの一例です。
- 市は、公聴会のテーマや案、資料、開催日時、会場、意見を述べられる人の条件、意見の提出方法や期限などを事前に知らせる
- 意見がある人は、決められた方法で文書にまとめて提出する
- 市は、提出者の中から会に出席して意見を述べる「公述人」を選ぶ
- 選ばれた公述人が、公聴会で意見を発表する
- 市は、会の内容や日時、公述人の情報、発言要旨ややり取りの概要などを公開する
公述人は利害関係者や学識経験者から公平かつバランスよく選ばれ、会議は公開が原則で、住民が自由に傍聴できます。集められた意見は政策決定の重要な参考資料となることからも、公聴会は透明性の高い手法であるといえます。
パブリックコメント
パブリックコメントは行政手続法に基づき、政令や条例の制定・改正前に案を公開し、広く住民の意見を募集する正式な制度です。近年は、e-Govなどのオンラインプラットフォームを活用し、時間や場所を問わず効率的に意見を収集できるようになりました。
集まった意見に対しては、行政がその考え方や対応方針を公表することで、透明性と説明責任を確保しています。これにより住民の理解と信頼が深まり、政策の妥当性も向上します。パブリックコメントは住民参加を促進し、行政と市民の双方向コミュニケーションを強化する重要な仕組みです。
アンケート調査
アンケート調査は、住民の意識や意見を数値的に把握するための重要な手法であり、政策立案に欠かせない基礎資料となります。無作為抽出によって調査対象の代表性を確保したり、特定の層を意図的に抽出して詳細な分析を行ったりでき、多角的なデータ収集が可能です。
調査方法は郵送やWeb、面接など多様で、誘導的でない中立的な質問設計が重要です。収集されたデータは統計的に分析され、住民の意識傾向やニーズが明確になります。こうした信頼性の高いデータは、具体的かつ実効性のある政策立案に活用され、地域の課題解決や住民の満足度の向上に寄与するでしょう。
SNSでのソーシャルリスニング
SNSを活用したソーシャルリスニングは、従来の公聴手法を補完する新しい方法として注目されています。最大の特徴は、リアルタイムで住民の声を広範囲かつ多様に収集できる点です。住民が自発的に投稿する意見や感想を通じて、従来の方法では把握しづらかった現場のリアルなニーズや課題を、的確に捉えることができます。
また、SNSの双方向性を活かして、行政と市民の対話を促進することで、政策への理解や信頼関係の構築にも貢献するでしょう。情報収集の際は漏れや偏りを防ぐために、AIや専用解析ツールなどを活用することが好ましく、これにより効率的かつ網羅的な分析が行えます。
結果として、迅速で柔軟な政策対応が可能となり、市民参加の質を高める効果が期待されています。これからの行政運営において、ソーシャルリスニングは重要な役割を果たすといえるでしょう。
【関連記事】ソーシャルリスニングツールの選び方とは?比較のポイントを詳しく解説
自治体がSNSでの公聴を成功させるポイント
自治体がSNSを活用した公聴を効果的に行うには、適切なツール選びや住民参加を促す工夫が不可欠です。双方向の対話を通じて、多様な意見を集めるポイントを解説します。
市民が参加しやすい工夫をする
市民が公聴に参加しやすくするためには、まず広報誌やWebサイト、SNSを活用して実施情報をわかりやすく伝えることが大切です。また、アンケートでは、専門用語を避けた平易な言葉と簡潔な質問で短時間で答えられる構成にするなどで、参加ハードルを低くできます。
さらに、SNSではコメントやいいね、シェア、ハッシュタグなど多様な反応方法を用意すると共に、意見が政策に活かされることを明示して、市民の参加意欲を高める工夫などが求められます。
意見募集の結果を市民に公表する
収集した意見の概要や意見数、行政の対応方針、政策への反映状況などの結果を必ず公表し、情報の透明性を確保することが大切です。SNSでの結果投稿に加え、公式Webサイトで詳細を公開し、可能な限り個別の意見に対しても回答や検討結果を示すことで、市民の理解と納得感を高めることができます。
また、政策実施後には効果や課題についても定期的に報告し、継続的な情報提供を通じて、住民との信頼関係の維持・向上に努めることが求められます。
公聴活動を継続的に実施する
公聴活動は単発で終わらせず、定期的に実施することで、住民との継続的な対話関係を築くことができます。政策の重要度に応じて適切な頻度で公聴活動を行い、住民の声を反映し続けることで信頼性が高まるでしょう。
また、実施後には効果検証と運用方法の見直しを定期的に行い、改善サイクルを確立することで、より効果的で質の高い公聴活動を継続的に展開できます。
自治体がSNSで公聴するときの注意点
SNSを活用した公聴は手軽で反応も得やすい一方で、誤解や炎上といったリスクも伴います。また、自治体がSNSで意見を募る際は、信頼性と公平性を保つ工夫も欠かせません。ここでは、自治体がSNSで公聴するときの注意点を解説します。
SNS利用規約や法律を遵守する
SNSを活用した公聴活動では、各プラットフォームの利用規約や関連法令の遵守が前提となります。たとえば、個人情報保護法や地方公務員法に基づく適切な情報管理、著作権法に準拠した画像や投稿の使用許諾などが求められます。これらの規定を軽視すると、住民との信頼関係を損なうリスクがあるので注意が必要です。
また、組織内で定期的にSNS運用に関する研修を実施し、職員一人ひとりのリテラシー向上を図ることも、安全かつ効果的な活用のために欠かせません。
個人情報やプライバシーに配慮する
SNSでの公聴活動では、個人情報やプライバシーの保護が不可欠です。住民の投稿やコメントに個人を特定できる情報が含まれている場合は、必ず匿名化や削除を行う必要があります。また、写真を投稿する際は、写っている人物に撮影・掲載の許可を得るか、顔にモザイクをかけるなどの配慮が求められます。
さらに、詳細な住所や個人宅が判別されるような位置情報の公開は避け、他利用者の個人情報を含む投稿を見つけた際には、速やかに削除対応を行うことが重要です。
炎上などSNS特有のリスクに備える
SNSでの公聴活動には、炎上など特有のリスクへの備えが欠かせません。政策に対する批判が誹謗中傷へと発展したり、誤解に基づく情報が拡散したりするケースも想定されます。そのため、投稿前の内容チェック体制を整え、想定される批判への回答案をあらかじめ準備しておくことが重要です。
行政機関は民間企業以上に透明性や中立性が求められるため、表現やコストのかけ方についても市民の視点から慎重に判断する必要があります。また、万一の炎上に備え、対応手順や責任者を明確にした危機管理マニュアルを策定しておくことも、信頼維持のために有効です。
寄せられた意見には誠実に対応する
SNSなどで寄せられた市民の意見には、誠実かつ丁寧に対応する姿勢が求められます。質問や要望には可能な限り迅速に返答し、即答が難しい場合でも検討中である旨と回答予定時期を伝えることで、信頼感が生まれます。
また、回答の際は専門用語を避け、具体的で分かりやすい説明を心がけることが大切です。やりとりの履歴は記録として残し、後の政策検討に活かすとともに、住民との継続的な対話の基盤として活用することが望まれます。
SNS上の意見の偏りに注意する
SNSでの意見収集は手軽で即時性が高い一方で、意見の偏りに注意が必要です。SNS利用者は若年層や都市部の住民が多く、高齢者や地方在住者の声が届きにくい傾向があります。また、少数の発信力の強いユーザーの意見が多数派のように見える場合もあり、実際の住民全体の意見を正確に反映しているとは限りません。
そのため、アンケートや公聴会など他の手法と併用し、多様な層や地域からの意見を意識的に集める工夫が必要です。
SNSを使った自治体の公聴には「Buzz Finder」
Buzz Finderは、SNSやWeb上の動向をほぼリアルタイムで把握し、分析するソーシャルリスニングツールです。X(旧Twitter)に投稿された内容をリアルタイムで収集・分析できるほか、過去の投稿履歴や複数のメディア情報も横断的に調べることができます。また、投稿数の急増を検知した際にはアラートメールで通知するなど、炎上のリスクにも迅速に対応可能です。
自治体の活動においては、住民が自発的に投稿した内容から、顕在化していない政策課題や地域ニーズを把握するのに役立ちます。また、特定エリアの反応把握やキャンペーン後の反響分析などにも活用可能です。
公聴は自治体と市民をつなぐ重要な取り組み
公聴は、自治体が市民の声を政策に反映させるための重要な取り組みです。意見を丁寧に聴き取り対話を重ねることで、住民との信頼関係を築き、より実効性のある施策づくりにつなげることができるでしょう。
SNS上の声を手作業で収集・分析するのは膨大な労力がかかるため、Buzz Finderのようなソーシャルリスニングツールの活用が効率的です。詳しい運用事例を収録したレポートは以下のリンクからダウンロード可能ですので、ぜひお役立てください。
関連記事

2022/03/14

2022/01/06