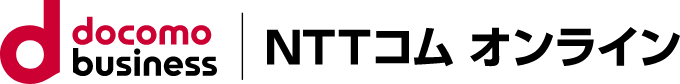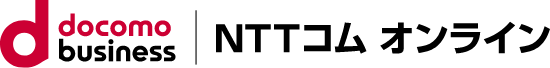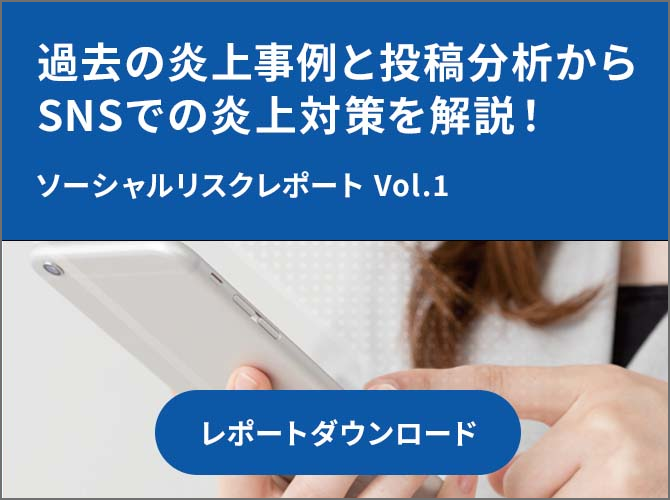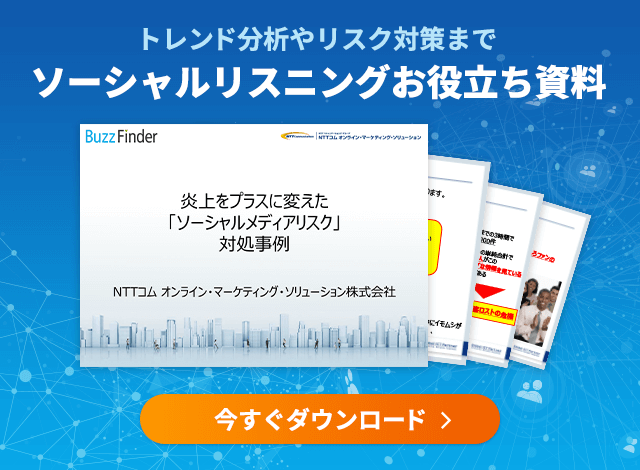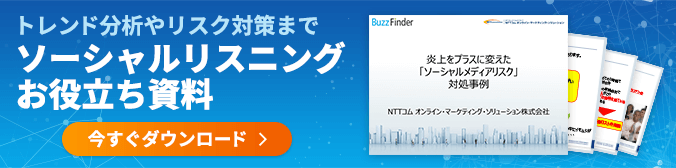更新日:2023/12/18(公開日:2021/08/02)
ソーシャルリスク対策
レピュテーションリスクの要因と対策とは|企業事例や定量化の方法も紹介
レピュテーションリスクの対策を取っておくことは、企業にとって重要なことです。十分な対策ができていないと、場合によっては企業そのものの存続が危ぶまれる可能性も出てきます。そこで、この記事では、そもそもレピュテーションリスクとは何か、風評被害との違いや起こる要因などを説明し、そのうえで対策や実際に起こったときの対処法などについて解説していきます。
- 企業のレピュテーション(評判)が低下し悪評が広がることで、損失を被るリスクをレピュテーションリスクと言う
- SNSの普及や企業価値が多様化したことなどが、レピュテーションリスクの重要性が高まった要因
- 不適切なメディアやSNSでの発信、顧客情報の漏えいなどがレピュテーションを下げる原因になる
- 関係各所にアンケートをとって企業の評判を調べるとともに、SNSなども監視して、レピュレーションリスクを避けるための対策をとりたい
レピュテーションリスクの意味とは何か?
レピュテーションリスクとはそもそも何かが理解できていないと、企業として十分な対策を打つことはできません。レピュテーションとは評判のことで、つまり、企業の評判が下がる危険性のことをレピュテーションリスクといいます。ネガティブな評判が広まってしまうと、企業イメージはまたたく間に悪化し、それによってさまざまな影響を受けることもあります。レピュテーションリスクにつながる評判とは、通常は事実に基づいた内容によるものです。ただし、中にはわずかな事実を基にネガティブな印象に情報操作されるケースも含まれます。
レピュテーションリスクの種類や導入事例についてはこちらでも解説しています。
【レピュテーションリスク】種類と実例
風評被害とはどう違う?
風評被害とは、悪質なデマや事実に基づかない不確かな情報などから企業の印象が悪くなり、それによって商品がまったく売れないなどの被害を受けることです。良くない評判によって企業がダメージを受けることはレピュテーションリスクと同じです。最悪の場合、企業そのものの存続が危ぶまれる事態にまで及ぶという点も両者で違いはありません。ただし、風評被害の場合は事実に基づいていないという点が違います。同じネガティブな評判でも、レピュテーションリスクは実際に起こった情報が基になっているもので、それだけに企業側が日々対策しやすいともいえるでしょう。
風評被害の概要や事例などについてはこちらで詳しく紹介しています。
風評被害対策とは?経済的損失を避けるための備え
オペレーショナルリスクとはどう違う?
レピュテーションリスクと似たような単語としては、オペレーショナルリスク(operational risk)があります。オペレーショナルリスクとは、企業の通常業務(オペレーション)を行う際に発生する可能性があるリスクという意味があります。不正だけではなくコンピュータシステムの誤作動、ハッキングによるトラブル、情報流出、事務の不手際など、企業の業務にまつわる全てに対するリスクのことです。レピュテーションリスクもその一種と考えて良いでしょう。
レピュテーションリスクの重要性が高まる背景
レピュテーションリスクの重要性が高まる背景として、「企業価値の多様化」「社会的・倫理的側面の要請拡大」「SNSの普及」があります。主に財務指標により判断されてきた企業価値ですが、近年は多様化し、レピュテーションという目に見えないものが影響を与えるようになりました。企業にも社会的・倫理的側面を期待する声が高まり、非財務指標であるESG(Environment=環境。Social=社会、Governance=ガバナンス)に注目が集まるようになったことが要因となっています。
また、企業価値を下げるレピュテーション・イベントが発生しやすい場として、SNSやネット掲示板があります。誰もが情報を広く発信できるようになったことで、企業の落ち度がわずかでも見られるとたちまち、悪い評判が広まり炎上するようになりました。
レピュテーションリスクにつながりやすい要因
では、レピュテーションリスクにつながりやすい要因にはどのようなものがあるか紹介していきます。
経営者や従業員など関係者の言動
レピュテーションリスクの要因となるのは、必ずしも商品やサービスなどの品質だけに限定されていません。経営者や従業員の言動がきっかけになるケースも増えています。本人は気軽に発言したことでも、聞く人によっては不快に感じることもあります。例えば、経営者の不倫問題や脱税などが発覚すれば、社会的に大きなダメージを受けるでしょう。企業の知名度が高いほど、こういったスキャンダルは噂として広がりやすくなります。このような問題だけでなく、差別的な発言や社会的に誤解を招くような言動などもレピュテーションリスクにつながります。例えば、女性蔑視と受け取れるような発言なども注意が必要です。
否定的なメディアによる情報発信
企業に対して、メディアが否定的な情報を発信することもレピュテーションリスクの要因になります。例えば、その業界としては特に非常識ではないことでも、あたかも常識を外した行動であるかのように情報を操作されてしまう場合もあります。このような場合、メディア側が専門知識を持たない状態で発信するケースも見られますが、中には故意にネガティブな情報を広めるケースもあるため注意が必要です。
ソーシャルメディアでの不適切な投稿
本人は気軽な気持ちでやったことが、大きな問題につながることも多いため注意が必要です。現代では、誰かが不快に感じればSNSで簡単に拡散できます。それに賛同する人が多ければまたたくまに広まり、いわゆる炎上することも少なくありません。例えば、コンビニのアルバイト店員がアイスクリームのショーケースに入って撮影した画像をSNSで投稿するといったこともその一例です。
他にも、顧客として訪れた有名人の免許証のコピーを銀行員が無断で持ち帰り、さらにその情報をSNSで発信するといった行動も、レピュテーションリスクの要因の一例としてあげられます。現代では、PRの一環としてソーシャルメディアを利用する企業も多いでしょう。ソーシャルメディアは、普段はわからない側面を知ることができ、親近感がわいたり好意的に感じたりするケースもあります。しかし、投稿する内容によっては多くの人に不快感を与える可能性もあり得るということです。
顧客情報の漏えい
企業にとって、顧客の個人情報が漏えいするのは大きなダメージになります。クラッキングなど第三者によるシステムの侵入だけでなく、従業員によるデータの持ち出しや紛失も顧客情報の漏えいにつながる要因です。個人情報が漏えいした場合、そこから悪用されるケースも多く、企業は信頼を損なうことになるでしょう。
景品表示法などの法令違反
原産国を偽ったり実際に使用されていない原材料を表示したりする行為は、立派な景品表示法違反です。景品表示法の法令違反が認められれば、消費者庁から措置命令を受ける他、社会的に信頼を損なうことになります。他にも、消費者を欺くような法令違反はどのような内容であっても信頼を失う原因になり得ます。
商品・サービスにおける質の低下
商品・サービスの質が低下するだけでもレピュテーションリスクにつながるケースがあります。店舗での接客対応や製品の耐久性、味の変化などでも、SNSなどで悪評が立ち、またたく間に拡散されかねません。既存の顧客に質が低下したと思われないように、店舗や商品などのリニューアルをする際には十分な注意が必要です。スタッフの入れ替わり時期も、しっかりとした研修を行って、顧客にサービスの質が低下したと評価されないようにしなければなりません。
同業他社の不祥事や業績の悪化
自社に問題がない場合でも、同業他社の不祥事や業績の悪化がレピュテーションリスクになることがあります。同業他社が不祥事を起こすことで、「同業だからこの会社も問題があるのでは?」と疑念を持たれてしまうケースが見られます。また同業他社が経営不振になることで、業界全体がリスクを抱えていると思われる場合もあります。
対策を怠ると、株価が下落したりステークホルダーからの信頼を失ったりする可能性があるので、積極的に自社の健全な体質をアピールすることが大切です。
レピュテーションリスクが企業に与える影響
続いて、レピュテーションリスクが実際にどのような影響を企業に与えるのか見ていきましょう。
信頼や売上、株価の下落
前述したように、レピュテーションリスクによって企業の信頼が損なわれます。実際にはケースによって変わってきますが、一度失った信頼を取り戻すには時間がかかります。信頼が損なわれれば、商品を購入したりサービスを利用したりする人はおのずと減少し、売り上げも伸び悩むでしょう。株価も下落しますし、最悪の場合、倒産や上場廃止という結果になるケースも出てきます。
経営層の引責辞任や従業員の解雇
どのような問題かで変わってきますが、場合によっては代表取締役など経営層が責任を取って辞任に追い込まれるかもしれません。特に、上層部の指示によるものであった場合には、引責辞任は免れないでしょう。また、経営が悪化することで従業員の整理解雇などを余儀なくされることもあります。いずれにしても、レピュテーションリスクによって従業員全体にも何らかの影響が及ぶことは確かといえます。
採用活動の悪化や人材の流出
レピュテーションリスクが発生すると、企業イメージが悪化して人材が集まりづらくなり、採用活動がうまくいかなくなるケースがあります。応募者は事前に企業研究を行い、SNSを始めとしたネットでの評判も細かくチェックしています。レピュテーションを低下させるようなイベントが発生すると、優秀な人材が確保できず、事業成長が難しくなるかもしれません。その結果、さらに人が集まらないという悪循環が起きたり、先行きに不安を感じた従業員が転職したりする可能性があります。悪い評判は一度ネット上に拡散されると、長期間その影響を受けることになるので十分に注意しましょう。
賠償金やリコール
顧客情報の漏えいなどは賠償金の対象になるのが一般的です。過去には、個人情報が漏えいしたことで対象の顧客全員に商品券を発送するなどで賠償したケースもあります。他にも、顧客にとって何らかの損害を与える結果になれば、賠償金を免れることはできないでしょう。また、商品全体に問題が見られれば、リコールとして処理しなければなりません。賠償金もリコールも、企業にとっては大きな損害につながります。
レピュテーションリスク事例
では、実際にどのようなケースがあるのか、過去に起こったレピュテーションリスクの事例を紹介します。
TOYOTAのリコール問題
北米から始まったTOYOTAのリコール問題は、世界で700万台を超えるリコールに発展しました。欠陥燃料ポンプでさらに問題が深刻となり、TOYOTAは2020年10月28日に国土交通省にリコールの届けを出しています。リコール対象となったのは、ノアやヴォクシー、クラウン、NX300など複数の車種に及んでおり、これによってTOYOTAには大きな損害が生じる結果となっています。TOYOTAは世界的に人気が高い自動車メーカーであり、日本を代表する企業の一つといっても過言ではありません。それだけに、TOYOTAの大規模なリコールは日本製品の品質そのもののイメージも問題となりました。
福島第一原子力発電所事故
2011年3月11日、東北地方太平洋沖で発生した地震が原因で、福島第一原子力発電所では大規模な原子力事故にみまわれました。地震と津波による電源の喪失に始まり、4号機の水素爆発、さらに放射能汚染と、福島第一原子力発電所事故は東日本大震災の中の大きな事故として位置付けられています。それまで、世界でもっとも大きな原子力発電所事故は、1986年4月に発生したチェルノブイリ原子力発電所によるレベル7の事故でした。福島第一原子力発電所事故も当初はレベル5だったものの、最終的にはレベル7とされ、チェルノブイリ原子力発電所に並ぶ大きな事故となっています。この事故で、東京電力は甚大な賠償金を求められる結果となり、その後も企業に大きな影響を与えています。
ATSUGIのイラスト問題
自社製品であるタイツをPRすることを目的に、ATSUGIがソーシャルメディアで発信したイラストが炎上したケースです。さまざまな女性がタイツを履いてポーズを取るイラストは、性的なイメージを受けるということから「公式アカウントとして発信するには不適切」「見識を疑う」といった意見が多く寄せられました。この広告の担当者は女性でしたが、男性を意識したイラストという印象を与えたことで、同性である女性から辛辣な意見を受ける結果となっています。イラスト自体は決して評判が悪いわけではありませんでしたが、公式アカウントであったことが炎上につながった要因となっています。
レピュテーションリスクを定量化する方法
現在、自社がどの程度レピュテーションリスクを抱えているか分かるように、レピュテーションリスクを定量化する2つの方法を解説します。
報道調査の結果を調べる
報道調査による定量化は、メディアに度々名前が出るような企業向けの方法です。具体的には、「入社したい企業ランキング」のような毎年実施されている調査を確認します。過去も含む報道を調査することで、自社のレピュテーションが見えてきます。
SNSや掲示板を確認することも重要です。SNSや掲示板は同じ意見に流されやすい傾向があるので、X(旧Twitter)、Facebookなど複数のSNSや掲示板でチェックしてください。検索エンジンで自社を検索するのも有効です。現在、自社とどのような事柄がひもづかれて検索されているかが分かります。そして、ネガティブな評判の原因を分析し、改善策を出すことが重要です。
アンケート調査を実施する
アンケート調査はステークホルダーに向けて行うため、中小企業などでも有効な方法です。顧客や従業員、株主などのステークホルダーにアンケートをとり、評判やイメージなどを調査します。顧客からの具体的な意見は、レピュレーションリスクを知る上で重要です。アンケートは本音を書きやすいように匿名にします。アンケートの設問内容は、自社における課題の仮説を立てておき、関連する内容を準備するようにしてください。また、インタビュー形式で調査する方法も効果的です。
レピュテーションリスク対策と起こったときの対処
普段から心がけておきたいレピュテーションリスク対策や起ってしまったときの対処について解説していきます。
企業側の情報発信に注意をはらう
商品やサービスのPRはもちろん、企業側が発信する情報には普段から注意をはらうことです。特に、ソーシャルメディアを使っての発信には十分注意した方がいいでしょう。単なる広告であっても、表現内容によっては不快に感じる人もいます。たとえ個人的な意見でも、その内容が常識に欠けるものであったり一定の層を誹謗するものだったりすると企業全体のイメージを損ないかねません。商品の広告から気軽に発信可能なソーシャルメディアまで、企業が発信する情報は十分注意することが大切です。もしも、不適切な内容を発信したときはすぐに謝罪し、適切な対応を心がけましょう。
品質と評判の落差を避ける
商品の品質と評判の落差が大きいことも、レピュテーションリスクにつながります。例えば、社運をかけた一大プロジェクトでも、一般消費者からあまり良い評価を受けないこともあります。その事実を受け入れることができずに自社製品の素晴らしさだけを強調していては、顧客の賛同を得ることはできません。最後には信頼を損なう危険も出てきます。時間と資金をかけて開発した商品でも、消費者のニーズに合っていないなら素直に意見を取り入れることは大切です。品質と評判が見合った製品を提供する真摯な態度がレピュテーションリスク対策につながります。
リスクマネジメントの徹底
リスクマネジメントとは、企業の損失を回避するために組織的に管理を行うことです。万が一レピュテーションリスクにつながる事態が発生した際、できるだけ損害を最小限にとどめなければなりません。そのためにどのような措置を取るべきか普段から組織的に考え、準備しておく必要があります。例えば、賠償を求められたときの資金をどうするかといった問題などもリスクマネジメントに含まれます。いざ何らかの問題が起こったとき、事実確認や謝罪、問題の改善と報告など、一連の流れをケースごとに決めておくといいでしょう。
レピュテーションマネジメントに注力する
レピュテーションリスクを回避するだけではなく、問題が起きた際の的確な対応や、より良いレピュテーションを手に入れるマネジメントにも注力しましょう。レピュテーションマネジメントは、レピュテーションを向上させる施策と回復させる施策に分かれます。向上させるための施策には、ブランドイメージの浸透を目的とした発信や、SNSでの能動的なコミュニケーションなどがあります。
回復させるための施策には、問題発生時の社内マニュアルの整備や炎上事例の共有などがあります。レピュテーションマネジメントの対象となる人は、企業に関わるすべてのステークホルダーです。たとえば、社員やアルバイト、取引先、株主、そして消費者などが挙げられます。いずれも企業と利害関係にあり、レピュテーションに大きく関わる関係者です。それぞれの立場にあったマネジメントを行い、レピュテーションを高めるようにしましょう。
企業の評判を落とす可能性があるSNSの炎上について詳しく紹介しています。
SNSにおける企業の炎上事例7選|炎上の対処法・事前対策を紹介
企業コンプライアンスを徹底する
コンプライアンスとは法令を遵守するという意味で使われますが、企業においては社会的な常識や倫理なども対象となります。景品表示法の遵守などはもちろんですが、情報発信なども企業コンプライアンスを徹底しておくことが求められます。特に企業規模が大きくなるほど、すべての従業員のモラルをまとめるのは難しいものです。しかし、1人の従業員が気軽に発信した内容で、企業が窮地に立たされることも珍しくはありません。また、顧客への対応なども企業全体の評判として拡散されることもあります。アルバイトであっても企業の一員であるという自覚を持ってもらうと同時に、企業として守るべき法令や社会常識について明確にすることが必要です。
ソーシャルリスニングツールでネット情報を常に監視する
企業としては問題なく業務を遂行していても、悪意のある情報を拡散されることもあります。また、1人の従業員によって思わぬ情報を拡散されることもあるでしょう。知らないうちに情報が広まり、取り返しのつかないことにならないよう、常にネット情報を監視しておくことが重要です。情報はできるだけ早い段階で察知し、事実確認や対象となる情報の削除などスピーディーな対処が求められます。
そこで便利なのが、ソーシャルリスニングツールです。ソーシャルリスニングツールはソーシャルメディアを監視するツールで、自社のマーケティングやレピュテーションリスクへの対応に活用できます。膨大なSNS上の情報をリアルタイムで収集・分析し、炎上が起こった場合には素早くアラートを送信してくれます。アラートを受け取ることで迅速な対応が可能となり、炎上を最小限に食い止められるでしょう。また、炎上とまではいかなくても、自社や自社製品に関するユーザーの発信を分析し、トラブルを未然に防ぐことも可能です。
レピュテーションリスクの対策には「Buzz Finder」
「Buzz Finder」は、レピュテーションリスクをいち早く察知し、企業のブランドセーフティを強固にするソーシャルリスニングツールです。X (旧Twitter)の公式全量の投稿をほぼリアルタイムで収集し、瞬時に分析・通知できます。
また、複数のメディア投稿を分析できるため、ネット炎上への迅速な対応ができます。日報やアラート機能があることで、迅速にレピュテーションリスクを察知し、被害を最小限に食い止めることが可能です。さらに、前日のポスト(ツイート)量や、話題の内容はデイリートピックメールとしてお届けするので、効率的に状況を把握できます。自社のレピュテーションリスクを抑えるため有効なソーシャルリスニングツールです。
ソーシャルリスニングで適切なレピュテーションリスク対策を
レピュテーションリスクは、いつどのように起こるかわかりません。企業が注意できる部分もありますが、すべてを管理するのはなかなか難しいものです。特に、ネット情報の管理や監視などは専門部署を置かないと対処できないことも出てきます。そのようなときはプロの力を借りることも必要です。炎上などを素早く検知し、早期対策が可能なソーシャルリスニングで、適切なレピュテーションリスク対策を取っておきましょう。
ソーシャルリスニングツールの「Buzz Finder」は、業界最速水準でXの公式全量データから、最新の投稿をリアルタイムで収集します。気になる方はこちらをご覧ください。
Buzz Finder
関連記事

2022/01/07

2021/10/11