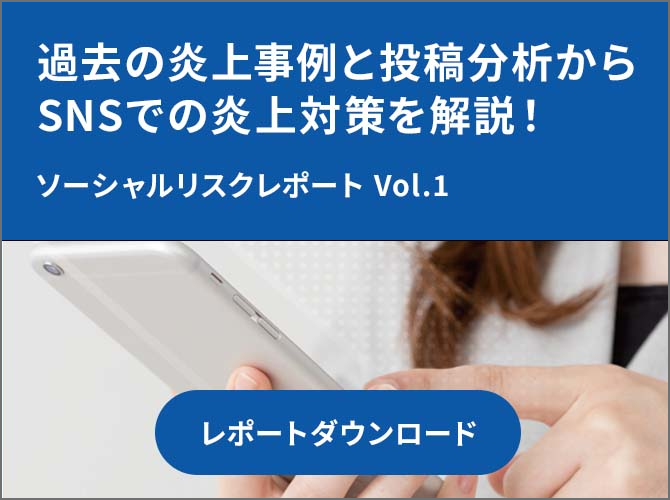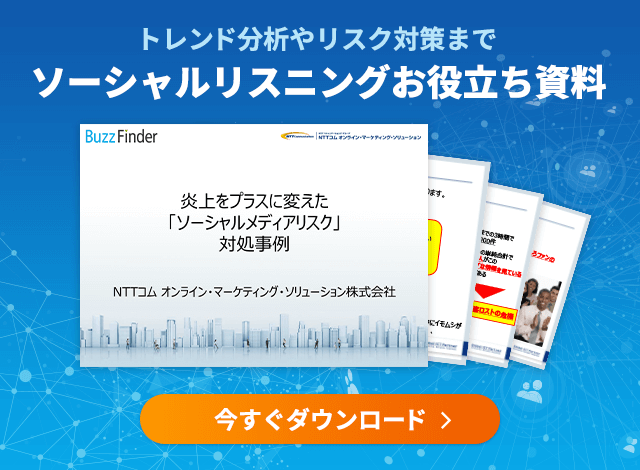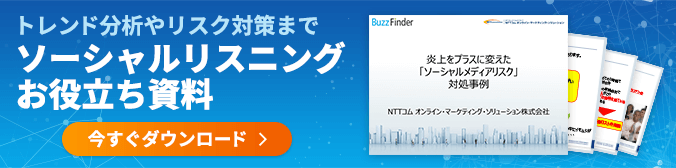2025/09/10
ソーシャルリスク対策
アクティブサポートとは?導入するメリット・手順・成功ポイントを解説
企業が自らユーザーのもつ不満や要望、意見などを見つけて対応するカスタマーサポートをアクティブサポートと呼びます。SNSの普及により、企業の顧客対応も大きく変わりました。今後、企業がユーザーの行動変化や炎上リスクに対応するためには、アクティブサポートが重要です。
本記事では、企業がアクティブサポートを導入するメリットや手順、成功のポイントなどを解説します。自社でもアクティブサポートをはじめたいとお考えの場合は、ぜひ参考にしてみてください。
- アクティブサポートとは、企業が能動的に顧客の不満や意見、要望などを探して、問い合わせを待たずに対応するカスタマーサポートの手法
- SNSの普及による顧客の声の可視化や購買行動の変化、炎上リスクなどから、近年ではアクティブサポートへの注目が高まっている
- アクティブサポートを導入すると、ユーザーの本音を把握でき、顧客満足度の向上や新規顧客の獲得、離反低下、炎上防止などのメリットがある
- アクティブサポートを成功させるには、丁寧なレスポンスや迅速な対応、顧客ニーズに合わせた柔軟性、有益情報の発信、ソーシャルリスニングなどがポイントになる
アクティブサポートとは?
アクティブサポートとは、企業がユーザーの悩みや不安、意見、要望などを見つけ出し、問い合わせを待たずに能動的に顧客の支援を行うカスタマーサポートの方法です。企業側が顧客に対して積極的なサポートを行うため、ユーザーの不満が問い合わせやクレームの形で顕在化する前に問題をケアでき、炎上や顧客離れなどを防止できます。
アクティブサポートは、SNSなどで個人の不満が表面化しやすい現代に求められるユーザーサポートといえるでしょう。
従来のカスタマーサポートとの違い
アクティブサポートと従来のカスタマーサポートの違いは、企業側から顧客の問題を見つけるために行動していく積極性です。従来のカスタマーサポートでは、ユーザーからの電話やメールなどへの受動的な問い合わせ対応が中心でした。
しかし、受け身のサポート体制には、ユーザーの意見やクレームへの反応が遅れてしまったり、迅速な対応ができないためニーズを逃してしまったりするなどの問題があります。アクティブサポートであれば、SNS上の投稿などから消費者の見えないニーズを先読みした対応が可能です。
アクティブサポートが注目される理由
近年、アクティブサポートが注目されるようになった大きな理由がSNSの普及によって顧客の声が可視化された点です。企業は問い合わせを待たなくても、ユーザーの生の声を見られるようになりました。
また、デジタル化により顧客の購買行動に変化が起き、口コミやレビューが購入決定に大きく影響するようになったのも理由の一つです。ほかにも、炎上リスクの早期検知や潜在顧客の発見など、アクティブサポートは企業にとって多くの利点があります。
SNS環境の変化により、従来型のコールセンターだけでは対応しきれない多様な顧客接点が生まれ、企業側にも新たなサポート手法が求められるようになり、アクティブサポートが注目されるようになりました。
アクティブサポートのメリット
アクティブサポートの主なメリットは、以下の通りです。
- 顧客の本音を把握できる
- 新規顧客獲得につながる
- 満足度向上・顧客離反の低下につながる
- 炎上防止につながる
それぞれのメリットを詳しく解説します。
顧客の本音を把握できる
1つ目のメリットは、顧客の本音を把握できる点です。SNS上の投稿には顧客の率直な感想や本音が現れやすいため、従来のアンケート調査やインタビューなどでは得られなかったユーザーの生の声を収集できます。また、カスタマーサポートに直接連絡してこない「サイレントクレーマー」の不満や要望も把握可能です。
すべての顧客が本音で意見を言ってくるとは限らないため、問い合わせを待つだけだと不満を見逃してしまい、大きな問題に発展する恐れもあります。顧客が企業に配慮して伝えない、本当の課題や改善点なども把握でき、商品・サービスの開発や改善に活かせるのはアクティブサポートの大きなメリットです。また、競合他社に対する顧客の評価も同時に収集できるため、市場における自社の客観的な位置づけも把握できます。
サイレントクレーマーについて詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
サイレントクレーマーのリスクや日本人の割合・対策方法を解説 - ソーシャルリスニングサービス
新規顧客獲得につながる
2つ目のメリットは、新規顧客の獲得に効果的な点です。企業がSNS上で良質なサポート対応を行うと、多くの人に見られるため、潜在顧客に対する間接的なマーケティング効果が期待できるでしょう。顧客の問題解決をサポートすると、ほかのユーザーにも好印象を与えてポジティブな口コミ拡散につながり、新規顧客獲得に寄与します。
また、企業の人間的な魅力や親しみやすさをアピールできるため、ブランドの差別化要因として機能する可能性もあるでしょう。
満足度向上・顧客離反の低下につながる
3つ目のメリットは、顧客満足度の向上と顧客離れの低下です。アクティブサポートなら、顧客が困っているタイミングで企業側から積極的なサポートを提供できるため、高い顧客満足度が実現できます。問い合わせ後の対応と異なり、問題の早期発見と迅速な解決ができ、顧客が不満を蓄積する前に対処ができます。
SQMグループが実施した調査では、FCR(初回通話解決率)が1%向上すると顧客満足度も1%向上するとの結果が出ました。顧客は問題の早期解決を望んでおり、達成されると企業に良い印象を抱くのがわかります。
出典:SQM Group, Inc.「First Call Resolution (FCR): A Comprehensive Guide」
アクティブサポートでは、企業が顧客を気にかけていることが伝わり、顧客との深い信頼関係の構築が可能です。また、個別対応による特別感も提供できるため、顧客ロイヤリティを向上させるとともに、競合他社への流出を防げる顧客離反の防止も期待できるでしょう。
炎上防止につながる
4つ目のメリットは、SNSなどでの炎上防止です。SNS上でのネガティブな投稿を早期に発見できれば、大規模な炎上に発展する前に適切な対応がとれるため、企業に対するダメージが大きくなる前に問題を解決しやすくなります。
現代の企業にとってSNSの炎上は、自社商品・サービスへの大きなリスクです。一度拡散したマイナス評価を収束させるのは困難になるものの、初期段階で対応できれば被害を最小限に抑えられます。風評被害やレピュテーションリスク(ネガティブな評価による企業・ブランド価値の低下リスク)の回避にもつながり、企業価値の保護と向上に貢献できるのもメリットです。さらに、迅速かつ誠実な対応に成功すれば、批判的な顧客を企業支持者に転換できる可能性もあります。
SNS上での企業の炎上事例と対策について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
SNSにおける企業の炎上事例9選|炎上の対処法・事前対策を紹介
アクティブサポート導入前の準備
企業がアクティブサポートを導入する際には、主に以下のような準備が必要です。
- 社内横断の運用体制を構築する
- 対応チャネル・対応範囲を事前に選定する
- ソーシャルリスニングを行う担当者を選定する
各準備作業を詳しく解説します。
社内横断の運用体制を構築する
アクティブサポートを導入する際は、顧客対応部門だけでなく、営業・マーケティング・開発・経営陣まで巻き込んだ全社的な取り組みが必要です。
アクティブサポートの内容は、単なる商品・サービスへの意見や問い合わせだけではないため、対応には顧客対応部門以外の協力も必要です。収集した顧客の声を関連部署に伝達できる情報共有の仕組みと、商品・サービスの改善を実行できる社内横断の運用体制を構築しましょう。各部門の役割分担として、カスタマーサポート部門は日常的な対応、開発部門は技術的な課題解決、マーケティング部門は情報発信戦略の策定などを担当します。責任者と意思決定権限を明確化するとともに、迅速な判断と対応を可能にする運用体制を整備するのが重要です。
対応チャネル・対応範囲を事前に選定する
アクティブサポートを開始する前に、対応するSNSやユーザー層などの範囲を明確にしておきましょう。SNSの利用者や投稿は膨大で、すべてをカバーするのは現実的に不可能です。企業のリソースと顧客層に応じて、監視・対応するのに最適なSNSプラットフォームを選定します。
X(旧Twitter)、Instagram、Facebook、YouTubeなどの主要SNSでも、ユーザーや投稿の傾向には違いがあるため、それぞれの特徴と顧客層を考慮して優先順位を決めてください。また、サポートの範囲として、質問回答、技術サポート、クレーム対応、顧客に対する感謝の返信など、どこまで対応するのか境界線を明確化するのも大切です。
ソーシャルリスニングを行う担当者を選定する
アクティブサポートの運用にあたっては、SNS上の情報を収集・分析する担当者を選定しましょう。アクティブサポート担当者に必要なスキルとして、コミュニケーション能力、商品知識、SNSリテラシー、クライシス(危機)対応力などがあげられます。
現在の社内に対応できる人材がいなければ、新たに育成が必要です。担当者向けの教育プログラムとしては、企業理念・方針の理解から商品・サービス知識の習得、SNSマナーとリスク管理などの研修を実施します。また、担当者は個人に任せるのではなく、複数名でのチーム体制を構築して、対応品質の均一化と業務継続性を確保することも重要です。
ソーシャルリスニングについて、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
ソーシャルリスニングとは|意味や分析方法の解説と導入事例を紹介!
アクティブサポートを導入する手順
アクティブサポートを導入する際の手順を以下の4ステップで解説します。
- SNSの公式アカウントを作成する
- キーワードを決めてソーシャルリスニングを実施する
- ユーザーの投稿にリアクションをする
- 投稿・やり取りのデータを管理・分析する
1|SNSの公式アカウントを作成する
はじめに、発信を行うためのSNS公式アカウントを作成します。企業のオフィシャルアカウントだと明確にするため、アカウント名、プロフィール、認証マークの取得などを適切に設定することが重要です。
企業アカウントはブランディングの1つでもあるため、ブランドイメージに一致したプロフィール画像やヘッダー画像、紹介文を作成して統一感のあるアカウント設計にしましょう。また、プライバシー設定、通知設定、セキュリティ設定を適切に設定しておくと、運用上のリスクを軽減できます。すでに別の企業アカウントがある場合は、アクティブサポート専用アカウントとの役割分担を明確化するのも大切です。
2|キーワードを決めてソーシャルリスニングを実施する
アカウントを作成したら、実際にソーシャルリスニングをはじめていきます。データの収集方法にはいくつかの手法がありますが、はじめはメディアの検索機能を使用しましょう。
自社ブランド名や商品名、サービス名などを基本キーワードとして設定して、関連語や類義語も含めて検索範囲を広げていきます。「困った」「使えない」「故障」「壊れた」など、ネガティブな表現や問題を示すキーワードを組み合わせて設定すると問題を見つけやすくなるはずです。
競合他社との比較や業界全体のトレンドを把握するため、それらに関連するキーワードを監視対象に含める必要もあります。設定したキーワードは定期的に見直しを行い、新商品や時事に応じて監視対象を更新すると良いでしょう。
3|ユーザーの投稿にリアクションをする
気になる投稿を発見した場合は、企業アカウントを使ってリアクションを行います。返信時には、顧客の投稿内容を正確に理解するとともに、適切なタイミングで丁寧にリアクションするのが大切です。炎上リスクを避けるため、公開された場でのやり取りであるのを意識して、ほかの顧客から見ても好印象をもってもらえる対応を心がけましょう。
SNS上でのリアクションには返信のほかに、「いいね」機能やXのリポストなど、さまざまな方法があるため、状況に合った対応を選択する必要があります。また、やり取りのなかに個人情報や機密情報が含まれる場合は、DMや電話などのプライベートな手段に誘導しましょう。
4|投稿・やり取りのデータを管理・分析する
SNSでの顧客とのやり取りの履歴は体系的に記録しておき、継続的な関係性の管理と改善に活用します。SNS上でのやり取りはテンプレート化が難しいものの、ある程度は可能です。収集したデータを分析により傾向やパターンを把握して、よくある問題の予防策や対応品質向上に役立てられます。アクティブサポートを継続運用していけば、よりよい対応ができるデータが集まっていくはずです。
情報の収集・分析にあたっては、個人情報保護法やプライバシーポリシーに準拠したデータ管理体制を構築する必要があります。個人情報の保護などは通常の顧客対応と同等と考え、情報漏えいなどが起きないようにしましょう。
アクティブサポート成功のポイント
アクティブサポートを成功させるポイントは、以下の通りです。
- 迅速かつ丁寧なレスポンス対応を行う
- 顧客ニーズに合わせた柔軟な対応を行う
- 対応マニュアルも作成しておく
- SNS上で有益な情報を積極的に発信する
- 顧客の声を社内で共有しサービス改善に活かす
- ソーシャルリスニングツールを活用する
各ポイントを詳しく解説します。
迅速かつ丁寧なレスポンスを行う
1つ目のポイントは、迅速かつ丁寧なレスポンスです。SNS上では情報の拡散スピードがリアルよりも速いため、問題の投稿を発見したら可能な限り迅速に初回対応を行う必要があります。時間をかけているとアクティブサポートのメリットである顧客満足度の向上や炎上防止などの効果が得られません。
即座に解決策を提示できない場合でも「確認中です」「調査しています」などの中間報告を送って、顧客の不安を軽減するようにしましょう。また、感情的な投稿に対しても冷静かつ建設的な対応を維持してください。感情的に返信するのではなく、顧客の気持ちに共感を示しながら解決に向けてコミュニケーションをとっていきましょう。
顧客ニーズに合わせた柔軟な対応を行う
2つ目のポイントは、顧客のニーズに応じた柔軟な対応です。アクティブサポートでは、画一的な対応ではなく、顧客の状況や感情、緊急度などを考慮して1人ひとりへの対応方法を調整する必要があります。
技術的な問題への回答なら詳細な解決手順を提示する、感情的な不満に対しては共感と謝罪を示すなど、内容に応じてうまく対応を使い分けることが重要です。説明の際も相手の知識レベルに合わせて内容の詳細さを調整したり、分かりやすい言葉で情報提供したりするのを心がけましょう。顧客からの要望が社内の規則と矛盾する場合は、可能な範囲での代替案を提案するなども検討してください。
対応マニュアルも作成しておく
3つ目のポイントは、対応マニュアルの作成です。アクティブサポートで画一的な対応は避けるべきではあるものの、対応の方向性や注意点などを示すマニュアルは作成しておくと、より安定したサポートを提供できます。
顧客からの意見や要望にも一定の傾向をもつ場合が多いため、よくある質問と回答例をまとめたFAQマニュアルを作成しておけば、対応品質の均一化と効率化が可能です。炎上やクレーム対応の手順も明文化して、担当者が迷わず適切な対応を取れるようにすると良いでしょう。また、NGワードや避けるべき表現をリスト化して、炎上リスクを最小化するガイドラインも設定します。
実際の顧客対応では、投稿内容のポジティブ・ネガティブによって対応を使い分けるのも重要です。
ポジティブ投稿への返答例
弊社の製品をご利用いただき、ありがとうございます。
○○様に気に入っていただいた部分は、お客様からの意見を参考に、社内でこだわりをもって開発しました。
これからも末永くご愛用ください。
ネガティブ投稿への返答例
このたびは、弊社製品についてご不快な思いをさせてしまい、たいへん申し訳ございません。
可能であれば、私どもで対応させていただきたいと思っております。
詳細をお伺いしたいため、DMにて注文番号をお知らせいただけますでしょうか。
お手数おかけして申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
SNS上での企業の炎上原因と対策について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
炎上対策とは?企業における主な炎上原因と対策 - ソーシャルリスニングサービス|NTTコム オンライン
SNS上で有益な情報を積極的に発信する
4つ目のポイントは、SNS上での有益情報の発信です。アクティブサポートに必要なのは、顧客との直接的なやり取りだけではありません。商品の使い方やメンテナンス方法、トラブルシューティングなど役立つ情報を定期的に発信するのも重要です。情報発信により、意見や要望を投稿しないユーザーとも接点をもてます。
特に季節やイベントに応じたタイムリーな情報提供は、顧客との接点を増やし、関係性を深めるのに有効です。ほかにも、よくある質問や問題の予防策を事前に情報発信すると、同様の問い合わせの削減や顧客満足度の向上につながります。
顧客の声を社内で共有しサービス改善に活かす
5つ目は、顧客の声の社内共有とサービス改善への利用です。収集した顧客の意見や要望は関連部署に定期的に報告して、商品・サービスの改善に活用できる仕組みを構築しましょう。頻繁に発生する問題や要望をデータ化して分析するとともに、根本的な解決策や新機能開発の判断材料にすると効果的です。
さらに、顧客の声を基にした改善実績を社内で共有すれば、アクティブサポートの価値と重要性を組織全体に浸透させることにも役立ちます。営業部門やマーケティング部門とも連携して、ユーザーの意見を営業戦略や販促活動に反映させれば大きな成果につながるでしょう。
ソーシャルリスニングツールを活用する
6つ目のポイントは、ソーシャルリスニングツールの活用です。手動によるSNS監視には、収集できる情報量、精度共に限界があります。ソーシャルリスニングツールを導入すれば、効率的な情報収集が実現できるでしょう。
また、トレンド分析や感情分析などのデータ分析機能により、顧客の声の傾向やパターンを把握して、戦略的な改善施策の立案も可能です。
マッキンゼーの調査レポートによると、「ソーシャルリスニングに優れた企業は、競合他社と比較した場合に顧客満足度が17%高くなる」との結果が出ているようです。より良いソーシャルリスニングの重要性を示すデータといえるでしょう。
出典:palowise「21 Key Social Listening Statistics Every Marketer Should Know」
ソーシャルリスニングツールの選び方について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
ソーシャルリスニングツールの選び方とは?比較のポイントを詳しく解説
アクティブサポートを導入した企業の事例
アクティブサポートを導入した、以下の2つの企業の事例を紹介します。
- NTTドコモ公式サポート
- Amazon Help
それぞれの事例の詳細や成功のポイントをみていきましょう。
NTTドコモ公式サポート
NTTドコモ公式サポートでは、Xを利用して、製品やサービス、キャンペーンの内容紹介や注意事項、よくある質問などを紹介するアクティブサポートを実施しています。
基本的には、公式情報の発信が中心で、ユーザー個人のアカウントとの直接のやり取りはあまりありません。携帯キャリアとして、顧客の利用数も多いと想定されるSNS上での有益情報の発信を優先しているアカウントです。しかし、イベントやトラブルなどのタイムリーなニュース、バッテリーやWi-Fi、災害時の伝言板サービス情報、海外の方向けの英語投稿など、多様な顧客にとって有益なサポートを提供しています。
Amazon Help
世界的にECサイトビジネスを手がけるAmazonは、X上にカスタマーサポートの専用アカウントを開設しました。グローバル企業のAmazonでは、サポートアカウントも英語はもちろん、日本語やフランス語など7言語に対応しています。
アクティブサポート用のアカウントとして、ユーザーからの問い合わせなどに回答しており、直接のリプライや「#Amazon」を付けた投稿以外でも自社に関する投稿には積極的に返信しているのが特徴です。たとえば、配送についての不満を投稿したユーザーに謝罪とサポートの案内を行うなど、能動的かつ非常に丁寧な対応をしています。
アクティブサポートの効率化に寄与する「Buzz Finder」
「Buzz Finder」は、企業のリスク・炎上対策・VOC分析に効果的なソーシャルリスニングツールです。
コストを抑えながら導入でき、以下のようにさまざまな機能が利用できます。
- X公式全量データを業界最速の水準でリアルタイム収集
- 日報や投稿急増時のアラートメールを自動通知
- Xのほかにも、ニュースサイトや掲示板、Facebook、Instagramなど多様なメディアに対応
- キーワード収集時のノイズ除去による情報収集の最適化
- 専門コンサルタントによる分析サポートも実施
アクティブサポートに必要な情報を迅速に収集でき、対応が必要な問い合わせを発見したり、炎上を防止したりする際に役立ちます。また、トレンド分析やポジネガ分析など各種分析機能も備えており、集めたデータをマーケティングにも活用可能です。
続いては、実際に「Buzz Finder」を導入した企業様の事例を紹介します。
導入事例|情報通信サービス業 様
ある情報通信サービス企業様では、SNS上にある顧客の声を自社サービスの改善に活かしたいと考え、「Buzz Finder」を導入しました。関係社員や幹部などとSNSの顧客の意見を共有し、全社的な改善意識の向上に成功しています。また、お客様センターでも、平時からSNS上の投稿を日報で把握するようにした結果、各種問い合わせへの対応力が高まりました。
導入事例:情報通信サービス業 様
アクティブサポートは顧客からの信頼を得る効果的な施策
企業側が積極的に顧客の意見や不満、要望などを見つけ、問い合わせを受ける前から対応するアクティブサポートは、顧客の本音を把握して信頼を高め、満足度の向上や新規顧客の獲得、炎上防止などにつながるメリットがあります。
アクティブサポートをはじめる際にはSNS上でのソーシャルリスニングが重要ですが、導入時の運用フローや体制構築などで戸惑うケースがあります。
自社でもアクティブサポートを取り入れたいと検討されている企業様は、ソーシャルリスニングの効率化・高精度化に役立つ「Buzz Finder」の導入をぜひご検討ください。
以下のリンクから「Buzz Finder」の資料請求やソーシャルリスクに関するサポートのダウンロードが可能です。ぜひご利用ください。
事例レポートダウンロード - ソーシャルリスニング
関連記事

2022/01/07

2021/10/11