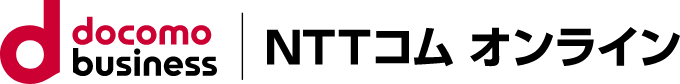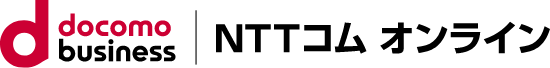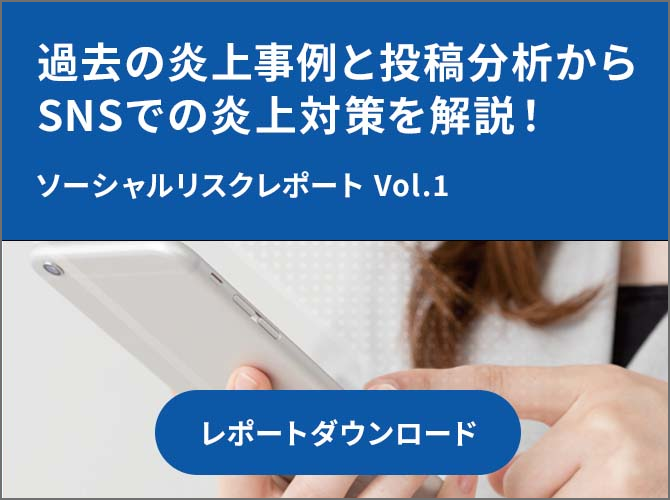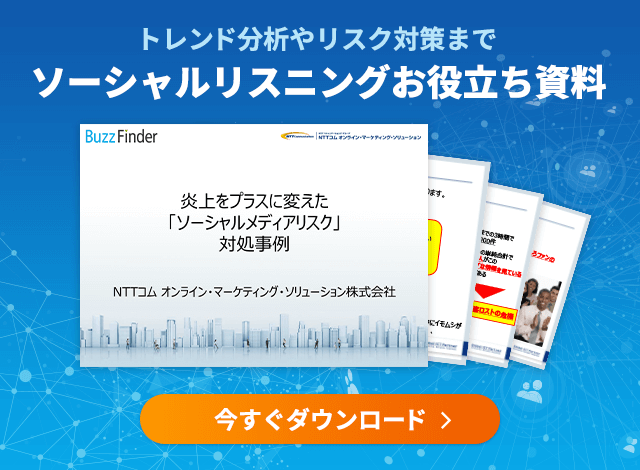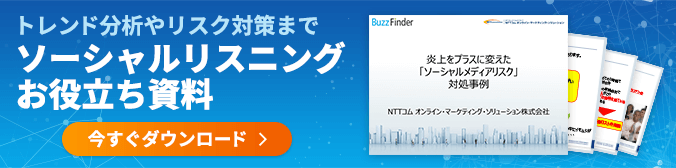更新日:2023/10/24(公開日:2021/08/24)
ソーシャルリスク対策
炎上対策とは?企業における主な炎上原因と対策
自社のソーシャルメディアの運用担当者は、投稿により予期せぬユーザーの反応に驚いたり困ったりしたこともあるのではないでしょうか。何が原因で、いつ、ソーシャルメディアが炎上するかは、完璧な予想が難しいものです。そのため、日頃の炎上未然防止対策が重要です。今回は、炎上する原因と対策について詳しく紹介します。
- 企業アカウントが炎上する主な原因は「企業側の不祥事」「内部告発」「プロモーションや失言」の3つ
- 企業の炎上対策はさまざまだが、特に「ソーシャルリスニングの活用」は効果が大きい
- もし企業に炎上が起こった場合、原因や状況を把握したうえで、メディアや投稿に対処することが大切
企業アカウントが炎上する3つの主な原因と事例
企業のSNSアカウントが炎上する原因をあらかじめ知っておくことが、炎上対策につながります。まずは原因から見ていきます。
原因1:企業側の不祥事
炎上する原因となりやすいのが、企業側の不祥事です。企業側の不祥事とは、情報漏洩や異物混入などが挙げられます。一度投稿されたクレームは、フォロワーだけでなくフォロワー外の閲覧者にも拡散され、炎上してしまいます。投稿時に、企業を炎上させる意図がなかったとしても、第三者がスクリーンショットを撮って拡散、炎上ということにもなりかねません。
企業側の不祥事の炎上事例
某自治体の協力企業において、個人情報が入ったUSBメモリを紛失した結果、情報漏洩が発生しました。企業のずさんな管理体制に加えて、自治体側が会見でパスワードの桁数を開示するというセキュリティ意識の低さに対し、多くの批判が集まっています。
また、某ECサイトの運営企業では、ユーザーから「クレジットカードの不正利用が発生している」という指摘がありました。しかし、トラブル発生から約半年後に情報漏洩を公表したので、対応の遅さが原因で炎上しています。
原因2:内部告発
社員や関係者が内部告発をして炎上を引き起こすケースも考えられます。企業に不満を抱えて退職していった元社員による告発が多い傾向です。この場合、炎上自体を目的として書き込まれている場合もあり、投稿者に対して閲覧者が同情しやすい内容となっています。企業がどのような対応をするかによって、不買運動につながるリスクもあるため、要注意です。
内部告発の炎上事例
某食品メーカーの公式YouTubeチャンネルでは、障がい者雇用に取り組むレストランの取材を実施しました。しかし、動画制作の担当スタッフが「企業から障がい者に関する差別的な指示があった」と告発しています。指示内容は以下の通りです。
- 障がいを持つ従業員のインタビューはカットして欲しい
- 障がい者と健常者が働いていることを伝えると、かえって区別してしまうので、普通のレストランとして紹介して欲しい
告発を見たユーザーからは「企業側の指示が不適切」「スタッフが指示内容を明かすことは契約違反では?」など、双方に対する批判が見受けられます。
原因3:プロモーションや失言
企業によるプロモーションや発言の失敗も、炎上の原因となるケースがあります。読み手がどのような捉え方をするかを予測できず、独りよがりな内容になっていると、炎上しやすいといえます。
このような、企業の評判が下がる危険性のことをレピュテーションリスクと呼び、企業全体で対策に取り組む必要があります。
(関連記事:レピュテーションリスクの要因と対策)
プロモーションや失言の炎上事例
某飲料メーカーはPR動画では、草原でインコを鳥かごから放つシーンを描きましたが、動画視聴者から「放鳥に向かないインコを屋外に放つことは不適切」という指摘が相次ぎ、動画の修正および謝罪に発展しています。
また、女性向けファッション誌の企業アカウントが公開したPR動画では、他社の有名な人形とドールハウスを燃やすシーンを描き、多くの批判を集めています。企業側はアカウント上で謝罪文を掲載したものの、24時間経過で自動的に削除される投稿だったので、さらなる炎上騒ぎを招きました。
SNSにおける企業の炎上事例7選|炎上の対処法・事前対策を紹介
https://www.nttcoms.com/service/social/column/20230213/
炎上を防ぐ7つの対策
情報発信に関する炎上対策を紹介します。
1|ソーシャルメディアポリシーを策定する
ソーシャルメディアポリシーとは、企業がソーシャルメディアを利用するにあたり、遵守すべきルールを定めた規約です。個人のSNS利用における姿勢を定義したものですが、企業アカウントを使って業務に取り組むケースだけではなく、従業員が私的なSNSを利用するケースも対象に含まれます。
「社内の機密情報を発信しない」「社内の写真を無断で掲載しない」など、ポリシーの具体例を提示すると、従業員にも伝わりやすくなります。
2|炎上リスクに関する研修を実施する
ソーシャルメディアの炎上を自分事として捉えてもらうためには、従業員への教育も欠かせません。SNSの影響力やルール・ポリシーの必要性、炎上発生による損失の大きさなどを伝えることにより、炎上リスクを抑制できます。
主な教育方法は研修ですが、新入社員だけではなく全従業員に対して実施する必要があります。炎上対策に関するディスカッションを行ったり、ヒヤリハットを集めて共有したりするなど、従業員の部署やポジションに合わせて研修内容を検討しましょう。
3|情報の発信基準を社内で決めておく
情報発信の基準を設定しておくことも重要です。基準としては、不確かな情報に関する発信は控える、政治・宗教などデリケートな話題には触れないなどが挙げられます。時事問題も拡散されやすく、読み手によっては賛否両論となり、避けた方がよい話題です。事実・根拠がはっきりしている情報に絞って発信することで、企業としての信頼に繋がります。このような基準が設定されていれば、基本的な炎上リスクは低減できるでしょう。
4|情報の発信内容は複数人で確認
発信しようとしている1つの情報を、複数の目で見ることで、リスクを回避します。この情報の受け手はどのような感想を持つのかということを常に意識し、発信するか、発信する場合どのような表現にするかを判断します。
5|発信した情報の反応を監視する
インターネット上にある自社の情報、ユーザーの反応を監視することで、炎上の原因となるつぶやきやコメントなどを見つけ、速やかに対処することができます。
6|炎上の事例や直近の傾向を収集する
企業の炎上と一口にいっても、さまざまなパターンがあります。そのため、実際に起こった炎上事例を収集したうえで、定期的に従業員へ共有することも大切です。炎上に関するリアルな情報を提供すれば、炎上防止への意識を維持・向上させることができます。
また、これまで特に問題にならなかった表現や発言が、時代や国際情勢の変化によって炎上を引き起こす可能性もあります。炎上事例の収集と併せて直近の傾向も分析しておけば、事前に対策できるでしょう。
7|ソーシャルリスニングを活用する
ソーシャルリスニングは、ユーザーの声を収集し分析することです。ユーザーの声はSNSから収集できるため、消費者の本音に限りなく近いデータを分析することができます。口コミや評判だけでなく、消費者のニーズやブランドイメージ、広告施策の方向性、炎上や風評被害など多様な視点からのデータが集まるのです。そのため、自社や市場の現状把握や将来予測に幅広く活用されています。
(関連記事:ソーシャルリスニングとは?その仕組みやメリットなどを解説)
ソーシャルリスニングによる炎上対策のメリット
ソーシャルリスニングを行うことで、ネガティブな声を投稿されてから短時間で発見し、対策することで、炎上のもととなる投稿の拡散を防ぐことができます。特に、X(旧twitter)などのSNSは、ネガティブな情報があっという間に広まってしまいます。誰がいつどんな発言を投稿するか分からない状況であるため、日頃からのソーシャルリスニングが重要なのです。ネガティブな投稿を検知したら、事実確認をしてから謝罪や説明を行うことで、炎上防止となります。不満や疑問を持っているユーザーに、企業側からアプローチすることは、ユーザーの満足度を上げることにもつながっているのです。
炎上リスクのある投稿を早期発見・早期対処できる
過去には、アルバイト店員が不適切動画をSNSに投稿し、炎上したというニュースが話題となりました。炎上原因となる、社員の不適切発言や情報漏洩に関する投稿があった場合、できるだけ早く発見して対処する必要があります。事実確認と現状把握を早急に行い、謝罪文の掲載や対応後の事後報告などを行います。
さらに、自社に関するネガティブな意見が掲載されることもあるでしょう。例えば「店員の接客が悪かった」「写真と出てきた料理に大きく差があった」といったものです。このような書き込みも、放っておくと炎上の原因になりかねません。ソーシャルリスニングサービスによって早期発見したら、書き込みに対し、意見に対してのお礼や謝罪、改善方針などを返信することができます。そうすれば、書き込んだ本人だけでなく、その書き込みを見たユーザーに対しても、企業イメージの悪化を防ぐことにもなるのです。
自社のサービス向上に役立つ
インターネット上にある様々な意見は、ユーザーの本音が詰まったリアルな声です。炎上対策としてネガティブな声を集め、分析することで、自社のサービス向上へとつながります。結果的に、顧客満足度が上がり、炎上のリスクを軽減することができるのです。
ソーシャルリスニングを炎上対策に活用するときのコツ
炎上対策にはソーシャルリスニングをうまく活用しましょう。ここでは、ソーシャルリスニングを炎上対策に活用するときのコツについて解説します。
適切なキーワードで情報収集を行う
ソーシャルメディア上には膨大な情報が存在しているため、適切なキーワードの選定が不可欠です。キーワード選定を間違うと、目的の情報が手に入らない可能性があります。そこでおすすめなのが、単体のキーワードではなく、「メイン+サブ」の組み合わせで検索することです。そうすることでより精度の高い情報が集まりやすくなります。
例えば、自社の炎上リスクを早期に発見したい場合には、「企業名+炎上(ネガティブなキーワード)」などのように、キーワードを掛け合わせて検索します。ほかに、「最悪」「謝罪」「ひどい」「反省」などのネガティブワードを使用するのもよいでしょう。
炎上対策に強いツールを選択する
ソーシャルリスニングを炎上対策に活用するためには、効率的な情報収集と迅速な状況の把握、炎上対応可能なツールの選択が必要です。ツールによって監視の頻度や方法、分析方法などが異なるため、拡散が速いSNSに対応するためには高スピード、かつ幅広いメディアに対応しているツールがおすすめです。
また、多くのソーシャルリスニングツールは、自社に関するキーワードを事前に登録しておくことが可能です。炎上が起こる可能性があるキーワードや投稿などをしっかりとモニタリングし、炎上が起こったときに通知機能があるものは炎上の早期発見に役立ちます。リアルタイムで情報を取得・分析できるものや、Twitterの全量データへ対応しているものもおすすめです。
ソーシャルリスニングとは|意味や分析方法の解説と導入事例を紹介!
https://www.nttcoms.com/service/social/column/20210730/
炎上のリスク分析をして対応フローを策定
炎上対策で発生するリスクは減少しますが、確実に防ぐことは出来ません。万が一に備え、社内でどのような業務・状況で、どのような炎上が発生する可能性があるか、リスクを全て洗い出します。また、発生した場合どこに連絡するか、誰が判断をして対応するのか社内の対応フローを策定します。夜間や休日の連絡体制、連絡がつかない場合の代替策など、様々な場面を想定して対応が滞らないようにすることが最重要です。
企業に炎上が起きたときの対処法
炎上対策の一環として、実際に炎上が起こった際の対処法を知っておくことも大切です。主な対処法を紹介するので、ぜひご確認ください。
炎上時に適切な対応を取る
万が一炎上が起きた場合は、何が炎上の原因となったのかを特定し、正確に状況を把握しましょう。まずは、炎上の規模やユーザーの批判内容などを見極めることが先決です。状況が確認できたら、それらをもとに対応の方向性を決定し、謝罪します。発言内容をコロコロ変えると誠意がないと受け取られる可能性があるため、弁解はせず謝罪だけに徹することが重要です。さらに、謝罪時には再発防止のための対策などを含めると、誠実さが伝わり効果的です。
企業によっては炎上対応のマニュアルが用意されている場合もあるので、マニュアルに沿って迅速に対応しましょう。多くの炎上は72時間以内に沈静化するといわれています。一旦謝罪をし沈静化できたら、改めて謝罪を行い改善策や今後の方針を表明します。
炎上後、すぐに投稿を削除したり、放置したりなどの間違った対応をするのは危険です。投稿を削除すると「逃げ」や「隠蔽」と思われ、さらに炎上する可能性があります。よほどの理由がない限り、投稿はそのまま残しておくほうが賢明です。また、「放っておけばそのうち勝手に収まるだろう」と放置することで事態がより複雑化するケースも多いため、何らかのアクションを起こしたほうがよいでしょう。
メディアごとに適した対応を取る
炎上のリスクを抱えた投稿を発見したメディアによっても、対応は異なります。Twitterの場合、情報拡散に適しているため、炎上リスクが高いという意識をもっておくことが大切です。そのため、対応には細心の注意を払いましょう。投稿者に対し、直接返信してコミュニケーションをとるアクティブサポートも可能なメディアです。ただし、他ユーザーにやり取りをスクリーンショットで保存される可能性があるため、回答は複数の目で確認するなど徹底しましょう。また、工場出荷後に虫が混入したなど、企業側に非がない場合は、証拠を提示しながら誤解のないよう説明します。
投稿内容が違法だった場合は削除依頼を出す
炎上の火種となる可能性がある書き込みや投稿を見つけたら、多くの人が目にする前にいかに早く対処するかが炎上防止の鍵となります。まずは、投稿された内容が事実かどうかを確認し、なぜそのような投稿が掲載されたのかにも目を向けます。もし投稿内容が法に触れるものであった場合は、投稿の削除依頼を行いましょう。企業に関する機密事項や名誉権の侵害、プライバシーの侵害などがこれにあたります。投稿されたサイトのルールを確認し、プライバシーポリシーや投稿ルールに反していないかを調べてみましょう。サイト内に削除申請の方法について説明があれば、その手順通りに依頼します。記載がない場合は、プロバイダ責任制限法に基づく書類を準備し、提出することで削除依頼となります。申請時には、どんな法律に違反しているか、その投稿からどんな被害を被ったのか、投稿内容がなぜ虚偽だといえるのかなど、具体的な内容の提示が求められることがあります。
レピュテーションの回復に努める
レピュテーションとは、日本語に直訳すると「評判」「評価」です。ビジネスの分野においては「企業に対する世間の評判や信用」を指す言葉として用いられています。
炎上対策の実施後は、レピュテーションの回復に向けた活動に取り組むことも大切です。しかし、Web上には炎上に関する情報が半永久的に残り続けるうえ、活動自体に多大な労力がかかるので、すぐに回復させることは難しいという実情もあります。
炎上に対する今後の改善案を公表したり、企業のイメージ回復につながる対策を実施したりするなど、長期目線で取り組みましょう。
レピュテーションリスクの要因と対策
https://www.nttcoms.com/service/social/column/20210802/
炎上の鎮火後は要因分析と改善を行う
炎上が起こった場合、上記のような対策を講じるだけではなく、二度と同じトラブルが発生しないよう要因分析と改善を実施することも大切です。炎上の要因はもちろん、対応フローや対応内容からも課題を洗い出し、その課題の解決に取り組む必要があります。
例えば、監視業務で見落としが発生した場合、2名の従業員による二重チェックをマニュアル化したり、検知を早めるために監視キーワードを見直したりするといった対策を講じます。
また、自社で起こった炎上事例を研修で取り上げるとさらに当事者意識を高められるため、改善策の一つとして検討しましょう。
Buzz Finderは炎上対策に効果的なソーシャルリスニングツール
Buzz Finderは、企業のブランドセーフティーを強固にするソーシャルリスニングツールです。業界最速レベルでTwitter公式全量データをほぼリアルタイムで収集・分析し、アラートやデイリートピックメールなどの通知ができます。リアルタイムで情報を把握し、任意に設定した投稿数を超えると、アラートメールを送信できるため、炎上の早期発見や早めのアクション・改善を実施できるのが強みです。デイリートピックメールでは、前日のツイート量と主な話題を確認できます。わざわざツールにログインする必要なく、メールチェックだけで状況が把握可能です。
また、要望に合わせて各種SNSやニュース、掲示板などにも対応でき、ダッシュボードやCSV出力による詳細分析も可能。設定や操作はとてもシンプルなのでわかりやすく、幅広く情報を監視できるのが強みです。BuzzFinderは「リスクを早期に把握したい」「自社でリスクモニタリングを始めたい」という企業様におすすめです。
導入事例:消費財メーカー 様
ある消費財メーカー様では、以下のような顧客課題を抱えていました。
- SNS上のネガティブな投稿をいち早く把握し、ブランド維持やトラブル抑制につなげたい
- インフルエンサーの動向や影響力をいち早く把握し、顧客応対やメディア応対に活かしたい
- 社内での情報共有・連携を横断的に行いたい
Buzz Finderを導入した結果、炎上の原因となる事象をリアルタイムで把握し、体系的に対処できるようになったとのことです。
また、社外のステークホルダーの意見を集めて自社での対策立案につなげる、SNS投稿の共有や業務フローの整理を通じて各部署の意識・連携が高まるなど、他にも有益な効果が出ています。
※要リンク:消費財メーカー様の導入事例
炎上の原因と対策を明確にしたうえで賢くSNSを活用しよう!
ソーシャルメディアは、自社にとって大きな強みになる反面、炎上というリスクを抱えたツールでもあります。炎上を防ぐためには、担当者だけでなく、会社全体で日常的に対策をしたり、SNSなどの運用に関する理解を深めたりする必要があるのです。最新の炎上情報収集と分析など、日常的にできることから炎上対策を始めましょう。
関連記事

2022/01/07

2021/10/11