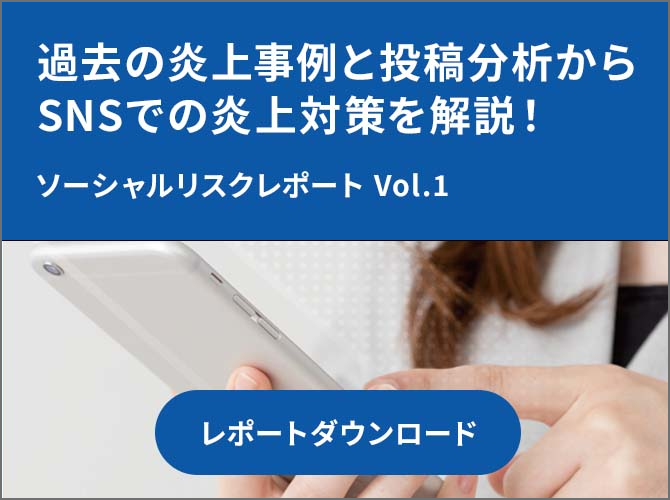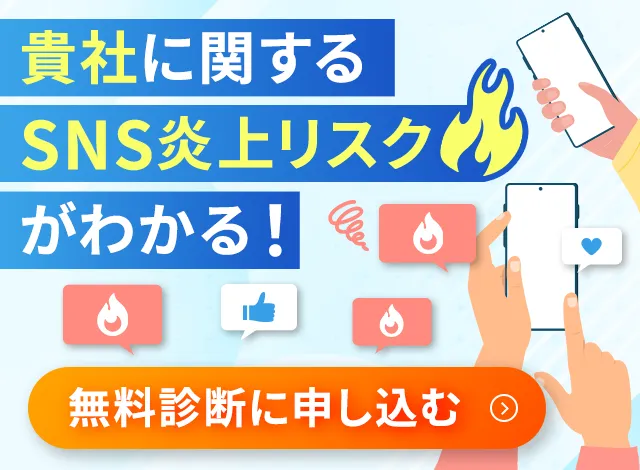更新日:2025/03/06(公開日:2022/04/13)
ソーシャルリスク対策
X (旧Twitter)企業アカウント成功事例【BtoC・BtoB】運用メリットとコツを解説
X (旧Twitter)の運用を検討している企業や、運用の成果を感じない企業では、「効果的な運用方法がわからない」という悩みはないでしょうか。X (旧Twitter)の運用を成功させるには、X (旧Twitter)の特徴やメリットを理解したうえでの運用が重要です。この記事では、X (旧Twitter)の特徴や運用するメリット、運用のコツなどを解説します。4つの成功事例も紹介するので、参考にしてください。
- X (旧Twitter)で企業アカウントを運用すると、商品・サービスの販売促進だけでなく、フォロワーによる拡散効果や幅広い年齢層への訴求、多様な意見の収集などのメリットがある
- X (旧Twitter)での企業マーケティング手法には、企業アカウントの運用や広告、キャンペーン、インフルエンサーマーケティングなどがある
- X (旧Twitter)の企業アカウント運用では、運用目的やターゲット層の明確化、アカウント設計、戦略に基づいた改善などが大切
- X (旧Twitter)で企業アカウントを成功させるには、拡散されやすい投稿やユーザーとのコミュニケーション、UGC・ハッシュタグの活用、ソーシャルリスニングを活用した炎上対策などが重要になる
X (旧Twitter)で企業アカウントを運用する5つのメリット
企業がX (旧Twitter)アカウントを運用すれば、「商品やサービスの販売促進や周知」「フォロワー獲得による拡散効果」「ユーザーの声を容易に聞ける」などが見込めます。日本のX公式アカウントが、2017年10月27日に公表(以降公表なし)した月間利用者数は4,500万人以上です。効果的に運用すれば、企業にとって大きなメリットが得られる可能性があります。ここでは、3つのメリットそれぞれについて、簡単に解説しましょう。
1|商品やサービスの販売促進を効果的にできる
X (旧Twitter)には「リツイート」「引用リツート」という機能があり、自社の商品やサービスの効果的な販売促進につなげられる可能性があります。リツイートとは、他人のツイート(自分のツイートも可)を自分のフォロワーと共有できる機能。一方の引用リツイートは、他人のツイートをコメント付きでリツートできる機能です。多くのユーザーからリツイート、引用リツイートされれば、自社のツイートが拡散されます。それにより、効果的な販売促進につなげられるのです。
また、リアルタイム性の高さもX (旧Twitter)の大きな特徴です。X (旧Twitter)では1人のユーザーの投稿が瞬時に多くのユーザーへと広がるため、アクティブユーザーはテレビやインターネット検索など従来の媒体よりも迅速に新しい情報を取得できます。加えて、情報伝達速度の速さもマーケティング戦略にとっても有用です。X (旧Twitter)を利用すると企業が発信するキャンペーンやプロモーション情報を、適切なタイミングでユーザーに伝えられます。
2|フォロワー獲得による拡散効果が期待できる
自社のツイートをリツイートなどで効果的に拡散するには、多くのフォロワーを獲得する必要があります。フォロワーとは、自社に興味がありX (旧Twitter)に投稿されたツイートや最新情報を確認したい、と感じているユーザーです。フォロワーが多ければ多いほど、リツイートや引用リツイートされる確率が高くなります。そのため、多くのフォロワー獲得が自社ツイートの効果的な拡散につながるのです。また、フォロワーは自社のファンといえます。X (旧Twitter)は多くのファンに直接情報を届けられるので、継続的に新商品やサービスを利用してくれることも期待できるのです。
X (旧Twitter)での投稿の拡散について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
X (旧Twitter)で拡散を狙うには?ツイートの時間帯や投稿のコツを紹介
3|幅広い年齢層に訴求できる
X (旧Twitter)で企業アカウントを運用すると、従来よりも幅広い年齢層に自社の商品・サービスを訴求可能です。X (旧Twitter)は若年層から中高年まで幅広い年齢層が利用しています。
2023年に総務省情報通信政策研究所が発表した「令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の、「主なソーシャルメディア系サービス/アプリ等の利用率」によると、X (旧Twitter)の年齢層別利用率の割合は以下の通りです。
- 10代:54.3%
- 20代:78.8%
- 30代:55.5%
- 40代:44.5%
- 50代:31.6%
出典:総務省情報通信政策研究所「令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」
多くの年代で利用されており、30代以下ではいずれも利用率が50%を越えています。
また、アライドアーキテクツ株式会社の「Twitter企業アカウント利用に関する意識調査(2021年度)」の調査結果から、年代別の企業アカウントのフォローに関する質問と回答をみていきましょう。
「Q.Twitterで企業の公式アカウントをフォローしていますか?」
A.年代別「フォローしている」の割合
- 10代:55.4%
- 20代:55.6%
- 30代:53.3%
- 40代:52.6%
- 50代:38.1%
「Q.Twitterの企業公式アカウントをフォローしている目的は何ですか?」
- 新情報やクーポン等のお得な情報を取得するため:46.9%
- そのブランドが好きだから:25.0%
- キャンペーンに参加するため:23.6%
出典:アライドアーキテクツ株式会社「Twitter企業アカウント利用に関する意識調査(2021年度)」
各世代で高い割合のユーザーが企業アカウントをフォローしており、企業の新情報などを取得したいと考えているようです。この結果からも、X (旧Twitter)アカウントを情報発信に利用すれば、幅広い年齢層に訴求できることが分かります。
4|ユーザーの声を聞きやすい
X (旧Twitter)を使えば、簡単に商品やサービスを利用するユーザーの声を聞けるので、マーケティングに役立てられます。ユーザーが商品やサービスについてどのように感じているのか、またはどのような商品を求めているのかなどを調査できるのです。X (旧Twitter)には、ユーザーとコミュニケーションが取れるさまざまな機能があります。例えば、ツイートへのコメント機能、ダイレクトメッセージ機能、X (旧Twitter)投票機能などさまざまです。このように、普段ではコミュニケーションを取るのが難しいユーザーと双方向でつながれるので、マーケティングに役立てられます。
5|匿名性があり忌憚のない意見を収集できる
匿名性が高く、ユーザーから忌憚のない意見を収集できるのもX (旧Twitter)を利用するメリットです。X (旧Twitter)でアカウントを作成したり、ポストしたりするのに本名での登録は求められません。X (旧Twitter)では、個人情報を公開せず匿名での情報発信が可能です。
匿名性が高いとユーザーは思っている内容を正直に発信する傾向があるため、商品・サービスに対する忌憚のない意見を収集できます。Facebookなど実名登録が必要なSNSは、情報の信憑性は高くなるものの、X (旧Twitter)ほど正直な意見を収集しづらいでしょう。
X (旧Twitter)の企業アカウントを使ったマーケティング手法
X (旧Twitter)での企業アカウントを利用した主なマーケティング手法は、以下の通りです。
- 企業アカウントの運用
- 広告の運用
- キャンペーンの実施
- インフルエンサーマーケティングの実施
各マーケティング手法を詳しくみていきましょう。
企業アカウントの運用
X (旧Twitter)で企業アカウントを開設すると、自社の商品・サービスに関する情報の発信やユーザーとのコミュニケーション、ブランディングなどに活用できます。企業アカウントで大切になるのは継続的な運用です。継続して情報発信を行うと、フォローしてくれたり、ファン化してくれたりするユーザーが増えていきます。フォロワーが多くなれば情報の拡散力が高くなり、低コストで効果的な宣伝が可能です。また、ユーザーからの意見やフィードバックも増えるため、商品・サービスの改善によるロイヤルティおよび売上の向上も期待できるでしょう。
広告の運用
X (旧Twitter)ではターゲットを絞った広告配信が可能です。X (旧Twitter)での広告は少額から配信でき、対象となるユーザーも細かく設定できます。X (旧Twitter)の広告は普通のポストと同じように、「いいね」やリポストによって二次拡散も期待できるのが特徴です。ユーザーが情報を広めてくれるため、広告費の節約にもつながります。また、画像広告や動画広告、フォロワー獲得広告など多様な種類の広告があり、さまざまなマーケティング施策を実施できます。
キャンペーンの実施
X (旧Twitter)では、リポストなどを条件としたキャンペーンを実施するのも有効です。よく行われているのが、自社アカウントのフォローと特定の投稿をリポストするのを応募条件として、当選者を決めて商品などをプレゼントする方法です。応募にフォローやリポストを必要にしているため、フォロワーの獲得やポストの拡散などでの認知拡大が期待できます。応募条件を簡単にすると多くのユーザーに参加してもらえるため、キャンペーンの効果も高くなるでしょう。
インフルエンサーマーケティングの実施
インフルエンサーを活用し、効果的に拡散してもらう方法もあります。インフルエンサーは、多くのフォロワーを抱えている影響力の高い人たちです。自社の商品やサービスを使ってもらいX (旧Twitter)で紹介してもらえれば、大きな宣伝効果が見込めます。依頼には費用がかかりますが、商品やサービスだけでなく企業の宣伝にもなるので、フォロワー獲得にもつなげられるでしょう。フォロワーが増えれば、自社のツイートがリアルタイムで人の目に触れる機会を増やせます。
X (旧Twitter)を企業のマーケティングに活用するためのさらに詳しい方法については、以下の記事も合わせてご覧ください。
X (旧Twitter)のビジネス活用方法や注意したいポイントなどを解説
X (旧Twitter)で成功する企業アカウントの作り方
X (旧Twitter)で成功する企業アカウントを作る際のポイントは以下の通りです。
- X (旧Twitter)を運用する目的を明確にする
- ターゲット層を明確にした戦略を立てる
- アカウント設計を行う
- 戦略を基に運用・分析・改善を行う
企業アカウントを成功させるための準備や戦略の立て方をみていきましょう。
X (旧Twitter)を運用する目的を明確にする
まずは、X (旧Twitter)で企業アカウントを運用する目的を決めましょう。企業アカウントの運営では、情報発信の一貫性が大切です。目的設定が曖昧なままだと、情報の拡散やフォロワー数の増加にこだわり、運用方針がぶれてしまい思ったような効果が得られない可能性もあるでしょう。最初に目的を設定しておけば、途中で方針が変わってしまう心配もありません。
企業がアカウントを開設する目的の例は、以下の通りです。
- 会社や商品・サービスの認知度向上
- ユーザーからの意見収集
- ファンの獲得
- ユーザー・ファンとのコミュニケーション
X (旧Twitter)を利用して何がやりたいのか、アカウントを作る前に目的を明確化させましょう。
ターゲット層を明確にした戦略を立てる
X (旧Twitter)で一度にツイートできる文字数は140字です。伝えたい内容は、少ない文字数で投稿しなければいけません。そのため、ターゲット層などを明確にした戦略を立てる必要があります。前述したように、X (旧Twitter)では幅広い層のユーザーが利用しているのが特徴です。
趣味や好きなことに関連する情報収集で利用されるX (旧Twitter)では、ターゲット層を絞り140字で「自分が欲しい情報に関連している」と思わせる必要があります。例えば、ホームページに誘導するのが目的でも、ツイート内容が一目で「自分には関係ない」と判断されると、商品の周知や拡散につながりません。最初の1文で「自分に関連する」と理解させるのがポイントです。
アカウント設計を行う
企業アカウントを開設する際は、あらかじめ決めた目的を達成するためにアカウント設計を行いましょう。アカウント設計を行うことで、情報発信に一貫性をもたせるとともに、目的に沿ったアカウントへと仕上げられます。
自社商品や業界の情報発信に重点を置くのか、ユーザーとの交流を目的とするのかなど、何がやりたいかでアカウントの方針も大きく異なります。
アカウント設計では、以下のような作業を実施します。
- 企業やブランドのイメージに沿った運用方針を決定する
- アカウントの運営目的に応じたKPI(Key Performance Indicators:重要業績評価指標。目標達成の進捗度合いを数字で測るための指標)を設定する
- アカウント運用チームやマニュアルを作成する
戦略を基に運用・分析・改善を行う
企業アカウントを開設した後は、今まで決めた戦略や設計に基づいて実際に運用を行っていきます。アカウント運用では、戦略・設計にズレがないか確認するために、定期的な分析・改善を行いましょう。
アカウント分析では、以下の指標を目安にします。
- フォロワー数:アカウントをフォローしているユーザーの数。フォロワーの推移を確認し、施策の成果を確認できる指標。
- インプレッション数:投稿が表示された回数。どれくらい投稿を見られたか確認できる指標。
- エンゲージメント率:投稿に対してユーザーが「いいね」やリポストなどのリアクションをとった割合。ユーザーが投稿内容やアカウントにどれだけ興味をもっているか確認できる指標。
細かな数字を分析すれば、ユーザーが何の投稿に反応したのか、何を改善すれば良いのかなどがみえてくるでしょう。
X (旧Twitter)のアナリティクスデータをマーケティングに活用する方法については、以下の記事も合わせてご覧ください。
X (旧Twitter)アナリティクスを使って効果的にSNSマーケティング
X (旧Twitter)の企業アカウント成功事例【BtoC編】
ここからは、X (旧Twitter)で企業アカウントを運用し実際に大きな成果を得られた5社、「丸亀製麺」「フォード」「味の素」「マイナビ転職」「SHARP(シャープ)」の成功事例を紹介します。
UGCの創出に成功した「丸亀製麺」
丸亀製麺(@UdonMarugame)は、2022年3月時点で99万4000フォロワーを獲得しています。2019年から、約3倍にフォロワー数を増加させた丸亀製麺。まずはフォロワーに商品やキャンペーンの魅力を知ってもらい、UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)を増やしました。UGCとは特定の商品・サービスに関して、ユーザーが制作・発信するコンテンツです。UGCが増えたことで、UGCそれぞれのフォロワーに丸亀製麺の魅力が伝わります。結果、丸亀製麺も多くのフォロワーを獲得しました。
新商品の認知度アップに成功した「フォード」
フォード(@Ford)は、2022年3月時点で139万2000フォロワーを獲得しています。フォードはEVトラック「F-150ライトニング」を認知してもらうためにX (旧Twitter)を活用し、Share of Voice39%、ライブ再生数450万回以上を達成。オリジナルブランド絵文字の作成や、X (旧Twitter)ライブでの最新モデルのお披露目などで、EVトラックの認知度を高めました。元々の認知度が高い企業では、新商品の発表をX (旧Twitter)で大々的に行うことで、高い宣伝効果が期待できます。
若年層の認知度アップに成功した「味の素」
味の素(@iza_gyoza)は、2022年3月時点で2万7000フォロワーを獲得しています。味の素では、冷凍食品のギョーザ関連に特化した公式アカウントを展開中です。若い世代への認知度を高める目的で、X (旧Twitter)の活用をスタート。テレビCMの新バージョンの告知や、テレビCMとは別バージョンのWebオリジナルCM動画を配信するなどして、若い層への商品認知度を高めました。
多様な手法で潜在層の獲得に成功した「マイナビ転職」
マイナビ転職(@MynaviTenshoku)は、2022年3月時点で2万5000フォロワーを獲得しています。
マイナビ転職では、X (旧Twitter)を活用し「マイナビ転職アプリ」のダウンロード数を4000%にした実績があります。転職の潜在層に興味や関心がありそうなキーワードでアプローチ。さらに、マンガや動画、ゲーム風クリエイティブなどを活用し、多くの潜在層を獲得しました。
面白い投稿で企業イメージの刷新に成功した「SHARP(シャープ)」
SHARPの公式アカウントは、2025年2月時点で85万3,000フォロワーを獲得しています。ユーザーから「シャープさん」と呼ばれており、親しみを感じられる投稿が特徴です。
自社商品に関する投稿だけでなく、会社の業績が悪化した際の「(´-`).。oO( きょうは眠れるかな…)」や台湾企業による買収契約時の「な ん て 日 だ !」といった投稿のように、会社から一歩引いたユーザー視点での投稿が話題になりました。現在では、大企業のSNS成功例として知られる有名アカウントへと成長しています。ユーザーとのフレンドリーな関係構築によりフォロワー数を伸ばし、自社へのイメージ向上に貢献している事例です。
X (旧Twitter)の企業アカウント成功事例【BtoB編】
続いては、X (旧Twitter)の企業アカウントを運営して成果をあげているBtoB企業3社「フセハツ工業株式会社」「大京警備保障」「ALSOK(アルソック)」の成功事例を紹介します。
製造工程を見せ製品のPRに成功した「フセハツ工業株式会社」
大阪府東大阪市のばねメーカー、フセハツ工業株式会社の企業アカウント「ばねのフセハツ工業(@fhk2014_kk)」は、2025年2月時点で7万4,000人のフォロワーを獲得しています。フセハツ工業は自社の製造工程をユーザーに紹介する方法で会社のPRに成功しました。
フセハツ工業では自社のものづくりにこだわったアカウント運営を行っており、投稿の多くは工場内での機械による製造工程を映した動画です。なかなか見られない工場内の様子やばねを使った脳活性・握力強化グッズのようなユニーク商品の投稿で多くのユーザーから注目を集めています。なかなか一般に知られにくいBtoBメーカーのPR成功例です。
面白投稿やハッシュタグの活用で認知の獲得に成功した「大京警備保障」
大京警備保障(@dkykeibi_tokyo)は、2025年2月時点で1万4,000人のフォロワーを獲得しています。大京警備保障では、面白投稿やハッシュタグの活用で自社アカウントの認知獲得に成功しました。
大京警備保障のアカウントには、社長や社員が出演する写真やショート動画などが投稿されています。例えば、あるあるネタや「~してみた」動画など、さまざまな切り口のおもしろ動画や社長の演技が幅広いユーザーから注目を集めています。写真や動画以外にも、プライベートで親しみを持てる内容を投稿しており、ユーザーとの距離の近さが魅力です。
本業とは直接関係のない投稿内容で、会社の認知度やイメージアップに成功している事例です。
フォロワーとの交流でアクセス増加に成功した「ALSOK(アルソック)」
ALSOK(@ALSOKnow)は2024年2月時点で8万5,000人のフォロワーを獲得しています。ALSOKの企業アカウントは、フォロワーとの交流によってアクセス増加に成功しました。投稿の中心は自社の本業である防犯や防災に関する内容で、真面目なトーンのポストです。
それに加え、自社が将棋のALSOK杯王将戦で特別協賛になっている関係から将棋関連の投稿も行っています。なかでも人気を集めているのが、フォロワーも挑戦できる詰将棋の投稿です。問題と解答を別の日に投稿する工夫によりアクセス数増加にも成功しています。
X (旧Twitter)の企業アカウント運用を成功させる7つのコツ
X (旧Twitter)で効果的な運用をするためには、コツが必要です。ここでは、7つのコツを紹介します。
1|目を引く内容で拡散されやすいツイートを行う
X (旧Twitter)の投稿には、画像や絵文字などユーザーの目を引くために工夫されたツイートが目立ちます。そのため、140字のテキストを並べるよりも、ユーザーの目に留まり見てもらえるツイートが効果的です。
X (旧Twitter)は暇つぶしで利用しているユーザーも多いので、目に留まらないツイートはスルーされる可能性が高くなります。例えば、クリスマスなどの季節のイベントに関連する画像や絵文字を入れたり、商品の画像を入れたりするなど工夫すれば、ユーザーがツイートを見てくれる可能性を高められるでしょう。それらの取り組みが、リツイートなどの拡散にもつながるのです。
2|ユーザーとのコミュニケーションを大切にする
ユーザーとつながることも大切です。X (旧Twitter)を使えば、通常では難しいとされる、企業とユーザーの双方向コミュニケーションが可能になります。
一般ユーザーからしてみれば、企業から何かしらのアクションをもらえるのは嬉しい体験となり、好感を持つ機会となります。ファンの獲得にもつながるので、積極的にユーザーとつながりましょう。例えば、自社の商品に関するツイートに、いいねしたりコメントしたりすれば、好感を持ってもらえます。クレーム投稿にも真摯に対応すれば、ファンになってくれるケースもあるでしょう。コミュニケーションを続けることで、自社の商品サービスの改善点も見えてきます。ユーザーとのコミュニケーションは、商品サービスのニーズを高めることにもつながるのです。
3|UGCを増やせば効果の高い拡散ができる
UGC(User Generated Content)を増やすことができれば、効果の高い拡散を期待できます。UGCとは、実際に商品サービスを利用したユーザーによるコンテンツです。自社の商品サービスを利用したユーザーのX (旧Twitter)によるUGCが増えれば、それぞれのフォロワーにも拡散されることになります。商品やサービスを選ぶときは、実際に利用したユーザーの口コミ評判などを参考にする人も少なくありません。X (旧Twitter)のUGCにより、商品の使用感やおすすめポイントなど、画像付きで紹介してもらえれば、潜在ユーザーへの効果的な広告になるのです。
UGCについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
UGCとは?マーケティングに重要な理由や活用方法・事例を紹介
4|運用体制を整理し安定した運用を続ける
X (旧Twitter)の運用は、片手間程度と考えてはいけません。しっかりと担当者を決めるなど、運用体制を整える必要があります。例えば、週ごとにX (旧Twitter)の投稿やコメントの担当部課を変えるなど、本業の片手間では効果は見込めません。他の仕事があるのにやらされていると感じ、「誰かがやるだろう」「自分には関係ない」などと考えてしまいます。これでは責任を持って対応する社員がいない状態なので、運用が難しくなるのです。企業ではX (旧Twitter)運用による大きな成果を理解し、専任の担当者を任命し運用する必要があります。
また、社内で人員を配置する余裕がないなら、専門知識のある企業や個人にアウトソーシングする方法も検討しましょう。
5|予約投稿を使い適切なタイミングで投稿する
X(旧Twitter)の予約投稿を利用すれば、担当者が直接投稿できないタイミングでもポストできるため、適切なタイミングでの投稿が可能です。例えば飲食店なら、昼食や夕食時を狙ってキャンペーンやクーポン情報を周知すれば、集客につなげられます。イベント時などで担当者が忙しい場合でも、予約投稿を使えば必要な情報を適切なタイミングで発信できるでしょう。
ユーザーが求めるタイミングで情報を提供できるため、ユーザーの行動を促す効果が期待でき、集客にもつなげられます。
6|関連性の高いハッシュタグを活用
ツイートに、キーワードを含めることも効果的です。「#」マークのついたキーワードをハッシュタグと呼びます。ハッシュタグは自動でリンク化され、同じキーワードを含むツイートを検索できる機能です。自社の商品やサービスに関連するハッシュタグを含めておけば、そのキーワードの投稿を探しているユーザーに見てもらえる可能性があります。これは、フォロワーだけに限定されるものではないので、そのハッシュタグを検索した全てのユーザーが対象です。
人気の高いキーワードを含めれば、効果的に投稿を拡散できます。ただ、商品やサービスに関係ないハッシュタグを含めてはいけません。ユーザーにとって、求めてない情報が表示されるのはストレスです。企業の評価にも関わることなので、関連性のないキーワードで拡散を目論むのは避けましょう。
7|炎上予防と対策
炎上予防や対策も、企業がX (旧Twitter)アカウントを運営するうえでは重要になります。企業アカウントにおける炎上の原因になりやすいのは、社員によるツイート内容や企業の活動などによるものです。経済や地域格差などに関連すること、政治や宗教関連、スキャンダルや芸能界関連などが、炎上しやすい傾向にあります。
企業アカウントは個人の思想を投稿するものではないので、自社の商品やサービス以外の内容をツイートする必要はありません。企業にとって炎上は、致命的なトラブルになる可能性があります。これは、担当者を曖昧にして、誰でもツイートできる状態にしていることも原因の1つです。X (旧Twitter)アカウントを運営する際は、教育を受けた専任の担当者を任命し管理することも検討しましょう。
加えて、X(旧Twitter)での炎上対策にはSNS上でユーザーの投稿を収集・分析するソーシャルリスニングも有効です。企業アカウントを運用する場合は、ソーシャルリスニングを効率的に実施できるツールの導入も検討しましょう。
SNSでの炎上対策やソーシャルリスニングについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
炎上対策とは?企業における主な炎上原因と対策
ソーシャルリスニングとは|意味や分析方法の解説と導入事例を紹介!
X (旧Twitter)の企業アカウント成功をサポートするソーシャルリスニングツール「Buzz Finder」
「Buzz Finder」は企業のブランドセーフティを強化させ、リスク・炎上対策に貢献するソーシャルリスニングツールです。
X (旧Twitter)の公式全量データをほぼリアルタイムかつ業界最速水準で収集・分析できることに加え、ツイート量やデイリートピックを日報で報告することもできます。さらに、ツイート数の急増を検出するとアラートメールで知らせてくれるため、炎上や風評被害の早期発見が可能です。炎上を早く察知できれば、ユーザーやメディアからの問い合わせに対しても事前に入念な対策を講じることができます。
X (旧Twitter)に限らず、要望に合わせてニュースサイト・掲示板・Facebook・Instagramなど、ほかのSNSでの情報収集・分析も可能です。
続いては、実際に「Buzz Finder」を導入している企業様の事例をご紹介します。
導入事例|情報通信サービス業 様
ある情報通信サービス業様では、ネットでのトラブルや炎上を先回りして把握し、SNSの反応を踏まえてメディア対策に備えたいと考えて「Buzz Finder」を導入されました。
「Buzz Finder」を利用したソーシャルリスニングの実施により、素早いリスク通知とレポートをもとにした的確なメディア対応、迅速なプレスリリースの発行が可能となりました。また、お客様センターでは、日報による投稿の定点把握によってユーザーの反応への対応力向上を実感しています。
X (旧Twitter)の企業アカウント運用は拡散が重要!成功事例を参考に運用しましょう
X (旧Twitter)の企業アカウント運用で、もっとも重要なのはツイートを拡散させることです。いくら商品やサービスについて詳しく紹介しても、誰にも届かなければ意味がありません。ツイートを効果的に拡散するには、現在のフォロワーから拡散してもらうことや、ターゲット層を絞った運用などが重要です。成功事例からも拡散や認知度を上げる方法が知れるので、参考にしてみてください。
X (旧Twitter)でのアカウント運用や炎上対策にはソーシャルリスニングが有効です。X (旧Twitter)で企業アカウントの運営を検討している企業様は、ソーシャルリスニングツール「Buzz Finder」の導入をぜひご検討ください。
以下のリンクから、炎上リスクやソーシャルレポートに関する資料をダウンロードできます。
関連記事

2022/01/07

2021/10/11