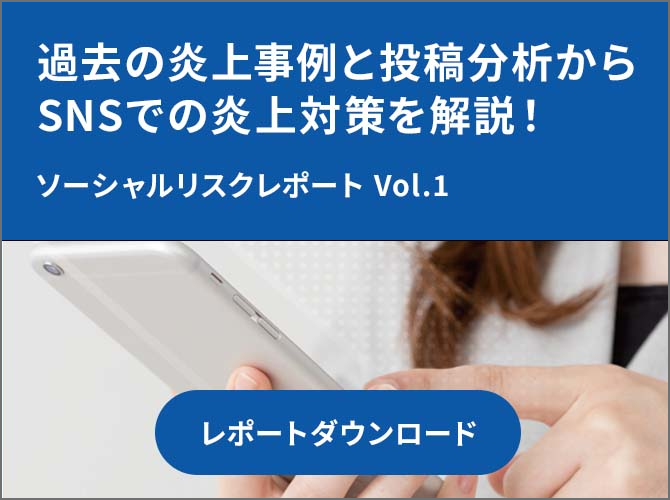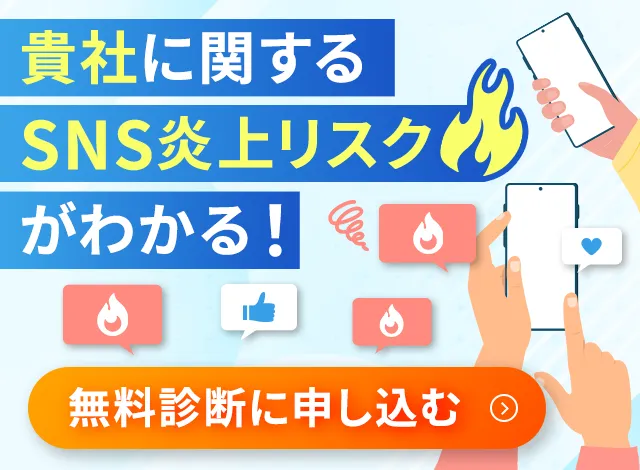更新日:2025/03/06(公開日:2023/02/13)
ソーシャルリスク対策
SNSにおける企業の炎上事例9選|炎上の対処法・事前対策を紹介
SNSが隆盛を極める中、企業にとって頭を悩ませるのが炎上問題です。些細な誤爆や顧客とのトラブルが原因で大炎上し、そのままデジタルタトゥーになってしまうケースも少なくありません。しかし、担当者が24時間すべてのSNSやブログ、掲示板を監視することは現実的ではなく、気づいたときには手遅れになっていることもあります。
この記事では過去に実際にあった炎上例を見ながら、炎上を起こさないための対処法やSNSの監視に便利なツールについて解説していきます。
- SNSが炎上するのにはいくつかのパターンがあるため、どのような投稿が炎上するかを理解しておくことが大切
- 政治や宗教などのセンシティブな話題でつぶやいたり、担当者が企業アカウントで個人的なことを投稿してしまったりしたことで、炎上が起こることもある
- 被害を受けたら素早い対応が必要であり、迅速な分析やステークホルダーとの情報共有などが重要
- 常にSNSなどを監視するのは難しいため、監視ができる専用のツールやシステムを導入するのもおすすめ
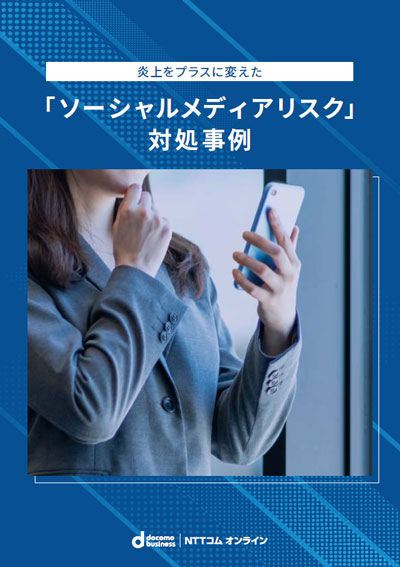
SNSの炎上対策には原因の把握が必要
炎上をする投稿にはさまざまな種類があります。まずはどのような投稿が炎上するかを知って、対策を立てるようにしてください。
ユーザーを不快にさせる投稿をした
炎上の一因として、拡散を狙った過激な投稿がユーザーを不快にさせるケースが挙げられます。
SNSは多くの人にとって身近なコミュニケーションツールであり、その手軽さゆえに投稿内容への配慮が不足しがちです。特に企業アカウントでは、わずかな言葉遣いや表現のニュアンスが炎上につながることもあります。
例えば、広告表現の意図が誤解を招いたり、軽率なユーモアが不適切と受け取られたりすることもあるでしょう。また、災害時にその災害を揶揄しているように受け取られるような発信をしてしまった例もあります。
従業員が不適切投稿をしてしまった事例や対処法を紹介しています。
従業員の不適切投稿を防ぐには?炎上事例や対処法も解説
センシティブな内容の投稿をした
政治や宗教、社会問題などを取り上げたために起こるのが、議論型の炎上です。例えば以下のような内容が挙げられます。
- 政治、宗教、社会問題に関する話題
- 人種差別につながると思われる発言
- 性的と受け取られる言葉、画像
- ジェンダーに関する偏った見解
- ルッキズムだと受け取られる意見
これらの話題は二項対立になりやすく、非常に炎上しやすいテーマの一つです。あくまでも個人的見解だと釈明しても、大きく炎上を招き企業の立場やブランドイメージが損なわれる可能性があります。そのため、センシティブな話題は特に、投稿前に内容を十分に精査することが重要です。
個人情報や機密情報の漏えいにつながる投稿をした
SNSでは、文章や画像・動画を通じて、意図せず個人情報や機密情報を漏えいし、炎上につながるケースがあります。例えば、以下のような事例が考えられます。
- 社内の会議資料や顧客情報が映り込んだ写真を投稿してしまう
- 社員が顧客情報に関わる内容や、未発表の商品について個人のSNSにうっかり投稿する
- 有名人の来店情報を従業員がSNSで公開してしまう
企業は多くの個人情報や機密情報を扱うため、SNSへの投稿には細心の注意が必要です。情報漏えいは意図せず発生することもあるため、公開前のチェック体制を徹底し、リスクを未然に防ぐことが重要です。
SNSで情報漏洩が起きる理由と、企業としてやるべき対策について知りたい方はこちらもご覧ください。
SNSによる企業の情報漏洩の原因とは?事例や5つの対策方法も詳しく解説
企業アカウントでプライベートな投稿をした(誤爆)
企業アカウントと個人アカウントを誤認し、「プライベートな写真を投稿してしまった」「限られた友人向けのメッセージを公開してしまった」などのミスが発生すると、企業の公式発言として不適切と見なされ、炎上につながることがあります。
誤爆(誤投稿)は、以下のようなケースで発生しやすいと考えられます。
- 企業アカウントで個人的な意見や私的な写真を誤って投稿してしまう
- 企業アカウントでセンシティブな内容を含む投稿に「いいね」やリツイートをしてしまう
- 複数の企業アカウントを一人で管理していたため、無関係な話題を誤って投稿してしまう
仮にすぐに誤爆であったことを説明し、投稿を削除しても、多くの場合、完全に消し去ることはできません。特に、運用フローが曖昧で、アカウント管理に使用するデバイスが統一されていない場合、属人的な運用になりやすく、誤爆のリスクが高まります。
企業が不祥事を起こした
企業が不祥事を起こすと、その事実がSNSで拡散され炎上するケースがあります。不適切な労働環境、不正会計、コンプライアンス違反などは、特に炎上の火種になりやすい問題です。
例えば、以下のような不祥事が考えられます。
- 企業のトップが社会通念上問題があるとされる行動をとった
- 食品に異物(虫など)が混入していた
- 社名の入った車が重大な交通違反をした
- 商品に関するデータの偽装が発覚した
- 社員へのセクハラ、パワハラを隠蔽した
不祥事がテレビや雑誌で報じられた後に、経営者や従業員がSNS上で不用意な反論を行い、さらに炎上が拡大するケースもあります。
内部統制が整備されておらず、コンプライアンス意識が低い企業では、不祥事の発生リスクが高まります。そのため、日頃からガバナンスを強化し、透明性のある経営を意識することが重要です。
SNSでコンプライアンス違反が拡散される要因や事例などを知りたい方はこちらをご覧ください。
SNSでコンプライアンス違反が拡散されるリスクとは?有効な対策方法を紹介
こちらでもSNS炎上の事例やリスク回避の方法について紹介しています。
企業のSNSアカウントが炎上する理由とリスク回避の対策とは
利用者の迷惑行為による炎上も増加している
近年、施設や店舗の利用者による迷惑行為が、炎上につながるケースが増加しています。
軽いいたずら程度の内容も多いですが、飲食店でのいたずらは衛生や安全を脅かすものです。SNSで拡散されれば、利用者の減少や株価の下落などを引き起こしかねません。
店舗への迷惑行為が増加している背景には客側のマナーの低下や、機械の普及によって従業員が減少し、細部まで目が行き届きにくいこともあるでしょう。また、SNSでウケたいという気持ちも要因の一つです。しかし、社会全体でコンプライアンス意識が高まっていることもあり、以前は大きな問題とならなかったことが、重大事案と捉えられあっという間に炎上します。
企業側からも迷惑行為のリスクを伝える活動や、迷惑行為ができない環境作りに取り組むことが大切です。
SNS対策をしない場合のデメリットや、対策方法などについて知りたい方はこちらをご覧ください。
SNSの迷惑行為は対策できる?増加の背景や炎上事例・対策方法を解説
SNSで起こりやすいカスタマーハラスメントについて知りたい方はこちらをご覧ください。
SNSで拡散されたカスタマーハラスメントの事例や対策方法・対処方法を解説
企業で起きた炎上事例9選
なぜ炎上するのかを知るために、最近の炎上事例をまとめました。炎上というと芸能人のものが知られていますが、広告の文言など、一見何事もないようなことでも炎上は起きます。なぜ炎上は起きたのか、原因やユーザーの動向を知っておくことで炎上対策に役立てることができます。
1|新商品のプロモーションPVでの炎上事例【2020年】
路上で一般の人をプロのカメラマンが撮影した「ストリートスナップ」が炎上となる事態がありました。
カメラマンが路上で不特定多数の人を動画撮影し、自社サイト上で紹介するというものですが、通行人のじゃまになるような行為があったうえ、撮影された人たちが不快な表情を浮かべているものが多くありました。
モラルに欠けると瞬く間に炎上し、企業は即、動画を削除しましたが、オンラインに一度掲載されたものは拡散されるため、その後もYouTubeなどでアップされては消されるということが繰り返され、批判が続いた炎上事例です。
効果的な対策
肖像権に関する法的な問題は微妙であるものの、企業のイメージを損なったことには変わりはありません。法務を通して問題なしとなっても、一般ユーザーから反感が起きれば、プロモーションは失敗となります。
関連する部署でチェックを重ね、一般的なモラル・マナーの概念で許容されるかを議論することが大切です。プライバシーが尊重される時代であることを再認識する必要があります。
2|インスタントラーメンのPR漫画での炎上事例【2020年】
SNS上にアップしたものが、意図したこととはまるで関係のないことで炎上することもよくあります。
ある企業はSNS上で、父が昼ご飯を作り子どもと食事をするだけのほのぼのとした漫画を掲載しました。問題がないように見えましたが、漫画の最後に、帰宅後の妻が夫と一緒に片づけをするシーンがあったことから、女性に家事を強要していると捉えられ、一部からの抗議をうけ、公式で内容を検討するとのコメントを発表。その後「問題はない」「削除したほうが息苦しい」という声が多く上がったこともあり掲載は再開されました。
効果的な対策
現在はジェンダーの問題はとてもセンシティブです。不特定多数を対象とする企業の場合、誰もがジェンダーギャップを感じない作品になっているか、公表前に社内で何度も精査する必要があります。その上で、投稿が炎上した際、すぐに謝罪を行った場合、物事を真剣に捉えていないいわゆるご不快構文ととらえられ、更に炎上が拡散するケースが多くみられます。
炎上発生時には投稿や記事の削除を行わない事と、論調が批判のみならず支持する投稿も多くみられる場合は、謝罪を行う事が必ずしも最適な対応ではありません。過去の炎上事例を参考に炎上から収束までの論調を把握することが重要です。
※記事初出時、二話以降の掲載は見送りとして記載しましたが誤りですので当該部分および対策法を修正させていただきました。
3|デリバリーチェーン店内での動画での炎上事例【2021年】
アルバイトが店内で問題行動をし、それを動画としてSNS上にアップして炎上するバイトテロも社会問題となっています。
ある店舗ではバイトが厨房でシェイクを何度もすすり、周囲がはやしたてた様子をInstagramにアップし、物議を醸しました。企業はバイトの不快な行為を謝罪して、投稿したアカウントも削除されましたがまとめサイトでも紹介され炎上が続きました。また、動画は転載・拡散されネット上に残った状態となった炎上事例です。
こうした炎上は企業の社会的な信頼を失墜するとともに、バイトへの不信感にもつながっています。
効果的な対策
アルバイト店員、社員へ徹底した教育が重要です。SNSに関するリスク研修を行い、企業だけではなく従業員本人の人生にも大きな影響があることを理解してもらう必要があります。
撮影を禁止するなどの事前対策を講じ、社内の個人も含めたSNSルールの徹底をしなければなりません。企業は常にSNSを監視し、早期発見の体制を整えておくことも重要です。
4|サプリメント企業の薬機法違反による炎上事例【2021年】
SNSでのPR過程で、薬機法や景品表示法違反が起き、炎上する問題もよくあります。
薬機法はコスメ、サプリメントなど、健康や美容に関する商品も対象となります。某スタートアップ企業はインフルエンサーを介してPRを行っていましたが、”乾燥知らずのうるおい肌”など、インフルエンサーの文章に違反が認められ炎上してしまいました。
初動対応にも問題があり、関係者が公式発表までに私見を発信したことや、説明のない投稿削除などが、余計に炎上をあおりました。品質への不信感も招いてしまったようです。
効果的な対策
関係者全員のコンプライアンスの強化をしなければなりません。薬機法のように法律が関わる場合には、法務の確認も必要です。
インフルエンサーのように、社外の人も関わる場合には、表現に関するマニュアルや炎上した際の対応マニュアルを策定しておくと良いでしょう。くれぐれも、あせって感情的な対応をしないようにコントロールすることが必要です。
5|人気アニメのグッズによる炎上事例【2021年】
人気アニメの公式がダビデの星の腕章を連想させる商品を販売したとして、国内外から批判を浴びる事態がありました。
腕章は原作に登場し、ストーリー的には差別、迫害を丁寧に描いていたことから許容されていたものの、グッズ化してカジュアルに身に着けて良いものではないというのが、批判の大筋です。原作ファン、アニメファンからも非難の声があがりました。
公式は謝罪文を掲載し、商品の販売は取りやめとなりました。
効果的な対策
作品、商品化するグッズへの適切な理解が重要です。どのようなストーリーで描かれたものなのか、深く理解した上でグッズ化を考えなければいけません。
また、世界の歴史は複雑であり、民族的に許容できることとできないことがあります。過去には問題がなかったものの、時代とともにタブー視されていくケースも注意しなければならないでしょう。歴史的背景など多角的な視点でのチェック体制が必要です。
6|企業の人事担当者の投稿による炎上事例【2022年】
企業の人事担当者が個人的にSNSにアップしたコメントが炎上した例もあります。
発言は金銭面や待遇面で会社を選ぶ人とは働きたくないという趣旨のものでしたが、拡散されて議論を呼びました。人事担当者個人の意見であり、内容も賛否両論分かれるものでしたが、否定的意見のなかには「ブラック企業を想起させる」「給与にこだわることの何が悪いのか」などもあり、企業イメージに悪影響があったようです。
最近はSNSも人材確保のツールになっていることから、個人的な意見が炎上を招くのは避けたいところです。
効果的な対策
SNSにおける使用方法の研修をするとともに、発信内容の制限を加えることも大切です。個人で発信する場合には、企業名をプロフィールに掲載しないことも徹底させなければなりません。
人事担当の社員にSNSを活用させる場合には、活用の目的について改めて確認しておくと良いでしょう。
7|地方放送局の公式X (旧Twitter)での炎上事例【2022年】
ラジオ局社員が社の公式SNSを通じて、特定の政党を批判して炎上、懲戒解雇となる問題もありました。
社員は新聞の記事を引用しながら「〇〇党って要らないよね」というハッシュタグをつけ、地獄へ堕ちろなどと厳しい言葉で糾弾しました。
個人のアカウントと間違えて、権限を持っていた公式アカウントに投稿してしまったのですが、会社は正式に批判対象となっていた政党に謝罪するとともに、本人だけではなく、社長およびラジオ局担当役員も減棒になるなどの処分が下されました。放送に関する会社の社員が行ったことも、社会的な影響は大きかったようです。
効果的な対策
公式アカウントの権限を持つ社員を吟味することが大切です。簡単に広く権限を付与するのではなく、SNS担当者として職務にあたれる社員に限定する必要があります。
投稿までに内容のダブルチェックをする体制を徹底することも大切です。社員に対してSNSに関するコンプライアンス研修を繰り返し行わなければなりません。
8|回転寿司チェーンでの迷惑行為による炎上事例【2023年】
ある回転寿司チェーンでは、男性が湯飲みをなめたうえで、未使用の湯飲み置き場に戻したり、しょうゆのボトルの口をなめたりする行為を行いました。さらに、レーンを流れる商品に唾液をつけ、それらの様子を動画撮影したものがSNSで拡散され炎上しました。
店側が行ったことではありませんが、全国の店舗で客足が遠のき、親会社の株価が急落するという事態に発展しました。店側は迷惑行為を男性に損害賠償を求める訴えを起こしています。
効果的な対策
店内で起こる迷惑行為は、誰でも自由に食材や食器、調味料などに触れられる環境により発生しています。スタッフが監視できるのが理想ですが、来店客が多いときなどは、目が行き届かないこともあるでしょう。
対策としては調味料を個包装のものにしたり、食器類や箸などは個別にスタッフが提供したりする方法などが挙げられます。店内での動画撮影のルールを設定したり、監視カメラを強化したりするのも効果的です。迷惑行為を察知できるAIカメラの導入も良いでしょう。
9|カラオケ店での炎上事例【2023年】
全国に店舗を持つカラオケチェーン店で、除菌用のスプレー缶にライターで引火し、その様子を撮影するという迷惑行為がありました。撮影した動画はSNSを通じて広まりました。
カラオケチェーン店を傘下に持つ会社は、大事故につながりかねない危険な行為として警察に相談し、民事・刑事の両面で厳正な対処をするとしています。
また、同じチェーンの別の店舗ではソフトクリームを出す機器から直接、ソフトクリームを食べるという迷惑行為も発生し、動画が拡散されました。企業側は、全国の店舗で同様の機械の使用を停止し、洗浄する対応をとっています。
効果的な対策
カラオケボックスは人目につきにくい場所が多いため、迷惑行為につながりやすい傾向があります。また、盛り上げようとする気持ちが迷惑行為を誘発してしまうこともあるようです。
監視カメラの強化と同時に、設置していることを張り紙で提示することが一定の抑止力になると考えられます。さらに、迷惑行為に対する対応を明示しておくなども効果的でしょう。
コロナ禍で消毒用のアルコールスプレーなどを置いている店舗もありますが、スタッフが管理し、受付などから見えやすい位置に置くのも対策の一つです。
企業がSNSで炎上するリスク
SNSでの炎上は、企業にさまざまな不利益をもたらす可能性があります。主なリスクとして、以下の点が挙げられます。
- ブランドイメージの低下
炎上による批判が広がると、企業の信用やブランド価値が損なわれる - 売り上げの減少
消費者の不信感が高まることで、商品の購入やサービスの利用が敬遠される可能性がある。近年では、不買運動が起こるリスクも指摘されている - 人材不足
企業の評判が悪化すると、採用活動に影響し、優秀な人材の確保が難しくなる可能性がある - デジタルタトゥー
一度炎上した内容はインターネット上に残り続け、長期的に企業の評判に影響を与える可能性がある。また、類似の問題が発生するたびに過去の炎上が掘り起こされ、再び批判の対象となることもある
SNSの炎上は、一時的な問題ではなく、企業の長期的なイメージや売上に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、SNSだけの問題と捉えず、適切な対策を講じることが重要です。
企業におけるSNSのリスクについて詳しく解説しています。
SNSによる企業のリスクとは?危険性・事例・対策方法を解説
企業アカウントで有効なSNSの炎上対策
炎上は一度起きると、鎮火をさせるのは難しいものです。炎上しないような防止策をとっておかなければなりません。防止策について見ていきましょう。
社内での教育・研修
従業員全員に対して教育・研修の機会を設ける必要があります。SNSの炎上リスクや発信の基本的な姿勢、方向性などを教育するようにします。
教育・研修のなかでは各SNSのガイドラインを押さえて周知しておくのも良いでしょう。例えばX (旧Twitter)のガイドラインには「暴力をほのめかす脅迫」や「グロテスク投稿」「個人情報の公開」などさまざまなものがあります。それらに抵触しないような指導が必要です。
■参考:Xルール
炎上事例の継続的な収集・分析
炎上が発生した際には、炎上の内容を迅速かつ正確に把握・分析し、それに対する対策を立てることが重要です。それには、過去の事例を収集し、炎上の原因や影響、どのような対応が効果を出したかを分析することで、いざというときのリスク管理に生かせます。特に同業他社に起きた事例は、漏れなく収集しておくと良いでしょう。
炎上の原因は時代背景や社会の価値観の変化によって異なるため、継続的にトレンドを把握することも欠かせません。SNSの動向を注視し、炎上の兆候をいち早く察知して事前に対策を講じることが望ましいでしょう。
運用マニュアル・ガイドラインの策定
運用マニュアルを作成し、厳守することで炎上リスクをかなり回避できます。また、運用マニュアルは複数人で確認・管理する体制を整えることが重要です。
ユーザーを不快にさせない基本的な発信のルールはもちろん「ステルスマーケティングを回避するため」「薬機法・景品表示法違反を回避するため」など、自社の商材に合った具体的なルールを設定しておくことも重要です。
運用マニュアルには、以下を含めるようにしてください。
- 企業アカウントを運用する端末でプライベートアカウントを操作しない
- 批判的なアカウントに対しては反論しない
- 投稿前にダブルチェックを行う
- 政治や宗教などデリケートなテーマは特に注意をする
さらに、炎上しやすいワードを一覧にまとめておくのもおすすめです。
セキュリティの強化
企業アカウントが乗っ取られ、不適切な投稿が行われたり、情報が流出したりするケースもあります。一度乗っ取られると、復旧までに時間がかかるうえ、失われた信頼の回復にも時間を要します。乗っ取りの主な手口としては、メールアドレスやパスワードを取得し、不正ログインを行う方法があり注意が必要です。
対策としては以下のような方法があります。
- 不審なメールやリンクを開かない
- アカウントのパスワードを複雑に設定し、定期的に変更する
- 多要素認証を設定し、セキュリティを強化する
- セキュリティソフトを活用し、対策を強化する
また、乗っ取りに気づいたら速やかに公式サイトなどで、状況を説明することも重要です。
緊急対応フローの策定
炎上につながってしまう原因に対応の遅さがあります。トラブル時やリスク察知時にスムーズな連携が取れないと対応が遅れ、結果として炎上してしまうこともあります。
そこで、緊急対応フローを策定しておけば、トラブル時に迅速な対応が可能です。また、スタッフの混乱も回避できるため、誤った対応をとるリスクも軽減できます。たとえば、関係部署の連絡網や連絡方法、担当者と連絡が取れない時の対応方法、各部署の役割などを定めておくと良いでしょう。
炎上の防災訓練の実施
緊急対応フローを策定してもスムーズにいくとは限りません。そこで、定期的にSNS炎上対策のための防災訓練を実施し、緊急時に慣れることが大切です。また、実施する中で不備がないか確認することで、今後の対策強化につなげられます。
訓練を行うことで従業員の意識や課題が見えてくるため、研修内容や運用マニュアルなどにも反映できます。特に、アルバイトが多い職場や従業員の入れ替わりが多い企業では、定期的な防災訓練が炎上回避につながるでしょう。
トラブル発生後の要因分析と改善施策の実施
業務でトラブルが発生した際、原因を特定せずに放置したままでいると、同様の問題が繰り返され、やがて炎上へと発展する可能性があります。たとえ小さなトラブルであっても、適切に要因を分析し、早期に対策を講じることが重要です。
例えば、顧客対応に関するトラブルが発生した場合、対応方法のどこに問題があったのかを明確にし、接客マニュアルの見直しや改善を行う必要があります。対応の仕方一つで企業の信頼度が大きく左右されるため、適切な改善策を講じることが求められます。
トラブルの原因を正確に突き止め、迅速かつ的確な対応を行うことで、より良い運用体制を構築し、リスクの最小化につなげることができます。
ソーシャルリスニングツールの導入
炎上が起きていないかを監視し速やかな対応をするには、ソーシャルリスニングツールの導入も考えたいところです。
ソーシャルリスニングツールとは、X (旧Twitter)やInstagramなどのSNSや掲示板、ブログで発信されたものを収集、分析し、マーケティングに役立てるためのツールです。オンライン上の動向を常に調査しているので、炎上の察知に役立ちます。大量の投稿をリアルタイムに収集・分析でき、トラブルの火種を察知できるのです。アラート機能を備えるツールであれば、より炎上への迅速な対応が可能となります。
24時間の監視体制は運用担当者の負担を大きくするものですが、ソーシャルリスニングツールを導入すれば、作業の軽減ができます。
企業に起こりやすい炎上の内容やリスク管理についてはこちらでも解説しています。
炎上対策とは?企業における主な炎上原因と対策
SNSを活用したマーケティング手法「ソーシャルリスニング」について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
ソーシャルリスニングとは|意味や分析方法の解説と導入事例を紹介!
企業がSNSで炎上するまでの流れ
SNSで炎上する場合、多くは以下のような経過をたどります。
- 投稿
- ユーザーが発見
- 拡散
- ネットニュースやまとめサイトへの掲載
- サジェストへの表示
- テレビや新聞などのメディアに掲載
- さらなる拡散と批判
多くの場合、上記の流れは炎上元となる投稿がされてから24時間以内に起こります。一度オンライン上に掲載されたものは、どんどん拡散されていくものですが、時間が経つほどに元の投稿や前後の文脈は見ないまま、ネットニュースやまとめサイトを読んだだけの批判も雪だるま式に増えていきます。
対応が遅ければさらに拡散と批判が繰り返されていくので、早期発見と的確な対応が重要です。
次項で効果的な対応方法を紹介します。
SNSの炎上対応を成功させる方法
炎上した場合の対処には「迅速な原因究明、初期対応」「関係各所との情報共有」そして「真摯な姿勢、拡散防止」が必要です。それぞれのポイントについて見ていきましょう。
1|迅速な原因究明
炎上が起きていることを早期発見するとともに、炎上の原因を正確に把握し、適切な対応策を練ることが重要です。
原因が分からない状態で説明をしないまま投稿を削除してしまうと、むしろユーザーの気持ちを逆なで、悪手になってしまう場合があります。炎上原因の投稿は誰かがスクリーンショットなどを保存しているため、慌てて削除することで、さらに拡散されていく可能性があります。
まずは、早期発見および原因究明が重要です。そのうえで迅速な初動によって、拡散や事態の悪化を最低限に押さえなければなりません。
2|ステークホルダーとの共有と方向性の決定
炎上をすると関係各所にも多大な迷惑をかけるため、社内の従業員や取引先、株主、顧客など、ステークホルダーに状況を共有した上で、対応の方向性を協議して計画的に対処することが重要となります。
対応を決める際は法的な側面だけでなく、ネット上におけるユーザーの論調も確認し、世間とのズレが生じないように注意しなければなりません。
炎上はいつ起こるか分からず、各ステークホルダーと十分な協議ができない時間に発生する可能性もあります。社内マニュアルを作成・共有しておき、いざという場合はまず、ガイドラインに沿って進めていくようにしましょう。
3|真摯な対応
ステークホルダーに対しても、ユーザーに対しても一貫性のある誠実な対応をすることが重要です。
対応に一貫性がないと不信感を抱かれる可能性があるので、社内で発信する内容を取り決め、周知したうえで一貫性のある対応をするようにしましょう。
謝罪に踏み切る場合は謝罪に徹し、拡散防止につなげることも大切です。言い訳、逆切れととられないようにしなければなりません。複数のメディアで経緯の説明、謝罪、対策方法、今後の対応の報告などを行うと効果的です。
最近ではSNSユーザーから過去に発生し類似の炎上事例に言及し、「反省がない」「学びがない」などの論調で炎上が更に拡散するケースも増えています。
過去の炎上を参考にすることも炎上対策に有効です。炎上レポートを季刊で発行しているので、こちらもご利用ください。
ソーシャルリスクレポート
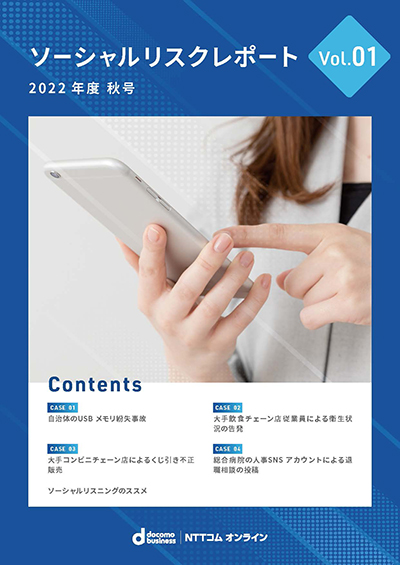
炎上したときのSNSユーザーの論調として、「過去にも類似の投稿で炎上したのに...」や「xxでは同様の投稿を行った際に適切な対応だったのに」というふうに同様のケースを参考にするいわば炎上慣れのような状態になってきています。
このため、過去の炎上ケースから、収束や称賛に至ったケースをあらかじめ知っておくことが重要です。
投稿が炎上に至ったケースをソーシャルリスクレポートとしてまとめています。ぜひご一読ください。
\リスクレポートを無料公開/
入力1分!資料ダウンロード炎上事例のような事態を防ぐには「Buzz Finder」
ソーシャルリスニングツールで炎上を防ぐためには「Buzz Finder」がおすすめです。
Bizz FinderはX (旧Twitter)公式全量データから投稿をリアルタイムに収集し、SNS上で何が起きているかを即時に把握できます。多彩なメディアの投稿分析によりマーケティングにも有効活用できるツールです。さらに、自社のブランド名をキーワード指定し、分析目的ごとに情報を収集、ユーザーのトレンド調査を可能とします。
また、ツイート急増検知機能があり、風評被害や炎上でツイート数が急増した場合に素早く察知し、アラートメールで教えてくれます。炎上になりつつある段階で、社内スタッフや電話オペレーターへ炎上に関する情報を共有し素早く対応することで、大きく企業イメージを損なう事態を避けられます。
導入事例|情報通信サービス業 様
ある情報通信サービス業様の広報部門では、ネット炎上時にSNSの声をふまえた上で適切なメディア対応に備えたいと思っていました。また、顧客サービス部門はSNSの声をサービス改善に活かしたいと考え、お客様センターは炎上やトラブルの入電影響を事前に把握したいと考えていました。
そこで、Buzz Finderを導入したところ、広報部門はリスク発生時、迅速に通知とレポートを受けることで的確な対応が可能となり、顧客サービス部門はSNSの声を共有することで改善意識が向上する効果がありました。また、お客様センターはSNSの反応を日報で定点把握したことで、対応力が強化されたようです。
企業のSNS運用には炎上対策が欠かせない
企業にとってSNSの炎上は、一度起こると事態の収集が難しく、企業イメージを大きく損なう場合もあります。今回、炎上事例をご紹介しましたが、似たような事例はまだまだ多くあるので、内容を調査し、同じことがないように事前に対策を練っておくことが大切です。従業員への教育・研修、マニュアル作りも必要ですが、ソーシャルリスニングツールを活用し、自社や自社ブランドに関するSNS上の調査を常に行っておくこともおすすめします。
X (旧Twitter)上で起きていることをいち早く察知し、早期対策を立て炎上を防止したい方は、「Buzz Finder」をご検討ください。
Buzz Finderでは様々ある機能をお試しいただくために無料トライアルをご用意しています!
お気軽にご利用ください。
関連記事

2022/01/07

2021/10/11