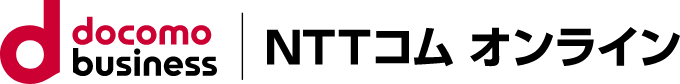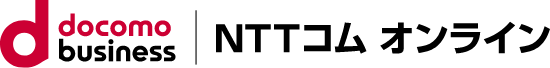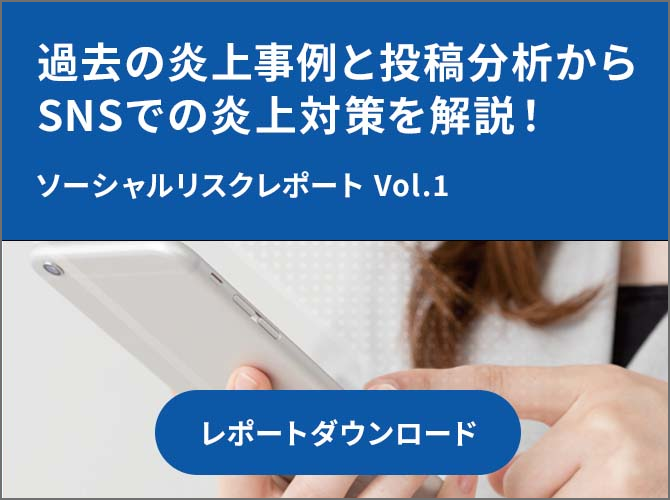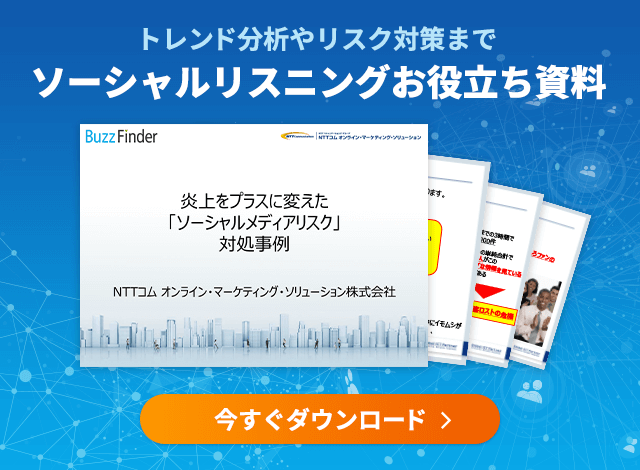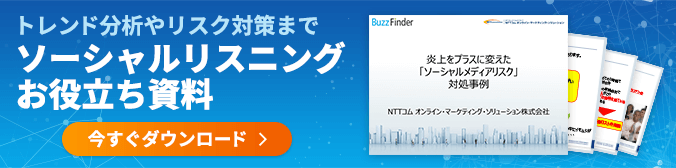2023/12/18
ソーシャルリスク対策
会社が社員のSNSを監視するのは問題?正しく監視する方法を解説
昨今では、SNSでの炎上が大きな注目を集めるようになりました。企業の従業員による投稿が原因で炎上するケースも多く、自社の社員も同じような事件を起こさないか心配している担当者様も多いかもしれません。しかし、対策をとるにしても「会社が社員のSNS利用を監視しても問題はないのだろうか」と疑問が生じるのではないでしょうか。
本記事では、会社が社員のSNSを監視するのは問題ないのか、監視するにはどのような方法があるのか、SNS利用を監視せずに安全性を高める方法などを解説します。社員によるSNSでの炎上を回避し、ソーシャルリスクを減らしたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
- 会社が社員のSNSを監視する目的には、公式アカウントの炎上を防止する場合と社員個人のアカウントでの炎上を防止する場合の2種類がある
- 会社が社員のSNS利用を禁止するのは法律的に問題だが、社内での利用禁止や許可制など、業務に影響をおよぼす範囲で一部制限を設けるのは認められている
- 社内でSNSのガイドラインを作成する、実際にあった炎上事例を共有するなど、監視をせずに安全性を高める方法もある
- ソーシャルリスクへの対策には、SNS上の投稿収集・分析ツールを利用したソーシャルリスニングが効果的
SNS監視についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
「SNS監視の重要性と具体的な4つの方法・炎上対策や対処法も解説(社員ではなくSNS投稿の中に潜むリスクを監視する内容)」
会社が社員のSNSを監視する2つの目的
会社が社員のSNSを監視する目的は、大きく次の2つです。
- 会社アカウントでの不適切な投稿を防止する
- 個人アカウントでの不適切な投稿を防止する
それぞれの目的について詳しく解説していきます。
会社アカウントでの不適切な投稿を防止する
会社が公式に運用しているSNSアカウントでのトラブルを防止するための監視です。スマホが普及した現代社会において、企業のSNS運用は低コストで効果の高いマーケティング手法になりました。会社で公式のアカウントを作り、広報担当などの社員が情報発信を行うケースが増加しています。しかし、社員の投稿内容に問題があり、炎上につながるケースも多発しているため注意が必要です。
過去には、人事担当者が「給与で会社を選ぶ人」を批判するような内容を投稿したケースや、不動産サイトの公式アカウントが「社畜」といった不適切なワードを投稿して炎上を起こした事例などがありました。このようなトラブルを未然に防ぐため、SNS監視の重要性が高まっています。
個人アカウントでの不適切な投稿を防止する
もう一方の目的は、個人アカウントの発言が原因で会社が炎上するのを防止するための監視です。社員もプライベートなアカウントだと、つい会社のイメージダウンや機密情報の漏洩につながる発言をしてしまう可能性があります。しかし、個人の発信であっても、所属する企業が判明すれば、会社も一緒に炎上してしまうため危険です。
また、過去には個人アカウントに投稿するつもりだった内容を誤って公式アカウントで発信してしまったために炎上するケースもありました。個人アカウントであっても普段から不適切な投稿は避けなければなりません。
ただ、リスクヘッジのためには監視が必要とはいえ、個人のSNS利用を会社がどこまで制限できるかは難しいところです。
個人のアカウントは監視してよいのか
まず前提として、社員のSNSを完全に禁止するのは私生活への不当な介入とみなされて、違法行為になる恐れがあるため避けたほうが良いでしょう。監視する場合でも、方法によっては不当な介入にあたるとみなされる可能性があるので注意してください。
しかし、SNSの発信内容が炎上した場合、企業に与える影響は大きく、リスクを抑えるためには何らかの対策が必要です。
以下のように、業務にとって必要性のある範囲で合理性があるとみなされる内容なら認められるケースがあります。
- 業務に支障があるため勤務中の利用を禁止する
- 会社の戦略や業績、商品・サービス、顧客情報を漏らすような投稿は行わない
監視を行う際は、単なるルールの押し付けにならないよう注意しましょう。社員のプライベートを管理する意味合いはなく、会社のリスクマネジメントであると伝えて納得してもらうことが大切です。
会社の社員が利用するSNSを監視する方法
社員が個人的に利用しているSNSを監視するには、主に次の3種類の方法があります。
- SNSの利用に許可や届け出を求める
- 社内でのSNS利用を禁止する
- 個人の発信であると明記してもらう
それぞれの具体的な方法について解説します。
SNSの利用に許可や届け出を求める
1つ目は、社員のSNS利用に許可や届出を求める方法です。スマホやSNSが普及した現代では、すでに多くの人がアカウントをもっているため、今から全面禁止にするのは難しく、法律的にも問題があります。そこで、社員にアカウントを提出してもらい、定期的に投稿内容を確認できるようにしておきます。
実名登録が一般的とされるFacebookのようなSNSでは、会社名の記載を許可制にする方法もあります。社員には、投稿内容やプライベートには干渉せず、あくまでもリスクの高い発信になっていないか確認するのが目的であると伝えてください。不適切な発信を防止すれば、社員自身を炎上などのリスクから守れると理解してもらいましょう。
社内でのSNS利用を禁止する
2つ目は、社内でのSNS利用を禁止する方法です。勤務中にSNSを利用していると、情報漏洩などの問題につながる可能性があります。SNSの禁止は違法行為に当たるのでは、と思われるかもしれません。しかし、会社は施設の秩序を保つ権利である「施設管理権」を有しており、業務に支障をきたす恐れがある場合には一定の制限が可能です。
また、社員には業務中は仕事に専念する「職務専念義務」があります。この義務を理由として、社内からのSNS利用を禁止したり、業務用端末からのアクセスをブロックしたりするといった方法も考えられるでしょう。
個人の発信であると明記してもらう
3つ目は、発信内容が個人のものであると明記してもらう方法です。炎上のなかには、個人アカウントの発信が会社の公式見解だと誤解されてしまったのが原因のケースもあります。
不適切な投稿や誤解を招く表現はなるべく避けるべきですが、社員にもSNSで自分の意見を発信する自由があるため完全な規制はできません。そのため、投稿の際は、個人の意見や考えであるとわかるように明記してもらうよう伝えてください。
会社の社員のSNS利用を監視せずに安全性を高める方法
企業が直接アカウントを監視する方法のほかにも、以下のように、社員のSNS利用時に安全性を高められる方法があります。
- SNSガイドラインを設ける
- 監視体制を強化する
- SNS発信での炎上事例を共有する
- ソーシャルリスニングを実施する
監視に比べて実施へのハードルが低い方法が多いので、まずはこちらから試してみると良いでしょう。
SNSガイドラインを設ける
社内でSNS利用に関するガイドラインを作成する方法です。SNS禁止は現実的ではないため、リスクを抑えられるガイドラインを設けて社員に遵守してもらいます。リスクとなる発信を明確に提示・教育していけば、社員自身のリテラシーが育ち、自分で正しい判断ができるようになります。昨今ではバイトテロなども頻繁に起きているため、社員だけでなく、アルバイトやパート等、すべての従業員を対象にしておくのが重要です。
ガイドラインの具体的な内容としては、以下の項目を盛り込みましょう。
- 会社の機密情報保護
- 顧客・取引先の情報保護
- 誹謗中傷の禁止
- 自社情報の発信に関するルール
- 著作権や肖像権など第三者の権利保護
- 真偽不明情報の発信禁止
- ステルスマーケティング禁止など透明性の確保
最近では、SNSガイドラインを公式サイトで公開している会社も増えており、企業のイメージアップにつながっています。
企業の炎上対策についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
「炎上対策とは?企業における主な炎上原因と対策」
社内の体制を強化する
社員のSNS投稿を直接監視するのではなく、社内における監視体制を強化して、事前に炎上リスクを排除できるようにする方法です。具体的には、次のようなやり方があります。
- SNSやインターネット対策の専門部署を設置する
- 専門家に相談・依頼する
ガイドラインを作成した後は、e-ラーニングや研修を使って従業員の教育を進めていくのが有効です。
監視体制が強化されると反発を覚える社員も出てくる可能性があり、進め方には一定の注意が必要です。しかし、会社がSNSでの炎上対策に本気で取り組んでいる姿勢を見せられるため、社員の意識が変化する可能性もあるでしょう。
SNS発信での炎上事例を共有する
社内でSNS発信の炎上事例を共有し、社員を啓蒙していく方法です。ネット上の炎上はユーザーに知識やリテラシーが欠けていたため起きてしまったケースもあります。SNSがどのように炎上するか知っておけば、リスクを抑えられるようになるでしょう。
SNSの炎上事例は数多く存在しているため、定期的に最近起こった事例などを共有し、具体的な理由や考えられる防止策などを話し合う機会を設けるのが効果的です。共有を繰り返していけば、社員のなかでSNS炎上に対する知見が深まるとともに、自身の発信にも気を使うようになるはずです。
SNSにおける企業の炎上事例について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
「SNSにおける企業の炎上事例7選|炎上の対処法・事前対策を紹介」
ソーシャルリスニングを実施する
ソーシャルリスニングを使い、SNS上で問題が起きていないかチェックする方法です。SNSやブログなど、ソーシャルメディアのユーザー投稿や口コミなどを収集・分析するマーケティング手法を「ソーシャルリスニング」といいます。商品開発やユーザー・社員の発信による炎上リスク対策として活用されている手法です。
ソーシャルリスニングを使って、以下のように自社関連のキーワードを単体、もしくは組み合わせて収集・分析し、不適切な投稿や炎上がないかを調べられます。
監視するキーワードの例
- 会社名:正式名称や略称、愛称、アルファベットなど
- 商品・サービス名:新商品の発売などは投稿数が増えるため特に注意
- 社長・社員の個人名:特にメディアへの露出経験のある社員や広報・人事など外部と関わる社員
- 業界に関するキーワード:食品なら「異物混入」など、業界と関わりの深いワード
導入の際は、監視や緊急時のアラートを自動化できるソーシャルリスニングツールの利用もおすすめです。対応するSNSメディアやアラート機能、分析機能などを比較検討して自社に合うものを導入しましょう。
ソーシャルリスニングについて、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
「ソーシャルリスニングとは|意味や分析方法の解説と導入事例を紹介!」
会社のリスクを抑えるSNS監視には「Buzz Finder」
「Buzz Finder」は、企業が炎上対策やリスクマネジメントを行うのに最適なソーシャルリスニングツールです。導入すれば、顧客の声(VOC)を活かしながら炎上などのリスクを回避できます。
「Buzz Finder」は業界最速水準でX(旧Twitter)公式全量データのうち、直近の投稿をリアルタイムで収集できます。キーワード収集時のノイズ除去機能も備えており、精度の高いソーシャルリスニングが可能です。
収集した投稿はタイムリーに分析され、日報によってポスト量やトレンドを知らせてくれます。さらに、ポストが急増した場合に自動通知されるアラートメール機能も備えており、炎上などのリスクが生じても迅速な把握と対応が可能です。X(旧Twitter)のほかにInstagramやFacebookなど、多様なSNS・メディアでの情報抽出・分析サポート機能が充実しています。
会社によるSNS監視は社員の理解も必要
ソーシャルリスクやSNSでの炎上が問題視される昨今、会社による社員のSNS監視にも注目が集まっています。しかし、社員には個人としてSNSを利用する自由もあるため、会社が一方的に禁止するのは法律的に問題です。
SNSでの炎上を避けるには、ソーシャルリスニングを活用して迅速に対応できる体制を整えましょう。同時に、社内でガイドラインを作成したり、研修を行ったりするなど、社員1人ひとりが主体的にリスクを回避するように意識を変えていく必要もあります。
SNS炎上を回避するソーシャルリスニングに最適な「Buzz Finder」の資料請求と無料トライアルはこちらから
関連記事

2022/01/07

2021/10/11