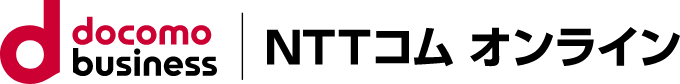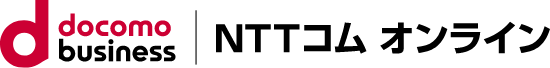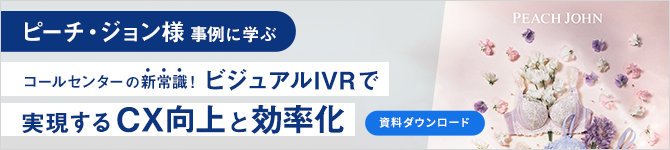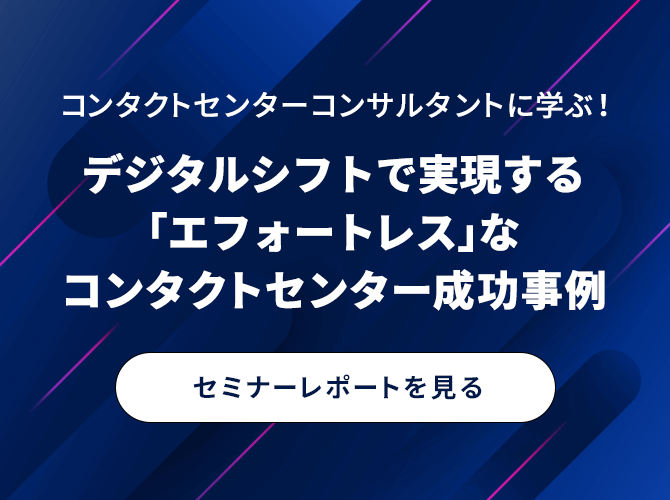更新日:2024/09/26(公開日:2021/07/28)
ビジュアルIVR
あふれ呼とは?対策を行うメリットと7つの対策法、事例を解説
コールセンターは顧客と企業が直に接する数少ない機会のひとつのため、コールセンターでの対応がそのまま企業やブランドのイメージに直結することが珍しくありません。コールセンターにおいて顧客満足や企業イメージに影響を与える要素のひとつが「あふれ呼」です。あふれ呼とは一体どのような現象なのでしょうか。ここではあふれ呼の問題点や発生原因を明確にするとともに、具体的な7つの対策方法を解説します。また、実際にあふれ呼を減らすことに成功した企業の事例も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
- あふれ呼とは、電話の回線数を上回る数の入電が原因となり、対応オペレーターとつながらない状態のこと
- あふれ呼が発生すると、応答率が低下したり、企業イメージ・信頼の低下につながったりする問題がある
- あふれ呼対策を行うことで、顧客満足度の向上、売上アップ、オペレーターの負担軽減といったメリットが期待できる
- あふれ呼対策にはオペレーターの増員やパフォーマンス向上、ビジュアルIVRの導入などが効果的

コンタクトセンターの実現方法
をご紹介!
「オペレーターの人材不足」「電話対応による限界」
「アンケート回収率の低下」などを解決する
SMSソリューションをご紹介します。
あふれ呼とは
コールセンターでよく使われる用語に「あふれ呼(あふれこ)」や「待ち呼(まちこ)」といったものがありますが、これらは一体どのような意味で使われているのでしょうか。
あふれ呼は何の略?意味や使い方
「あふれ呼」とは、電話の回線数を上回る数の入電が原因となり、対応オペレーターとつながらない状態を指します。電話への対応ができずに「あふれてしまっている状態」であることから、このような呼び名が付いています。具体的な場面だと、消費者があるサービスについて企業のコールセンターに電話をした際に「ただいま電話が大変混みあっております。しばらくお待ちください。」という音声ガイダンスが流れることがありますが、これもあふれ呼の状態です。
後ほど詳しく解説しますが、あふれ呼になる原因にはさまざまなものがあります。たとえば商品を販売する企業が期間限定のセールを開始したり雑誌や新聞などメディアへの露出が増えたりした場合には、一時的に電話が殺到するためあふれ呼が発生しやすくなります。このようなポジティブな内容だけでなく、製品のリコールが発生するなどネガティブな内容も顧客からの問い合わせが増える原因のひとつです。
原因は何であれコールセンターにつながりにくい(またはつながらない)状態というのは顧客にとって不便なだけでなく、企業側にとってもデメリットは多いと言えます。なぜなら電話がつながらないことによって顧客の満足度が下がり、結果として企業やブランドのイメージを悪化させることになりかねないからです。顧客満足を実現し企業のイメージアップにつなげるためにも、あふれ呼への対策は必要不可欠です。
待ち呼の意味と使い方
待ち呼はあふれ呼と同じ意味の言葉で、別名「待機呼(たいきこ)」とも呼ばれます。通常コールセンターでは「どれだけの顧客が対応待ちをしているか」をオペレーターに知らせるために、待機している顧客の人数や待機時間などを表示しています。この表示を見てオペレーターどうしが「現在待ち呼が何人いる」という使い方をするのが一般的な使い方です。
そもそもあふれ呼の「呼」とは何のこと?呼量とは?
あふれ呼や待ち呼に使われている「呼(こ)」ですが、これは電話のコールを意味しています。ただ単に電話がかかってくる「呼び出し」だけを指すのではなく、オペレーターから電話をかけることや実際に通話することも含まれます。つまり呼とは、電話が通話の相手につながってから切るまでを表したものです。
コールセンターにおける業務改善の指標とするために呼が使われる場面があります。それが「呼量(こりょう)」です。呼量とは簡単に言うと「1時間あたりにどれだけ電話を使用しているか」を表し、「呼の回数×呼の平均利用時間÷測定時間」によって求められます。呼量の単位はアーランを用います。
たとえばあるコールセンターの1時間あたりの呼数(電話の回数)が100回で、呼の平均利用時間(電話の時間)が3分だったとした場合、呼量は100回×180秒(3分)÷3600秒(1時間)=5アーランとなります。この呼量をさまざまな時間帯や曜日などで計測をし、分析をすることで業務改善などに役立てます。
あふれ呼の問題点

あふれ呼が発生することで顧客だけでなく企業側にもさまざまな問題が起こります。コールセンター機能を持つ企業はこれらの問題点を放置せず、いち早く対策することが大切です。
待ち呼や放棄呼に繋がる
あふれ呼が発生すると待ち呼が生まれるだけではなく、「放棄呼(ほうきこ)」という次なる問題が起こります。放棄呼とはその名のとおり「放棄された呼」のことで、コールセンターにつながらないことが原因で顧客が待機途中で電話を切る、もしくはコールセンターのシステム側で強制的に遮断してしまうことを表す言葉です。放棄呼は別名「アバンダンコール」とも呼ばれます。この放棄呼は電話のつながりやすさを表す指標としてコールセンターの中でも重要視されているものですが、放棄呼が多く発生しているのであれば問題です。
応答率が低下する
あふれ呼が増えると問題になるのが「応答率」の低下です。応答率とは電話の着信数に対してオペレーターがどれだけの割合で対応できたかを表すもので、「応答数÷着信数×100」で求められます。応答率はコールセンターへ問い合わせをする顧客の満足度を表すひとつの指標にもなります。なぜなら応答率が低ければそれだけ顧客の問題解決が後回しになっているということだからです。先ほどの放棄呼は少なければそれだけ顧客満足度は上がりますが、応答率は低いと顧客満足度の低下につながります。その意味で放棄呼と応答率は対の関係にあると言えるでしょう。
企業イメージ・信頼の低下につながる
顧客を電話の先で長時間待たせてしまうというのは、コールセンターだけでなく企業そのものに対するイメージや信頼を低下させる原因につながります。電話がつながらないと顧客は「自分が軽く扱われているのではないか」と不信感を感じるだけでなく、商品やサービス購入後のアフターサービスにも不安を感じるかもしれません。「もし商品に何かあったときも同じように待たされるのではないか」と顧客に思われてしまっては、せっかくの販売のチャンスを逃してしまうリスクもあるのです。また電話を長時間待たされたことに怒りを感じ、クレームを言ってくる顧客も現れるでしょう。このようにあふれ呼は、本来なかったはずの新たなクレームを生み出す可能性があります。
機会損失を生み出す
コールセンターの業務は、既存顧客からの問い合わせ対応だけにとどまりません。これから新たに商品の購入やサービスへの入会を検討している見込み客からの問い合わせも含まれます。消費者の中には、商品やサービスを購入する前に疑問点を解決したいという人が少なくありません。そのような見込み客がコールセンターに問い合わせの電話をした際に、つながらずあふれ呼になってしまったらどのように感じるでしょう。辛抱強い人なら何度もつながるまで待ち続けてくれるかもしれませんが、商品の購入を断念してしまう人が現れても不思議ではありません。
オペレーターのモチベーション低下・離職率の向上
あふれ呼が多くなると増えてくるのが顧客からのクレームです。オペレーターが電話をつないだ途端に、長時間待たされたことに対する怒りをぶつけてくる顧客も少なくないかもしれません。このような頭ごなしのクレームをぶつけられると、オペレーターは精神的な負担が大きくなり、モチベーションが低下するリスクが高くなります。オペレーターのモチベーションが低下すると顧客への対応に悪い影響が出るばかりか、離職を考えるオペレーターが出てくる可能性も考えられます。離職率が高くなると新たに求人広告を出してオペレーターの募集をして人員の補充をしなければいけませんし、コールセンターが新人ばかりになると全体のサービス低下にもつながりかねません。
あふれ呼が発生する原因
このようにさまざまな問題が起こり得るあふれ呼ですが、あふれ呼が発生することにはいくつかの原因があります。ここからはあふれ呼の原因となる事象を紹介します。
曜日やイベントなどの理由で入電が多くなる
コールセンターでは休日明けの月曜日などは電話が多くなる傾向があります。また一日の間でもお昼の時間帯は電話が増えがちです。このようにあるタイミングで顧客からの問い合わせが一時的に多くなることがあり、その結果あふれ呼が発生しやすくなります。また期間限定のキャンペーンを開催したり新商品の予約販売を開始したりといったイベント直後にも、一時的にあふれ呼が増える傾向にあります。
このような場合は一時的にオペレーターを増やすことで対応できるかもしれませんが、通常時に戻るとオペレーターが余ってしまうことになるので、単に人を増やせばよいという問題ではありません。
FAQが使いづらい
FAQとは企業のホームページなどに掲載されている「よくある質問」のことですが、これが顧客にとってわかりづらいものであると問い合わせの電話が増え、結果としてあふれ呼が発生しやすくなります。FAQは顧客がコールセンターに問い合わせをしなくてもいいようにあらかじめよくある質問をQ&A方式でまとめたもので、コールセンターの業務軽減には非常に役立つツールです。しかしFAQがなかったり使いづらいものだったりすると、コールセンターへの問い合わせが減ることはありません。
関連記事:FAQを作成するメリットと作り方の手順・ポイントを解説
コールセンターのリソースに問題がある
たとえばコールセンターに電話以外の問い合わせ手段がないとすると、当然顧客からの電話が多くなり対応しきれなくなります。もし電話以外に問い合わせ方法がないのであれば、メール問い合わせやチャットシステムの導入、FAQの活用、IVR(自動音声応答システム)の導入など、コールセンター内のリソースにテコ入れをすることであふれ呼対策になります。
またオペレーターの数が足りていないことも、あふれ呼が発生する原因のひとつです。各種イベントの開催や曜日、時間帯等に合わせて適切な数のオペレーターを配置しなければ、あふれ呼が増えてしまいます。しかし先ほども述べたように、ただ単に人を増やせばよいというわけではありません。人だけでなくシステムの導入などコールセンター業務の改善につながるあらゆるリソースを見直す必要があるのです。
IVRの問題
すでにIVR(自動音声応答システム)を導入しているコールセンターでも、IVR自身に問題があることであふれ呼が発生することがあります。例えばIVRの音声ガイダンスによる誘導が紛らわしかったり無駄に自動音声が長かったりすると、かえってあふれ呼が増えてしまう可能性があるのです。またIVRの問題が起因となって顧客のストレスが増えてしまい、クレーム発生の原因になってしまうこともあります。IVRを導入する際には、「顧客にとって役立つものか」「自社に合っているものか」を慎重に検討しなければなりません。
あふれ呼対策を行うメリット
ここまで紹介したように、あふれ呼はさまざまな問題を生み出します。そのため、企業があふれ呼対策を行うことは重要であり、主に次のようなメリットがあります。
- 顧客満足度の向上
- 売上アップ
- オペレーターの負担軽減
まず、顧客にとってストレスとなる電話がつながらないことや長時間の待ち時間を解消することによって、顧客満足度の向上につながります。スムーズな対応を受けられればリピートにつながりやすくなり、売上アップも期待できるでしょう。既存顧客だけでなく見込み顧客の機会損失も減り、購入につながりやすくなります。
また、あふれ呼が減ればクレームも減り、対応するオペレーターの負担を軽減できることもメリットです。オペレーターの心理的ストレスが減ることで、離職率の低下も期待できます。
あふれ呼への7つの対策方法

ここからは具体的なあふれ呼への対策方法を解説します。
オペレーターのパフォーマンスを上げる・増員する
あふれ呼対策として、すぐに着手できる方法はオペレーターのパフォーマンスを向上させることです。顧客との通話や後処理にかかる時間を短縮できれば、より多くの顧客への対応が可能になります。KPIを設定し、オペレーターに意識してもらうとよいでしょう。
具体的には、オペレーターが顧客からの問い合わせを処理する時間の平均を表すAHT(Average Handling Time)の指標を設定すると効果的です。まずは現状のAHTを確認し、どこを短縮・改善できるか検討してみてください。
また、オペレーターを増員することもあふれ呼対策になります。ただし、やみくもに増員すると無駄なコストを増やしてしまうことになるため注意しましょう。AHTや1時間あたりのコール数、サービスレベル目標などを考慮し、適正なオペレーター数を算出することがおすすめです。
関連記事:コールセンターのKPIとは?KPIの重要性と種類をご紹介
ワークフォース・マネジメントを導入する
適切な人員配置を考えるうえで、効果的なのがワークフォース・マネジメントの導入です。ワークフォース・マネジメントとは、サービス品質を向上させながら人員配置・活用の最適化を図るマネジメント手法のことを指します。
少ない人数でより多くの成果をあげるために、業務量に合わせて適切な人員配置を行います。具体的には入電数を曜日・時間ごとに記録して業務量の傾向を算出し、効果的なオペレーターの配置を検討します。さらにオペレーターのシフト管理やスキルマネジメントまで細かく把握し、最適化することも重要です。これらのマネジメントを行うことで、あふれ呼を減らし、コールセンター全体の生産性を向上させることができます。
アウトソーシングを利用する
イベントの開催など一時的に顧客からの問い合わせが増えそうな場合には、アウトソーシングを利用することであふれ呼を防ぐことができます。たとえばあふれ呼が発生したタイミングに合わせてアウトソーシング先へ転送できれば、顧客を待たせることがなくなります。しかしアウトソーシングは一時的な解決方法で、自社のコールセンターの根本的な業務改善にはつながらないかもしれません。
チャットシステムを導入する
電話以外の問い合わせ窓口としてAIによるチャットシステムを導入するのは、あふれ呼への対策には有効です。チャットシステムを導入することで顧客からの問い合わせに対してAIが自動回答してくれるので、業務時間外でも24時間対応することが可能になります。また休日中に顧客の疑問の一部が解決することで、休日明けの電話の数を減らすことにも役立ちます。
自動応答システムを導入する
自動応答システムとは、AIが顧客の発した内容を理解し、返答したりオペレーターにつないだりするシステムです。「ボイスボット」と呼ばれることもあります。オペレーターを介さずに顧客対応を行えるため、あふれ呼対策に効果的です。
AIは事前に設定したシナリオに沿って対応し、顧客の話す内容を解析して回答します。会話によって収集したデータが蓄積されていくため、繰り返すうちにAIが学習し、精度が向上していくことが特徴です。AIで解決できない問題はオペレーターが対応する必要がありますが、顧客の利便性向上やオペレーターの負担軽減に役立つでしょう。
IVRを導入する
IVR(自動音声応答システム)を導入することで、あふれ呼の発生を抑えることが可能です。顧客がコールセンターに電話をかけたときに「商品のお問い合わせの場合は1番を、修理の場合には2番を押して下さい」のように自動音声ガイダンスによって誘導することで、顧客のたらい回しによる時間のロスを防ぐほか、オペレーターの対応スピードの向上にもつながります。顧客が窓口に辿り着いた頃には問い合わせ内容がある程度把握できているので、あらためて顧客に問い合わせ内容を聞き出す必要がないからです。また難しそうな問い合わせの窓口にはベテランオペレーターを配置し、比較的簡単な問い合わせ窓口には新人オペレーターを配置しておくことで、全体的に対応のスピードアップにつながり、結果としてあふれ呼削減につながります。
また、電話対応が混雑している場合、自動音声ガイダンスで案内して折り返し先の電話番号を登録してもらい、後から掛け直すこともできます。コールバック予約機能があるIVRであれば、顧客がコールバックを希望する時間を予約することも可能です。時間を指定できれば、顧客にとってはいつ折り返しがくるのかわからないストレスが軽減され、オペレーターにとってはつながるまで何度も電話をかける負担が減るため、双方にとってメリットが大きいでしょう。
関連記事:コールバックとは?コールセンターでの活用例とメリットを解説
ビジュアルIVRを導入する
ビジュアルIVRの導入もあふれ呼対策に効果的です。ビジュアルIVRとは、電話での問い合わせをWebに誘導し、顧客が自分自身で課題を解決できるシステムです。SMSのメッセージでビジュアルIVRのURLが送信され、アクセスすると目的に合ったメニューを選択できます。従来のIVRとは異なり、電話口で長時間音声ガイダンスを聞くことなく、自分自身で簡易な問合せを解決できることが特徴です。
メニューの数や内容は自由に設定できるため、顧客にわかりやすく、コールセンターの特徴に合わせた画面を提供できます。待ち時間なく問題を解決できるため、顧客のストレス軽減にも効果的でしょう。
IVRを活用してあふれ呼を減らした事例
最後に、実際にビジュアルIVRを導入することであふれ呼を減らした企業の事例を紹介します。
おもに自動車メーカー関係会社の従業員に向けて損害保険商品を販売しているT&N保険サービス株式会社様は、コンタクトセンターにおける自動車保険の満期更新手続きの際の応答率に課題を感じていました。とくに沖縄では高齢のお客様が多く、電話での手続きが集中するために応答率が7割にまで落ち込んでしまったのです。そこで、対策としてNTTコム オンラインが提供する「ビジュアルIVR」の導入を決定しました。
まずは音声IVRで「電話での応対を希望する方は1、Webで手続きしてもよいという方は2を押してください」といった案内を行います。2を押してくださった方に対して、ビジュアルIVRに誘導するURL入りのSMSを送信する方法で活用をはじめました。
結果、「試しにWeb手続きをやってみました」というお客様も徐々に増えてきており、あふれ呼対策として効果を感じています。プレゼントキャンペーンやチラシ送付なども組み合わせることで、今後もWeb手続きの認知拡大と利用を促進していくつもりです。
あふれ呼対策にはモバイルウェブのビジュアルIVRを

あふれ呼は顧客満足度を低下させるだけでなく企業イメージにも大きなダメージを与えかねないので早急な対策が必要です。あふれ呼対策には主にIVRの導入がありますが、中でも自動音声ガイダンスを可視化したビジュアルIVRは有効な手段です。ビジュアルIVRは電話でのお問合せをWebに誘導して顧客が課題を自己解決できるので、顧客は電話口で長時間音声ガイダンスを聞くことなく問題解決ができるというメリットがあります。回答を示したサイトへスムーズにご案内できれば、オペレーターにつながらない、オペレーターに繋がるまでの待ち時間が長いといった問題を解消することが期待できます。
顧客の満足度・利便性向上のために、あふれ呼対策としてぜひビジュアルIVRをご検討ください。