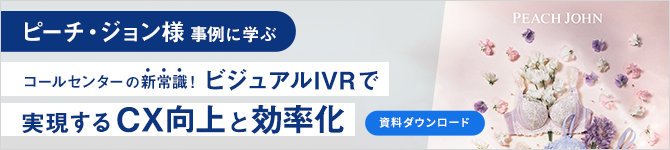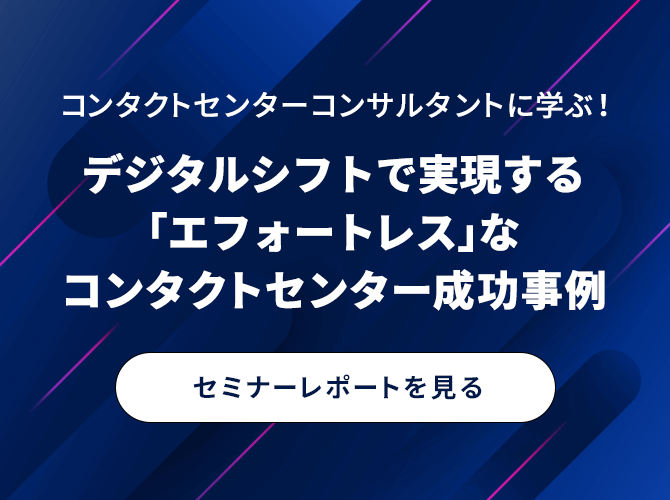2025/02/21
ビジュアルIVR
待ち呼(あふれ呼)とは?コールセンターで発生するリスク・原因・改善方法を解説
コールセンターにおける「待ち呼(あふれ呼)」は、オペレーターが対応できずに保留状態となる着信のことを指します。顧客が待たされることで、満足度の低下やクレームの増加につながり、最悪の場合、企業の信頼を損ねる原因となるため注意が必要です。
特にピーク時やトラブル発生時など問い合わせが集中する時には待ち呼が急増し、業務効率が低下するリスクも高まります。そのため、顧客対応の品質向上と業務効率化を目指す企業にとって待ち呼の最適な管理が重要な課題となっています。
本記事では、コールセンターで発生する待ち呼のリスクや原因を詳しく解説し、企業が取り組むべき改善策について紹介します。
- 待ち呼により顧客満足度の低下をはじめ深刻なリスクが生じる
- 待ち呼が発生する原因はカスタマーサクセスの不徹底や社内のリソース・システムの欠陥など
- 待ち呼数や放棄呼数を減らすためにできることは数多くある
- 待ち呼数改善には顧客接点を強化するWebマーケティングツールの導入も効果的
関連記事:あふれ呼とは?対策を行うメリットと7つの対策法、事例を解説

コンタクトセンターの実現方法
をご紹介!
「オペレーターの人材不足」「電話対応による限界」
「アンケート回収率の低下」などを解決する
SMSソリューションをご紹介します。
コールセンターの待ち呼(あふれ呼)とは?
コールセンターにおける待ち呼とは、問い合わせをする顧客の数、あるいは電話の着信数に対してリソースが不足しており、迅速な顧客対応ができていない状態のことです。コールセンターに電話をかけた際に待ち時間が長くなってしまうと顧客はストレスを感じ、それが企業への不満につながってしまいます。
さらに待ち呼は、待っている途中で問い合わせを諦めて電話を切る「放棄呼」の増加にもつながり、その結果、応答率の低下を招いてしまいます。応答率とは電話の着信数に対してオペレーターが対応できた割合のことで、重要なKPI(重要業績評価指標)の一つです。コールセンターにおいて顧客満足度の改善を達成するためには、この応答率を上げていくことが重要とされています。
関連記事:コールセンターの応答率とは?計算方法と改善策を紹介
コールセンターの待ち呼により発生するリスク
ここでは、コールセンターの待ち呼により発生する主要なリスクについて解説します。
放棄呼につながり顧客の満足度・ロイヤルティが低下する
待ち呼は放棄呼につながり、結果的に顧客の満足度低下を招きます。また、顧客が企業やブランドに対して持つ継続的な愛着や信頼、すなわちロイヤルティも低下する恐れもあるでしょう。
たとえ商品やサービスに満足していても、問い合わせに時間がかかったり対応してもらえなかったりすると、何事にも迅速さと高品質を期待している顧客はストレスを感じて不信感を持つ恐れがあります。結果として、サービスや商品購入のリピート率低下にもつながってしまいます。
関連記事:放棄呼率を低くするには?コールセンターの悩みを解決!
見込み顧客を失う
コールセンターへの問い合わせを行うのは既存顧客だけではありません。商品やサービスについて詳しく知りたいと考えている見込み顧客も問い合わせを行います。そのような見込み顧客を待たせてしまうと、放棄呼につながってしまいます。
放棄呼となった見込み顧客が、再びコールセンターに問い合わせを行うとは限りません。これは見込み顧客の喪失を意味し、さらには未来のロイヤルカスタマーを失うことにもつながりかねないのです。
クレームの増加・KPIの悪化によりオペレーターの離職につながる
待ち呼が多いと、クレームの増加・KPI(重要業績評価指標)の悪化につながります。 顧客からのクレームが増加するとオペレーターの精神的負担が大きくなり、離職にまでつながりやすくなります。
またKPIが悪化すると働くモチベーションが低下して、これも離職の増加につながります。さらに離職率の高い職場は求人に対する応募数も減少する恐れがあり、人材確保においても苦労することになります。
コールセンターにおけるKPIの例
- 応答率:
着信に対してオペレーターが対応した割合。「対応件数÷着信件数 」で求められる。 - 放棄呼率:
着信に対する放棄呼(オペレーターが対応する前に切れたコール)の割合。「放棄呼の数÷コール数」で求められる - 平均応答速度:
着信から応答までにかかった時間、顧客を待たせた時間の平均。 - サービスレベル:
設定時間内にオペレーターが対応した割合。「設定時間内の対応件数÷着信件数」で求められる。
関連記事:コールセンターのKPIとは?KPIの重要性と種類をご紹介
関連記事:コールセンターの人材不足の解決法とは?7つの施策をご紹介
コールセンターで待ち呼が発生する原因
ここからは、コールセンターで待ち呼が発生してしまう原因について解説していきます。
特定のタイミングで入電が増加している
コールセンターへの問い合わせ量は日時やタイミングによって異なります。 特定の日時やタイミングで問い合わせが増加し、その結果、待ち呼が多く発生してしまうことがあります。下記のような入電が増えるタイミングをあらかじめ見極めておき、対応を強化しましょう。
入電が増加するタイミングの例
- 新商品の発売時
- 季節行事、イベント時
- 請求書などに関する問い合わせが増える月末
- システム障害の発生時
- 休日明け
電話以外の問い合わせ手段が少ない
現代では多様な問い合わせ方法があるにもかかわらず、電話以外の手段がうまく活用されていないケースもあります。
電話での問い合わせは時間がかかるため、FAQ(よくある質問)、メールやSNSなど時間を節約できる手段を希望する顧客もいますし、また電話という行為自体に抵抗感を持つ顧客もいます。そのため、問い合わせの方法は複数用意しておくべきです。
また、既に問い合わせの手段を複数用意していても、そのことが顧客へ伝わっていない可能性もあります。周知させるためには、ホームページでの掲載方法やアフターフォローの見直しが必要なケースもあるでしょう。
十分なカスタマーサクセスを提供できていない
カスタマーサクセスとは顧客が商品やサービスを最大限に活用できるよう能動的に関わり、顧客の成功体験を支援する取り組みです。例えば、サービスの導入支援や商品活用ハウツー・ノウハウの提供、継続的なフォローアップなどが含まれます。
似たような概念としてカスタマーサポートがありますが、これは顧客からの問い合わせや問題を受け付け、解決する受動的な対応を指します。
顧客の問題解決手段がコールセンターへの問い合わせのみの場合、スムーズに問題を解決できないケースがあります。能動的に顧客が問題を解決できるようカスタマーサクセスを充実させることが重要です。
コールセンターのリソース・システムに問題がある
単純にコールセンターの人員が足りておらず、待ち呼が発生しているケースもあります。 もしくは人員は十分に確保されていても、その配置やシフトの組み方、さらにシステムに問題があるとやはりオペレーターは効率的に稼働できず、顧客対応の遅延や対応品質の低下を招く恐れがあるため見直しが必要です。
また、IVR(自動音声応答)やCTI(コンピューター電話統合)などを導入していない場合も適切な担当者への振り分けなどがスムーズに行えず、対応に時間がかかってしまう場合があります。
コールセンターの待ち呼数・放棄呼数を改善する7つの方法
コールセンターの待ち呼数・放棄呼数を改善するために企業ができることは様々です。ここでは7つの方法を紹介します。
1|オペレーターを増員する
オペレーターを増員すれば、その分対応できる顧客の数が増え、待ち呼の改善に直結します。ただし増員しすぎてもコスト負担が増えるため、適正人数を把握することが重要です。
コールセンターにおけるオペレーターの適正人数は、「アーランC式」等の計算式を用いて算出できます。計算に必要となる数値の例は以下の通りです。
- 1時間で寄せられるコール数
- 平均処理時間(AHT)
- 目標とする応答時間
- 目標応答率など
複雑な計算式なので、無料で試算できるサイトなどを利用するとよいでしょう。
2|ワークフォースマネジメントを実施する
ワークフォースマネジメント(WFM)は、コールセンターにおける業務効率を最適化するための人員管理手法です。主に入電予測(予想されるコール数)や平均処理時間(AHT)を基に、適切な人員配置を行うことで顧客の待ち時間短縮と業務効率化を図ります。ワークフォースマネジメントを適切に実践すれば、顧客満足度の向上とコスト削減を同時に実現できます。
ワークフォースマネジメントの手順
- 入電予測の作成:
過去のコールデータや時間帯ごとのトレンドを分析して入電数を予測する。 - 平均処理時間(AHT)を算出する:
ATT(平均通話時間)+ACW(平均後処理時間)で算出する。 - 必要人員数の計算:
入電数とAHTを基に適切な人員数を算出する。 - シフトスケジュールの作成:
人員各自の能力や希望も考慮しながら、ピーク時に人員が不足しないように適切な配置を計画する。 - リアルタイム管理と調整:
実際の入電状況をモニタリングして急な増減に対応する。 - 業務評価と改善:
定期的に運用結果を分析して予測精度や配置の最適化を進める。
ワークフォースマネジメントの計算は変数が多く難しいため、自動化ツールを活用するのがおすすめです。
3|アウトソーシングを活用する
コールセンターの業務はアウトソーシングを活用することも可能です。実際、人材不足などを背景にコールセンターのアウトソーシングは市場規模を拡大しています。「Stratistics MRC」の調査によると、世界のコールセンターアウトソーシング市場は2024年に1,127億7,000万米ドルを占め、2030年には1,711億4,000万米ドルに達すると予想されています。
アウトソーシングのメリットは、コスト削減、応対品質の改善、生産性の向上などです。デメリットは、情報漏洩のリスクがある、連携がスムーズにいかない場合がある、ノウハウを蓄積できないなどが挙げられます。リスクもあるため、まずは社内コールセンターの改善に取り組んでから検討するのがよいでしょう。
4|カスタマーサクセスを実施する
カスタマーサクセスに積極的に取り組むことで、顧客の課題を事前に解消できます。それにより、問い合わせ件数が減少して待ち呼を改善できます。
カスタマーサクセスのその他メリット
- 問い合わせ件数の削減により、カスタマーサポートの負担が軽減する。
- 顧客満足度が上がることで、ブランドイメージや信頼性が向上する。
- 既存顧客のポジティブな口コミやレビューが新規顧客の獲得につながる。
- 商品・サービスのリピート率が伸び、LTV(顧客生涯価値)の向上につながる。
カスタマーサクセスの具体策には、メールやLINE、SNSなどによる能動的なコミュニケーション、役立つコンテンツの提供などが挙げられます。CRM(顧客関係管理)などの顧客管理ツールも活用すると、パーソナライズの実現によりさらに高品質のカスタマーサクセスを提供できます。
5|AIチャットボットを導入する
AIチャットボットは、人工知能を活用して自動で顧客対応を行うシステムのことです。24時間365日対応できるため、営業時間外や深夜でも問い合わせに即時対応でき、コスト削減や業務効率向上につながります。具体的な活用例としては、注文状況の確認やFAQ対応、有人対応への切り替えなどがあります。
また、AIチャットボットは複数の問い合わせを同時に処理できるため、待ち時間を削減し、顧客の満足度を高めることもできるでしょう。さらにAIが顧客からの問い合わせデータを収集し、それを基に学習を繰り返すことで精度が向上するため、長期的な運用でより高い効果が期待できます。
6|IVRを導入する
IVR(Interactive Voice Response)は自動音声応答システムで、電話をかけた顧客に音声メニューを提供し、適切な部門や担当者に案内する仕組みです。オペレーターが対応する前に顧客の意図やニーズを把握できるため、効率的な対応が可能になります。
また、IVRでは用意された選択肢から顧客自身が問い合わせ内容を選ぶことから待機時間の短縮にも効果があります。営業時間や住所の案内など基本的な情報を提供したり、折り返し電話の予約を受けたりできる点も特徴です。
これらの機能によりオペレーターは直接対応の必要がある問い合わせに集中でき、対応スピードの向上とともに負担軽減も実現します。
関連記事:IVRとは何か?コールセンターに導入するメリットや導入方法
7|ビジュアルIVRを導入する
ビジュアルIVRとは、従来の音声IVRを視覚的に操作できる仕組みです。Webサイトや専用アプリ内に設置したり、SMSでURLを送信することで利用を促すことができます。
ユーザーは画面上のメニューを選択するだけで目的の情報に迅速にアクセスでき、音声案内に従うIVRよりも直感的な操作が可能です。また、コールセンターへの問い合わせに加え、チャットやLINEでの問い合わせやFAQの確認など、複数の選択肢を提示することもできます。
こうした機能によりコールセンターに問い合わせする際の待ち時間が短縮され、顧客満足度の向上とともにオペレーターの負担も軽減されます。
関連記事:ビジュアルIVRとは?メリットや導入事例、IVRとの違いを解説
待ち呼数・放棄呼数の改善をサポートする「モバイルウェブ」
NTTコム オンラインが提供する「モバイルウェブ」は、顧客接点を強化するWebマーケティングツールです。コールセンターの業務を効率化するビジュアルIVRや、Webアンケートシステムを備えています。
ビジュアルIVRを活用することで顧客は画面上で視覚的に選択することができ、誘導・案内がスムーズに進みます。また、お問い合わせを適切なチャネルに誘導できるため、有人対応を必要としている顧客にリソースを集中できる点もメリットです。こうした機能により待ち呼数・放棄呼数が減少します。
また、メール送信、SMS送信などのメッセージ機能を活用することで顧客とのコミュニケーションが強化され、コールセンターにおける業務負担の軽減も可能です。さらにはデータベース機能も備えており、データを基にした多様なマーケティング活動にも利用できます。
ビジュアルIVRで待ち呼を改善した事例|アイペット損害保険株式会社 様
犬・猫向けの医療保険を販売するアイペット損害保険株式会社様。実績の高さからペット保険のリーディングカンパニーとして支持されています。
毎月2万件を超えるお問い合わせ電話があり、つながらない事態が頻発して課題になっていたことから、お客様からのお問い合わせ対応をより充実させるためにモバイルウェブを活用しビジュアルIVRを導入。その結果、「電話をかけてきたお客様をWeb手続きへ誘導できるようになった」「お客様をお待たせすることが減った」と改善を実感されています。
ビジュアルIVRで待ち呼を改善した事例|T&N保険サービス株式会社 様
主に自動車メーカー関係会社の従業員に向けて損害保険商品を販売するT&N保険サービス株式会社様。以前は年間16,000件程度、月1,200件程度の電話が入る状況で、応答率が約7割まで下がってしまったこともありました。そこで待ち呼を減らすためにビジュアルIVRを導入。
自動車保険の満期更新のためコンタクトセンターに電話をかけてきたお客様にWeb手続きをご案内するために活用したところ、「試しにWeb手続きをやってみました」というコメントが徐々に増加傾向に。今後Web手続きの認知拡大、待ち呼低減への効果発揮が期待されます。
コールセンターの待ち呼は早急に改善すべき課題
この記事で解説した通り、コールセンターの待ち呼は顧客満足度の低下や企業の信頼性に影響を及ぼす重要な課題です。特に長時間の待ち時間や度重なる保留の体験は顧客の不満を招き、サービスの解約や企業イメージの悪化につながります。それだけではなく、社内の人的リソースの浪費や離職増加を招いてしまう恐れもあるでしょう。
NTTコム オンラインが提供する「モバイルウェブ」では、ビジュアルIVRを始め、多彩な顧客接点を活用してコールセンター業務の効率化を支援します。待ち呼数や放棄呼数の改善への取り組みを検討している方は、ぜひこの機会に「モバイルウェブ」の導入も検討してみてはいかがでしょうか。