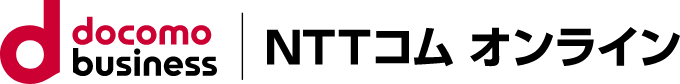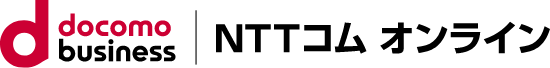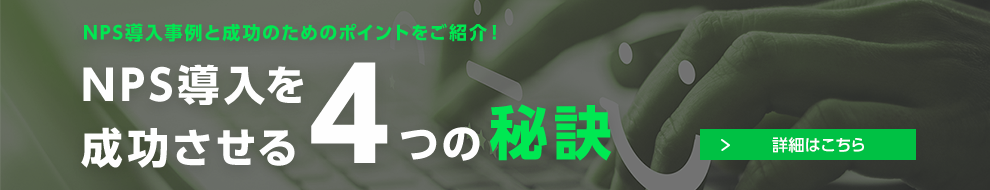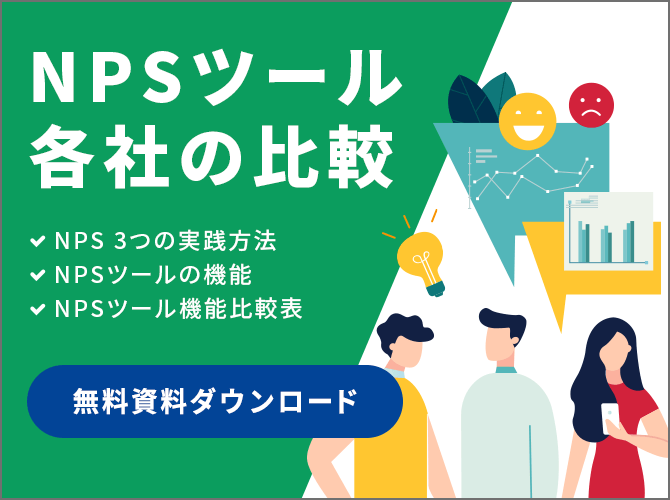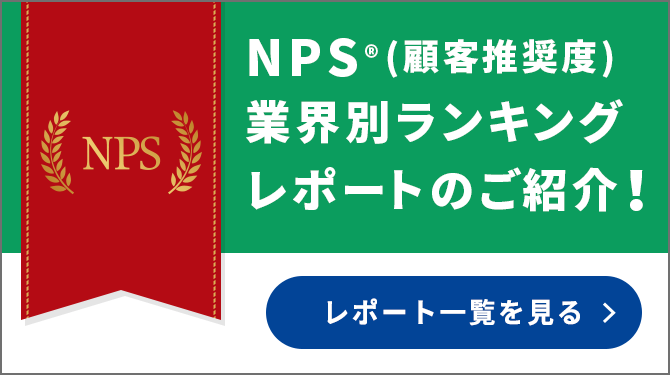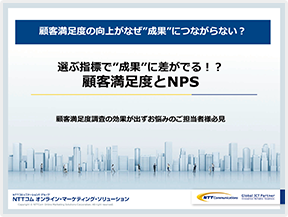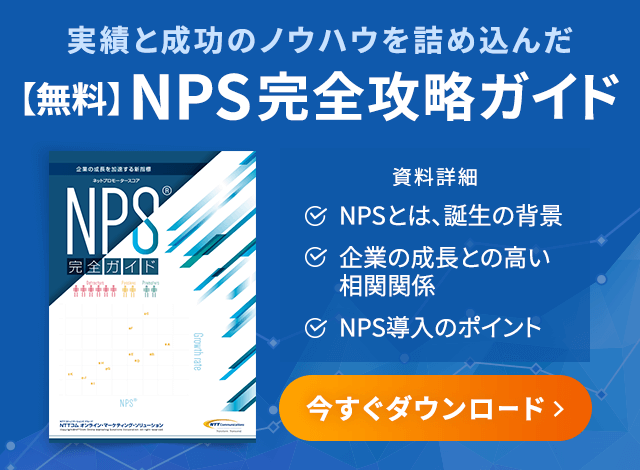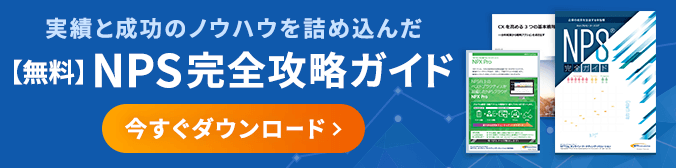2023/03/23
NPS®(ネットプロモータースコア)入門・導入編
ブランドエクイティの意味とは?高めるメリットや測定方法・企業事例を解説
企業がもっているブランドなどの目に見えない価値を表す「ブランドエクイティ」。あまり聞きなれない用語ですが、ブランドエクイティには、顧客ロイヤリティの向上や他社との差別化実現など、多数のメリットがあります。安定した経営や長期的な企業成長にはブランドエクイティ向上が不可欠といえるでしょう。
本記事では、ブランドエクイティの意味やメリット、構成要素、測定方法、ブランドエクイティ向上を実現させた企業の事例など、ブランドエクイティが企業に与える影響とブランド価値を高める方法を解説します。
ブランドエクイティの意味とは「無形資産の集合体」
ブランドエクイティとは、企業が顧客や取引先、社会に対してもっている「目に見えないブランド価値」を資産として捉える考え方です。
ファッションなどに代表される企業のブランド名やロゴなどのシンボルは消費者の購買行動にも影響を与えており、企業が保有する資産や生産設備、有価証券などの「有形資産」と対比して「無形資産」と呼ばれます。
エクイティには「自己資産」の意味がありますが、ブランドエクイティは利益を生むプラスの資産だけでなく、企業に対するマイナスイメージなど負債部分も含めた総合的な価値を示す概念です。
ブランド価値は、リピーターの獲得や顧客1人あたりが企業に与える利益である「LTV(顧客生涯価値)」向上にもつながっており、企業の事業成長や経営の安定にも結びつく重要な要素といえます。
ブランドエクイティを高めるメリット
ブランドエクイティの向上は、企業の売上や経営にメリットをもたらすのはもちろん、商品・サービスを購入する顧客にとっても大きな利益を生み出します。ブランドエクイティを高めると、どのような効果があるのか、企業側・顧客側の双方からみていきましょう。
企業側のメリット
ブランドエクイティは企業にとって豊富なメリットを生み出す要素です。有名なブランドになるほど、既存顧客のブランドに対する愛着や親しみといった「顧客ロイヤリティ」が向上します。満足度やポジティブな口コミが増加して、リピーターになりやすくなるとともに、新規顧客獲得にかかるコスト(CPA:Cost Per Acquisition)も低下します。
高いブランドエクイティが確立されると、顧客がファン化するため他社との差別化も図りやすく、ライバル企業の新規参入障壁も高くなって顧客流出も防げるでしょう。
また、ファンになってくれた顧客は、商品価格を気にせず購入してくれるようになるため、価格プレミアムが向上して利益率が良くなり、熾烈な価格競争からも解放されます。
顧客側のメリット
ブランドエクイティの恩恵を受けるのは企業側だけでなく、顧客にとってもさまざまなメリットがあります。
ブランドエクイティが顧客に与える大きなメリットは、有名ブランドになるほど、ユーザーの商品・サービスに対する信頼や安心感、満足度が高まる点です。顧客の心理として、お金を出して購入する以上、不良品や不満点などのリスクはできるだけなくしたいと考えます。
誰もが知っている有名な企業なら、ブランド名だけでも安心して購入できるため、買う前に商品・サービスの比較やリサーチを行う負担を減少させられるでしょう。
また、有名ブランドの商品は、もっているだけでステータスを感じられ、所有そのものがユーザーにとっての価値や満足感を生み出します。
ブランドエクイティを構成する要素
ブランドエクイティの構成要素を説明する方法は、「アーカーモデル」「ケラーモデル」の2つが代表的です。以下、それぞれのモデルを詳しく解説していきます。
5つの要素からなる【アーカーモデル】
アーカーモデルはブランドエクイティの提唱者であるデイヴィット・アーカーによる考え方で、抽象的なブランドエクイティの概念をより具体的に理解するためのモデルです。アーカーモデルではブランドエクイティを、次の5つの構成要素から捉えています。
1|ブランドの認知(Brand Awareness)
ブランドが顧客や社会一般に認知されている度合いです。顧客は購買の際、知っているブランドを優先する傾向があるため、認知度が上がるほど選ばれる可能性が高まり、ユーザーの企業に対する安心感にもつながります。
食べ物や飲み物、クルマ、家電など、商品・サービスのカテゴリーにおいて一番に想起される企業は、強いブランドエクイティをもっているといえるでしょう。
最近では、単にブランド名が知られているだけでなく、商品内容や文化など細かな部分まで理解されているといった意味合いで使われるケースが多くなっています。
2|ブランド連想(Brand Associations)
ブランド名を聞いたときに消費者が思い浮かべるイメージです。例えば、トヨタのクルマなら安心や高品質、リッツカールトンと聞けば、信頼やステータス性を連想するように、顧客の中には、企業や商品・サービスへの多様なイメージが形成されています。
ブランドイメージに影響を与えるのは、広告や口コミから、ユーザーが実際に利用した際の個人的な体験までさまざま。ブランド連想が弱いと他社との差別化やブランドロイヤルティの獲得が難しくなるため、豊富かつポジティブなイメージを作る努力が求められます。
3|ブランドロイヤルティ(Brand Loyalty)
ロイヤルティは日本語で「忠誠心」を意味しており、「ブランドロイヤルティ」とは、特定のブランドに対するユーザーの愛着度や信頼度を表す用語です。
ブランドロイヤルティが高いほど、消費者は同じブランドの商品・サービスを継続して購入する傾向があります。結果、リピーターが生まれやすくなり、長期的な事業の安定につながるでしょう。
また、ブランドに愛着をもつユーザーは、簡単に競合他社へ乗り換えようとしなくなるため、スイッチングを低下させて顧客をしっかりと確保する意味でも特に重要な構成要素です。
4|知覚品質(Perceived Quality)
ブランドがもっている品質イメージを「知覚品質」といいます。大切なのは、企業側の認知ではなく、顧客がブランドに対して抱いている品質イメージを表している点です。
知覚品質は、商品・サービスの基本的な性能やオプションはもちろん、不良品の少なさやアフターサービスの充実度、CMや広告に対するイメージなど、さまざまな要素から判断されます。
なかにはブランドの雰囲気や信頼性など、漠然とした要素も含まれ、スペックだけでなく、顧客への配慮やブランドのこだわりなども合わせた細かな戦略が必要です。
5|その他ブランド資産(Brand Assets)
企業がもつブランド以外の無形資産です。例えば、特許や商標、著作権といった知的所有権、取引先との良好な関係性、独自技術やノウハウなどが含まれます。
こうしたブランド資産は、ブランド価値を支えてくれる存在であると同時に、商標をもっていれば、他の企業が同じ名称やマークなどを使用できなくなるように、ブランドを守る役割も担っているのです。
ブランドエクイティの構成要素としても重要で、ものによっては、これだけで高い競合優位性を獲得できるケースもあります。
4つの要素からなる【ケラーモデル】
ダートマス大学のケビン・レーン・ケラー教授によるケラーモデルで、アーカーモデルより顧客視点を重視するのが特徴です。ブランドエクイティピラミッドとも呼ばれ、ブランドエクイティを4段階に分け、上に行くほどよりレベルが高くなるとされます。
1|ブランドの認知(Salience)
「ブランドの突出性」ともいわれ、顧客のなかにブランドを広めていく段階です。
自社がどのような商品・サービスを提供しているか、他社との違いは何か、どのような文化・考え方をもっているかといったブランドの特徴をユーザーに広め、競合と識別されるよう認知してもらいます。
アーカーモデルでは「ブランドの認知」にあたる部分で、ピラミッドの上部をしっかり支えるためには、ブランドに対する深い理解の獲得が必要です。
2|ブランドの意味付け(Brand Meaning)
アーカーモデルの「ブランド連想」にあたる段階で、次の2つの観点から顧客によるブランドの意味づけを考えます。
- Performance:ブランドのパフォーマンス。顧客にブランドの特徴や価値、機能などが理解されているか、ユーザーのニーズと合っているかの確認。
- Imagery:顧客が自社の商品・サービスからどのようなブランドイメージを抱いているか。
両方から総合的に判断して、企業が意図した通りのブランドイメージが顧客に伝わっているかが重要になります。
3|ブランドへの反応(Brand Response)
レベル3はアーカーモデルでの「知覚品質」に相当し、ブランドに対する顧客の反応(評価)が決定する段階です。第3段階も2つの視点に分けられており、理性評価と感性評価から構成されています。
- 理性評価(Judgement):品質や安全性、信頼感など商品・サービスに対する理性的な評価。
- 感性評価(Feelings):商品・サービスを利用した際の楽しさや興奮、社会的なステータス、満足感など感情で判断される評価。
それぞれの評価項目はブランドのコンセプトやポジショニングに沿うものにする必要があります。
ユーザーは大きく、これら2つの視点からブランドの優劣を判定しており、理性評価は主にブランドの意味づけにおける「Performance」、感性評価は「Imagery」の延長上といえるでしょう。
4|ブランドへの共感(Resonance)
最終段階で、ピラミッドの頂上となるのはブランドへの共感です。ブランドエクイティが最も高い状態で、ブランドと顧客の間に強い絆が生まれています。
アーカーモデルのブランドロイヤリティにあたり、ここへ来てはじめて、ブランドに対する愛着や信頼感などが芽生えるのです。
レベル4に達したブランドはユーザーにとって「なくてはならない存在」になっており、ファン同士が交流したり、家族や友人に勧めたりして、顧客同士がコミュニティを形成する場合があります。
ブランドエクイティの測定方法
ブランドエクイティは目に見えない無形資産のため、客観的な数値による測定は難しいとされています。ただ、全く不可能なわけではなく、次の3つの方法を用いれば測定が可能です。続いては、ブランドエクイティの代表的な測定方法を解説します。
財務情報を基に測定する
1つ目は企業の財務情報の指標を使用してブランドエクイティを測定する方法で、いわゆる企業の「のれん」を導き出します。
のれんとは、M&Aの際などに買収する企業が支払った金額のうち、買収される企業の純資産を上回った額を指す用語です。例えば、純資産100億円の企業が130億円で買収された場合、30億円がのれんになります。
企業が潜在的にもっている目には見えない価値である「超過収益力」を見積もり割り出す方法で、具体的には、将来見込まれる収益を現在価値に割り引いて求めたり、無形資産の価値を算出していったりなどの測定法があります。
ブランドリプレイス費用から測定する
2つ目は、ブランドをリプレイスするためにかかる費用から測定する方法です。ブランドリプレイス費用とは、ブランドの商圏外に出店してブランドとしての地位を確立する際に必要とされるコストで、次の3種類に分けられます。
- アイデンティティ確立のための費用:ブランドイメージの確立に必要なWebサイト制作やキャッチコピーの宣伝費用など。
- 認知獲得のための費用:ユーザーに認知されるための広告費用。テレビCMや雑誌広告、ネット広告の出稿費など。アイデンティティ確立費用と似ていますが、直接広告宣伝費として使われるものを指します。
- 顧客維持のための費用:CRM(顧客関係管理)にかかる費用。見込み客の育成や自社の人材確保に必要なコストも含まれます。
NPS®(ネットプロモータースコア)で測定する
3つ目は、NPS(ネットプロモータースコア)を利用して企業への評価を可視化する方法です。
NPSとは、「ブランドの商品・サービスを他人に薦めたいか?」などの質問に0~10までの11段階で答えるアンケートを実施して顧客のブランドに対する好感度を測る方法で、顧客ロイヤリティの測定などに用いられます。
ブランドに肯定的な回答をした人の割合から批判的な回答をした人の割合を差し引いたスコアがNPSの指標です。ブランドエクイティにおける全ての要素を測定できるわけではないものの、ブランド価値を可視化するのに最適な方法とされています。
多くの企業で採用されており、ベンチマークもあるため、目に見えないブランドエクイティを測る際には有効な手段といえるでしょう。
ブランドエクイティを向上させる方法
ブランドエクイティを向上させるには、ブランドアイデンティティの確立と企業内への浸透が重要です。ブランドエクイティは曖昧な概念のため、社員自身が自社ブランドはどういうもので、どのような価値があるかを理解していなければ実現は難しくなります。
ブランドは独立して存在するわけではなく、企業や社員と密接に結びついているため、ブランド価値を高めるには、企業としての理念を確立して社内に浸透させる必要があるでしょう。
そこで重要になるのが、ブランドのもとになっている企業が果たすべき価値や目標などを言語化した「ミッション・ビジョン」です。
社員1人1人によるミッション・ビジョンの理解および商品・サービス提供時における体現を徹底すれば、企業のブランド価値が生まれ、育っていきます。
そのうえで、ソーシャルメディアを活用したマーケティング戦略や顧客とのコミュニケーションなどに用いて積極的な顧客ロイヤリティ醸成を目指せば、ブランドエクイティの向上へとつながっていくのです。
ブランドエクイティの向上を実現した例
ここからは、ブランドエクイティの向上を実現させた事例の紹介です。有名企業のなかには、ブランドエクイティがマーケティング用語として一般化する前からブランド価値を高める取り組みを実施し、成果をあげているケースがあります。ブランドエクイティの主な成功事例をみていきましょう。
Apple
iPhoneなどで有名な「Apple」は、株式会社インターブランドジャパンが発表している「『ブランド価値』によるグローバル・ブランドランキングTOP100」で10年連続1位を獲得しており、2022年の時点でブランド価値は4,822億ドルとされています。
Appleはパソコン、スマートフォンなど主要分野でトップシェアを獲得している企業ではありません。
しかし、ライバルと一線を画するイノベーションや「Think Difference」のスローガンなど、元CEOスティーブ・ジョブズ氏が確立した企業としてのアイデンティティが源泉となって、大きなブランドエクイティが生まれています。
スターバックス
誰もが知る世界的なコーヒーチェーン「スターバックス」は、戦略的・意識的なブランドエクイティの向上を目指している企業です。
スターバックスでは、「自社の強み」「競合他社の特徴」「顧客のニーズ」の3つを分析する3C分析をブランドイメージの構築に活用。さらに、従業員に対しては、顧客に家庭や職場以外の居心地良い空間を提供する「サードプレイス」のコンセプトを共有・定着させています。
その結果、スターバックスでは、単なるコーヒー店にとどまらないブランドロイヤリティの醸成に成功しているのです。
楽天トラベル
「楽天トラベル」は、NPS向上支援ツール「NPX Pro」によりブランドエクイティ向上に成功している企業です。オンライン旅行予約サービスを提供している楽天トラベルでは、楽天グループ全体での品質向上活動をきっかけに「NPX Pro」を導入。
顧客に直接メールを配信するトランザクショナル調査によって、従来はCS部門で集めていたユーザーの声が直接サービス担当者に届くようになり、課題分析や改善アクションがボトムアップで進むようになりました。
従業員のなかにも顧客の意見をもとに良いサービスへとつなげていく意識が芽生えたため、PDCAサイクルが従来よりも速く回るようになり、改善プロセスもスピードアップしています。
顧客に対する迅速かつきめ細やかな対応は、楽天トラベルのブランドエクイティ向上に大きく貢献しているといえるでしょう。
ブランドエクイティの測定には「NPX Pro」
「NPX Pro」は、ブランドエクイティの向上において重要になる顧客ロイヤルティを効率的に計測できるツールです。目に見えないブランド価値を正確に測定し、NPSを効率的に活用するには、専用ツールの存在が欠かせません。
「NPX Pro」を利用すれば、アンケート作成から配信、解答回収、分析まで一連のプロセスを一元管理できます。さらに、データを可視化して各部門でスムーズに共有できるため、優先すべき課題の素早い特定が可能です。
顧客のネガティブな意見を知らせるアラートなど、迅速な改善やフォローアップアクションを促進する機能も搭載。調査・分析・改善までを「NPX Pro」1つで実現します。
社内に十分なノウハウがない場合も、NPS公認資格をもつコンサルタントが導入から運用をサポート。ブランドエクイティの改善・向上を目指すなら、ぜひ「NPX Pro」の導入をご検討ください。
ブランドエクイティを向上させ長期的な成長を目指す
ブランドエクイティは、企業がもつ目に見えない価値で、顧客ロイヤルティの向上や他社との差別化など多様な利益をもたらしています。企業の長期的な成長にもつながる大切な資産ですが、形をもたないブランド力を高めていくのは簡単ではありません。
ブランドエクイティ向上には、現在の自社ブランド価値を計測して問題点を分析。企業の理念となるミッション・ビジョンをもとに改善プロセスを実施していくのが重要といえるでしょう。
特に、自社のブランド価値を正確に測定するには「NPX
Pro」などの専用ツール導入が不可欠です。ブランドエクイティ向上と長期的な成長を目指すなら、ぜひNTTコム オンラインの「NPX Pro」活用を検討してみてください。NPSに関するご相談・問い合わせはこちらから
【
NPS®(ネットプロモータースコア)入門・導入編
】
最新のコラム

2024/07/26

2024/07/26

2024/06/25

2024/06/06