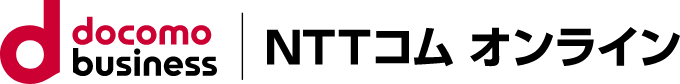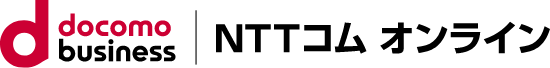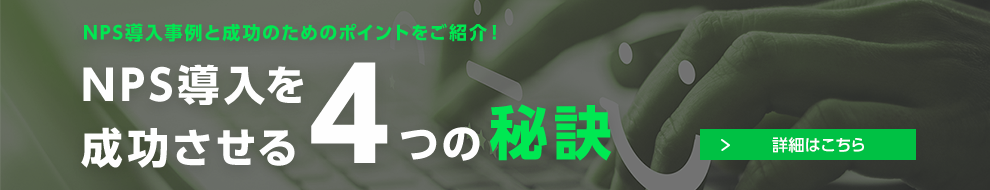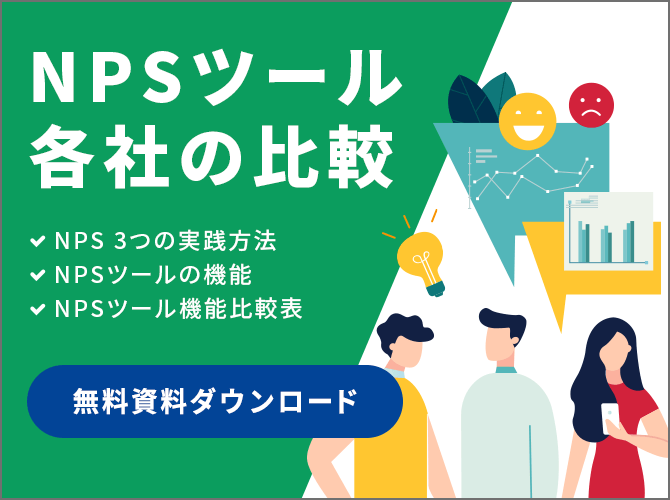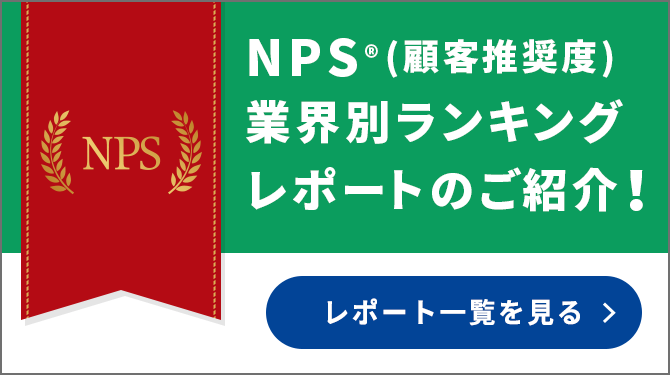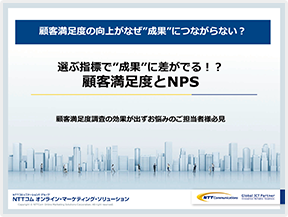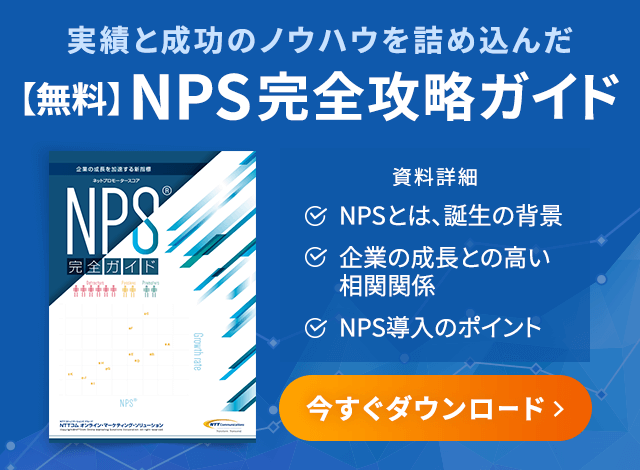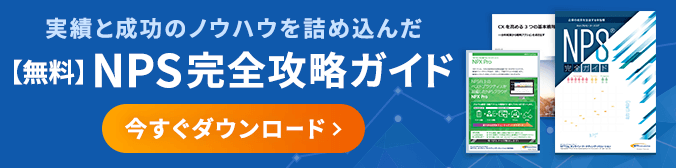更新日:2024/01/30(公開日:2021/02/22)
カスタマーロイヤルティxビジネス
アンケート調査の目的設定は重要?作成例や回答率を高めるポイントを解説
アンケート調査の目的設定は重要?作成例や回答率を高めるポイントを解説
アンケート調査は、自社サービスや提供商品の評価を知り課題を発見すること、顧客ロイヤルティを測りその向上となるポイントを発見することなどにも活用することが出来ます。いつどこでだれにどのようなアンケートを取るのかによって結果は大きく変わってくるため、本記事では、アンケート調査の目的設定や、アンケートの回答率・回答の信頼性を上げるコツ、調査手順などについて解説します。あわせてNPS®アンケートの例文も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
- サービスの開発・改善、顧客ロイヤルティの向上などが期待できる
- アンケートの回答率・結果の信頼性を上げるためには、設問をシンプルに短くする、自由記述式のアンケートを取り入れる、回答しやすい順番を意識する、報酬を明確に提示するなどがポイント
- NPS®は顧客ロイヤルティを測る指標。企業成長とも相関性があり、ベンチマークとして活用できる
アンケート調査の目的設定や類似用語との違いを解説
ここでは、アンケート調査の目的や類似用語との違いについて見ていきましょう。
アンケート調査を行う目的設定(目標・ゴール)とは
企業がアンケート調査を行う目的はさまざまです。「売上向上」「リピーターの増加」「顧客満足度の向上」などを目的に、自社商品・サービスの質の定期的な調査として行う企業も多いでしょう。アンケート調査を通じて、自社商品やサービスへの顧客の意識や評価を把握でき、アンケート結果は商品やサービスの改善・開発に役立てられます。また、顧客の不満点をスピーディーに改善することで、顧客ロイヤルティの向上にもつながります。
以下はアンケート調査項目の一例です。
- 回答者の属性
- 商品やサービスを認知したきっかけ
- 商品やサービスを購入・利用したきっかけ
- 評価の理由
- 競合他社との比較
- 商品やサービスへの要望・意見
アンケート調査には、オンライン・電話・メールで行う、直接顧客にヒアリングする、ユーザーインタビューを実施するなどの方法があります。また、コストはかかりますが、外部のリサーチ会社を利用する方法もあります。
アンケート調査と意識調査・市場調査との違い
アンケート調査の類義語に「意識調査」や「市場調査」があります。意識調査とはある物事に関する人々の心理や行動を調査することです。意識調査を行うための方法の一つにアンケート調査があります。
また、市場調査とは市場を数値化して把握することです。マーケティングにおいて商品やサービスの需要を調べたり、競合他社のシェアを把握したりする際に役立ちます。アンケート調査は市場調査の一環として実施します。
アンケート以外の調査方法
ここからは、アンケート以外の調査方法以下3つについて解説します。
- インタビュー調査
- Web・SNSリサーチ
- ホームユーステスト(HUT)
インタビュー調査
インタビュー調査は対象者の意見を集める調査方法です。主なインタビューの種類には「街頭インタビュー」「グループインタビュー」「デプスインタビュー」があります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
- 街頭インタビュー:不特定多数からさまざまな意見を幅広く収集したいときに有効
- グループインタビュー:参加者同士のコミュニケーションが発生するので議論が発展しやすく、集団における消費者心理を把握できる
- デプスインタビュー:1人のユーザーに詳細な質問ができるので本音を引き出しやすい
インタビュー調査の目的に応じて使い分けるとよいでしょう。
Web・SNSリサーチ
Webリサーチは、インターネット上のブログや口コミサイトなどの発信内容を調査する方法です。実際に商品やサービスを利用した人の意見を収集しやすいのが特徴で、評価の内容が詳細に記載されている傾向があります。
一方のSNSリサーチは、X(旧Twitter)やInstagram、Facebookなどの投稿を収集・分析する手法。消費者のニーズや購買行動などを調査でき、特に匿名性が高いX(旧Twitter)は本音を収集しやすいソースです。ソーシャルリスニングツールなどを活用すれば、収集・分析の作業を効率化できます。
関連記事:ソーシャルリスニングとは|意味や分析方法の解説と導入事例を紹介!
これらの手法を活用して消費者のリアルな声を拾い上げることで、自社商品・サービスの改善や開発に役立てることができます。
ホームユーステスト(HUT)
ホームユーステスト(HUT)とは、調査対象者の自宅に商品を送付し、一定期間利用もしくは試食などをしてもらい、対象者の生の声を集める調査方法です。特に栄養機能食品や美容機器など、効果を感じるために一定期間使う必要がある商材を扱う際に有効です。
ホームユーステストは日常生活のなかで一定期間使ってもらえるので、実態に近い本音が収集しやすい点が特徴。また、対象者は無料で商品を使用できるのも魅力です。
一定期間使用することで、商品に対する飽きや商品の消耗度などの途中経過も把握できます。さらに、テストを通じて対象者が商品を気に入れば、顧客ロイヤルティが高まる可能性もあります。
アンケート調査のポイント
ここでは、アンケート調査を実施する際のポイントについて詳しく解説します。
調査のポイント1「企業やブランド全体の評価」を目的としたアンケートの場合
「企業やブランド全体の評価」は顧客体験の全体アンケートを行うことで、どのような顧客体験が重要だったのかを知ることが可能となります。提供する商品やサービスによって異なりますが、ブランドイメージ、サービスの魅力、お客様対応、アフターフォロー、コールセンターでの問合せ対応などの顧客体験における重要なポイントの全体を通じてお客様の満足度や重要度などを把握します。
調査のポイント2「重要な顧客体験直後の評価」を目的としたアンケートの場合
調査のポイント1「企業やブランド全体の評価」で提供する商品やサービスの重要な顧客体験を知ることができました。
次は重要な顧客体験”直後”にアンケートを行い、より具体的な課題を探っていきます。
例として、コールセンターでの問合せ対応が顧客体験における重要なポイントだと把握できた際には、次のステップとして、コールセンターの顧客体験後にアンケートを行い、具体的な改善につなげるといったケースです。
例えば、コールセンターにおける
- 親身な対応・マナーの良さ
- 説明のわかりやすさ、回答の的確さ
- 対応の迅速さ
- 専門性の高さ
など、より細分化しアンケートを実施することによって、何をどうすればいいのかより具体的な課題が発見できます。発見した課題の早急な改善、更にアンケートを繰り返すことでポイント1の「企業やブランド全体の評価」で明らかになった評価の低かった顧客体験を向上させ、全体のロイヤルティ向上に影響を与えていきます。
「企業やブランド全体の評価」「重要な顧客体験直後の評価」この2つのアンケートを実施することが顧客ロイヤルティの向上につながっていくということです。
アンケートの回答率、回答の信頼性を上げる7つのコツ
アンケートは一定の回答数、適切な評価を得ることが分析につながります。
「アンケートのお願いをしたがほとんど回答者がいなかった」「質問項目が多く、ほとんどが同様の回答になっていた」というようなアンケートにならないためにも、ここでは回答者を配慮したアンケートの作成例を紹介します。
1|アンケートの目的、回答目安時間をしっかり伝える
セミナーを例に挙げますと「本日はご参加いただき誠にありがとうございました。〇〇セミナーをさらにお客様に喜んでいただく場にするため、本日の内容についてのアンケートにご協力をお願いいたします。回答時間:5分程度」などと、冒頭に挨拶とアンケートの目的、回答目安時間を入れておくと、心証が良く、なおかつ所用時間がわかることで取り組んでもらいやすくなります。
2|アンケートの回答時間は5分以内を目安にする
より多くの人に率直なアンケートを回答してもらうには、極力シンプルにします。
具体的には設問は7問以内に収めかつ、3~5分で回答できるようなアンケートが理想です。
重厚長大なアンケートでは回答者の負荷が高まり、回答率が下がり、かつ率直な回答をいただけない場合もあります。また、景品やポイントなどで過度な報酬の引き換えとしたアンケートで回答いただいたとしても、データの信頼性に欠けます。回答者1人1人に、正当な評価をしていただけるように、アンケートを構成していきましょう。
3|アンケートの評価は何段階が適正か検討する
アンケートで顧客満足度などを判定する際には、一般的には 「よい・ややよい・どちらでもない・やや悪い・悪い」のような5段階評価が利用されます。NPS®のアンケートでは大事な人に自社製品やサービスをお勧めしたいですかという設問に対して、0-10の11段階評価を用います。
4|自由記述式のアンケートも取り入れる
自由記述式のアンケートは、回答の選択肢を用意せず、回答者が自由に回答できる形式です。フリーアンサー(FA)やオープンアンサー(OA)などとも呼ばれます。自由記述式を取り入れることで、定性的なユーザーの思いや考えを把握できます。
選択式だけだと「満足」を選択しても、何に満足したのか、何が改善されればより満足度が高まるのかなどの情報がわかりません。例えば、売上が伸びない場合、企業は「価格」がネックになっていると考えていても、ユーザーは「使用感」や「パッケージ」を改善してほしいと思っている場合もあるでしょう。
このように、自由記述式によりユーザーの想定外のニーズを発見できる可能性もあります。
5|質問に答えやすい順番を意識する
アンケートの回答率を上げるためには、質問の順番を意識することが必要です。質問の順番が適切でない場合、ユーザーは面倒に感じて回答してもらえなくなる可能性があります。まずは、年齢や居住地域、家族構成、利用することが多い交通手段など、答えやすい質問から始めましょう。また、関連する質問はまとめて配置すると回答しやすくなります。
アンケートの序盤に自由記述式の質問を配置すると、回答するのが億劫に感じることがあるので注意しなければなりません。自由記述式の質問は回答に時間を要するため、アンケートの最後あたりに配置するなど工夫しましょう。質問は重要なものだけに絞り込み、数も多くなりすぎないよう意識してください。
6|報酬を明確に提示する
アンケートでは、報酬の有無を事前に提示することも大切です。報酬があることがはじめに認識されると、回答へのモチベーションを高められ、回答率の向上につながります。モチベーションを高めるためにも、報酬は回答者が価値を感じるものを用意することが大切です。ユーザー層をしっかりと考慮して検討しましょう。
ただし、報酬を目的とする回答者が増えると、アンケートの精度が低下する可能性も出てきます。精度を保つためにも、回答者が答えやすいアンケート設計を意識することが必要です。
7|デバイスに適したレイアウトにする
Webでアンケートを行う場合、回答に使用するデバイスは人それぞれです。回答者の使用率が多いと思われるデバイスに最適化することで回答しやすくなります。例えば、パソコンとスマートフォンでは画面のサイズや選択方法が異なるため、どちらでも見やすいレイアウトや、各デバイスに合った選択方法を採用することが大切です。
回答者のデバイスに合ったアンケートを作成することで、回答率・回答の精度に好影響があります。
アンケート実施の手順
アンケートは事前準備をせずに実施すると、十分な回答が集まらなかったり、思うような回答が集まらなかったりします。アンケートを実施する際には、以下のような手順で行うとよいでしょう。
- 収集したい情報やゴールを設定する
- 質問票のタイプと回収方法を決定する
- 質問内容を決定する
- 回答形式を決定する
- 質問項目の文を決定する
- 質問の順番を決定する
- 質問の量や質問用紙のサイズなどを決定する
- 全体を再検討する
- プリテストを実施する
- アンケートを実施する
- 結果を集計する
- レポートを作成する
- フィードバックを行う
アンケートの目的設定や質問内容の設計はもちろん、綿密な分析やフィードバックも重要です。
NPS®とは?
「NPS®(Net Promoter Score)」とは、顧客ロイヤルティを測るための指標です。まずは「商品やサービスを家族や友人にどの程度お勧めしますか」という質問をし、0~10の11段階で回答してもらいます。
回答が0~6の回答者を「批判者」、7~8を「中立者」、9~10を「推奨者」に分類し、以下の計算方法によって算出します。
NPS®スコア = 全体に占める推奨者の割合(%)- 全体に占める批判者の割合(%)
NPS®は多くの企業が採用する指標ですが、注意点もあります。NPS®はサンプル数により精度の違いが出てきて、400以上のサンプルを集めた場合で精度の誤差が±5%、2000以上のサンプルを集めた場合で誤差±2%程度が一般的です。
また、日本人は中間あたりの評価を行う傾向があるため、日本の顧客を対象としたNPS®の調査結果はマイナスになるケースが多く見られます。
NPS®の有用性
NPS®は顧客ロイヤルティを測る指標だけでなく、企業成長とも相関性も示されています。Satmetrix社のホワイトペーパー「THE POWER BEHIND A SINGLE NUMBER」によると、400社以上の企業やブランドに対して調査を行い、15万人以上からの評価を分析したところ、NPS®は企業の売上高成長率と高い相関があることが分かりました。
実際に多くの企業がNPS®を導入しており、業界別の平均スコアも公表されているため、ベンチマークとして活用できます。
当社で毎年実施している業界別のNPSスコアはこちらをご覧ください
出典:THE POWER BEHIND A SINGLE NUMBER
NPS®アンケートの例文
ここでは生命保険会社を例にした顧客ロイヤルティ向上のためのNPS®アンケートの内容をご紹介します。
まずは推奨度を測る質問を
NPS®のアンケートでは、バイアスのかからない適切な評価をもらうために「推奨度」を最初に聞いていきます。
Q:「あなたは、“製品・サービス“を家族や友人にお勧めしたいと思いますか?」
A:推奨度0~10(11段階評価)
Q:「その理由を教えてください」
A:自由記述
シンプルなアンケート例(生命保険会社の場合)
具体的なアンケートのイメージとして以下のようなものがあります。
Q1:あなたは○○生命を家族や友人にお勧めしたいと思いますか?
Q2:上記のように評価された理由をご自由にお書きください。
Q3:○○生命に関する次の各要素の満足度をお聞かせください。
1:ブランドイメージの良さ
2:保険商品の魅力
3:保障内容や保険金請求条件のわかりやすさ
4:手続きの簡単さ
5:アフターフォローの手厚さ
6:お問合せ時の応対の良さ
7:保険金請求時の対応のスムーズさ
8:コストパフォーマンス
Q4:○○生命に改善してほしいことがあれば1つ挙げてください
アンケート結果の分析
アンケートで評価が得られたら分析をしていきます。分析のポイントは数値での評価だけでなく、自由記述でご記入いただいた内容をかけ合わせます。
・「定性的な分析(数値の評価)」×「定量的な分析(自由記入の評価)」
数値の評価だけでは課題の特定が困難なケースもありますので、自由記入の評価も同様に分析データとして扱っていきます。
また、改善に繋げるために予め関係各部署に共有しておくこともポイントの一つです。改善出来ないようであればアンケート自体の意味がなくなってしまいますので、注意が必要です。
【関連記事】
アンケートに有効な5つの分析方法|集計〜分析の流れや効果を高めるコツ
NPS®アンケートの効果を高める「NPX Pro」
「NPX Pro」はCX向上を支援するNPS®ツールです。顧客のフィードバックを分析し、改善アクションの実施までをスムーズに実現できます。以下は、NPX Proの主な機能です。
- NPS®アンケート作成、配信
- NPS®アンケート集計、分析
- NPS®アンケート分析結果の共有
- 改善アクションの促進・管理
カスタマージャーニーの設定と各タッチポイント上にアンケートを作成でき、複数の調査を一括管理できます。SMSやメールなどでのアンケート配信にも対応しているので、従来の郵送に比べ回収率が高いのも特徴です。複雑な分析作業は不要なうえ、リアルタイムで結果をチェックすることができます。
導入事例|日立ハイテクサイエンス 様
日立ハイテクグループの分析計測装置メーカーである「日立ハイテクサイエンス」様。約15年間、自社でアンケートフォームによる顧客満足度調査を実施されてきましたが、「この設問は効果的か?」「この運用方法でよいのか?」といった悩みから、NPX Proを導入されました。
NPX Proを実際に使用されてみて、もっともよいと感じたのが「アクションドライバー分析」だといいます。製品の強みや弱みが可視化され、どこを改善すればよいかが一目でわかるようになったそうです。また、コンサルタントやテクニカルサポートの存在も大きく、設問の内容や設問数などについても的確な回答を得られたことが役立ったといいます。
NPX Pro導入後は社内におけるアンケート調査のイメージも変わり、経営幹部からも「重要な取り組み」として評価されていらっしゃるとのことです。
アンケート調査は適切な設計で回答率・精度を高められる
アンケート調査でユーザーの本音を引き出せれば、自社の商品やサービスの改善に役立てられます。効果を出すためには、適切な設計で回答率や精度を高めることが重要です。本記事で紹介したアンケートの回答率や回答の信頼性を上げるコツも参考に、適切な設計を行いましょう。
NTTコムオンラインでは、企業のみなさまの顧客ロイヤルティ向上のための活動を、NPS®アンケートの設計から分析までコンサルタントが伴走しご支援いたします。また、効率的な改善活動を実現するSaaSツール、NPXもご提供しています。 是非お気軽にご相談ください。
以下NPS®の基本情報や各種NPS®レポートなどもご用意していますので、どうぞご活用ください。
【
カスタマーロイヤルティxビジネス
】
最新のコラム

2024/08/02

2024/08/02

2024/02/01