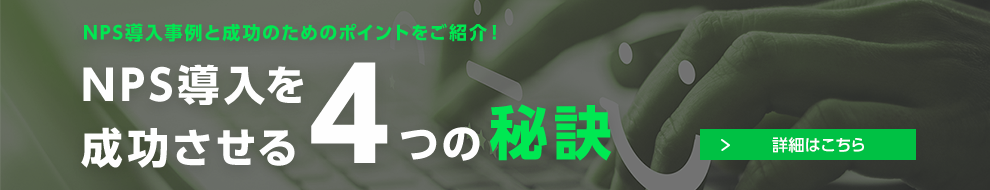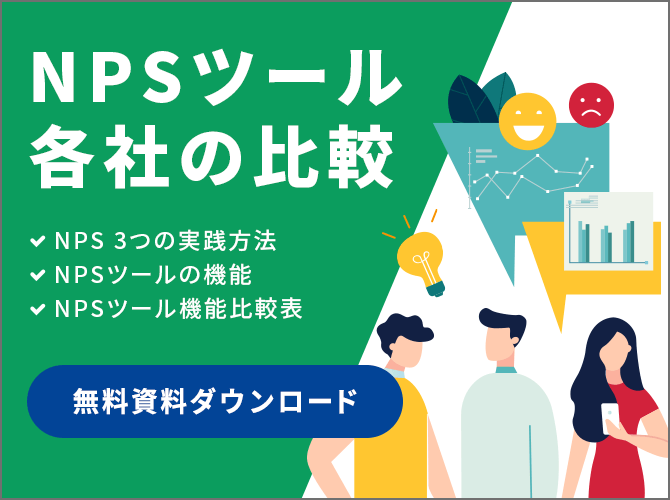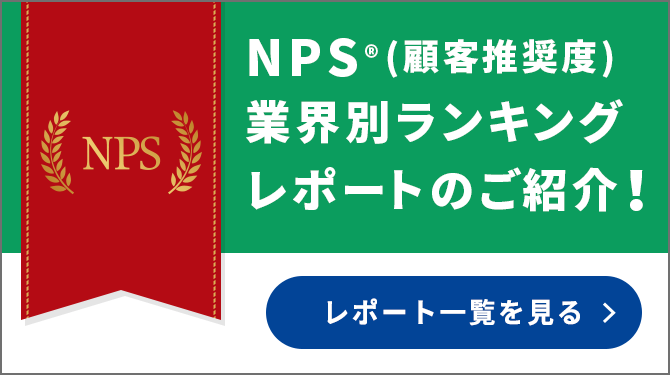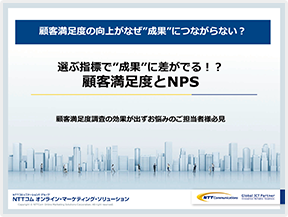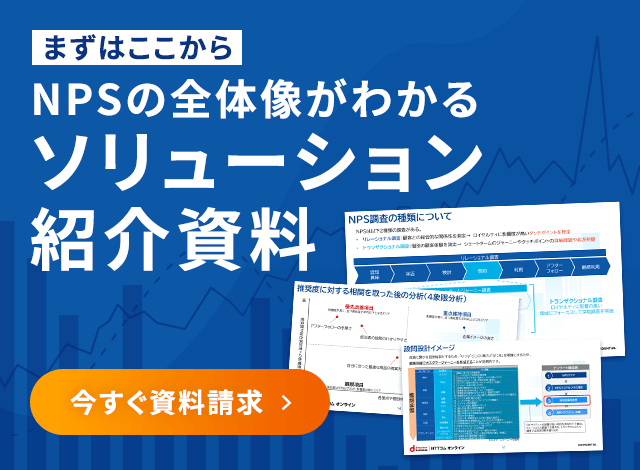更新日:2025/03/28(公開日:2015/07/24)
NPS®(ネットプロモータースコア)入門・導入編
第2回 顧客ロイヤルティを測る新指標「NPS」とは?~究極の質問の発見とその本質~
第1回では、企業にとってロイヤルティの高いお客様がなぜ必要なのかについてお話ししました。
第2回のテーマは「ロイヤルティの高いお客様をどのように見つけるか」、「顧客ロイヤルティをどのように測り、把握するか」です。
- ロイヤルティの高いお客様は、NPS®の核となる「究極の質問」で見つかる。
- NPS®とは、再購入比率が非常に高い「推奨者」の正味比率を指す。
- NPS®の本質はお客様が推奨者になる要因を把握・強化しつつ、批判者が出る原因を取り除くことにあり、その際に「トランザクショナル調査」と「リレーショナル調査」が役立つ。
- NPS®を有効活用するためには、アクションドライバー分析をはじめとする分析方法の選定が重要。
NPS®の核となる「究極の質問」の発見
「ロイヤルティの高いお客様」を発見するためには、お客様にどのような質問をすればいいのでしょうか?この問いは、「ロイヤルティの高いお客様」の特徴である以下の行動につがる質問を見つけることになります。
- 自社の製品・サービスを何回も購入してくれる(=継続購入)
- 友人などの他者へポジティブなクチコミを広めてくれる(=推奨)
ベイン・アンド・カンパニー社のフレッド・ライクヘルド氏は、6つの業界(金融・CATV/通信・eコマース・自動車保険・ISP・PCハードウェア)の計4,000の顧客を対象に、いくつかのロイヤルティを測る質問に対するスコアを調査し、次いで6-12ヶ月後に実際の行動を調査しました。その結果、全ての業界において将来の顧客行動に対してトップまたは2番目に高い相関を示すひとつの質問を発見しました。(*1)
それが「この会社を友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」という究極の質問と呼ばれるものです。
では、この質問からどのように「ロイヤルティの高いお客様」を見つければよいのでしょうか?
顧客は3つのセグメントに分類できる
このシンプルな質問に対し、0から10の11段階で回答してもらい、顧客行動を調べてみたところ、以下の3つのセグメントに分類できることがわかりました。
1) 推奨者(プロモーター)(9-10)
再購入比率が群を抜いて高く、紹介客のうち、このセグメントの顧客に薦められた顧客が80%を超えている。
2) 中立者(7-8)
受け身でも満足している。再購入比率と推奨率が推奨者より大幅に低く、50%以上も差がつくことも多い。ロイヤルティや熱意よりも惰性が動機付けとなっているので、この層の顧客は他社が好条件を提示するまでは留まる可能性がある。
3) 批判者(0-6)
否定的なクチコミの80%以上を占める。彼らの一部は、会計上、収益性が高く見えるかもしれないが、彼らの批判や否定的な態度によって企業の評判は傷つき、新規顧客の購入意欲に水を差し、従業員の意欲をそぐ。企業の活力を奪いとってしまう存在。
引用:『ネット・プロモーター経営 顧客ロイヤルティ指標NPSで「利益ある成長」を実現する』p.78
この「1) 推奨者」こそが「ロイヤルティの高いお客様」なのです。
第1回でも書いたとおり、企業経営者にとって「ロイヤルティの高いお客様」をつなぎとめることには大きな意味があります。加えて、「ロイヤルティの高いお客様」を新たに創り出すことも企業の成長にとって必要不可欠です。
この「ロイヤルティの高いお客様の維持・新規創出」という企業活動を促進することができ、上記の顧客分類に基づき生み出されたのがNPS®(ネットプロモータースコア)です。
NPS®とは?
NPS®(Net Promoter Score:ネットプロモータースコア)とは、日本語で「推奨者の正味比率」を意味します。顧客満足度(CS)とよく混同されがちですが、この2つは異なる概念です。
顧客満足度はその名のとおり、製品・サービスに対するお客様の満足度を測る指標です。こちらは、仮に高い数値を獲得できたとしても、リピート率が上昇するとは限りません。
一方、NPS®は製品・サービスにおける他者への推奨度を質問することで「顧客ロイヤルティ」を測る指標です。こちらは業績との相関性が高いので、NPS®の向上によってリピート率の上昇が期待できます。
顧客満足度(CS)とは?向上させる目的・方法・注意点を徹底解説
NPS®の計算方法とは?
NPS®の計算方法は以下のとおりです。
NPS®=推奨者の割合(%)-批判者の割合(%)
NPSは批判者しかいないことを示す-100から全員が推奨者であることを示す100までの間に収まり、この計算方法を見てもわかるとおり、NPS®は推奨者が多く、批判者が少なければ高くなります。
そして、NPS®を上げるには、推奨者を増やし、批判者を減らす必要があります。すなわち「ロイヤルティの高いお客様の維持・新規創出」という企業活動を継続していく上で、NPS®を継続的にモニターすることで、推奨者を増やし、批判者を減らすという行動が取れているかどうかを一目で確認することができます。
NPSの計算方法とアンケートの評価方法とは?導入のメリットや活用のポイントも解説
NPS®が注目される理由とは?
NPS®は先述のとおり、業績と強い相関関係がある指標です。NPS®によってお客様が製品・サービスをリピートする可能性を測定できるため、将来的な収益を予測するための指標としても重要視されています。
また、NPS®は各業界のベンチマークに活用できる点も注目を集める理由です。業界内における自社のポジションを確認したり、競合他社の状況と比較したりする際に役立ちます。
さらに、NPS®が注目される理由として「顧客体験」の改善につながる点も挙げられます。顧客体験とは、顧客が製品・サービスに関心を持ってから、実際に購入・利用するまでの一連の体験を指す用語です。
顧客体験を改善するためには、企業とお客様の接点(タッチポイント)における顧客ロイヤルティを向上させる必要があります。NPS®を活用すれば、顧客ロイヤルティを可視化できるため、よりスムーズに改善を進めることが可能です。
顧客体験(CX)の調査はどうすればよい?NPS®の有効性と調査のポイントを解説
NPS®の本質とは?
もうお気づきかと思いますが、NPS®は一度調査を行い、スコアを得て、その結果に一喜一憂して終わり、では意味がありません。
NPS®の向上、すなわち、推奨者を増やし、批判者を減らすというフレームワークに沿って行動する過程で、お客様が推奨者になってくれる要因把握を行い、さらに強化する、または批判者が出ている原因分析を行い、それを取り除くように改善活動を行うことに意味があるのです。
このお客様からのフィードバックに真剣に向き合い、改善のために行動を起こしお客様に働きかけるサイクルのことを「クローズドループ」と呼びますが、これを全社挙げて組織的に行っていくこと、 単なるスコアではなく、「ロイヤルティの高いお客様の維持・新規創出」のためのマネジメントシステムとして活用することがNPS®の本質と言えるのではないでしょうか。
「トランザクショナル調査」と「リレーショナル調査」
NPS®調査は、主に「トランザクショナル調査」と「リレーショナル調査」の2種類があります。
トランザクショナル調査とは、各タッチポイントを利用した直後の顧客を対象とする調査方法です。特定の顧客体験における課題発見に適しており、週1回や月1回など比較的短いスパンで実施します。
一方、リレーショナル調査とは、企業そのものや製品・サービスに関するタッチポイント全般を調査する方法です。複数の顧客体験を比較・分析できますが、調査範囲が広いゆえにコストや負担がかかりやすいので、年1回など間隔を空けて定期的に行います。
まずはリレーショナル調査でNPS®への影響度が大きい要素を特定しつつ、トランザクショナル調査でさらに詳細な分析を行うと効果的です。
NPS®を有効活用するための分析方法とは?
NPS®の分析方法は、大きく分けると「定量分析」と「定性分析」の2種類があります。
定量分析とは、数値データ(推奨度・収益性など)を基に分析する方法です。数値という客観的な事実を示すデータを用いて分析するので、誰もが共通の認識を持てます。
もう一つの定性分析は、数値化できないデータ(口コミ評価のレビュー内容など)を基に分析する方法です。数値では捉えられない内容も分析できる一方、個人の受け取り方によって認識の違いが生じやすい点には注意しなければなりません。
それぞれ具体的な分析方法の一例を紹介するので、以下も併せてご確認ください。
【定量分析】
- アクションドライバー分析:専用の図を用いて、NPS®への影響度が大きい項目を分析
- 6象限分析:NPS®と収益データを用いて、優良顧客とそれ以外の顧客の特徴を分析
【定性分析】
- テキストマイニング:単語同士のつながりを図で表し、自然言語処理技術で分析
- 頻出語分析:文章内に頻出する言葉を分析
定量分析だけでは情報不足によって分析の精度が低下しやすいため、定性分析と併用することが望ましいといわれています。
NPSの分析方法とは?定量分析・定性分析の具体的な手法を解説
改善すべき要素を抽出する「アクションドライバー分析」
アクションドライバー分析とは、4象限で構成される「ドライバーチャート」という図を用いてデータの傾向を分析する方法です。各象限に当てはまる項目を把握・分析することで、NPS®への影響度が大きい箇所から改善を進められます。
4象限における各項目の概要をまとめたので、こちらも併せてご確認ください。
| 優先改善項目 推奨度への影響度は高いが、顧客満足度が低い。自社の弱みを表す。 |
重点維持項目 推奨度への影響度・顧客満足度ともに高い。自社の強みを表す。 |
| 注意観察項目 推奨度への影響度・顧客満足度ともに低い。優先度は低いが、継続的に観察すべき。 |
基本維持項目 顧客満足度は高いが、推奨度への影響度が低い。顧客が「当たり前」と考える部分を表す。 |
適正なNPS®スコアとは?
NPS®は推奨者の割合から批判者の割合を引いた数値なので、推奨者が多いほどスコアが高くなります。日本においては、中間点を回答する傾向にあるため、NPS®がマイナスになるケースが多くみられます。
日本国内の場合、0以上なら平均的なスコアと判断されることもありますが、業界や業界によって適正値は変わるため、参考程度に覚えておきましょう。
NTTコム オンラインの「NPS®業界別ランキングトップ企業 2024」を紹介
NTTコム オンラインでは、NPS®ベンチマーク調査を実施しています。その調査結果をもとに2024年の業界ランキングとNPS®スコアを一部紹介するので、ぜひ参考にしてください。
【対面証券部門】
1位:三菱UFJモルガン・スタンレー証券(-32.3)
2位:SMBC日興証券(-39.8)
3位:大和証券(-43.0)
【銀行部門】
1位:住信SBIネット銀行(-20.7)
2位:ソニー銀行(-28.1)
3位:auじぶん銀行(-28.7)
【生命保険部門 アフターフォロー調査】
1位:ソニー生命(-35.0)
2位:東京海上日動あんしん生命(-39.2)
3位:アクサ生命(-46.0)
NPS®ランキング【銀行部門】の詳細
銀行部門でランキング1~3位が評価されたポイントは、以下のとおりです。
- 住信SBIネット銀行
公式アプリの使いやすさ・分かりやすさ - ソニー銀行
企業イメージ・ブランドイメージのよさ、お客様に寄り添う姿勢・大切にする姿勢 - auじぶん銀行
手続きの簡単さ
銀行部門全体の「重点維持項目」と「優先改善項目」も一部紹介します。
【重点維持項目】
- 企業イメージ・ブランドイメージのよさ
- 利用時の安心さ
- セキュリティの信頼性
【優先改善項目】
- 担当者の説明のわかりやすさ
- お客様に寄り添う姿勢・大切にする姿勢
- ニーズを満たす商品のラインナップ
この調査では、銀行の発信内容やアフターフォローが金融・資産運用への理解度を高めており、結果的にロイヤルティの向上へつながっていることも判明しています。また、NPS®が高いほど利用継続意向も高くなる結果となりました。
NPS®のお悩み解決をサポートするNTTコム オンラインの「NPS®ソリューション」
NTTコム オンラインでは、NPS®の導入・活用をサポートする「NPS®ソリューション」を提供しています。
主なサービスや特徴、企業の導入事例を紹介するので、引き続きご覧ください。
NPS®の導入・活用に有効な「NPS®調査・コンサルティング」
NPS®ソリューションでは、NPS®の本格導⼊を支援する「NPS®調査」を実施しています。NPS認定資格者が設問設計・実査・レポートなど一通りサポートするため、よりスムーズな導入を実現可能です。
自社のポジショニングを調べる「NPS®ベンチマーク調査」や、NPS®の有効性を調べる「NPS®アセスメント調査」なども実施しており、収益性との相関や推奨者・批判者の経済的な価値の検証なども可能です。
また、高いロイヤルティの要因分析や優先改善項⽬の把握など、改善施策につながる調査もサポートしています。ブランドロイヤルティ調査では、以下のようなメリットを享受できます。
- 4つの品質保持(モニター・調査票・アンケートシステム回答結果)を柱とした「クオリティポリシー」に基づく徹底した品質確保の実現
- 自社の位置づけや課題を把握し、ブランド価値向上に効果的なアクションを実行
- 自社の認知度向上や新規顧客獲得に向けた戦略立案
さらに、NPS®の導入・活用・部門拡大といった各フェーズを専門コンサルタントが支援する「NPS®コンサルティング」も提供しています。
日常的な調査を自社で実行する「NPS分析・顧客体験管理ツール」
NTTコム オンラインでは、AI活用による顧客体験管理プラットフォーム「クアルトリクス」を提供しています。
クアルトリクス(顧客体験管理ツール)はカスタマージャーニーを直接把握できるため、然るべきタイミングで顧客の不満を解消することが可能です。オムニチャネルでユーザーインサイトを分析し、AIによる改善案を素早くフィードバックできる点も見逃せません。
導入事例|株式会社 ジャルパック 様
株式会社ジャルパック様は、NPS®ソリューション導入前から常に顧客満足度が90%を超えていました。しかし、今後は顧客満足度を高めるより、NPS®を採用したほうが得策と判断し、導入に至りました。
従来の顧客満足度は5段階評価でしたが、NPS®調査は11段階評価なので回答結果にばらつきが出やすく、未知の課題が浮き彫りになったといわれています。また、NPS®と他のデータの相関も見えるようになり、改善の効率が上がったとのことです。
NPS®を上げることは本当に売上アップにつながるのか?
今回はNPS®の誕生とその本質についてお話ししました。
第1回と合わせて、顧客ロイヤルティを上げることが企業の売上および成長につながる、NPSはそのための企業活動を支える仕組みであることが「なんとなく」ご理解できたでしょうか?
次回はNPS®が注目を浴びている大きな理由のひとつである「売上との相関」について詳しくお話しします。
また、今回の記事を読んで「NPS®ソリューション」に関心を持った方は、以下のページで詳細をご確認ください。
【
NPS®(ネットプロモータースコア)入門・導入編
】
最新のコラム
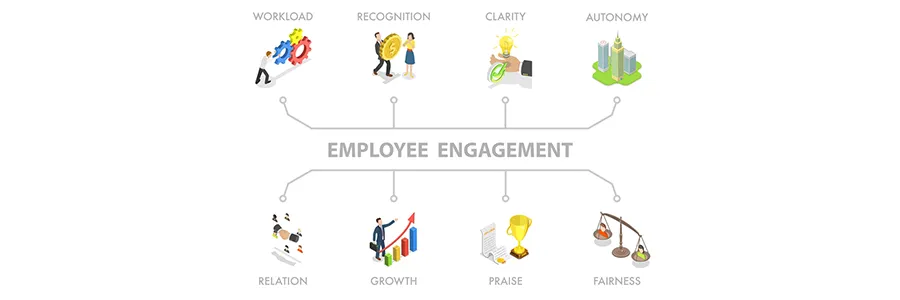
2025/12/26

2025/12/26

2025/08/01

2025/07/17