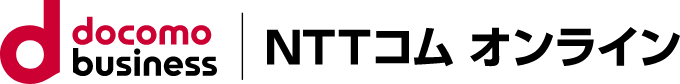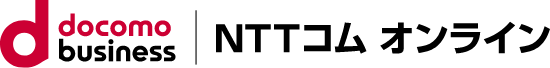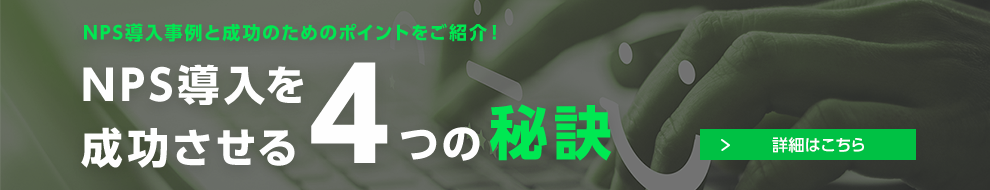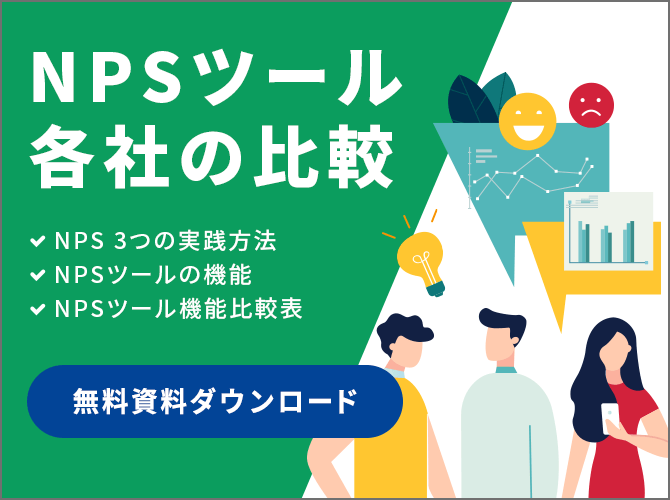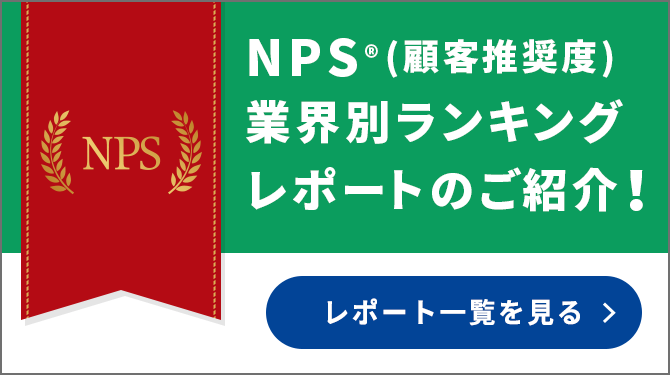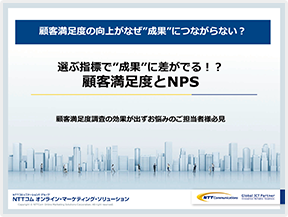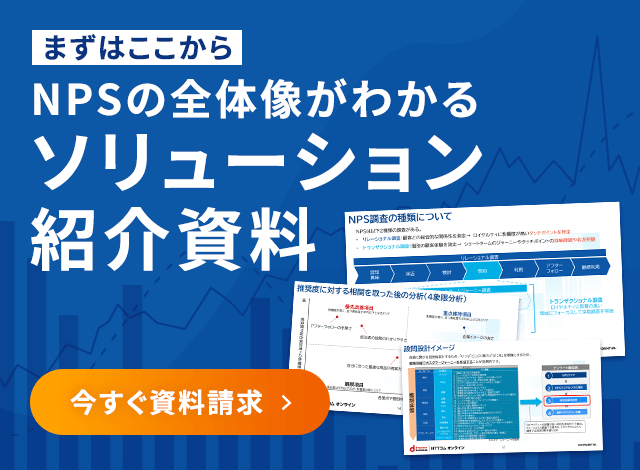2025/01/31
顧客満足度とNPS®
自動車業界の顧客体験(CX)にデジタルを活用すべき?重要性や具体的な活用例を紹介
近年、自動車業界の顧客体験(CX:カスタマーエクスペリエンス)におけるデジタル活用が注目されるようになりました。従来は自動車の性能など、ハード面に焦点が当たるケースの多かった自動車業界の顧客体験にも変化が訪れています。顧客体験へのデジタル活用にはさまざまなメリットがあり、自動車業界でも積極的に導入すべきといえるでしょう。
本記事では、自動車業界の顧客体験にデジタルを活用するメリットや実際の活用事例、デジタルを活用する際のポイント、顧客体験の向上に欠かせないNPS®(顧客ロイヤルティを測る指標)などを解説します。自動車業界における顧客体験へのデジタル活用に興味をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
- 自動車業界の顧客体験でデジタルを活用すると、ロイヤルティ醸成やブランド価値の向上、競合他社との差別化などのメリットがある
- カスタマージャーニーの各タッチポイントでデジタルを活用したさまざまな顧客体験が提供できる
- 自動車業界の顧客体験にデジタルを活用する際は、ブランディングやパーソナライゼーション、コミュニティ育成、顧客情報管理などがポイントになる
- NPS®を活用すると、顧客ロイヤルティの調査・分析をもとに、優先順位をつけて効果的な施策が実施できる
顧客体験について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
企業成長を導く「顧客体験(CX)」とは?その重要性と高める方法や事例を紹介
自動車業界の顧客体験にデジタルを活用すべき理由
自動車業界が顧客体験にデジタルを活用すべき主な理由は、以下の通りです。
- ロイヤルティの醸成につながる
- ブランド価値の向上につながる
- 競合他社との差別化につながる
- 長期的な成長につながる
それぞれの理由を詳しく解説します。
ロイヤルティの醸成につながる
デジタルによる顧客体験の向上は、顧客ロイヤルティの醸成につながります。ロイヤルティとは顧客が企業へ抱く「愛着」や「信頼」を意味する用語です。ロイヤルティを高めれば、他社との競争においても顧客からより選ばれる企業になれます。
グローバルでのブランド調査を行っているKPMGの「生活者に支持される顧客体験に関する調査2023-2024」によると、顧客体験において重視されるのは「パーソナライズ」や「誠実性」「親密性」です。
出典:KPMG「生活者に支持される顧客体験に関する調査2023-2024」
自動車業界でデジタル化を実現すると、シームレスかつストレスフリーな顧客体験が可能です。また、顧客の抱える悩みや問題点にもアプローチしやすくなり、パーソナライズや誠実さ、親密さをアピールしやすくなるでしょう。結果、顧客との距離も近くなり、顧客ロイヤルティ醸成が期待できます。
顧客ロイヤルティについて、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
顧客ロイヤルティ(顧客ロイヤリティ)とは?向上させるメリットと事例
ブランド価値の向上につながる
デジタルを活用した顧客体験はブランド価値の向上にも有効です。顧客から認識されている会社や自社商品・サービスに対するイメージをブランドと呼び、顧客がブランドに対して感じる魅力や満足度をブランド価値といいます。ブランド価値が高ければ顧客が商品・サービスを選ぶ際に優位に立てるため、企業にとっては目に見えない強みです。
昨今はSNSの普及により口コミが拡散しやすい環境になりました。良質な顧客体験はインターネットやSNSを通じて短期間に広まり、ブランドイメージや評判の向上に貢献します。また、顧客の満足度が高くなれば「UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)」も生まれやすく、より多くの人にブランド価値を伝える役割を担ってくれるでしょう。
競合他社との差別化につながる
デジタルを活用した良質な顧客体験は競合他社との差別化につながります。近年の自動車業界は自動車の品質だけで差別化するのが難しくなってきました。従来のような走行性能や運転の快適さなど、自動車本体やハードウェアに付随する価値が重要なのは変わりません。しかし今後、自動車業界で他社との差別化を目指すなら、顧客体験のようなソフト面の価値を提供していく必要があります。
デジタル化を導入して顧客体験全体を改善すれば、競合他社と差別化しながら自社の魅力をアピールできます。たとえば、顧客一人ひとりにパーソナライズされた情報提供やサービス提案などは、他社にない大きな強みとなるでしょう。
長期的な成長につながる
自動車業界における顧客体験にデジタルを活用すれば、自社の長期的な成長も期待できるでしょう。デジタルによる顧客体験の最適化を実施すると、顧客からの長期的な支持を得られるようになります。
自社に信頼や愛着をもつ顧客なら、購買行動は一度の自動車購入では終わらず、メンテナンスや買い替えなどでリピートしてくれる可能性が高くなるでしょう。良質な顧客体験を積み重ねていけば、継続して自社の商品・サービスを利用してくれる顧客も増加していきます。優良な顧客が多くなれば、売り上げも持続的に増えていき、長期的な会社の成長へとつながるでしょう。
カスタマージャーニーから見るデジタルを活用した自動車業界の顧客体験
自動車業界のカスタマージャーニー(顧客が商品・サービスを認知して購入・利用に至るまでのプロセス)における以下の各タッチポイント(商品・サービスと顧客との接点)で、デジタルを使い、どのような顧客体験が提供できるかを解説します。
- 認知フェーズ
- 情報収集フェーズ
- 試乗・購入検討フェーズ
- 購入フェーズ
- 利用フェーズ
それぞれのタッチポイントと顧客体験を詳しくみていきましょう。
顧客体験を提供する際の企業側における顧客体験設定について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
顧客体験設計(CXD)とは?マーケティングでの重要性や設計のポイントを解説
1|認知フェーズ
自動車業界の認知フェーズは、顧客が自社の自動車にどのような製品があるかを知り、興味をもってもらう段階です。良い製品を開発しても顧客に関心を示してもらえなければ購入には結びつきません。認知フェーズでの顧客体験は、顧客が今後どれだけ真剣に自社製品の購入を検討するかを左右するため重要です。
多様なタッチポイントからの認知獲得
認知フェーズでの顧客体験では、顧客とのタッチポイント(接点)を増やして、より多くの認知を獲得するデジタルマーケティングを目指しましょう。獲得できる認知が増えるほど、自社製品を購入してもらえる可能性も高くなります。
昨今では、Web広告やSNSを使ったプロモーションやインフルエンサーとコラボレーションした動画企画など、マーケティングの選択肢も広がりました。自社のブランドイメージにマッチしたデジタルコンテンツで幅広い顧客の認知を獲得していきましょう。
2|情報収集フェーズ
情報収集フェーズは、自社製品に興味をもった顧客がWebサイトや広告、SNSなどを調べて情報を集めていく段階です。従来の自動車業界では、カタログを取り寄せたり、販売店に足を運んで実物を見たりするアナログな体験が主流でした。デジタル技術を活用すれば、今までになかった新しい顧客体験の導入が可能になります。
AIチャットボットの活用
AI(人工頭脳)チャットボットを活用すれば、情報収集フェーズで新鮮かつ有効な顧客体験を提供可能です。公式サイトでユーザーが効率良く欲しい情報を入手できるように、AIチャットボットを導入します。チャットボットとは、人間に代わってロボットが会話するプログラムです。
AIチャットボットはユーザーからのさまざまな問い合わせ・質問に対して、AIが自動で応答・会話を行ってくれます。ユーザー一人ひとりの質問に丁寧に答えたり、アフターフォローをしたりなど多様な利用方法が可能です。こまめに問い合わせができれば顧客とのコミュニケ―ション密度も高くなるため、ロイヤルティの向上も期待できるでしょう。
バーチャルショールームの活用
情報収集フェーズでの顧客体験には、バーチャルショールームの活用も有効です。バーチャルショールームとは、販売店舗の一角などに設けられた展示設備で、デジタル技術を利用した以下のような顧客体験を提供できます。
- 大型モニターで実寸サイズのカーシミュレーターを閲覧:店舗に置いていないモデルでもリアルな映像で実物に近い形で確認できる
- AR、VRを使った360°ビュー:スマホアプリを利用して、気に入った自動車から発売前の新型車も体験できる
バーチャルショールームでは顧客体験をユーザーに合わせてカスタマイズでき、Webやカタログだけでは手に入らない情報を提供する機会として効果的です。
3|試乗・購入検討フェーズ
試乗・購入検討フェーズは、顧客が集めた情報をもとに自動車を購入すべきか検討する段階です。購入検討の際、試乗が大きなウェイトを占めるのが自動車業界の特徴といえます。試乗においてもデジタル技術を導入すれば、より満足度の高い顧客体験を提供でき、製品の購入へとつなげられるでしょう。
シームレスな試乗体験の提供
デジタル技術の活用により、試乗の予約や当日の手続きなど、オンラインとオフラインでシームレスな体験を提供可能です。公式サイトで試乗に関する十分な情報を提供するとともに、実店舗に行かなくても簡単に試乗予約ができるように設計します。顧客管理システムとの組み合わせでオンラインでの予約内容を店舗スタッフが共有し、店頭・オンラインのどちらで予約してもスムーズに試乗へ移行できる仕組みを構築しましょう。
手軽なセルフ試乗の提供
オンラインを利用して、スタッフを介さずユーザーが1人でできるセルフ試乗を提供するのもデジタルを利用した施策の1つです。セルフ試乗には、以下のようなメリットがあります。
- 自分の好きなタイミングで気軽に試乗できる
- 試乗する際も近くに販売員がいないため緊張せずに済む
自動車メーカーのテスラでは、スマートフォンのTeslaアプリからオンライン予約でき、1人で試乗を行なえるセルフサービス試乗を提供しています。アプリで車種と時間を選び、当日、指定の場所に行くだけで試乗でき、スタッフへの対応なども必要ありません。
コネクテッドカーでの新しい体験
ユーザーに今までにない顧客体験を提供できるコネクテッドカーは、自動車業界のDXとして注目されている手法の1つです。DX(Digital Transformation:デジタルトランスフォーメーション)とは、AIやIoT (モノのインターネット)などを利用した業務改善やビジネスモデルの変革などを意味する用語です。
コネクテッドカーにはIoT技術が使われており、以下のような機能を搭載しています。
- スマートフォンを使った遠隔でのドアロックやエアコン、エンジンの操作
- 事故発生時の自動通報や盗難時の車両追跡機能
- リアルタイムで渋滞情報を提供
- ドライバーの事故リスク分析により安全運転をサポート
コネクテッドカーの実現により、従来にはなかった新鮮な体験をユーザーに提供できます。
AIを使ったスムーズな査定
AIを利用したスムーズな査定システムの導入により顧客体験の向上が期待できます。自動車業界でのAI利用では自動運転などに注目が集まっていますが、下取り・査定もAIを活用すべき分野といえるでしょう。
試乗中にスピーディーかつ精度の高い査定が可能になれば、買い替え時にストレスを与えずに済むため顧客体験の向上が見込めます。たとえば、店舗の入り口にカメラを設置しておき、駐車場に入ってくる車両を自動的にAI画像で査定する仕組みを構築すれば、査定時間を大幅に削減できるでしょう。
4|購入フェーズ
顧客が自社製品の購入を決め、実際に自動車を購入する段階です。ユーザーは既に商品を決めており、あとは購入してもらうだけではあるものの、顧客体験は購入フェーズにおいても大切です。購入手続きがスムーズに進まなかったり、ストレスを感じたりすると購入を止める可能性があります。また、購入時の顧客体験が良好なら、長期的な付き合いや再購入にも結びつくでしょう。
オンラインでのスムーズな購入手続き
近年では、オンラインで自動車を販売するケースも出てきました。オンラインでスムーズな自動車購入が可能になれば、以下のようにユーザーに多くのメリットがあります。
- 店舗に足を運ばなくても良いため時間・場所を問わずに自動車を購入できる
- 見積りが簡単かつわかりやすく価格や販売プランが明確になる
- 車の色・内装などオプションやカスタマイズの追加・変更が簡単にできる
オンライン販売のシステムは、購入フェーズの顧客体験にもプラスになるため、今後導入する企業も増えていくかもしれません。
5|利用フェーズ
購入した製品を顧客が実際に利用する段階です。自動車業界は製品を販売して終わりではなく、以後も点検・メンテナンスや新車への買い替えなど、ユーザーとの接点が多くあります。顧客との良好な関係を継続していけるよう、利用フェーズにおいても質の高い顧客体験を提供していくのが大切です。
パーソナライズされた情報提供
購入後のサポートやお役立ち情報、メンテナンスのお知らせなど、顧客情報をもとにパーソナライズしていけば、良質な顧客体験を提供できます。パーソナライズされた有益な情報提供により、顧客は自分が必要とする情報やサポートを問い合わせなどの手間をかけずに入手できます。
顧客は自分がブランドから大切にされていると感じるようになるため、ロイヤルティの向上につながり、商品・サービスの継続利用や再購入が見込めるでしょう。
自動車のサブスクリプション・カーリースも顧客体験の向上につながる可能性がある
自動車のサブスクリプションやカーリースなどのサービスも、顧客体験の向上に有効な可能性があります。近年では、自動車のサブスクリプションやカーリースも注目されるようになりました。
NTTコム オンラインが行った自動車の所有に関する調査によると、「以前に自動車を所有していたが現在は所有していない人」で「今後自動車のサブスクリプション・カーリースで自動車を所有したい」と回答した割合は14.8%にのぼり、特に自動車を手放した人から高いニーズがあるのがわかります。
出典:NTTコム オンライン「自動車の所有と利用に関する調査」
メンテナンスや維持費をかけずに車を利用できるサブスクリプションやカーリースは、自動車を利用したいけれど、所有するのは負担が大きいと考えている人から支持を得ているようです。サブスクリプション・カーリースをサービスに取り入れれば、従来よりも幅広いユーザーの顧客体験を向上させられるでしょう。
自動車業界でデジタルを活用した顧客体験を提供するポイント
自動車業界でデジタルを活用した顧客体験を提供する際のポイントは、以下の通りです。
- 一貫したブランディングを行う
- パーソナライゼーションを取り入れる
- オンラインコミュニティを育成する
- 顧客情報を適切に管理・分析する
- 顧客体験の現状と推移を把握する
それぞれのポイントを詳しく解説します。
一貫したブランディングを行う
自動車業界が顧客体験にデジタルを活用する際は、カスタマージャーニーの各タッチポイントで一貫したブランディングを実施するのが大切です。ユーザーは単に自動車の販売だけを求めているわけではなく、各メーカーのもつブランド価値やステータスも重視しています。
タッチポイントごとにブランディングの方向性が異なると、ユーザーに混乱を与えてロイヤルティの低下につながる恐れがあります。SNSでの情報発信の仕方や公式サイトや実店舗が与える印象などにズレが出ないように、自社のブランドイメージを明確にして一貫性を保つことが大切です。
パーソナライゼーションを取り入れる
顧客体験にパーソナライゼーションを組み込むと、顧客との間でより深い関係構築が可能になります。たとえば、顧客の趣味・嗜好や購入履歴、属性に基づいて商品・サービスの情報やコンテンツを提供したり、おすすめプランを提案したりする手法が有効です。
パーソナライズされた顧客体験は、ユーザーの特別感や信頼感を醸成する役目を果たし、ロイヤルティの向上や自社商品の再購入といった購買行動につながるでしょう。
オンラインコミュニティを育成する
ブランドや同じ自動車をもつユーザーとのコミュニケーションを促進するのに有効なのが、オンラインコミュニティの育成です。自動車業界でもWebサイト内でユーザーの声を紹介したり、自動車に限らずさまざまな趣味のコンテンツを充実させたりするなど、各社がコミュニティ育成施策を取り入れています。
コミュニティに参加すると、顧客がブランドをより身近に感じられるようになり、ロイヤルティ醸成に結びつくでしょう。企業側は顧客からのフィードバックも収集できるため、顧客体験の改善にも役立てられます。
顧客情報を適切に管理・分析する
各タッチポイントで得た顧客情報を一元管理すると、精度の高い分析とパーソナライズが実施できます。オンラインと店舗で情報共有ができなければ、顧客一人ひとりに合わせた良質な顧客体験の提供は実現できません。電話での問い合わせやオンライン、店舗など、一度でも接点ができた顧客の情報は、社内で一元化して管理・分析できる仕組み作りが必要です。
顧客情報を適切に管理するには、BIツール(Business Intelligenceツール:データを管理・分析・可視化して業務や経営に役立てるソフトウェア)やCRMツール(Customer Relationship Management:顧客との良好な関係を構築・継続するための顧客管理ソフトウェア)などを活用した顧客情報管理システムの構築が求められます。
顧客体験の現状と推移を把握する
顧客体験の現状と推移を把握するには、顧客ロイヤルティを測る指標であるNPS®(Net Promoter Score)が有効です。NPS®では、以下の計算方法を用いて顧客ロイヤルティを評価したNPS®スコアを導きます。
- NPS®アンケートを実施して商品・サービスに対する評価を0~10点の11段階で表す
- 顧客を「批判者(0~6点)」「中立者(7~8点)」「推奨者(9~10点)」の3種類に分類する
- 推奨者の割合から批判者の割合を引いた値がNPS®スコアとなる(推奨者の割合-批判者の割合=NPS®スコア)
NPS®スコアはベンチマークとしても活用でき、自社の現状と数値の推移を確認しながら改善策を検討・実施できます。NPS®の調査や分析を行う場合は、クラウドサービスなどの利用がおすすめです。
顧客体験の調査とNPS®について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
顧客体験(CX)の調査はどうすればよい?NPS®の有効性と調査のポイントを解説
NPS®の活用でロイヤルティに深く関係する項目を明確化できる
ツールを使って自社のNPS®を調査・分析すると、NPS®への影響度が高い項目を可視化できるようになります。
そのために活用される手法として有効なのが、NPS®に影響を与える4つの要因をドライバーチャートで分析する「アクションドライバー分析」です。ロイヤルティを醸成するポイントである「重点維持項目」や、ロイヤルティを阻害するポイントである「優先改善項目」を可視化できます。その結果、実施すべき施策の優先順位を明確化でき、より効率的に顧客体験を改善できるでしょう。
NTTコム オンラインでは、業界ごとのNPS®ベンチマーク調査を実施しています。たとえば「自動車おすすめランキング」では、対象の自動車ブランド利用者に、家族や知人など周囲の人に対して自分が乗っているブランドをどれくらいおすすめできるかを質問しています。
出典:NTTコム オンライン「【NPS®(顧客推奨度)ベンチマーク調査】自動車おすすめランキング」
調査の結果、ランキング上位のブランドでは、「企業イメージ・ブランドイメージのよさ」「ブランドのステータスの高さ」などブランドに対するイメージや「運転しやすさ」「運転する楽しさ」「走行性能」など商品に対する評価が顧客ロイヤルティ醸成に影響度の高い項目となりました。
ほかにもNTTコム オンラインでは、同様にNPS®(顧客推奨度)ベンチマーク調査として、「代理店型自動車保険おすすめランキング」「ダイレクト型自動車保険おすすめランキング」の調査も実施しています。興味のある方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
代理店型自動車保険おすすめランキング
ダイレクト型自動車保険おすすめランキング
顧客体験の向上をサポートするNTTコム オンラインの「NPS®ソリューション」
NTTコム オンラインでは、以下のような「NPS®ソリューション」を提供しています。
- NPS®の導入・活用をサポートする「NPS®調査・コンサルティング」
- 課題に合わせて選択できる「NPS®分析・顧客体験管理ツール」
それぞれのソリューションを詳しく解説します。
NPS®の導入・活用をサポートする「NPS®調査・コンサルティング」
NPS®の有効性を検証してアクションにつなげたいと考えている方に向けて、以下のようなNPS®調査・コンサルティングを実施しています。
- 競合他社と比較した自社のポジショニングを調査するNPS®ベンチマーク調査や、社内でのNPS®の有効性を検証するNPS®アセスメント調査などの各種NPS®調査を実施
- 調査にあたっては、NPS®認定資格者が設問設計から実査、レポートまでサポート
- 収益性との相関や推奨者/批判者の経済的な価値の検証など、NPS®の有効性に対する分析にも対応
- 高いロイヤルティの要因分析、優先改善項⽬の把握など、最適な改善アクションのための調査を支援
- NPS®の導入から活用、部門拡大など、各フェーズでNPS®コンサルタントが適切なサポートを提供
ブランドロイヤルティ(顧客がブランドに対して感じる愛着や忠誠心)に関する調査では、4つの品質保持(1:モニターの品質、2:調査票の品質、3:アンケートシステムの品質、4:回答結果の品質)を柱として「クオリティポリシー」に基づく徹底した品質確保を実現。自社の位置づけや課題を把握したうえでブランド価値向上に効果的なアクションへとつなげられるため、自社の認知度向上や新規顧客獲得に向けた戦略立案を可能にします。
課題に合わせて選択できる「NPS®分析・顧客体験管理ツール」
コンサルティングのほかにも、クアルトリクス(顧客体験管理ツール)やNPX Pro(NPS®支援調査ツール)など、課題に合わせて選べる各種ツールをラインナップしています。
- クアルトリクス(顧客体験管理ツール):
顧客・従業員に関するデータを収集して一括管理。カスタマージャーニーの調査・分析から顧客体験・ロイヤルティ向上施策を支援 - NPX Pro(NPS®調査支援ツール):
アンケート設計や調査実施に加え、顧客からのフィードバックを収集・分析して改善アクション・フォローアップ促進までをシームレスに提供。顧客体験・ロイヤルティの向上、収益性の高い顧客関係の構築をサポート
続いては、実際にNPX Proを導入している企業様の事例を紹介します。
導入事例|株式会社 ジャルパック 様
旅行商品を取り扱う株式会社ジャルパック様は、従来実施していた顧客満足度調査の結果は90%越えと良好ではあるものの、さらに満足度を1%向上させる目標は実行的ではないと感じていました。また、満足度調査は5段階評価であったため、具体的な課題を突き止めることが難しかったようです。
NPX Proの導入後は、今までの5段階評価では見えてこなかった課題や自社の強み・弱みなどを可視化できるようになりました。さらに、アクションドライバー分析により顧客ロイヤルティに影響する要素の相関関係もわかるため、優先順位をつけて改善施策を実施できるようになりました。
自動車業界における顧客体験の向上にはデジタル活用が必須
自動車業界の顧客体験に対するデジタル活用には、ロイヤルティ醸成やブランド価値の向上、競合他社との差別化など、さまざまなメリットがあります。現在の自動車業界で顧客体験を最適化するには、カスタマージャーニーの各タッチポイントでのデジタル活用が必須といえるでしょう。
よりよい顧客体験を提供するには、NPS®を利用した調査・分析と適切な改善アクションが欠かせません。顧客体験へのデジタル活用を導入する際は、同時にNPS®調査も取り入れ、ロイヤルティ向上に有効な施策を実現していきましょう。
以下のリンクからNPS®活用をサポートするツールやコンサルティングなど、NTTコム オンラインのNPS®ソリューションに関する資料をダウンロードできます。ぜひご活用ください。
【
顧客満足度とNPS®
】
最新のコラム

2025/05/30

2025/05/30
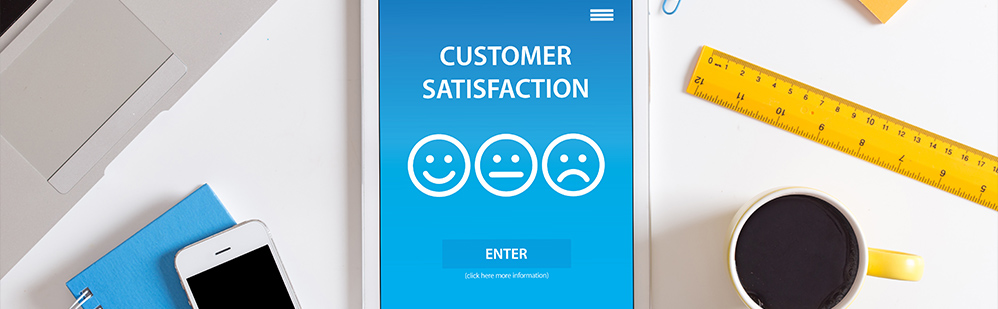
2025/03/13

2025/01/31